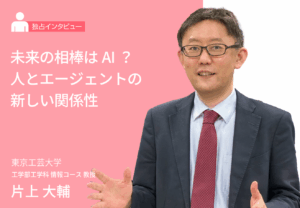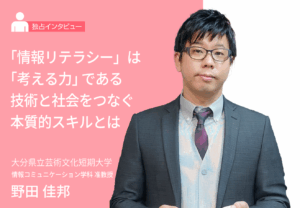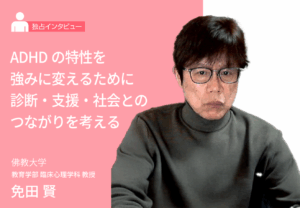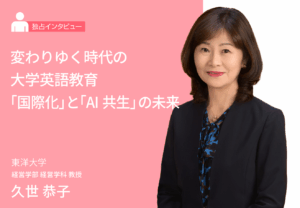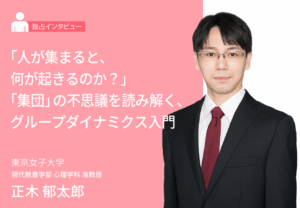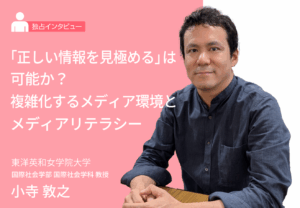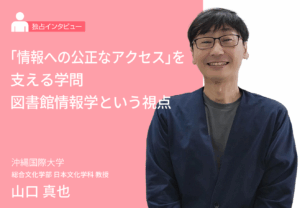近年では、女性の社会進出の加速や少子化対策としての保育支援政策の充実が、保育需要の増加を後押ししています。一方で、現場で働く保育士の人数は十分ではなく、また虐待などの不適切行為も一時ニュースで注目を浴びました。
そのような厳しい状況の中、多様化する家庭環境や子どもの支援の必要性が高まり、現場には柔軟かつ専門的な対応が求められています。
今回は、保育教育学の第一人者である矢藤誠慈郎先生に、保育士養成や教育現場における組織運営の課題、さらにはICTやAIの活用による未来の保育像について伺いました。

矢藤 誠慈郎
和洋女子大学 人文学部 こども発達学科 教授
【biography】
広島大学大学院教育学研究科教育行政学専攻博士課程中退(教育学修士)。
岡山短期大学講師・助教授、新見公立短期大学助教授、ニューヨーク州立大学客員研究員、愛知東邦大学教授、岡崎女子大学教授を経て現職(和洋女子大学教授)。全国保育士養成協議会常務理事、日本保育学会評議員等も務める。
専門は教育学。著書に『保育の質を高めるチームづくり』(わかば社)等。
研究分野は、養成から現職を見通した保育者の専門性の開発、保育における組織マネジメント・リーダーシップ等。
矢藤先生の研究内容
ナレッジアート(以下:KA):まずはじめに、矢藤先生が研究されている分野について具体的に教えていただけますか?
矢藤氏:はい。現在の私の研究分野は保育学、教育学ですが、もともとは教育学、特に教育経営学が専門です。大学院では、組織論や専門職論を扱い、教育に関わる組織の運営や専門職としての教育者の成長について研究しました。この知識を保育分野に応用し、保育者の専門性をどのように組織的、制度的に向上させるかを中心に研究しています。
KA:その研究を始めたきっかけは何でしょうか?
矢藤氏:もともと専門の教育経営学において、学校という組織の中で人々がどのように学び合い成長するかを研究していました。その後、保育の仕事に携わる中で、より規模が小さい組織である保育所や幼稚園においても、こうした組織論が活用できるのではないかと感じるようになりました。多様な背景を持つ保育士たちが、共に学び成長し合うことで、質の高い保育を提供するための組織作りが必要だと考えたのです。かつては各々の保育士が自己研鑽し、結果として保育が成り立っているという側面が強かったように思います。このやり方が成立していたのは、保育者の人数が今ほど必要ではなかったため、保育者になるモチベーションや能力がある人たちが保育士になっていました。しかし現在では保育の必要性が増し、それに伴い保育所と保育士がより多く必要になってきました。結果として以前よりも多様な人々が保育という業界に人材として入ってくるようになり、能力やモチベーションにどうしても以前より幅が出てきます。結果として「成り行き管理」が成り立たなくなり、組織的に人材を育成する必要性が出てきました。また、現在では離職率も高まってきていますので、どのようにより良い職場にしていき、また保育の質を高めるかを考えたときに、組織で人をどう育てるかが重要である時代に変化してきました。このような考え方は、特にここ十年ほどで顕著に重要視されるようになった傾向にあります。このような状況で、私が研究している組織論や専門職論が有効なのではないかと考えています。
多様な人材の育成と組織の課題
KA:多様な人材のマネジメントというのは興味深いテーマですね。具体的な課題としては、どのような点が挙げられますか?
矢藤氏:一つは、基礎学力や規範意識に差がある多様な人材が保育の現場に入ってくる中で、どう育成し、良い保育を提供できる組織を作るかという点です。また、離職率の高さやモチベーションの低下も大きな課題です。
KA:そうした課題に対して、具体的にどのような解決策を提案されているのでしょうか?
矢藤氏:現場でのOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を強化することが一つの方法です。ベテラン保育士がリーダーシップを発揮しやすい環境を整え、後輩保育士を育てる仕組みを作ることが重要です。また、研修プログラムの充実や、保育士同士が相互に学び合える場を提供することも効果的です。
保育士人材確保の高い必要性
KA:保育士の養成についても課題が多いと伺いましたが、具体的にはどのような点が問題とされていますか?
矢藤氏:一時期、需要の増加に応じて、保育士養成校の数がすごい勢いで増えました。ところが今、保育の必要性がある程度落ち着いてきた一方、18才人口が減ってきたこと、保育のような対人援助の仕事の人気が低下していると見られることにより、保育者になりたいという人は減少傾向にあります。それに伴い養成校の数にも微減傾向が見られます。また、養成校の教育の質にはばらつきがあります。授業や実習が学生の成長を十分に支えられているか、教員の質が十分確保されているかなどが課題です。また、保育士資格の取得が比較的容易であるため、その社会的地位や専門性の向上が求められます。
KA:養成校の質を向上させるためには、どのような取り組みが必要だとお考えですか?
矢藤氏:養成校の教員が互いに学び合い、研修や研究活動を通じて教育の質を高めることが必要です。また、保育士の専門性を段階的に向上させるために、資格制度そのものの改革も求められます。
例えば、看護師には「専門看護師」のような上位資格がありますが、保育士にはそうしたグレードがありません。ジェネラリストとして広く学んだ人を基礎資格とし、乳児保育や障害児保育、子育て支援などに特化したスペシャリストを上位資格として位置付けることが一つの方法です。こうした階層化された資格制度を導入すれば、保育士の専門性や魅力が高まり、処遇の改善にもつながると考えています。
短期大学と四年制大学の違い:教育の質と時間
KA:保育士養成課程の期間に応じて専門性が変わるというお話がありましたが、具体的にはどういった違いがあるのでしょうか?
矢藤氏:二年制が基本の短期大学や専門学校では、限られた期間内に非常に多くの単位を取得する必要があるため、時間の余裕が乏しく、詰め込み型の教育になりがちです。一方で、四年制大学では時間をかけて学ぶことで、学生は興味のあることを自分なりに学んだり、保育現場に多く関わったり、あるいはアルバイトなどを通じて幅広い視野を養うことができます。
たとえば、短期大学では通常62単位で卒業できますが、保育士養成課程では68単位が必要です。幼稚園教諭の免許も合わせて取得する場合、養成校にもよりますが、90単位以上に及ぶこともあり、負担が大きいのが現状です。そのため、学業が厳しすぎて中退率が高まる養成校もあります。四年制大学もいろいろですが、一般的にはゆとりがある分、じっくりと保育について学ぶことができる環境がより整っているといえます。
不適切な保育を防ぎ、良い保育を実現する
KA:保育士による子どもへの不適切な保育が社会問題となったケースもありますが、対策はどのように進められていますか?
矢藤氏:不適切な保育を防ぐため、国や保育団体がガイドラインを作成し、研修を実施しています。しかし、現場ではまだ十分に認識されていない部分もあります。
重要なのは「悪い保育を防ぐ」という消極的な姿勢ではなく、「良い保育を実現する」という積極的な取り組みです。保育士同士が学び合い、例えばチェックリストなどを活用して保育の質を向上させることで、こうした問題の防止につながると考えています。
AI・ICTの活用と保育現場の未来
KA:AIやICTの導入が進んでいますが、保育現場への影響についてどうお考えですか?
矢藤氏:保育士不足を背景に、業務の効率化が求められています。例えば、窒息防止センサーの導入や、業務記録のICT化が進んでいます。直接体験では得られない学びを得ることも可能になりますただ、現場ではAIに対する抵抗感もあり、導入には時間がかかるでしょう。
未来のリーダー層へ向けたメッセージ
最後に、矢藤教授はこう語ります。
矢藤氏:子どもの権利の保障と成長の保障は、社会全体の課題です。地方であっても過疎地であっても全国どこででも質の高い保育を受けられる体制を整えるためには、多くの若いリーダーの力が必要です。志を持ち、社会に貢献したいと考えるみなさんが、保育という分野に目を向けて、仲間に加わってくださることを期待しています。
KA:貴重なお話をありがとうございました。