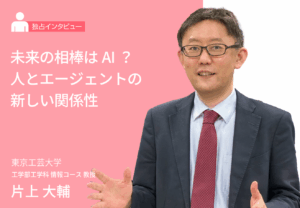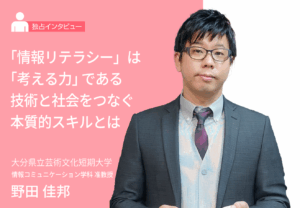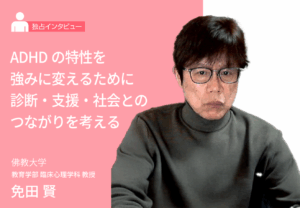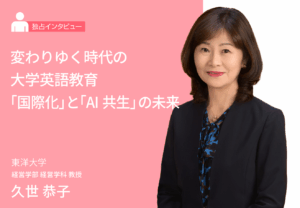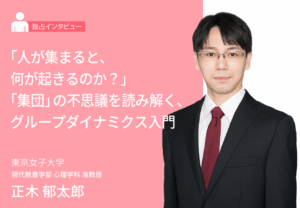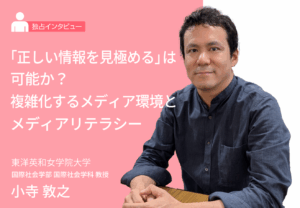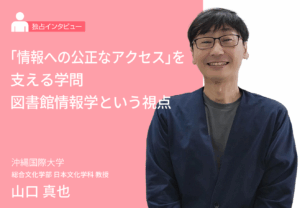「うちの子」「家族の一員」など、 現代社会で当たり前のように使われるようになったこれらの言葉は、ペットと人との関係が変化したことを物語っています。
かつて番犬や家畜として屋外で飼育されていたペットは、今や家の中で暮らし、高度な医療サービスを受け、さらには供養までされる存在となりました。
この変化は、単なるペット飼育の形態の進化だけにはとどまりません。人々の絆のあり方が変容する現代社会において、ペットの存在は新しい「家族」の形を象徴しています。このペットと人との関係性の変化について、中央大学の山田昌弘教授に伺いました。

山田 昌弘
中央大学 文学部 教授
【biography】
1957年東京生まれ、1981年東京大学文学部卒。1986年同大学院社会学研究科博士課程退学。東京学芸大学教授を経て、2008年より中央大文学部教授。現在、内閣府・男女共同参画会議民間議員、東京都社会福祉審議会委員等を務める。
専門、家族社会学。愛情やお金を切り口として、親子・夫婦・恋人などの人間関係を社会学的に読み解く試みを行っている。「学卒後も基礎的生活条件を親に依存している未婚者」の実態や意識について分析した著書「パラサイト・シングルの時代」(ちくま新書、1999年)は話題を呼んだ。1990年代後半から日本社会が変質し、多くの若者から希望が失われていく状況を「希望格差社会」(ちくま文庫)と名づけ、格差社会論の先鞭をつけた。結婚活動、略して「婚活」の造語者でもある。著書は『家族ペット』(ディスカヴァー21)『婚活時代』(共著・ディスカヴァー21)『日本はなぜ少子化対策に失敗したのか』(光文社新書)など多数。近著に『希望格差社会、それから、幸福に衰退する日本の20年』(東洋経済新報社)読売新聞人生案内回答者を2008年より続けている
ペットが「家族」になる時代
ナレッジアート(以下KA): まず初めに、山田先生が現在研究されている分野について教えていただけますか。
山田氏: 私の研究テーマは、現代社会における愛情の向け先の変化についてです。伝統的な家族という枠組みに閉じ込められていた愛情が、現在では様々な対象に分散しているという現象に注目しています。
少子化や家族関係の変化により、従来の家族を作ることが難しくなり、また壊れやすくなっている現状があります。その中で、人々が愛情をどのように向け、どのような形で親密な関係を築いているのかを研究しています。その1つの方向性として、ペットが重要な対象となっています。
KA: ペットの家族化に関する研究の歴史について教えていただけますか?
山田氏: 私は1989年に「ペットは家族か」というテーマに取り組みはじめ、2004年には「家族ペット」(サンマーク出版→文春文庫→ディスカヴァー21)という本を出版しました。このテーマについては、何十年も前から継続的に研究を行っています。ペットの家族化は、単なる動物の飼育を超えた現象であり、現代社会における新しい家族の形を象徴するものです。
また、私の研究はペットだけにとどまりません。推し活などバーチャルな関係性や、キャバクラ、ホストクラブといった人間同士の親密さを満たす新しい形態についても取り組んでいます。これらの現象は、現代社会における愛情や親密さの多様化を示しており、ペットはその中でも特に重要な要素の1つです。
ペットと人間関係の境界線
KA: ペットを家族と見なすことと、見なさないことでは、どのような違いがあるのでしょうか?
山田氏: 最も重要な違いは、ペットを「個性を持った存在」として認識しているかどうかです。物は取り替えが可能ですが、ペットは取り替えが不可能な存在と見なされます。この「取り替え不可能性」が、ペットと飼い主の間に特別な絆を生み出します。
例えば、物が壊れた場合は新しいものに取り替えることができますが、ペットが亡くなった際には、すぐに別のペットを迎えようとはなりません。この点は、家族の喪失と同じ感覚に近いものがあります。さらに、ペットの場合、人間関係以上に強い絆が生まれることもあります。これは、ペットが無条件の愛情を提供する存在であることが大きな要因です。
KA: ペットとの関係は、人間関係とどのように異なるのでしょうか?
山田氏: 人間関係、特に夫婦や恋人関係では、相手も選択権を持っています。つまり、相手が関係を終わらせることも可能です。しかし、ペットの場合、飼い主が捨てない限り、ペットは飼い主を選び続けます。この一方的な選択の構造が、ペットとの関係を特異なものにしています。
20年前に独身男性を対象に行ったインタビュー調査では、「女性は裏切るけど、ペットは裏切らない」という発言がありました。このような意識から、家族よりもペットの方が「家族らしい」と感じる人が増えているのです。
また、ペットとの関係には「相手を幸せにすることが自分の幸せにつながる」という循環的な関係性が生まれやすい特徴があります。これは、家族的な関係の本質とも言えるでしょう。ペットはこのような関係性をたいへん築きやすい存在であり、飼い主にとって精神的な安定や癒しを提供する重要な存在となっています。
ペットの地位向上が示す社会の変化
KA: 昔と比べて、ペットの家族化に関する変化はどのようなものがありましたか?
山田氏:まず、ペットの飼育頭数や飼育率自体は、過去数十年で大きく変化していないというデータがあります。しかし、変化したのはペットとの関係性や接し方です。
最も顕著な変化は、かつては家畜や番犬として屋外で飼われていたペットが、現在では家の中で「家族の一員」として扱われるようになったことです。この変化は、ペットに対する支出の増加にも表れています。
ペットの医療費や健康管理にかける費用は大幅に増加しており、人間の家族と同じようにペットの健康や生活の質を重視する傾向が強まっています。
例えば、ペットが寒さを感じないように暖房設備を整えたり、病気になれば高額な治療費を惜しまず支払ったりするケースが増えています。また、ペットが亡くなった後も葬儀や供養を行うなど、ペットを単なる動物ではなく「かけがえのない存在」として扱う文化が広がっています。
これは、ペットが「所有物」から「家族」へと位置づけを変えた象徴的な変化と言えるでしょう。
KA:このような変化の背景には、どのような要因があるのでしょうか?
山田氏:背景にはいくつかの社会的要因が挙げられます。まず、現代の家族関係の変化が大きな影響を与えています。少子化や晩婚化、離婚率の増加、さらには核家族化の進行により、従来の家族の形が変わりつつあります。これに伴い、人々が愛情や癒しを求める対象としてペットが注目されるようになりました。
現代社会では人間関係が複雑化し、ストレスや孤独感を抱える人が増えています。その中で、ペットは裏切らない存在として、シンプルで純粋な愛情を提供してくれる存在としての価値が高まっています。
ペットとの関係は、現実の家族関係が壊れやすい時代において、安定した心の拠り所となっているといえるでしょう。
また、経済的な側面も見逃せません。ペット関連市場の拡大や、ペットフードや医療サービスの高度化により、ペットを「家族」として扱うことがより現実的になりました。
さらに、SNSやメディアを通じてペットの家族化が広く共有され、社会的な認識として定着してきたことも一因です。
KA: ペットの家族化が進むことで、社会にはどのような影響があるとお考えですか?
山田氏:ペットの家族化は、個人や家庭だけでなく、社会全体にも影響を与えています。1つは、ペット関連産業の成長です。ペットフードや医療、保険、さらにはペット葬儀やペットホテル、ペットとの旅行ツアー、といったサービスが拡大し、経済的な波及効果を生んでいます。
また、ペットを家族として扱う文化が広がることで、動物福祉の意識も高まりました。ペットの権利や福祉を守るための法律や制度の整備が進み、ペットを取り巻く環境が改善されています。
一方で、ペットを飼うことができない人々との間で意識のギャップが生じることも課題です。
例えば、ペットを公共の場に連れて行くことや、ペットにかける費用の増加が、他者との摩擦を生むケースもあります。このような課題に対して、社会全体での理解と調整が求められるでしょう。
KA:ペットとの関係性は今後、どのように進化していくとお考えですか?
山田氏:今後もペットの家族化は進むと考えられますが、さらに「社会の一員」としての位置づけが強まる可能性があります。例えば、ペットと共生するための住宅設計や、ペットと一緒に楽しめる観光地の整備など、ペットを含めた社会全体のインフラが進化していくと考えられます。
また、AIやテクノロジーの進化により、ペットの健康管理やコミュニケーションがさらに高度化することも期待されます。ペットは単なる癒しの存在ではなく、私たちの生活を豊かにするパートナーとして、より重要な役割を果たしていくでしょう。
ペットがもたらす経済と福祉の影響
KA: ペットの家族化における現状の問題点と、その改善策について教えてください。
山田氏: 現在、主に二つの社会的な課題が浮かび上がっています。
一つ目は少子化との関連です。特に独身のキャリアウーマンなどが、ペットを飼って満足してしまい、結婚を考えなくなるというケースが見られます。ただし、これは必ずしも改善すべき問題とは言えません。むしろ、現代社会における新しい生き方の選択として捉えることもできます。
二つ目は、より深刻な問題として、高齢者のペット飼育の課題があります。多くの高齢者が「自分が先に死んでしまうと、ペットが不幸になる」という不安から、ペットを飼うことを躊躇しています。私自身も67歳になり、同じ悩みを抱えています。以前飼っていた猫は19年生きていました。高齢になってからペットを飼うことへの不安は大きいのです。
この問題に対して、最近では保護猫・保護犬団体が「飼い主が亡くなった後は、こちらで引き取ります」という保証をつけたサービスを始めています。しかし、このようなサービスはまだ北海道など一部の地域に限られています。
さらに、ペットの介護や医療の費用の問題もあります。ペットの養老院や医療費は高額で、保険も損害保険として扱われるため、人間の医療保険のような充実したケアを受けることが難しい状況です。
ペット共生社会の未来図
KA:ペットの家族化が進む中で、今後の展望について教えてください。
山田氏:ペットの家族化が進む中で、人間向けのサービスをペット向けに展開する動きがさらに広がると考えられます。例えば、ペットロス専用のカウンセラーや、ペット用の供養を行うお坊さん、ペットと一緒に入れる墓地などが既に増加傾向にあります。また、ペットの養老院や幼稚園、保育園といった、人間向けサービスのペット版も充実してきています。
これらのサービスは、ペットを単なる「飼い主の所有物」としてではなく、家族の一員として扱う意識の高まりを反映しています。特に、ペットの高齢化が進む中で、介護や医療の需要が増加しており、これに対応するサービスの拡充が求められています。例えば、ペットのリハビリ施設や、認知症を患ったペットのケアを専門とする施設などが今後注目されるでしょう。
ただし、猫カフェのような一時的な癒しを提供するサービスは、ペットの「家族化」という観点からは異なる方向性だと考えています。重要なのは、ペットと飼い主の継続的な関係性を支えるサービスです。例えば、ペットの健康管理をサポートするアプリや、飼い主が不在時にペットの世話を代行するサービスなどが挙げられます。
さらに、ペットを通じた地域コミュニティの形成も期待されています。東京都では、孤立化対策としてペットの活用が提言されており、犬の散歩をきっかけに地域住民同士が交流する仕組みが注目されています。こうした取り組みは、ペットの家族化が単なる個人の癒しを超え、社会的な課題解決にも寄与する可能性を示しています。
ペット市場で成功するための鍵
KA:起業を考える学生へのアドバイスをお願いできますか?
山田氏:新規サービスを考える際には、人間向けの既存サービスをペット向けにアレンジする視点が非常に有効です。ただし、現在では多くのサービスが既に提供されているため、差別化が重要になります。
例えば、ペットシッターに訓練サービスを組み合わせたり、ペット養老院と保険を組み合わせたりするような複合的なサービスが考えられます。また、ペットテック(ペット向けのIoTデバイスやアプリ)を活用したサービスも、今後の成長が期待される分野です。GPS機能を搭載したウェアラブルデバイスや、ペットの健康管理を支援するアプリなどは、既に市場で注目されていますが、さらなる進化の余地があります。
特に注目すべき点は、ペットの家族化が単なるビジネスチャンスを超えて、社会問題の解決にも貢献できるということです。例えば、高齢者向けには「引き取り保証付き」のペット飼育支援サービスが新しいニーズとして生まれています。また、孤立化対策としてペットを活用する取り組みも進んでおり、ペットを通じた地域コミュニティの形成が期待されています。
若い起業家には、こうした社会貢献の視点を持ちながら、新しいサービスを考えていってほしいと思います。ペットの家族化は、単にペットビジネスの拡大だけでなく、人々の孤立化や高齢化といった社会問題に対する一つの解決策としても機能し得ます。個人の幸せと社会課題の解決を両立させるサービスが、今後ますます重要になっていくでしょう。