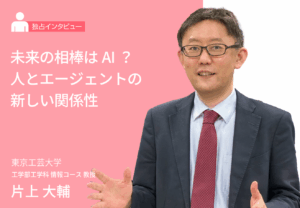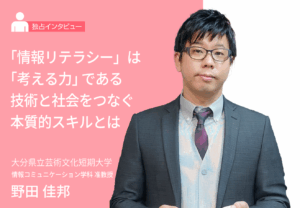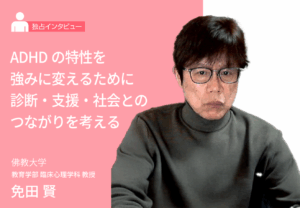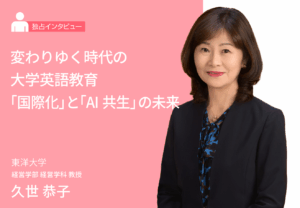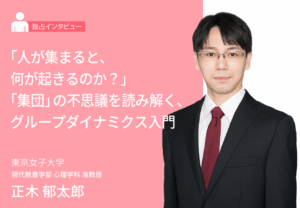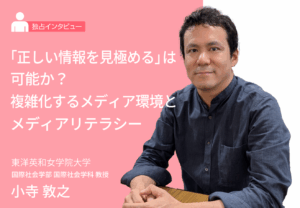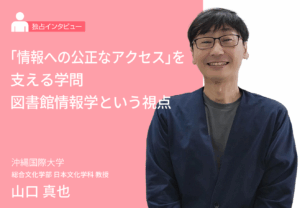教育心理学とは、教師を目指す人にだけ関係のある学問だと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、実際は教育現場だけでなく、職場での人間関係や自分の人生を考える上でも役立つ学問です。
そこで今回は、法政大学の田澤教授に教育心理学とはどのような学問なのか、どのような場面で日常生活に活かせるのかお話を伺いました。

田澤 実
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
【biography】
2001年 中央大学文学部教育学科心理学コース 卒業
2003年 中央大学大学院文学研究科心理学専攻修士課程 修了
2007年 中央大学大学院文学研究科心理学専攻博士後期課程 単位取得退学
2010年 中央大学大学院文学研究科より博士号(心理学)取得(博士論文タイトル『大学生のキャリア発達の心理学的研究』)
2007年 法政大学キャリアデザイン学部 助教。専任講師、准教授を経て、2020年より教授
教育心理学は教育に関するあらゆる場面で役立つ
ナレッジアート(以下KA):まず、教育心理学とはどのような学問なのでしょうか?
田澤氏:教育心理学とは、人間の学びや教育のプロセスを心理学的な観点から研究する学問です。この分野を理解する上で、大きな基盤となるのは「子どもの心と体の発達」、いわゆる心身の発達です。
教育心理学では、学びのプロセスを支える土台として、この発達の理解が欠かせません。これは発達心理学や生涯発達心理学とも重なる部分がありますが、教育心理学では特に「学び」との関連性が重要視されます。そのうえで、私は3つの点が柱になると考えています。
KA:心身の発達が基盤となるのですね。それでは、柱となる3つの要素についてお聞かせいただけますか。
田澤氏:まず、一つ目は「人がどのように学ぶのか」です。これは、学習者が知識やスキルをどのように習得するのかを研究する分野です。例えば、記憶の定着メカニズムや問題解決能力、学習意欲を高める動機づけの研究があります。また、条件づけを含む学習理論もここに含まれます。
二つ目は「学習環境をどう整えるか」という点です。学習が行われる環境の整備は、学びの成果に大きく影響を与えます。例えば、物理的環境としての座席配置や、心理的環境としての教師と生徒の関係、クラスの雰囲気などが重要な要素になります。スクールカウンセリングや教育相談も、この分野に関係しています。
三つ目は「教育現場で実践される指導方法の研究」です。例えば、授業設計の工夫や、子どもたちの理解を深めるための教授法などが含まれます。効果的な指導法を探ることは、学習成果の向上につながる重要な研究テーマの一つです。
KA:教育心理学の研究は、学校の先生を目指す人だけが対象なのでしょうか?
田澤氏:いいえ、決してそうではありません。教育心理学の知見は、学校現場だけでなく、人材育成や企業研修、さらには家庭教育の分野にも応用できます。つまり、教育に関わるあらゆる場面で役立つ学問なのです。
教育心理学は部下の育成や子育てにも活かせる
KA: では次に、教育心理学を学んだ後、日常生活にどのように活かせるのかについて教えてください。
田澤氏: 教育心理学には、人の学びと成長を支援するための多くのヒントが詰まっています。子どもに興味がないから関係ないと考える人もいるかもしれませんが、教育心理学は「人の学びと成長」に関する学問です。誰にとっても役立つものなんですよ。
KA: 具体的には、どのように日常生活に活かせるのでしょうか?
田澤氏:私は大きく三つの点で活かせると考えています。
まず一つ目は、「自己理解や自己成長」です。例えば、自分がどのように効率よく学べるのか、具体的には試験前の勉強方法を考える際にも役立ちます。また、動機づけの研究は、生徒への動機づけだけでなく、自分自身のやる気を維持するためにも応用できます。教育心理学を学ぶことで、自分に合った学び方を見つけ、自己成長につなげられるのです。
二つ目は、「人間関係の向上」です。対人関係の発達やグループ内のコミュニケーションについて学ぶことで、家庭や職場での人間関係を円滑にするヒントが得られます。発達の理解を深めれば、相手の成長プロセスを知り、より適切な関わり方ができるようになるでしょう。
三つ目は、「子どもの育児や関わり」です。教育心理学を学ぶことで、子どもがどのように発達するのかを理解し、適切なサポートができるようになります。これは将来、教師になる人だけでなく、親として子育てをする際にも役立ちますよね。実際、学生の中には、「将来の子育てに生かしたい」という理由で教育心理学を学ぶ人も多いです。
KA: なるほど。教育心理学は、学びだけでなく、自己成長、人間関係、子どもとの関わりなど、生活のあらゆる場面で活かせる学問なのですね。
仕事面では教師や子育てが役立つとおっしゃっていましたが、多くの社会人は上司と部下という関係を持っています。上司として部下に教える場合、教育心理学がどう役立つのでしょうか?
田澤氏:教育心理学と直接関わる部分もあれば、産業・組織心理学の方が適している場合もあります。
例えば、記憶や動機づけについてだけ取り上げても十分に関わります。記憶心理学は、人間がどのように記憶を処理し、覚えやすいものや覚えにくいものがあるかといった点を学びます。これを理解しておくと、学習理論に基づいて教える方法を意識することができ、例えばご褒美や罰を使って学習を強制するのか、既存の知識を活用して類推を促すような方法を取るのかなどを考えることができます。自分の教え方がどの学習理論で説明できるかを知っておくことが大切です。
また、動機づけに関して学んでおくことも重要です。例えば、内発的動機づけという言葉を耳にする機会も多いと思いますが、これは理想と現実が一致しないこともあります。
自分が教えている立場であれば、相手には内発的にやってもらいたいと思っていても、実際は他人に言われてやっていることがありますよね。外発的な動機づけも内発的な動機づけも理解すれば、競争や協力を上手く利用できるようになることがあります。たとえば自分がライターを目指す場合、いきなりライターとしての文章を書くことそのものが目的となるような内発的動機づけになることは稀だと思います。そこで、仲間と一緒にやって競争心や協力心が刺激された際に、「あの人もやっているから私も頑張ろう」として学びが深まることがあります。このようなことは職場にも応用可能です。社員同士の協力や努力を促進することもあります。
仕事の現場ではすべてがうまくいかないかもしれませんが、動機づけや記憶に基づいた関わり方ができると、部下に対して「どうしてできないんだ」といった否定的な態度ではなく、少し余裕をもって支援ができるようになるかもしれませんね。
KA: 確かにそういった面で教育心理学を活かせるのですね。仕事と子育てで教育心理学を活かす場面には、大きな違いがあるのでしょうか?
田澤氏:大きな違いがあると思います。例えば「親は教師になれるか?」という問題がありますが、親が完璧な学習理論に基づいて教えることができても、子どもがその学びを受け入れたくないこともありますよね。親が教師のように指示を出して、「宿題をこうやりなさい」ということはできるかもしれませんが、家庭でそれをやりすぎると、子どもが逃げ場を失うことになりかねません。
また、動機づけに関しては「アンダーマイニング効果」というものがあり、勉強をしようと思っていたのに「やりなさい」と言われるとやる気が失われることがあります。自分ができることと、実際にやることは必ずしも一致しません。できるからこそやらないこともあるという心の余裕が大事です。
そのため、家庭で仕事のようにガンガンとできることを増やすことを持ち込むと、子どもにとっては恐怖になり、逃げ場がなくなります。家庭と仕事ではアプローチが異なり、適切なバランスを見つけることが重要です。何でも仕事で学んだことを使おうとするのではなく、家庭には家庭に合った柔軟な対応が必要だということを覚えておくべきです。
教育心理学が現場に浸透しきっていない現実も
KA: では次に、教育心理学における課題点とその課題点に対する改善策について教えていただきたいです。
田澤氏:これは個人差が大きいテーマですが、私の関心事を踏まえて三つの課題を挙げます。
まず一つ目は「研究成果と現場のギャップ」です。教育心理学の研究は蓄積されていますが、それが実際の教育現場に十分に反映されていないという問題があります。最新の知見は学会やジャーナルで発表されますが、すでに教師になっている人にはなかなか届かないことも多いのです。かつては教員免許更新講習制度がありましたが、現在は廃止されました。
これに対する改善策としては、研究者と現場が密接に連携し、専門用語を噛み砕いた情報発信を行うことが重要です。教員向け研修や保護者講座を充実させ、科学的な知見を分かりやすく伝える機会を増やすことも有効です。
二つ目の課題は「個別ニーズへの対応と支援体制」です。学習困難を抱える子どもたちの支援が十分でないという問題があります。例えば、不登校の増加や、特別支援が必要な子どもへの対応が求められています。
これに対する改善策として、特別支援教育や臨床の専門家との連携を強化し、多方面から子どもをサポートする体制を整えることが挙げられます。また、ICTの活用も重要です。従来、高額な機器を使って支援していたものが、現在ではスマートフォンやクラウド技術を活用することで、より手軽に支援が可能になっています。こうした技術を活用し、個別の学習者に適した支援方法を導入することが求められます。
三つ目の課題は「学力評価の多様化」です。従来のテストや偏差値だけに頼る評価方法では、多面的な学力や人間性を十分に捉えることができません。大学入試においても、一般試験だけでなく、推薦入試や総合型選抜など多様な評価方法が導入されています。
さらに、近年では「探求学習」の重要性が高まっています。これは、学習者自身がテーマを決め、試行錯誤しながら学ぶプロセスを重視する学習方法です。しかし、これを適切に評価する方法はまだ確立されていません。単なるポートフォリオ評価だけでなく、「問いを立てる力」そのものを評価するスタイルに変えていくことが重要ではないかと考えています。
KA: ありがとうございます。私自身、私立大学の一般入試の受験者が減少し、面接で評価される機会が増えていると聞いたことがあります。この点について、都会と地方で「学校で頑張ってきたこと」を作る機会に差があるのではないかと感じているのですが、実際に地方格差というものは存在するのでしょうか?
田澤氏:確かに、留学経験や部活、文化祭など、何を評価するかは様々です。特に派手な活動が注目されることはありますが、重要なのはその活動を通してどんな役割を果たし、どんなことを学んだのか、そして、その学部で学ぶことによって、将来にどう役立つのかという点です。多くの大学では、このような枠組みで面接や選考が行われます。
都市部と地方の違いについても触れると、地方においては、財力の差が影響を与えていることは確かです。例えば、都心の高校生が海外留学を経験し、その経験を武器にすることができますが、地方ではそのような機会が限られていることもあります。ただ、お金をかけて派手なイベントを経験したからといっても、その学部に入る際に必要な学びになっているとは限りません。経験したことだけで勝負するのではなく、経験したことを言語化し、いかに学びにつなげるかが大事なのです。
また、大学の入試においては、特に地方では推薦入試が多くなり、一般入試が減少しているケースもあります。私立大学では顕著です。地方に住む様々な高校生を地方の大学が受け入れるという役割を果たしている場合もあるようです。地域によっては大学進学率が増えている中で、学生の多様化が進んでいるという現状もあります。
大学生という存在も一様ではなく、多様な背景を持った学生が増えており、この点を教育心理学でも考慮し、さまざまな教育現場の違いを理解することが重要だと思います。
オンラインとオフラインの柔軟な使い分けが肝となる
KA: 教育心理学にはまだまだ課題があるのですね。それでは、その課題を踏まえて教育心理学における今後の展望について教えていただけますか。
田澤氏:本当に、デジタル技術の進歩と社会変化のスピード、この二点に集約されると思います。今の状況を見ても、米国での変化が劇的で、それが世界規模で影響を与えているわけですが、それ以前の話としても、デジタル技術の発展は著しいですね。
コロナ禍を経て、オンライン教育の普及が進みましたが、単なるオンライン授業にとどまらず、ICTと学習科学の融合が大きなテーマになっています。例えば、生成AIの登場により、大学では「生成AIを使ってレポートを書いてはいけません」といったガイドラインが出ています。しかし、実際には学生たちはすでに活用しています。
昔は紙の資料やインターネットを使って調べた内容をまとめてレポートを書いていましたが、今では生成AIに指示すれば、それなりの回答が短時間で得られます。この状況は、「インターネットのコピペとどう違うのか」という議論にもつながりますね。重要なのは、生成AIの使用が学びを阻害しないようにすることです。
KA: ほかに、学びとの関わりが深いデジタル技術の進歩には、どのようなものがあるのでしょうか。
田澤氏:例えば、技術の発達により、自動文字起こし機能や瞬時の要約機能が非常に優れたものになっています。すでに大学でも対面授業が戻っていますが、今でも部分的にはオンデマンド配信をする授業の回もあります。学生は授業を受けずとも、文字起こし機能を使って90分の講義を瞬時に要約し、それを活用してレポートを書くことが技術的には可能になっています。もちろん、実際にやるかどうかは別ですが。
こうした変化が学習のモチベーションにどう影響を与えるかが重要な課題です。「90分間対面で授業を聞くよりも、後で要約を読んだ方が効率的では?」という考えが広まれば、対面授業の意義自体が問われることになります。人間が人間に対して対面で講義をする価値とは何か、生成AIが話す講義と何が違うのか、という問いが今後さらに重要になっていくでしょう。
この変化と関連して、多文化共生や障害の有無にかかわらず共に学ぶインクルーシブ教育の重要性が高まっているのもポイントだと思います。通信技術の発達によって、学ぶ環境さえ整えれば、学べる子どもの数が増えたともいえます。
また、教師は、一般の学生に対する指導だけでなく、学ぶことが困難な子どもたちに対する支援も求められるようになっています。能力の差がある学生同士がどのように相互理解を深めるかという課題もあります。
聴覚障害の学生支援の分野では、以前からノートテイクの仕組みがありました。これは教員の話をリアルタイムでパソコンに打ち込み、耳の不自由な学生に伝えるというものです。今ではほぼ全ての学生がノートパソコンを使用しているため、学習支援の方法も変わってきています。自動文字起こしや要約機能が進化したことで、学ぶ環境の選択肢が広がっています。
KA: 特に高校生や大学生にとって、AIの活用は避けられない課題ですね。一方、社会人は教育心理学とどのような場面でかかわっていけるのでしょうか?
田澤氏:社会人が学び直すリスキリングの需要が高まっており、成人学習の分野がますます重要になっています。特に、社会人大学院生の数が増えていることからも、学び直しのニーズが拡大していることがわかります。
企業の研修としての学びだけでなく、個々の関心に応じた学びをどう支援するかが今後の課題です。教育心理学は、こうした学びの支援にも大きく関わる分野です。
KA:職場ではコロナ禍を契機としてリモートワークが普及しましたが、アフターコロナでは出社を必要とする企業が多くなったようです。教育現場では、コロナ禍とアフターコロナでの違いがどのように現れているのでしょうか?
田澤氏:もともと、コロナ以前からICTの活用や、小学校での一人一台ノートパソコンの導入などが進んでいました。つまり、コロナ禍によってそれらの動きが前倒しになった部分があります。例えば、大学でもLMS(学習管理システム)を利用してPDFをアップロードするようなシステムは以前からありましたが、オンライン学習の大きな違いとして、Zoomを使った授業や会議が普及したことが挙げられます。
一方で、出社の問題に関しては、教育心理学の枠を超える部分もありますが、評価の問題が重要です。例えば、同じ人がオンラインで学びや作業をして生産性が高いことが分かっていても、それを評価する枠組みが従来の対面評価に基づいている場合、問題が発生することもあるでしょう。
これは学校現場や企業に共通する問題です。企業では、リモートワークが進んでフルリモートを許可する会社もあれば、「週1回は出社する」という方針に変わる場合もあります。このように急な変化があるため、企業側は納得できる評価システムを構築する必要があります。
特に、現在はアフターコロナの時期であり、大学生の中にはコロナ禍の影響でオンライン授業が中心だった世代も多く、これから就職活動をする学生にとっては、オンラインでできることへの理解が進んでいます。今後は、オンラインでの学びを活かす柔軟な働き方が求められるようになるでしょう。
KA:ありがとうございます。教育現場でも職場でも、オンラインでできること、対面でしかできないことを理解し、そのバランスをどう保つかが鍵となりそうですね。
教育心理学を学ぶ意義は、学生だけでなく社会全体に広がっているのだと実感できました。
田澤氏:その通りです。しかし、「私は子どもに興味がないので教育心理学は受けません」という学生もいます。これは非常にもったいないです。教育心理学は、子どもだけでなく、あらゆる学びの場に関わる学問です。
その魅力を伝えるためにも、より多くの人に教育心理学を学んでもらう機会を増やしたいですね。ガイダンスを通じて関心を持ってもらうのも一つの方法ですが、こうしたインタビュー記事で多くの人に知ってもらうのも大切な手段だと思っています。
身近な疑問と教育心理学を結び付けてみよう
KA: 教育心理学の勉強を検討している学生や社会人に向けてアドバイスをお願いします。
田澤氏:まずは身近な疑問から興味を広げることが大切だと思います。子どもがどのように学ぶのか、モチベーションはどこから来るのかといった疑問は、教育心理学においてよく取り上げられるテーマです。
こうした身近な疑問を出発点として、「関連する理論があるのか」「具体的な事例があるのか」といった形で学びを深めていくことが重要です。日常の些細な「なぜ?」を大切にし、それを学びの起点にするよう意識しましょう。
こうして教育心理学を学んだ先には、学校の先生だけではなく、教育関連の民間企業やスクールカウンセラーなど、さまざまなキャリアパスが広がっています。また、教育心理学は人材育成や研修にも役立つため、企業で働く際にも強みとなるでしょう。
「就職だけを考えると関係ないかもしれない」と思うかもしれませんが、就職後のキャリアを考えると、教育心理学の知識はさまざまな場面で活用されることが分かるはずです。
KA:人間の心身に関する学問なので、直接教育と関係ない仕事をしていても活かせる場面はありそうですね。教育心理学を学ぶにあたって、ほかに勉強しておいたほうがいいことはありますか?
田澤氏:教育心理学に関心を持ったら、他の心理学分野にもぜひ関心を持ってほしいと思います。例えば、生涯発達心理学や認知心理学は、教育心理学と密接に関連しています。
また、「臨床心理学やカウンセリングに興味があるが、教育心理学は関係ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、実際には学習理論がカウンセリングにおいても重要な役割を果たします。例えば、カウンセリングでは「強化」という概念が大切になります。教育心理学における学習理論の「強化」を理解していると、カウンセリングにおいて「この概念がこういう風に使われるのか」と、より深く理解できるようになりますよ。
KA:教育心理学を取り巻く環境について理解でき、教育心理学に興味がわきました。今後、教育心理学の重要性は高まっていきそうですね。
田澤氏:お分かりの通り、社会や学習環境は刻々と変化しています。そのため、教育心理学の視点はますます重要になっていくと考えています。「教育心理学は、学校の先生が子どもたちに教えるための学問」という伝統的な見方をする方もいるかもしれませんが、変化の激しい現代だからこそ、教育心理学の理論を押さえた上で今後のことを考えることが求められています。
KA:本日は貴重なお話をありがとうございました。