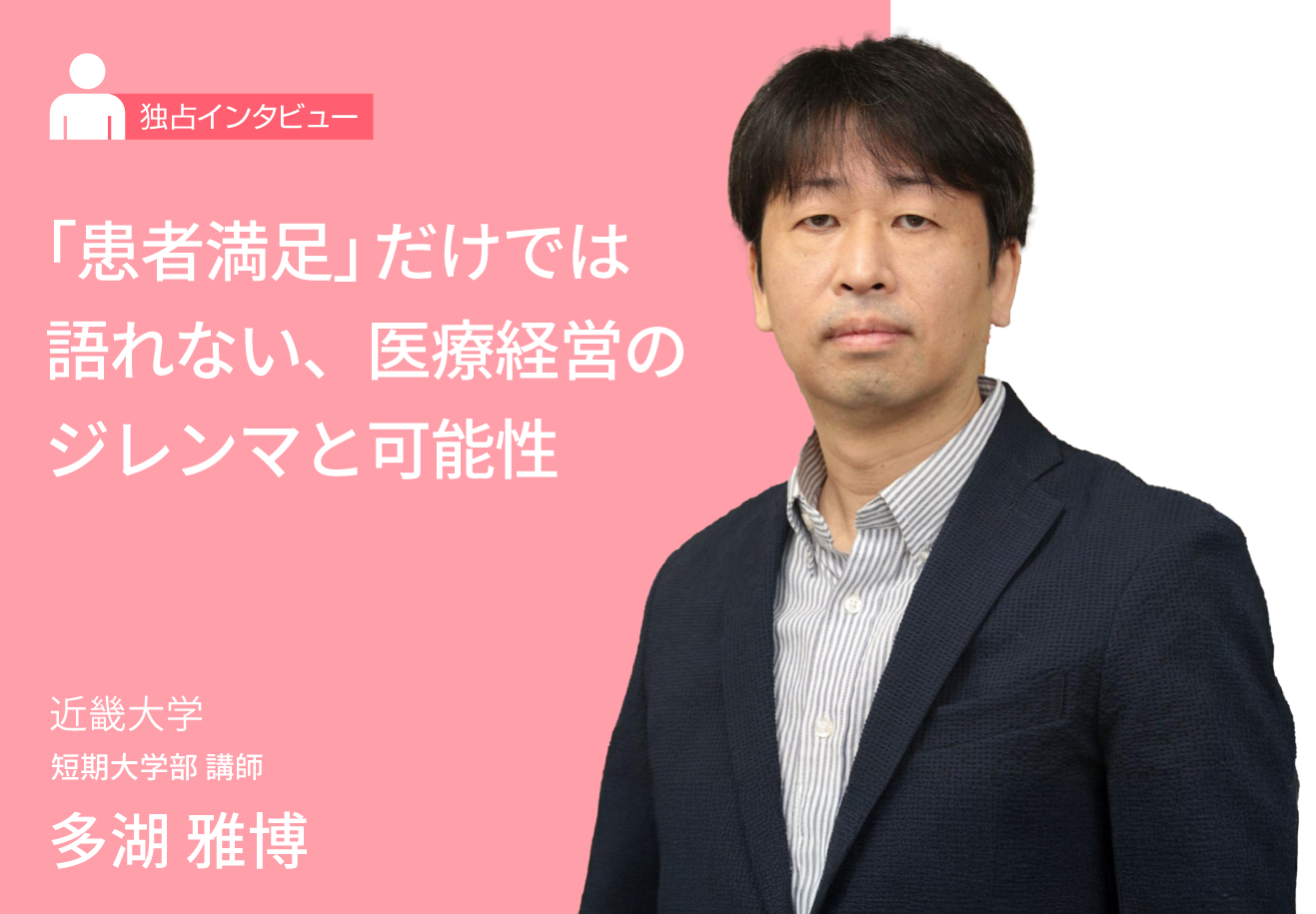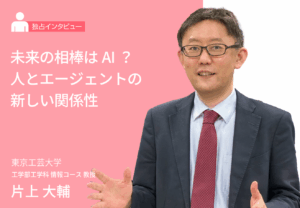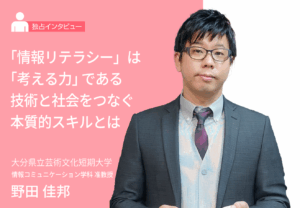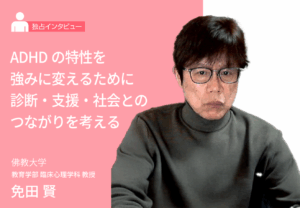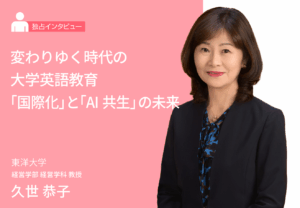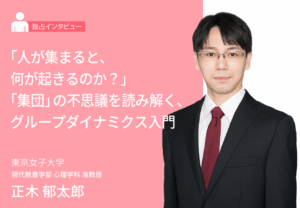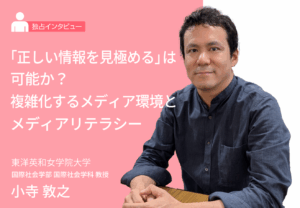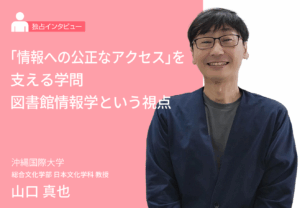少子高齢化、医療財政の逼迫、医療人材の確保と定着など、現代の日本の医療現場は、かつてない課題に直面しています。
そうした中で、今あらためて注目されているのが「医療経営」という視点です。
今回は、近畿大学の多湖雅博先生に、医療経営の基本的な構造から現場の課題、今後の展望に至るまでお話を伺いました。
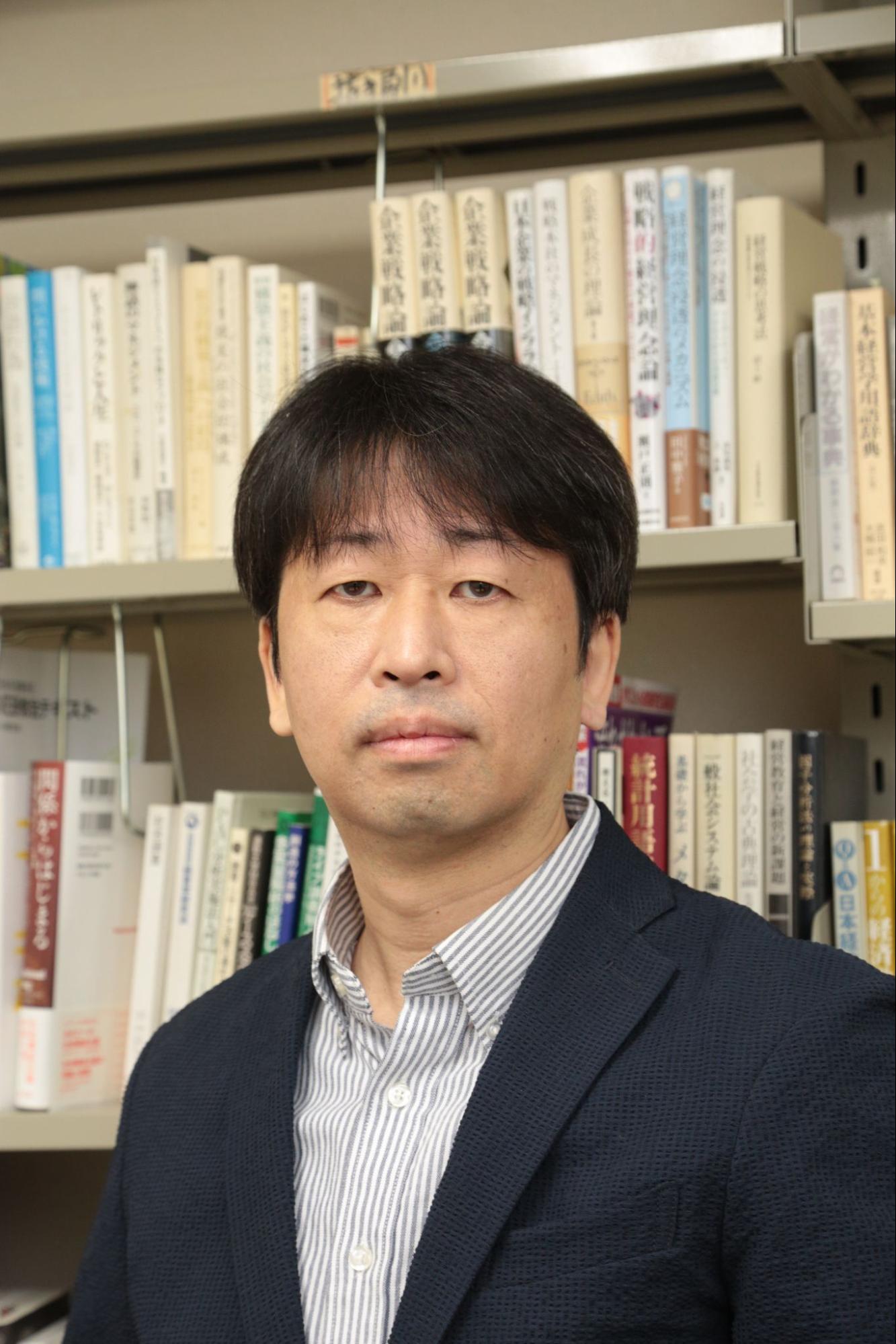
多湖 雅博
近畿大学 短期大学部 講師
【biography】
医療機関を対象とした組織開発を中心に、マネジメントやリーダーシップ、メンタルヘルスなどについて研究しており、働く皆さんがWin-Winの関係を築ける組織を経営学の視点から考察している。著書に『経営理念・経営ビジョン/経営戦略』(日本医療企画)、『職場の経営学:ミドル・マネジメントのための実践的ヒント』(中央経済社)、『対話型組織開発(AI)を用いた活き活き社員のつくり方』(パブファンセルフ)などがある。
制度と人材の視点から見る医療経営の特徴とは
ナレッジアート(以下KA):まず初めに、医療経営の仕組みについて教えていただけますでしょうか。
多湖氏:医療経営という言葉が指す範囲にもよりますが、一般的には「通常の企業経営と医療経営はどこが違うのか」といった点がよく話題になります。
大きな違いとしてよく挙げられるのは、制度的な要素が非常に強く影響するという点、そしてもう一つが「人」に関する部分、すなわち人材マネジメントの比重が非常に大きいという点です。これは、他の業種と比べて際立った特徴だと思います。
KA:なるほど。制度的な話については、どういった点が関係してくるのでしょうか。
多湖氏:基本的なところからお話ししますね。
日本には「国民皆保険制度」があります。保険証を提示すれば、全国どこでも医療機関で一定の割合で医療サービスを受けられます。最近ではマイナンバーとの統合も進んでいます。
そして、医療の価格、つまり診療報酬は国によって定められています。どんなに経験豊富な医師でも、免許を取りたての医師でも、同じ診療内容であれば、患者が支払う金額は同じです。つまり、保険診療の範囲においては、全国どこでも料金に差が出ないように設計されているのです。
一方で、美容整形などの自費診療に関しては保険の対象外であり、価格設定は自由です。ですが、一般的な医療機関での収入は、保険診療に基づくものが中心となるため、収入の面では施設間の差が出にくいという特徴があります。
KA:病院ごとに収入の差があまりない理由を、もう少し具体的にお聞かせいただけますでしょうか。
多湖氏:確かに、規模の大きな病院では、経営戦略をきちんと立て、我々のような外部の人間を招いて議論することもありますが、実際のところ、診療報酬制度がしっかり整っているため、あまり戦略的な経営をしなくてもなんとかなる、という医療機関も多く存在します。
特に地方では、「患者さんが来たら治療すればいい」という意識が根強く、経営に対して無頓着な病院も少なくありません。そのため、全体的に見て、医療機関間の経営差はあまり大きくはない印象です。
ただし、大規模な病院になると、様々な制度を活用する余地が出てきます。たとえば、「急性期」「慢性期」「終末期」「地域包括ケア」などの区分けに応じた診療報酬制度があり、それに応じて看護師の配置人数や設備などにより、報酬が増減します。
ですから、「うちは急性期に特化する」「慢性期は別の施設に任せる」など、法人単位で役割分担を明確にするケースも増えてきました。大病院ほど、そういった体制を整えやすくなっています。
とはいえ、実際には多くの病院が似たような戦略を取っているのも事実で、大きな差が生まれにくい構造になっているという印象を受けます。
このような制度のもとでは、「いかに患者さんが多く来院してくれるか」「再び利用してもらえるか」、つまり患者満足の向上が経営において重要になってきます。
KA:制度面だけでなく、「人」についても重要ということですね。
多湖氏:はい。医療はサービス業の一種でもあるので、患者さんと接するのは人、つまり医師・看護師・事務スタッフなどです。彼らが効率的かつ円滑に動ける体制を整えることが、患者満足の向上に直結すると考えています。
また、医療業界の人材は、他の業界に比べて転職が比較的しやすい傾向があります。なぜかというと、先ほど申し上げたように、どの医療機関でも基本的には同じ業務内容だからです。
つまり、看護師や医療従事者が「より条件の良いところへ」流出しやすい。だからこそ、経営者側は、ただ給与を上げるだけでなく、いかに働きがいを持って定着してもらうかを考える必要があるのです。
さらに、医療従事者は職業的な教育の影響もあり、「患者さんのために」という想いを非常に強く持っている方が多いです。その結果、より良い医療を提供しようとする気持ちが強くなりすぎて、制度で定められた報酬ではまかなえないような手厚いケアを提供し、結果的に病院経営が赤字になってしまうというケースも少なくありません。
まとめると、制度によって収入の上限が決められている一方で、医療従事者はそれ以上のケアを志す。そういったジレンマが、現代の医療経営にはあるのが実情です。
医療経営が直面する課題と改善の方向性
KA:続いて、現在の医療経営における課題と、その課題に対する改善策があれば教えていただけますか。
多湖氏:課題の一つは診療報酬制度です。診療報酬は国が定めており、厚労省が2年に一度程度見直します。この制度に医療機関は大きく左右され、業界としての依存度は非常に高いです。
それ以外にも、健康診断や自由診療などの分野で差別化を図っていく必要があると考えています。たとえば、コロナ禍では一つの医療系大学が大変な状況になりました。感染症病床を確保するために病棟の数を減らし、結果として通常の診療による収入が大幅に減少したのです。医療従事者は懸命に働いたにもかかわらず、診療報酬上では赤字になり、結果としてボーナスが支給されず、離職者が増えるという事態になりました。
ですから、診療報酬以外の部分、先ほど述べた検診や自由診療などに目を向ける必要があると考えています。ただし、自由診療に関しては制度的にも運営的にも難しさが伴うのも事実です。
KA:ありがとうございます。他に課題があれば教えてください。
多湖氏:もう一つの課題は「人」に関することです。離職率が他業界と比較しても高い傾向がありますので、どうすれば働きがいを感じてもらえるのかを考えなければいけません。最近では「やりがい搾取」とも言われるようになってきていますが、心理的な働きがいの重要性は以前から指摘されています。
特に看護師は女性が多く、お子さんがいる方も多いため、託児所を設けている病院や、夜勤専門・日勤専門など、柔軟な勤務体制を整えているところもあります。他にも、2時間勤務でも可能にするなど、働きやすさを工夫することが重要です。実際、そのような取り組みをしている病院の方が定着率は高いと感じました。
また、医療はチームで動くことが重要です。医師一人では何もできませんし、看護師や薬剤師だけでも限界があります。少し前に放送されていた朝ドラ『おむすび』は、医療ものではなかったのですが、栄養士を題材にチーム医療を描いていました。内容はさておき、実際、現代の医療では職種ごとの専門性が非常に高く、病気や怪我を一人で対応するのは難しくなっているのです。
特に高齢者は複数の疾患を抱えていることが多く、チームで対応する必要があります。ただ、その連携がうまくいかないことが大きな問題となっており、私自身もチーム育成の研修などでよく呼ばれる機会がありますが、簡単なことではないと身をもって実感しています。
さらに、医療業界では経営に対して無頓着な方が多いと感じています。「医療経営」という言葉がいつから使われ始めたのか定かではありませんが、大学で医療経営を学べる場も少ないですし、学校経営に至ってはほとんどありません。一般企業とは異なる考え方で経営を捉える必要がありますが、その理解がまだ十分とは言えないのです。今後はそのような人材の確保が重要になるでしょう。
KA:ありがとうございます。最近よく言われているDX化について、医療現場の状況はどうでしょうか。
多湖氏:一般企業に比べて医療業界はITやDXに弱い傾向があります。研修の打ち合わせで「Zoomで」とお願いしても、「Zoomって何ですか?」と返される役職の方がまだいらっしゃいます。また、「Excel使えますか?」と聞いても、「数字の入力はできます」と返されることもあります。事務部門はある程度進んでいますが、医師や看護師、薬剤師は自分の専門領域以外は分からないというケースが多いのです。もちろん全員がそうではありませんが、ITリテラシーの向上は今後の課題です。
最後に、地域との連携も重要です。診療報酬は今後も減額されていく可能性があります。これはあくまで私の予測にすぎませんが、人が長生きするようになり、医療費が増大している一方で、健康度は高くないため、高齢になれば病院か介護か、選択を迫られることになります。国としても医療費の増加は大きな問題で、医療を「病院」と「地域」に分けようとしているのです。
しかし、地域の医療やケアは、保険を使わず、ボランティア精神に依拠するような、昔の村社会的な方向性へ進もうとしているように見えます。「地域包括ケアシステム」も20年ほど前からありますが、実際には地域の人々への依存度が高く、なかなか機能していないのが現状です。
医療機関と地域とがうまく連携し、一方に負担が偏らないような仕組みを構築することが重要です。今後、そうしたモデルケースが生まれてくることを期待しています。
KA:近年の医療従事者の増減状況について、特に医師の不足などの課題はないのでしょうか。都道府県ごとに医師の数に差があり、この地域では医師が足りていないといった状況があるのか、お聞きしたいです。
多湖氏:それは大きくあります。やはり都会と地方での格差が顕著です。これは一般の企業でも同様ですが、都会には医療機関が集中しており、田舎では圧倒的に少ないです。
私は現在大阪にいますので、少し歩けばクリニックや病院が見つかりますが、以前、地方に勤務していた際は、医療機関が少ないように感じました。さらに離島となると、本当に医療機関がありません。ドラマの『ドクターコトー』のように、医師や看護師が住み込んで対応するしかないような状況です。
こうした環境を好む方もいますが、若い人たちは敬遠する傾向があります。都会の方が最新の技術や医療機器にアクセスしやすいですし、地方に行くと古い設備で診療しなければならないこともあります。
そのため、若手医師にとっては魅力を感じにくいという側面があります。実際、栃木にある自治医科大学では、入学時に授業料が無料である代わりに、卒業後は一定期間、離島などの地域医療に従事するという制度があります。それほどの仕組みがないと、なかなか地域に定着してもらえないという現状です。
また、医師は専門化されている分、誰にも頼れない孤立した状況は大きな不安要素です。一人ですべての責任を背負うのは、現在の医師教育の仕組みを考えると、非常にハードルが高いと感じます。
超高齢社会を見据えた医療経営の未来像
KA:続いて、医療経営における今後の展望について教えていただけますでしょうか。
多湖氏:先ほども少し触れた話になりますが、やはり日本はすでに「高齢化社会」ではなく「超高齢社会」となっていて、今後もさらに進んでいくと思います。しかも、元気なお年寄りばかりではないという現状があり、どうしても治療やケアの必要性は増していきます。
そうした中で、地域との連携、いわゆる「地域包括ケア」との関わりは非常に重要になってくると思います。そして、最近よく言われるようになっているのが「予防」です。できるだけ病気にならない、あるいは病気になるのを遅らせるという方向ですね。
偉そうなことを言っていますが、私自身、最近体重が増えてきて少し危機感を持っているところです。現代の社会人は、運動不足でカロリーの摂取が多すぎる傾向にありますから。運動なども含めた予防への取り組みが重要ですし、早期発見の意味で健康診断もその一環と言えます。
KA:若いうちから健康に気をつけて生活することが大切なのですね。
多湖氏:はい、こうした予防の観点からも、デジタル技術やIT化はどんどん進めていくべきです。たとえば、手首に装着して歩数を測るデバイスや、スマートフォンのアプリなどを活用して、自分の健康に興味を持ってもらう取り組みはすでに始まっていますが、今後さらに推進していく必要があると思います。
また、人材の面でも課題があります。これから働く労働人口は減っていく一方で、患者数は増えていきます。今いる人材を大切にするのはもちろんですが、たとえば、看護師や医師、薬剤師など、妊娠や出産を機に職場を離れた方々を現場に戻す取り組みも必要です。
さらに、介護領域では外国人材の活用も重要なテーマです。すでに10年ほど前からその動きはありますが、外国人材が日本の国家資格に合格するのは非常に難しい。冷静に考えれば、私たちが海外に行って現地の言葉で国家試験を受けるようなもので、ハードルが高いのは当然です。そういった現実を踏まえて、新たな資格制度を設けるなど、何らかの形で緩和する方向性が望ましいと考えています。
それから、先ほど申し上げたような経営やITを担う人材ももっと増えてほしいと思います。医療経営に関しては一般企業と同じで、関わる全員が経営マインドを持つのが理想ですね。ただ、これは正直なところ難しい面もあります。
KA:経営マインドを持つのがなぜ難しいのでしょうか?
多湖氏:特に教育の分野では、お金の話になると「汚いもの」「悪いもの」といったネガティブなニュアンスが残っているように思います。「お金のために仕事をするべきではない」といった価値観ですね。でも、そういった両極端な考え方ではなく、もっと現実的な視点を持つ必要があると思います。
私自身、病院で管理職になったときに、マネジメントや経営のことが全く分からず、どうしようかと悩みました。結果として、さまざまな研修に参加したり、大学院に進学したきっかけにもなったのですが、そういった知識をもっと身近に感じられるような仕組みが必要だと思っています。
KA:ありがとうございます。今後の展望として、たとえば医療従事者向けのIT教育サービスの導入などの可能性はあるのでしょうか。
多湖氏:あると思います。ただ、これは私の主観も入っていますが、医療系の人は、自分の仕事に直接関係があると感じられる研修にはすごく興味を持つんです。でも、直接的な関係が見えにくいと感じると、あまり関心を持たない傾向があります。
たとえば、医療経営に関する研修でも、役職者は興味を示すのですが、一般のスタッフの参加率は低いということもあります。ですので、IT教育のプログラムも、どのように設計するかが非常に重要です。
現場でよくあるのは、特定の機器の使い方をメーカーの方が直接指導するケースで、こういった実践的な内容には非常に関心が高いです。一方で、「統計の使い方」などになると、数字アレルギーというか、敬遠される傾向があります。
いかにその知識やスキルが重要であるかを理解してもらうことが、今後の鍵になるのではないでしょうか。
医師不足と地域偏在の現実、その背景と対応策
KA:それでは、医療経営を成功させるために重要なことについて、聞かせていただけますでしょうか。
多湖氏: 病院や医療機関における医療経営を成功させるには、これまでお話ししてきた内容が基本になると思います。つまり、制度を正しく理解し、人と円滑に連携しながら、経営に対しての認識を持つことが重要です。それらを常に感覚として持ちつつ、戦略を立てていくことが求められます。
ただ、診療報酬制度などについて、医療現場では知られていないケースが多いのが現状です。例えば、この治療には何点というように診療報酬が設定されていて、それが1点10円で換算されるのですが、医師はまだしも、他のコメディカルの方々は必ずしもそれを把握していない場合があります。もしかすると、「それは事務が知っていればいい」という感覚があるのかもしれません。専門職集団としての特徴かもしれませんが、職種ごとにどのような業務をしていて、それが医療機関全体にどう貢献しているのかを知ることは非常に重要だと思います。
KA:確かにお互いの業務内容を把握することで、連携がスムーズに進む気がします。
多湖氏: ただし、そうしたことを強く主張しすぎると、辞めてしまう人も出てきます。医療業界は転職先が多く、流動性も高いですから。また、一般の企業と比べると、医療機関では「人」の存在が非常に強く、人件費も50%を超えるのが当たり前です。それでも「安い」と思われるくらいです。
医療機関で働く人たちは、病院にコミットしているというよりは、自分の職業にコミットしている方が多いです。ですから、「病院のために」と訴えても、逆効果になる可能性があります。そのあたりが難しいところで、正直なところ、私自身も「こうすればよい」と明確に言える答えは見つかっていません。その人それぞれで異なるのだろうと思います。
ただ、どの医療機関に行っても、「こういうことは知っておくべき、意識すべき」という認識が刷り込まれていれば、モチベーションにはつながると思います。そういう意識を持っている人を中心に考えていくことが大切だと思います。
KA:実際、先生は病院に対してどのようなアドバイスをされているのでしょうか?
多湖氏: 最近はDXなども話題ですが、アドバイスとして一括りにするのは難しいです。企業と同様に、「うちの病院、どうしたらいいですか?」と聞かれることもありますが、他の病院でやっていることをそのまま持ってきても通用しないケースが多いためです。ですから、情報収集をして、私たちが伝えられることを提供し、その中でトップの方に最適なものを選んでもらうしかありません。
ただ、そのトップがまた難しいのも事実です。病院では、理事長や院長、つまり社長にあたるポジションは医師しかなれません。医療経営に興味を持ち、取り組もうという意思のある医師がトップに立てばよいのですが、そうでない場合は、やはり差が出てきます。
KA:たしかに、医療業界は医師中心のイメージがあります。
多湖氏:そうですよね。だからこそ、院長や理事長がこうした点を意識することで、組織全体に伝わりやすくなるのではないでしょうか。特に開業医の方々は、そういった意識が強いように感じます。逆に、経営がうまくいかずに潰れるところは、そういった意識が薄いのではないかと思います。
KA:ありがとうございます。次に、医療経営を成功させるうえで、患者満足度と収益性のバランスについてもお聞きしたいです。例えば、ある医療機関では患者満足度を優先する一方、別の機関では収益性を優先するというようなケースもあるのでしょうか。
多湖氏:表立って経営効率を重視していると示す医療機関は少ないので、外からは分かりにくいですが、サービス業全般に言えることとして、患者さんが来なければ収入は入りません。また、医療機関には大口の顧客がいるわけではありませんので、病気や怪我によって来院される方の属性は様々です。
そのため、特にリピーターの確保が大事です。例えば、風邪をひいたときなど、皆さん基本的には近くの病院に行かれると思います。その際、受付の対応が悪いと、次からは行きたくなくなるわけです。そうした小さな不満が積み重なると、来院数に影響を与えます。
満足度と収益の関係については、昔から研究されています。ただ、病院では患者さんが「自分の命を握られている」と感じるため、アンケート等で本音を書きづらい側面もあります。ですから、アンケート結果が必ずしも実態を反映しているとは限りません。
それでも、「この病院はいいな」と心から思ってもらえるような満足、あるいは「特に不満はない」と感じてもらえるレベルの満足度を目指すことは、どこの病院でも共通して目指しているところだと思います。
現場の課題を解決する目的で医療経営を学ぶのがおすすめ
KA:最後に、医療経営を志す方へのアドバイスをいただけますでしょうか。
多湖氏:医療は他の業界と異なり、直接的に人の生活や命に関わる分野だということを常に意識しておくのは大切です。ただ、医療経営はそれと同時に、ここで働く人たちが生活できるようにするという側面もあります。経営と使命の両輪をバランスよく回す感覚が重要です。
KA:ありがとうございます。医療経営の勉強方法について、例えば、書籍の購入やスクール通学など、どのような方法が有効なのでしょうか。
多湖氏:本を読んだり、スクールや大学院に通ったりすることはもちろん良いと思います。ただ、それだけでなく、実際に現場で実践できる環境を確保することが重要です。
私も昨年まで某大学院で、医療経営プログラムの非常勤講師をしていました。私の講座は特に「人」に関する内容が多く、どうやってチームを作るかといった話が中心でした。そこに来る受講者の多くは、現場での課題を抱えていて、その解決のために学びに来ているという印象です。
医療経営を目指すというよりは、すでに直面している問題に対応するための学びが多いように思います。ですので、現場の課題に向き合いながら学ぶという姿勢が大切だと思います。
もちろん、最初のとっかかりとしては本を読むことも良いですし、医療系の大学やスクールの講座を受けてみるのも良いと思います。あとは、診療報酬制度などについては、医療事務系の書籍や、厚生労働省のホームページなども参考になりますよ。
KA:ちなみに、先生のおすすめの書籍などはございますか?
多湖氏:正直なところ「どんなものでも良い」と思っています。私自身も医療経営協会が出している資格試験用のテキストを書いていますが、医療経営や病院経営というタイトルの本であれば、どれでも取っ掛かりになると思います。
分野としても、「人」「お金」「マーケット」など様々ですから、自分が興味を持てるところから始めてみるのが良いでしょう。一般的な経営書でも構いません。私は一般の経営学を医療にどう適用するかというスタンスですが、それも一つの考え方に過ぎないので、色んな考え方に触れてみてください。