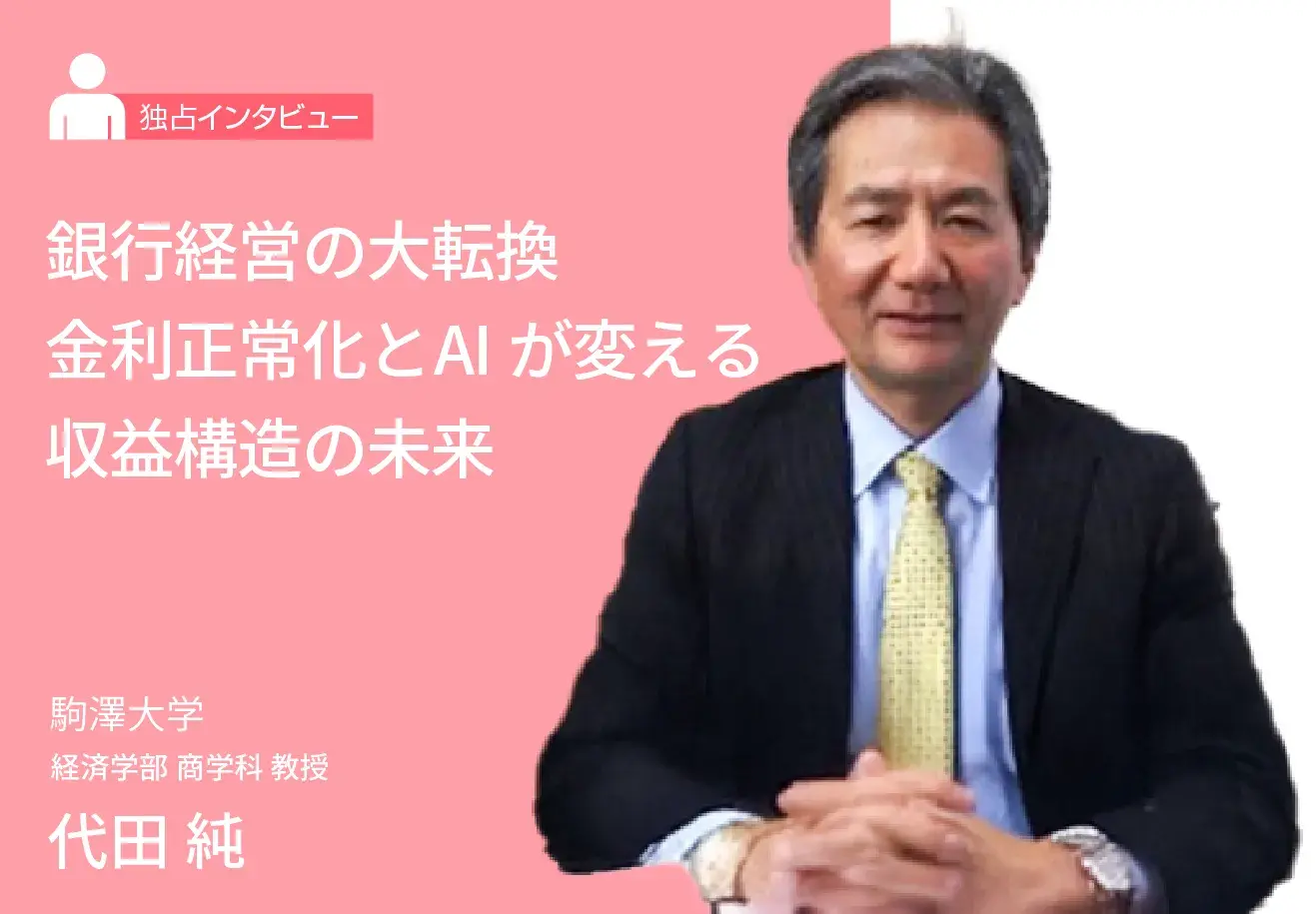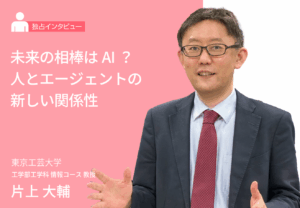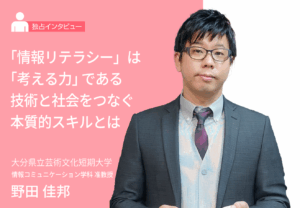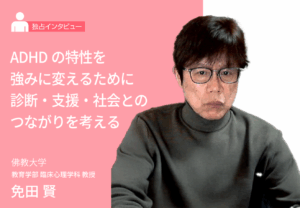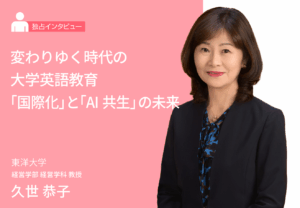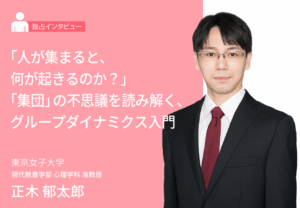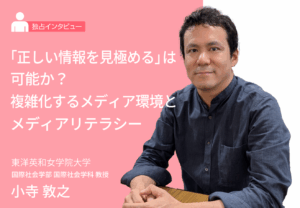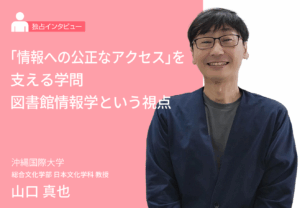2024年、日本銀行はついにマイナス金利政策を終了。2025年初頭には政策金利が0.5%に達し、金融業界はかつてない転換期を迎えています。安定した収益源とされていた貸出業務や有価証券の運用も、今やその安定性が揺らいでいます。金利の正常化と顧客ニーズの変化が、銀行経営に新たな課題を突きつけているような状況です。
その一方で、GoogleやAmazon、中国のアリババといった巨大テック企業がAIを駆使して金融ビジネスに参入し、伝統的な銀行モデルに挑戦を仕掛けています。
この記事では、駒澤大学の代田純教授へのインタビューを通じて、銀行がどのようにこの変化に適応し、生き残り、成長していくのかを詳しく伺っています。

代田 純
駒澤大学 経済学部 商学科 教授
【biography】
1957年生。中央大大学院博士課程中退。博士(商学)。1991年日本証券経済研究所大阪研究所研究員。1994年立命館大学国際関係学部助教授を経て2002年より現職。駒澤大学で経済学部長、副学長を努め、現在、同大学院研究科委員長。近著に、『入門銀行論』(有斐閣、2023年、編著)、『デジタル化する証券市場』(金融財政事情研究会、2023年、共編著)など。2025年4月より、ユバスキュラ大学客員研究員、在フィンランド。
銀行収益の二本柱 資金運用と手数料ビジネス
ナレッジアート(以下KA):初めに銀行経営の仕組みについて教えていただきたいです。
代田氏:銀行の収益構造にはいくつかの柱があります。中でも重要なのが「資金運用収益」と呼ばれる部分です。これは主に以下の2つに分かれます。
- 貸出業務
銀行は預金者から預かったお金を企業や個人に貸し出すことで利益を得ています。預金金利(銀行が預金者に支払う金利)と貸出金利(銀行が融資先から受け取る金利)の差、いわゆる「利ざや」が銀行の主な収入源の1つです。例えば、企業が設備投資を行う際に、銀行から資金を借りる場合、この仕組みが活用されます。 - 有価証券の運用
銀行は株式や国債などの有価証券を保有し、そこから得られる配当金や金利収入を収益としています。例えば、日本国債を保有することで金利収入を得たり、株式の配当金を受け取ったりします。
これらの「貸し出し」と「有価証券運用」を合わせたものが「資金運用収益」と呼ばれ、現在の銀行収益の約7割を占めています。さらに、銀行収益のもう1つの柱として「役務取引等収益」があります。これは、いわゆる手数料収入です。一例として、具体的には以下のようなものがあります。
- ATM手数料
ATMを利用して現金を引き出す(振り込む)際に発生する手数料です。最近では、多くの銀行が一定の条件下でATM手数料を無料にしていますが、他行のATMを利用したり、時間外に利用したりすると手数料が発生します。 - 金融商品の販売手数料
銀行は投資信託や生命保険などの金融商品を販売しており、その際に得られる手数料も重要な収益源です。
まとめると、銀行の主な収益は「資金運用収益」と「役務取引等収益」の2つに大別されます。前者は貸し出しや有価証券運用による利益、後者は手数料収入を指します。この2本柱が銀行経営の基盤を支えています。
金融商品販売の光と影 情報格差の課題
KA:ご説明いただいたような金融知識に乏しい人も多いのではないかと思います。そういった人に対する銀行の営業が度々問題視されることもあるかと思います。このような問題について教えていただけませんか。
代田氏:それは、銀行に限らず証券会社を含む金融機関全般で指摘されることですが、一例として、最近問題視されている「仕組み債」のケースがあります。仕組み債は債券の一種ですが、通常の債券とは異なり、特定の条件が組み込まれています。例えば、「日経平均株価が3万7000円を割った場合、元本が半分になる」といった条件が設定されているものです。このような商品を、債券の一種であることを強調しながら、高齢者など金融知識が乏しい人々に販売し、手数料を得るケースが報告されています。本来、一般的な債券は元本が保証されるのですが、仕組み債の場合、条件次第で元本が大きく減少するリスクがあります。例えば、株価が一定のラインを下回ると、元本の半分しか戻らないといった事態が発生します。このようなリスクを十分に理解しないまま購入する人が多く、トラブルに発展することが少なくありません。
こうした問題を受けて、金融機関には販売時の説明責任を徹底するよう指導が行われています。具体的には、商品のリスクや条件を顧客に分かりやすく説明し、誤解を招かないようにすることが求められています。しかし、現実には、説明が不十分なケースもあり、完全に問題が解消されたわけではありません。
金利正常化時代の経営課題
KA: なるほど、問題は継続しているということですね。では、その銀行自体の課題点や、改善策について教えていただけますか。
代田氏: はい、まず現状についてお話しします。ご存じのとおり、2024年3月に日本銀行はマイナス金利政策を終了しました。それ以前は長期間、非常に低い金利が続いていました。しかし、2024年3月以降、政策金利は段階的に引き上げられ、2024年7月には0.25%、直近の2025年1月には0.5%にまで上昇しています。問題となるのは、政策金利の引き上げが民間銀行の貸出金利にどのような影響を与えているかです。実際、一部の銀行は貸出金利を上げていますが、多くの銀行では政策金利が上がっているにもかかわらず、貸出金利を十分に上げることができていません。顧客を引き留めるために、預金金利も上げざるを得ず、結果として「利ざや」(貸出金利と預金金利の差)が縮小してしまいます。地方の金融機関、特に第二地方銀行などでは、貸出金利を上げると顧客が他の金融機関に流れてしまうリスクが高いため、金利の引き上げが難しい状況です。このような状況が、地方銀行の経営をさらに厳しいものにしています。
KA:利上げが難しいという現状に対し、何か改善できる余地はあるのでしょうか?
代田氏:改善策としては、まず銀行の担当者が顧客とのコミュニケーションを強化することが重要です。利上げが進み、預金金利も上がっている現状を丁寧に説明し、貸出金利の引き上げについて理解を得る努力が必要です。しかし、最近では、書面での通知だけで済ませるケースが増えています。例えば、「来月から貸出金利を0.2%から0.5%にします」という通知を送るだけでは、顧客が不満を抱き、他行に乗り換える可能性があります。したがって、顧客との直接的な対話を重視し、信頼関係を築くことが基本的な改善策になるでしょう。信頼関係を築くことにより、顧客の理解を得やすくなり、貸出金利の引き上げがスムーズに進む可能性があります。
KA: 信頼関係があるからこそ、顧客も貸出金利の引き上げに対し、理解を示せるわけですね。では次に、銀行経営における今後の展望について教えてください。
代田氏: 現状の課題を踏まえて、今後の銀行経営の展望についてお話しします。従来、銀行は預金を集め、その資金を貸し出す与信業務で利益を上げてきました。しかし、低金利環境が長引く中、この方法だけでは十分な収益を確保するのが難しくなっています。したがって、銀行は与信業務以外の分野で収益源の多角化を図るため、以下のような動きを強めています。
- 有価証券の運用
現在、金利上昇の影響で日本国債の利回りも上昇しています。例えば、10年物国債の利回りは1.2%以上となっています。預金金利を0.3%~0.5%程度に抑えながら1.2%の利回りで運用できれば、貸し出しと預金の金利差、すなわち「利ざや」を確保することが可能です。ただし、長期国債は金利変動の影響を受けやすいため、多くの銀行はリスク管理の観点から中期国債を選ぶ傾向にあります。 - 外国債券の運用
外国債券の運用に関しては慎重な姿勢が求められています。最近では、農林中金がアメリカの債券運用で大きな損失を出した事例があるため、金利変動リスクを十分に考慮した運用が重要になります。 - コンサルティング業務の強化
銀行法の改正を受け、銀行はコンサルティング業務の強化にも取り組んでいます。具体的には、中小企業のM&A(企業の合併・買収)支援を通じた手数料収入の獲得や、地方の製造業者を流通業者に紹介したり、百貨店に地方の名産品を販売する業者を紹介したりするなど、新たな収益源の確保が進められています。
このように、銀行は従来の与信業務に加え、証券運用や各種コンサルティング業務など複数の分野で収益の多角化を図り、経営の安定化を目指しています。
デジタル時代の銀行戦略 AI活用の可能性
KA:今後の展望について、中でもAIの発達によって、銀行のビジネスモデルに変化が起こる可能性はありますか?
代田氏: これは非常に重要な問題であり、銀行業界全体が深刻に捉えているテーマだと思います。現在、GoogleやAmazonといった巨大テック企業が、AIを活用して金融ビジネスに参入しつつあります。これに加え、中国のアリババや百度(バイドゥ)といった企業も、AIを活用した金融サービスを積極的に展開しています。
中でも、中国の巨大テック企業は、銀行免許を取得し、実際に銀行業務を行っています。例えば、融資を行う際に、AIを活用して与信(信用力の評価)を判断しています。これらの企業は、過去の金融活動データをビッグデータとして蓄積しており、それをAIに分析させることで、迅速かつ正確な融資判断を可能にしています。企業の過去の借入履歴や返済実績などをAIが評価し、短時間で融資の可否を決定する仕組みです。
一方で、GoogleやAmazonはまだ銀行免許を取得していませんが、アメリカの銀行と提携する形で、同様の金融サービスを提供しています。このように、巨大テック企業が金融ビジネスに本格的に参入してきており、銀行業界にとって大きな脅威となっています。
従来の銀行では、融資の申し込みを受けてから審査を行い、融資の可否を決定するまでに時間がかかるのが一般的でした。しかし、AIを活用すれば、これらのプロセスを大幅に短縮することが可能です。迅速な融資判断は、顧客にとっても大きなメリットとなります。
このような状況を踏まえ、日本の銀行もAIの活用を急務としています。AIを導入しなければ、巨大テック企業との競争に太刀打ちできなくなる可能性があるためです。AIは、銀行のビジネスモデルを大きく変える可能性を秘めており、今後の銀行経営において重要な鍵を握る存在となるでしょう。
規制環境の変化がもたらす機会と制約
KA:続いて、銀行に関連する金融規制についてお伺いします。例えば、海外では為替取引における、高いレバレッジの利用が可能です。しかし、日本では25倍に制限されています。金融規制が強化されることで、銀行の経営にも影響が出るのでしょうか。
代田氏:確かに、金融規制が強化されているという点は事実です。例えば、リーマンショックのような大規模な金融危機を受けて、アメリカをはじめとする世界各国で銀行に対する規制が強化されました。規制強化は、銀行業務に関する規制を緩めると、再び同じような問題が起こる可能性があるためです。
具体的には、自己資本比率(銀行がリスクに備えて持つべき資本の割合)を一定以上に保つことが義務付けられるなど、銀行の健全性を確保するための規制が強化されています。このような規制強化により、銀行はリスクの高い投資や融資を抑えざるを得なくなり、経営の安定性が向上するというメリットがあります。しかし、収益性が制約される可能性も指摘されています。なお、米国大統領にトランプ氏が復帰し、米国で銀行や金融への規制が緩和される可能性があります。
一方で、規制が緩和されている部分もあります。例えば、日本の銀行法では、かつて銀行は銀行業務以外の事業を行うことが厳しく制限されていました。しかし、現在では、銀行が子会社を設立し、総合商社のような業務を行うことが許可されています。銀行は新たなビジネスチャンスを得ることが可能になっています。
つまり、銀行に対する規制は、強化されている面と緩和されている面の両方が存在します。銀行としては、規制強化によるリスク管理の向上を図る一方で、規制緩和によって生まれた新たなビジネス機会を活用することが重要だといえるでしょう。
新規参入のヒント 異業種からの銀行業参入
KA:近年、様々な企業が銀行経営に参入してきているように思えます。銀行経営への参入ハードルは低くなったのでしょうか?
代田氏:銀行業は基本的に許認可事業ですので、金融庁の認可がないと始められない業種です。したがって、新しく銀行を立ち上げて銀行業を行うことは、非常にハードルが高いと言えます。
しかし、近年成功している銀行の多くは、楽天銀行やSBI銀行のように、他業種から参入してきたケースです。セブン銀行もその一例です。これらの銀行は既存銀行とは異なるビジネスモデルやサービスを提供することで成長しています。
つまり、銀行業を始める場合、ゼロからスタートするのは難しいかもしれませんが、他業種からの参入という形であれば成功の可能性が高まるでしょう。例えば、既存の事業基盤や顧客基盤を活用し、銀行業務を付加する形で展開するのが有効です。最近は、Baas(Banking as a service)と呼ばれる仕組みが注目されており、銀行が非銀行企業と連携して、非銀行企業の顧客が銀行口座等を利用できるといったものです。
したがって、銀行業を目指す場合、まず自分の強みや既存の事業とのシナジーを考えた上で、銀行業への参入を検討することをお勧めします。楽天やSBI、セブン銀行のような成功事例を参考にするのも良いでしょう。
まとめ
銀行業界は金利正常化やAI技術の進展といった外部環境の変化に対応しながら、収益構造の多角化と競争力の強化を進める必要があります。AIによる迅速な与信判断や中小企業向けコンサルティング業務の強化といった新たな収益源の開拓は、今後の銀行経営の成否を左右する重要な要素になると考えられます。これらの変化が自身の金融サービスや資産運用、ひいては投資判断にどのような影響を与えるのかを注視していく必要があるでしょう。