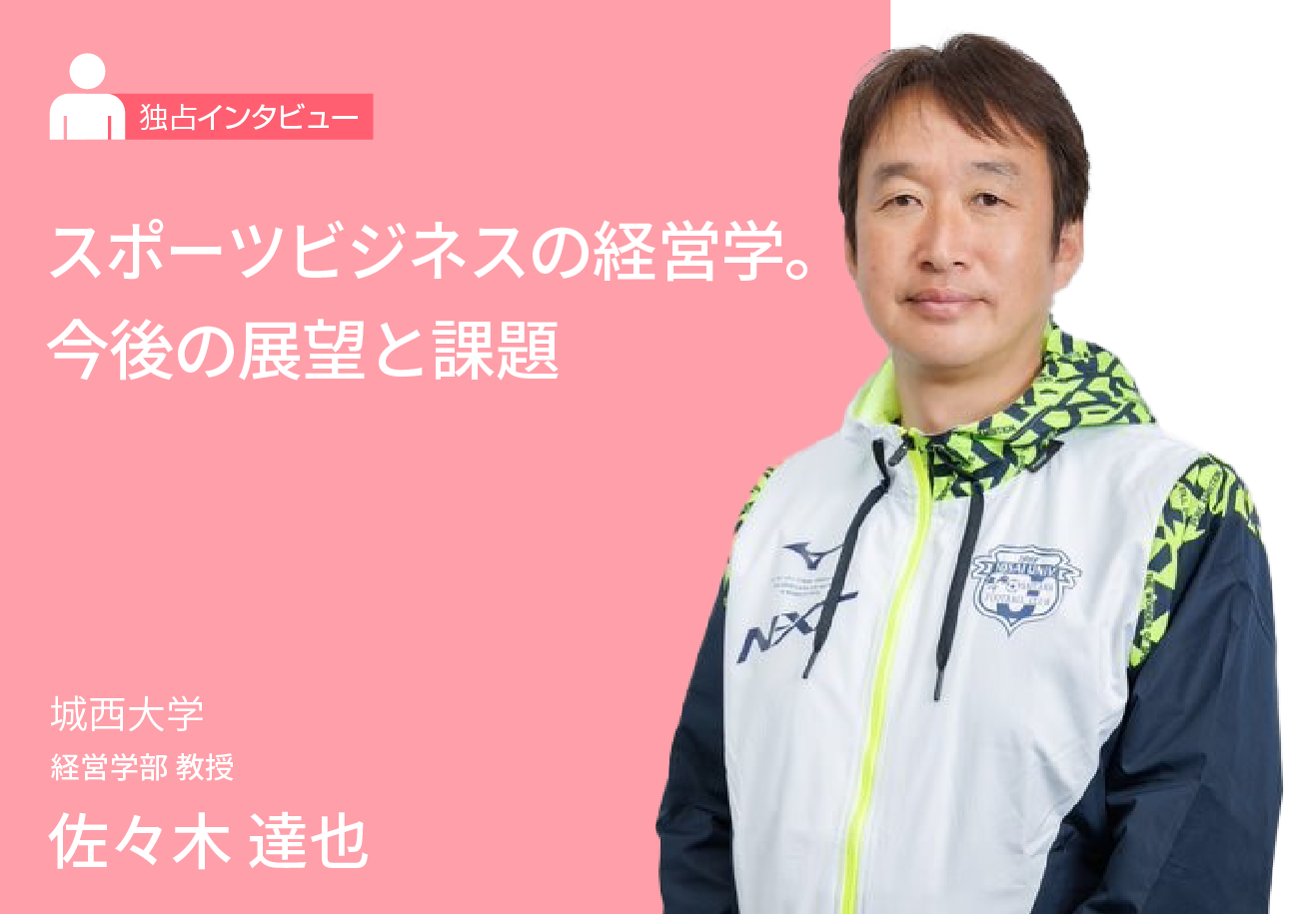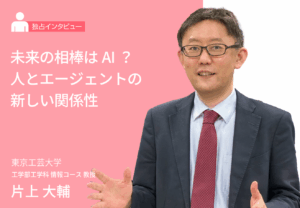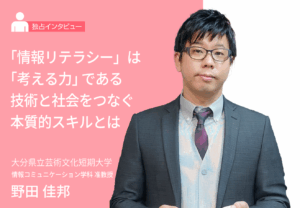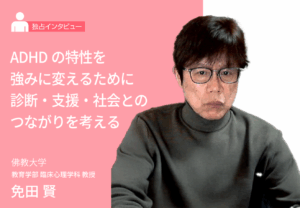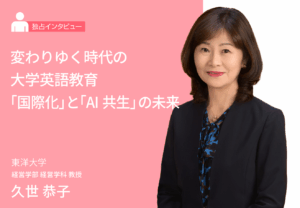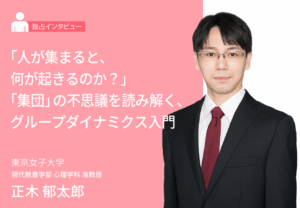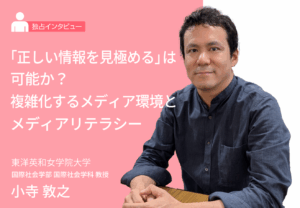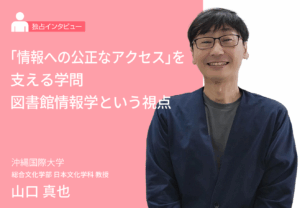今や多くのアスリートがSNSや動画サイトで人気を博しています。これまではマイナースポーツとしてあまり知られていなかった競技も注目を浴びる機会が増えており、スポーツ球団の公式のインターネット動画チャンネルも珍しいものではなくなっています。
スポーツ界も企業経営からファンあってのものに大きく変貌を遂げている昨今。
新時代のスポーツビジネスについて、城西大学経営学部の佐々木達也教授にお話を伺いました。

佐々木 達也
城西大学 経営学部 教授
【biography】
東京都出身。早稲田大学人間科学部スポーツ科学科卒。早稲田大学スポーツ科学学術院修了。大手広告代理店からJリーグクラブ東京ヴェルディ、ツエーゲン金沢での勤務を経て、金沢星稜大学人間科学部専任講師として教鞭を取り現在に至る。過去に、J2リーグ中継の試合解説や朝日新聞のJリーグのコラムを担当。
スポーツビジネスの仕組み
ナレッジアート(以下KA):まず初めに、スポーツビジネスの仕組みについて教えていただけますでしょうか?
佐々木氏:はい。まずは、スポーツビジネスの初歩的なところからですが、端的に言いますと、ファンの人数が多ければ多いほどビジネスとして成功する。つまり、ファンの拡大を第一義的な目標とするビジネスです。
そして、ファンの存在は球団運営側に四本の収入の柱をもたらします。
まず第一の柱は、入場料収入です。試合の会場で有料にて観戦チケットの販売を行い、そこに多くのファンが観戦に訪れたとする。こうしてスタジアムが満員となれば当然、収入は増えていきます。この入場料収入が第一番目の柱として重要です。
次に第二の柱ですが、スタジアムが満員で入りきれなかったファンがいらっしゃれば、そうしたファンのためにテレビをはじめとしたメディアで放送されるわけですね。そして、そうした要望が増えれば増えるほど、注目されればされるほど、放送したいというメディアも増えて放映権料も高騰していくわけです。このような放映権収入が二番目の柱ですね。
さらに、第三、第四の柱ですが、放送を視聴するファンが多ければ多いほど、広告を展開したいというスポンサーの企業も現れる。チームの運営資金が増えるわけです。それを選手の給与に反映することもできますし、スタジアムへの投資やグッズの企画や販売にも繋がる。飲食の展開もできますね。こうして、スポンサー収入やグッズの売上収入が、チームに多大な収入をもたらします。第三、第四の柱と言えるわけです。
そして、観戦や購買を目的としたファンがさらに来場したり視聴したりする。さらにファンが拡大する。収入が上がればまた新たな投資に繋がる。このように、ファンの存在の大きさが全てに影響を及ぼすわけです。
スポーツビジネスにおける現状の課題点と改善策
KA:ありがとうございます。では、次にスポーツビジネスにおける現状の課題点と改善策を教えてください。
佐々木氏:はい。日本はスポーツビジネスにおいては後進国です。その点、欧米諸国は先進国です。理由としては、スポーツビジネスを学問的な見地から考察されているかどうかという点です。アメリカにおいては、スポーツビジネスやスポーツマネジメント、スポーツマーケティングといったテーマを、学問として大学で履修することが早い段階から可能でした。日本においては、そうしたスポーツビジネスが大学で研究されるようになったのは、欧米よりも相当遅れた頃でした。
そんなスポーツビジネス後進国の日本においては、最も人気のあるスポーツ競技は日本プロ野球(NPB)かと思います。1936年に始まっていますから、約90年の歴史があります。そんな歴史あるプロ野球ですが、スポーツビジネスの観点から言うと、厳密には企業スポーツに近い形式にあるかと私は思います。
野球に限らずサッカーもバスケットボールもバレーボールもラグビーも出発点は企業スポーツ、実業団スポーツでしたが、野球のみが成功を収めました。そのため、厳しい状況にあった野球以外の各競技は、プロクラブチームとして成り立てるようにスポーツビジネスの面で改革に取り組みました。
そして現在、スポーツビジネスは黎明期から成長期に入っております。いち早く1993年に地域密着型のクラブ化を達成したサッカー(Jリーグ)だけは、成熟期に達しています。
バレーボールのSVリーグやバスケットボールのBリーグなど、色んな競技が地域密着型のプロクラブチームへと脱却を始めており、スポーツビジネスの面で成長をしていると思います。今まさに、日本国内でもこのスポーツビジネスが成功するか失敗に終わるか、分岐点を迎えていると私は思います。
成長のためには、チャレンジ精神が非常に重要で、トライアル&エラー、スクラップ&ビルドの精神で進めていくべきです。サッカーが好例です。
サッカーは1993年当時、マイナースポーツでした。私自身も、まさかこのようなマイナースポーツが成功するとは夢にも思っていませんでした。
しかし、Jリーグの船出後は注目されるようになり人気が上がり、特に1998年のサッカーワールドカップフランス大会の本戦出場を契機として、日本国内で一気にサッカー熱が高まりました。今や、さすがにプロ野球ほどの観客動員数はなくとも、非常に人気のある競技に、人気のあるリーグに成長しました。
サッカーで達成できた以上、他のマイナースポーツもできないとは思えません。日本は非常に保守的な土壌ではありますが、改革志向のあるリーダーの元で、色んな競技のスポーツビジネスが発展していってほしいと願っています。
また、マイナースポーツの未来だけではなく、人気の競技のこれからも重要だと思います。
日本において人気のスポーツである野球やサッカーですが、野球はアメリカのメジャーリーグとの年俸の格差が非常に大きくなっており、またサッカーもヨーロッパのビッグクラブとの賃金格差は非常に大きいです。欧米と日本では選手の給与が桁一つ変わってきてしまうわけです。そのため、NPBもJリーグも選手の海外流出という問題を抱えています。
それを解消するために何をすればいいのか。例えば、NPBではまだダイナミックプライシング(変動料金制。チケットの価格を需給ギャップに応じて天候や対戦カードを考慮し変動させる制度。)を大半のチームで導入しておらず、需要が高い=もっと値上げしても完売する対戦カードでも安値で販売してしまい、ビジネスの機会を失っている可能性があります。また、Jリーグでは、所属する選手の報酬の制限が低すぎるせいで海外に流出しているということも理由にあげられます。
とにかく、日本ではスポーツ選手の報酬額が低すぎるのです。これでは優秀な人材が海外に流出して当然だと思います。日本の球団、クラブチーム運営者、実業団もまだまだ多いですが、とにかくチャレンジ精神を持って改革を進めてスポーツビジネスを浸透させてコンテンツを成長させ、そして選手の報酬に還元してもらいたい。声を大にして訴えていきたいところです。
スポーツビジネスにおける今後の展望
KA:ありがとうございます。それでは、スポーツビジネスにおける今後の展望についても教えてください。
佐々木氏:はい。今後のスポーツビジネスの展望ですが、マルチメディア化し幅広い選択肢がある視聴コンテンツの中で、いかに選んでもらえるかが重要だと思います。
放映権収入はスポーツビジネスの根幹の一つですが、放映と言えば地上波の一択であったメディアも、現在ではテレビだけでも地上波の他にBSやCSでの放送もありますし、インターネット放送も増えてメディアの選択肢が多くなってきております。当然、スポーツ観戦以外でも魅力的なコンテンツはある中で、いかに観戦してもらえるかが重要です。
そうした中で、スポーツというコンテンツは、ライブ配信が最も価値が高いです。視聴者さん達は録画よりもリアルタイムで観戦したいはずですから。それはつまり、多少コンテンツ中に広告が入ったり、あるいは競技場内にスポンサー名が表示されたとしても、余程視聴の妨げにならない限りは継続的にご覧いただけるということだと思います。ライブ配信が基本ということは、広告主さん、スポンサーさんにとっても魅力的なコンテンツです。これがスポーツビジネスの強みであると思いますし、地上波以外にも広がった視聴手段により、新たなファンの獲得ということが可能になっていると私は考えます。スポーツビジネスには伸びしろが大きいです。
そして、選手が人気を得るチャンスが広がっているということでもあります。テレビでなくともインターネット上で人気になった選手もいますね。なかなか地上波のテレビでは取り上げられる機会のなかった競技の選手にとっても、新たなチャンスが広がっているということです。
その方法の一つとして、SNSを用いたセルフマネジメント、セルフプロデュースも可能となっています。大手のプロデュース会社、マネジメント会社に所属せずとも、あるいは所属可能な実績がなくとも、それぞれの頑張り次第で人気を得ることも可能な社会になってきている。つまり、とにかくチャレンジ精神が重要である、私はそう思います。
スポーツビジネスを成功させるために必要なこと
KA:ありがとうございます。では、スポーツビジネスを成功させるために重要なことは何でしょうか?
佐々木氏:はい。それはやはり、冒頭にお話ししたとおりですが、いかにファンを獲得するかに尽きます。いわゆるファンディベロップメントというものです。
では、そのためには何が重要なのか。魅力的なコンテンツとして仕上げて収益をスタジアムや選手への投資や還元に充てるということが大事であるとは、先に説明したとおりです。
その上で、人気のリーグに有名選手を輩出するとか、国際大会などを通じて実績をあげる、などといったことが重要だと思います。バスケットボールがNBA選手の登場で人気が出たりしましたが、そういった実績ある選手がいれば、テレビ露出やインターネットニュースに取り上げられる機会も増えますし、競技自体の人気も増えてファンの裾野の拡大に繋がるかと思います。
では、そうしたスター選手はどうやったら登場するのか。結局それは競技のレベルの向上に尽きるのではないでしょうか。そのためには、競技人口を増やす、チャレンジするアスリートを増やす。国際大会で高い実績があれば、メディアも取り上げてくれます。いかに国際イベントで活躍できるか。例えば、バレーボール男子ですが、長い期間低迷期にありました。それが最近では注目を浴びている。バレーを題材にした漫画『ハイキュー!!』人気による好影響もありますが、やはり国際大会での実績が大きいのではないでしょうか。オリンピックやワールドカップで実績を高め、人気実力共に見事に復活を遂げています。
そして、人気の高まりに比例して新たなスポンサーも現れます。例えば、フェンシング。マイナースポーツで以前はスポンサー料も高額ではなく、100万円ほどの拠出金でも大口スポンサー扱いとされていました。しかし、オリンピックを制覇して色々なニュースでも取り上げられるようになり、スポンサーからしたら非常に割安感のある費用対効果の高い広告になったはずです。一昔前の女子カーリングなど、いかにマイナースポーツでも国際大会で活躍してファンの拡大やスポンサーの獲得に繋げられるかが重要かと思います。
競技のレベルアップが国際大会での活躍に繋がり、それがファンの拡大にも繋がる。そしてスポンサーの獲得にも役立って収入が伸び、また新たな投資を呼び込む。うまく循環していってほしいと願っています。
起業家志望の方へのアドバイス
KA:ありがとうございました。では、読者の皆さんや起業家志望の方へのアドバイスがありましたらお願いいたします。
佐々木氏:はい。起業される皆さんは非常にチャレンジ精神が豊富かと思います。日本人は非常に保守的な方が多いのかなと思いますし、ビジネスの世界でもまだまだそうした土壌にあるかと思います。そのような中において、新たに起業して船出をするわけですから、これからもチャレンジ精神を忘れないで欲しいなと願っています。
また、スポーツビジネスの観点で言うと、マイナースポーツでも努力をして結果を出せば才能が認められますし、人気が高まります。
しかも、その競技では第一人者となるわけです。言わばブルーオーシャンというか、そうした隙間を上手く縫う形で活躍する機会もあると思います。
また、今ではアスリート個人でのセルフマネジメントによるPR活動のように、大手の広告代理店などを挟まずとも費用対効果の高い広告戦略は実現が可能かと思います。
とにかく、可能性はいくらでもあるということですね。チャレンジ精神を忘れずにどんどんと挑戦していってほしいと願っております。