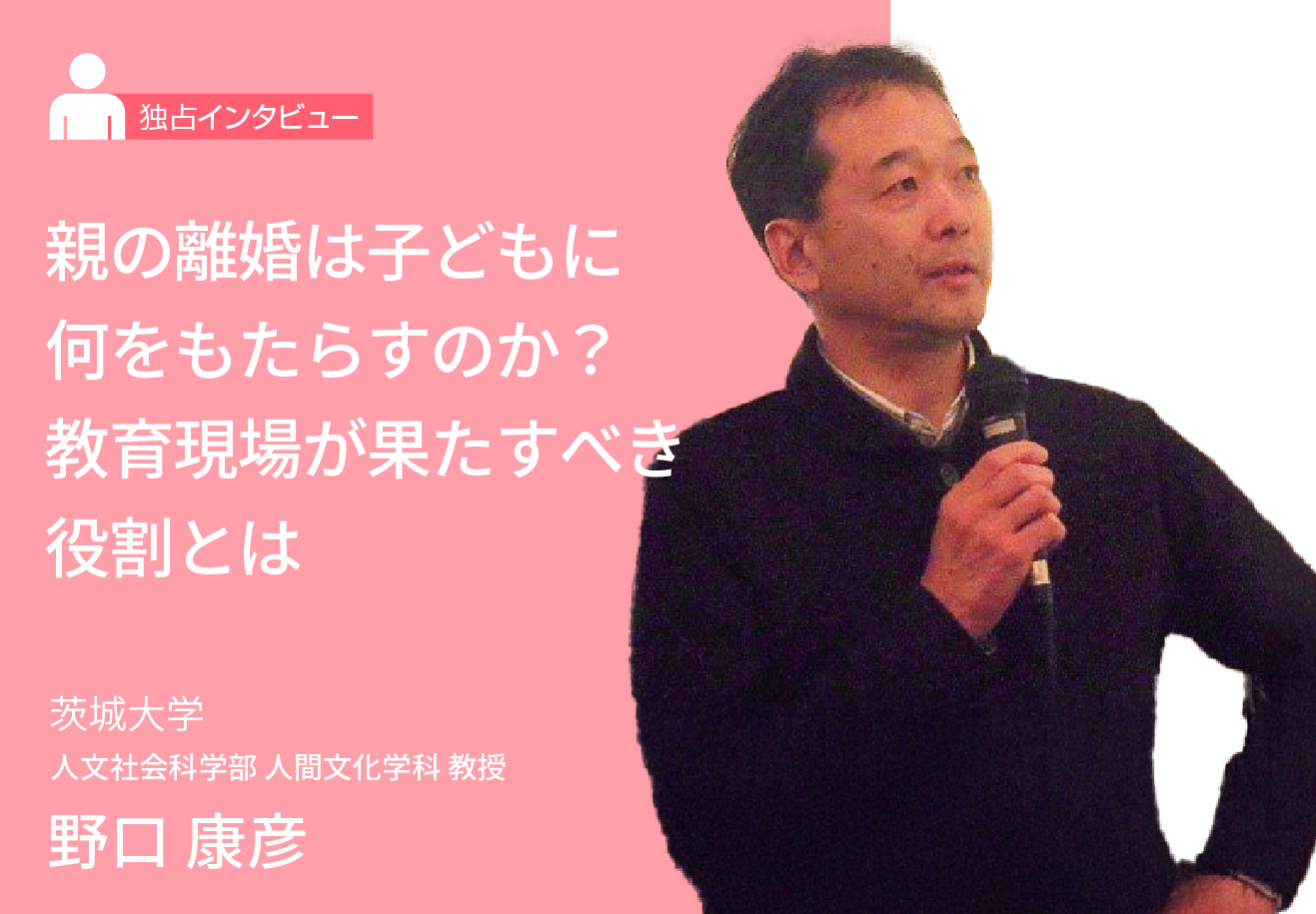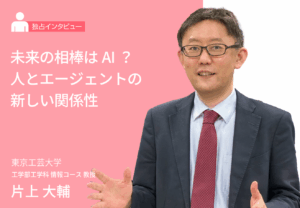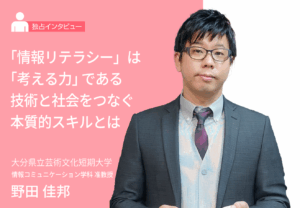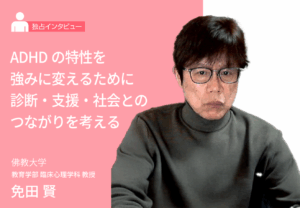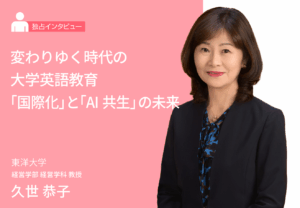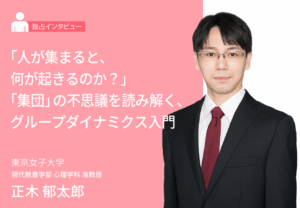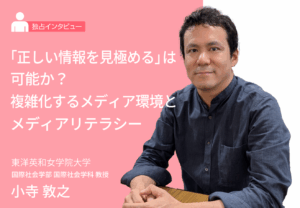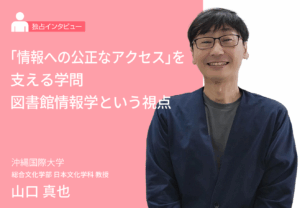近年、日本の離婚率は上昇しており、「単独親権」から「選択的共同親権」へと移行する法改正も控えています。
しかし、離婚が子どもに及ぼす影響や、教育機関がどのようなサポートをすべきなのか、理解できていない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、茨城大学の野口康彦教授に日本における離婚の現状や、親が離婚した子どもへの教育方法などについてお話をうかがいました。

野口 康彦
茨城大学 人文社会科学部 人間文化学科 教授
【biography】
茨城大学人文社会科学野教授。専門は臨床心理学。公認心理師、臨床心理師、社会福祉士、精神保健福祉士の資格を持つ。
法政大学大学院人間社会研究科人間福祉専攻修了。博士(学術)。
医療ソーシャルワーカーの勤務を経て、大学の学生相談や精神科クリニック、保健所等での心理臨床に携わってきた。また、20年以上にわたって、小中学校のスクールカウンセラーとして活動してきた経験がある。
過去に比べて婚姻件数は減っているが離婚件数は増加傾向にある
ナレッジアート(以下KA):まず初めに、近年の離婚率や離婚する人の特徴について教えていただけますでしょうか?
野口氏:直近のデータで言うと、2023年の婚姻件数は474,741組、離婚件数は183,814組となっています。一番婚姻件数が多かったのが1972年で、その時は約110万組でしたから、今では半分以下に減少している一方で、長期的に見れば離婚件数は年々増加傾向にあります。
離婚する人の特徴についてですが、調停による離婚は全体の1割ほどで、残りの約9割程度が協議離婚です。
調停離婚では、離婚の理由について主な動機を3つまで選ぶことができるのですが、最高裁判所による司法統計年報によれば、2023年における一番多い理由は「性格の不一致」で、妻側が38%、夫側が59.9%でした。これは夫婦ともに共通した主な理由ですね。二番目の理由には違いが見られます。妻側では「生活費を渡さない」が28.9%、夫側では「精神的に虐待する」が21.4%と続きます。三番目も違いがあり、妻側では「精神的に虐待する」が26.1%、夫側では「その他」になっています。また、四番目として、妻側は「暴力を振るう」、夫側は「異性関係」という結果も出ています。
協議離婚の場合は具体的な離婚の理由のデータが少ないのですが、私が2020年12月にリサーチ会社に委託して行ったアンケート調査でも、「価値観や性格の違い」が男女ともに最も多い理由でした。加えて、借金やモラルハラスメントなども男女で違いが見られました。さらに、少数ではありますが「相手の親族との付き合い」も挙げられます。特に宗教が絡んでくると、勧誘や入会を求められるなどがストレスとなり、離婚の原因になるケースもあるようです。
KA:では、離婚件数が増えている原因について、具体的に教えていただけますか?
野口氏:これについて確定的な理由を見つけるのは難しいのですが、考えられるのは、離婚に対する抵抗感が薄れたり、夫婦関係が破綻しているのならば、婚姻関係を解消するといった「離婚観の変化」ということですね。
1972年当時のデータと比較しても、当時は婚姻件数が110万組に対し、離婚件数は11万件ほどでした。しかし、現在は婚姻件数が半減する一方で、離婚件数は倍増しています。これはやはり、離婚そのものに対する心理的ハードルが下がったのが大きいと考えられます。
また、女性の経済力の上昇も影響しているでしょう。ひとり親家庭の母子世帯の平均就労収入は約240万円程度と依然低いですが、以前に比べれば女性が働きやすい環境になり、子育てと仕事を両立しやすくなっていることも背景にあると思います。
KA:つまり、職場環境や社会の変化によって、離婚をネガティブに捉える人が減ってきた、ということでしょうか?
野口氏:そうですね。それに加えて、結婚に対する価値観も変わってきています。現在の平均初婚年齢は男性31歳、女性29歳です。昔に比べて結婚のタイミングや目的も変わってきているのではないでしょうか。
親の離婚が子どもにもたらす影響は必ずしもマイナスではない
KA:では、離婚が子どもに与える影響について教えていただけますでしょうか?
野口氏:これは非常に難しい質問です。端的に言うと、生活環境や子どもの年齢、さらには別れた後の親同士の関係性によって影響の受け方が異なります。一概には言えませんが、私がこれまでスクールカウンセラーとしての経験や量的・質的調査をしてきた中で感じたことをお話ししたいと思います。
まず、子どもの年齢による違いですが、幼児期から小学校低学年くらいの子どもは「自分が悪い子だから親が仲が悪いんだ」「離婚するんだ」と、自分を責めてしまう傾向があります。「自分がいい子になれば親同士がまた仲良くなるのではないか」というファンタジーを抱いてしまうんですね。
また、離婚によって「生き別れ」を経験することも大きな影響を与えます。単独親権制度をとってきた日本では、約9割近いケースで母親が親権を取ります。その結果、父親と離れて暮らす子どもが多いのですが、生き別れの場合、別離の理由が曖昧になりやすいんです。同居している親が離婚の理由を話さなかったり、子ども自身が「聞いちゃいけない」と感じたりすることもあります。
さらに、離婚をきっかけに引っ越しや転校を経験する場合も多く、これが「喪失体験」につながります。友達を失ったり、慣れ親しんだ場所を離れたりすることは、子どもにとって非常に大きな負担になります。これにより無力感や喪失感、さらには「誰にも理解してもらえない」という苦しさを抱えやすいのです。
KA:思春期になると、離婚が及ぼす影響も変わってくるのでしょうか?
野口氏:はい、思春期になるとまた違った側面が出てきます。離婚を経験した子どもたちの中には、しっかりして自立する子もいます。「自分のことは自分でやらなきゃ」と考え、甘えを抑えて我慢することを覚えるんです。ただし、「親に甘えたい」「わがままを言いたい」という気持ちを抑え込むと、反抗期が体験できなくなり、親との関係を通して、自己を吟味するという大事な時期を失い、苦しむ場合もあります。
さらに、同居親に新しい恋人ができた場合も、思春期の子どもにとって複雑な感情を生みます。たとえば、母親と暮らしている中学生の男の子・女の子が、母親の恋人が家に来て泊まるなどの状況を経験すると、「親の性」を感じ取ってしまい、戸惑いや悩みを抱えることもあるのです。
KA:なるほど。青年期になると、どのような影響を受けるのでしょうか?
野口氏:青年期、特に大学生くらいになると、親を一人の人間として俯瞰して見るようになります。親の離婚を経験していない人と比べたりしながら、「自分にとって家族とは何なのか」「結婚とは何なのか」という疑問が生まれることが多いです。また、「自分は結婚生活をうまくやれるのだろうか」「このまま恋愛相手と結婚してもいいのだろうか」と、恋愛や結婚観にも影響が及ぶこともあります。
ただ、離婚が必ずしもネガティブな影響ばかりを与えるわけではありません。たとえば、夫婦間の激しい争いがある家庭や、暴力や悪口が絶えない環境では、離婚することで子どもがのびのびと生活できる場合もあるのです。そういうケースでは、離婚がポジティブな方向に働くこともあります。
KA:確かに、私の周りにも小学生のときに母親に引き取られた方がいるのですが、すごくポジティブで元気な人という印象があります。親御さんも優しくて明るい方で、そういう家庭では悪影響が出にくいのかもしれませんね。
野口氏:そうですね。親の離婚を経験しても、必ずしも悪影響が出るわけではありません。特に子ども自身に「褒められる要素」や「ストロングポイント」があると、苦しい体験を乗り越えられることが多いんです。
具体的には三つあります。「勉強ができること」、どんな科目でもいいので、得意科目があると自信につながります。「スポーツができること」、運動が得意だと、周りからの称賛を受けやすいですね。「人気がある」、 見た目を褒められたり、人を笑わせたりするのが得意など、自信を持つきっかけになることがあります。
子どもにとって、思春期は他者からの承認欲求が得られないと何かと不安になる時期ですが、担任の先生や顧問、友達、先輩・後輩などから「すごいね!」と言われる経験が支えになるんです。そういう子は、離婚を乗り越えていける可能性が高いですね。
KA:確かに、その知り合いも勉強ができて、野球もすごく上手でした。
野口氏:逆に、そういったストロングポイントがないと、学校生活や家庭生活が辛くなることもあります。そういう子どもには周りのサポートが必要です。ただ、あまり「頑張れ」とか「つらいね」と言い過ぎると、かえって追い詰めてしまうこともあるので、適切な距離感を持ったサポートが重要です。
やはり、子どもが一番求めているのは親からの愛情や関わりです。同居している親も、離れて暮らしている親も、できるだけ子どもに寄り添ってほしいと思います。
公教育で「結婚」について教えることが望まれる
KA: 次に、離婚後の子どもへの適切な関わり方について教えていただけますでしょうか?
野口氏: これは調査だけではあまり分かっていないので、実際にスクールカウンセラーをしていた経験から考えてみます。
サポート資源としてすごく大事だなと思うのは「教師の存在」ですね。それは担任じゃなくてもいいんですよ。生徒指導の先生でもいいし、部活動の顧問の先生でもいい。子どもの持っている悩みや苦しみにふっと気付いてあげるだけでもいいんです。子どもの生活に関心を持ってくれたり、何気なく話を聞いてくれる、そういう存在ってすごく大事だと思います。
もう一つ大事なのは、同じ経験を持っている子どもたちの存在です。離婚経験や、親が不仲だという経験を持つ子ども同士って、そこで一つつながっていくことがあるんです。経験を分かち合う——、いわゆる「ピアサポート」と呼ばれるものですね。そういう体験はとても意味があると思います。
KA:ありがとうございます。続いて、将来的に子どもが社会的に“ダメな大人”にならないための教育方法について教えていただきたいです。
野口氏: まずは、子どもには人権があるという意識をしっかり教えることが大事なんです。「子どもの権利条約」っていうのがあって、子どもには「父母から養育を受ける権利がある」と明記されています。こういった学習を義務教育の中で学んだ方がいいと思うんです。
また、学校では“結婚生活”に関する授業がほとんどないので、「将来的には家庭を持つ」といったような漠然としたイメージになりがちではないでしょうか。
KA:科目としては、社会科や家庭科になりそうですね。
野口氏:あまり暗記させるような内容じゃないので、たとえば、家庭科の方が向いているかもしれません。ただ、日本の教育って、試験に出ない内容になると教える側も授業を受ける側も熱量に個人差ができるんですよね。そこが非常に難しい。でも、公教育の中で「結婚とは何か」「結婚生活とはどういうものか」「離婚後の子どもの養育をどのように考えるのか」といったように、離婚も含めた結婚について学ぶ機会はあった方が良いと思います。
結婚を安易に捉えてしまい、子どもができたとしても、離婚後に親としての責任を全く果たさない人もいるので、教育の場できちんと伝えていくべきじゃないかなと感じています。
法改正されても虐待・DV問題が解決するとは限らない
KA:日本の離婚制度やサポート体制における課題点と、その改善策について教えていただけますでしょうか?
野口氏:全部を挙げるのは難しいですが、シンプルにまとめると、現在進行中の法改正が大きなポイントです。民法の一部を改正する法律が2026年5月までに施行される予定です。
これを端的に言うと、日本もいよいよ「単独親権」から「選択的共同親権」へと移行する、ということです。つまり、親権を一方の親が持つか、共同で持つかを選べる制度になります。G7の中でも、日本だけが単独親権を維持してきたので、これは非常に大きな変化です。
さらに、子どもの権利条約に照らしても、日本の状況には問題がありました。日本は1994年に子どもの権利条約を批准していますが、子どもが父母双方から養育を受ける権利を守れていない現状が続いてきました。つまり、名目上は子どもの権利条約を締結していましたが、その一方で、子どもの権利を担保するような制度を作っておらず、いわば長年にわたって条約に背いてきたと言えます。
KA:これまでの問題が解決しそうですが、法改正によって新たに生まれる課題などもあるのでしょうか。
野口氏:はい、特に虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)事案が問題です。たとえば、夫が妻に暴力を振るう、または妻が夫にモラルハラスメントをするようなケースでは、親権や面会交流をどうするかが非常に難しくなります。
面会交流や養育費についても、「子どもの利益」という観点から考えるべきですが、誰がどう判断するのかが重要です。当事者間で合意が取れない場合、家庭裁判所がその調整を担うわけですが、人員的な問題もあって、家庭裁判所がこの役割を十分に果たせるかどうかには疑問も残ります。
海外の事例を参考にするなら、たとえばノルウェーでは公的な第三者機関が夫婦双方の話を聞き、子どもの意見も聞き取る仕組みになっています。日本でも、地域レベルの専門相談機関が必要ではないかと感じています。市役所などの身近な場所で、専門家が子どもの声を聞きながら調整できる仕組みがあれば、離婚後の子どもの養育問題がより適切に扱われるのではないでしょうか。
月単位あるいは年単位で、一定の期間をおかないと離婚ができなかったり、離婚自体が認められていない国もあります。日本では比較的簡単に離婚できるので、離婚前に公的機関が介入して家族の問題に向き合う機会を作るべきだと思います。もちろん、そのための専門家育成も必要です。
KA:離婚後の面会交流のトラブルについて、どれくらいの件数があるのでしょうか?
野口氏:具体的な件数までは把握できていません。現行の協議離婚の制度では、離婚届の提出の際に「面会交流や養育費について話し合いましたか?」というチェック欄がありますが、チェックするだけで口約束に終わるケースも多いのです。家庭裁判所で取り決めをしても、実際に面会交流が実行されないケースもあります。罰則規定もないので、トラブルの正確な実態は掴めないのが現状です。
法務省が「面会交流支援団体等」の一覧を公表していますが、離婚後の親子での面会交流の実施が難しい場合に、当事者間の連絡調整や子どもの受け渡しといったように、民間の団体や個人による支援がされています。また、そういった面会交流支援団体間のガイドラインを作成するという動きもあります。
過去には、面会交流をめぐってのトラブルも発生しました。たとえば、別居親が子どもを連れ去ってしまうような事例もあったり、別居中の父親が面会交流中に子どもと無理心中をするといった悲しい事件もありました。
このような悲劇を防ぐにはどうすべきか、難しい課題です。虐待やDV事案については、離婚後の共同養育には反対であるという意見もあります。離婚後にも元夫婦の紛争が続くようであるならば、面会交流が必ずしも子どもの健やかな発達や身体の安全を保証できるとは限らない、という懸念があります。その点も含めて、慎重な議論が必要ですね。
離婚後の未来について考えることが子供にとっても大切
KA: 最後に、離婚を経験した、もしくはこれから離婚を検討している方に対してアドバイスをお願いしてもよろしいでしょうか?
野口氏:私が2020年に行った独自調査の結果を参考にしながら、いくつかのアドバイスをお伝えしたいと思います。
まず、離婚にはメリットもあります。412人の離婚経験者(再婚未経験者)にアンケートを行った際、自由さや気楽さ、パートナーとの争いがなくなること、ストレスの軽減などが挙げられました。これらの変化が、結果的に子どもに良い影響を与える場合もある、という意見も出ています。
しかし、一方でデメリットも確実に存在します。経済的な困難や生活基盤の不安定さが大きな問題として浮かび上がりました。特に女性にとっては厳しい生活状況になりがちです。
また、ひとり親家庭になる際には、例えば母親が子どもを連れて実家に戻る、新しい仕事を探して引っ越すなど、大きな変化が伴います。子どもも転校や転居を余儀なくされ、慣れない環境で苦労することもあります。家族の構造が変わることで生まれる負担は、決して軽いものではありません。
さらに、別居によって子どもと自由に会えなくなる問題も避けられません。父親でも母親でも、子どもと距離ができてしまい、関係が希薄になることがあります。再婚すれば、さらに前の家族との縁が切れてしまうように感じることもあるでしょう。離婚によって多くの人間関係が変わり、時には途切れてしまうことも現実です。
KA:では、どうすれば「より良い離婚」に近づけるのでしょうか。
野口氏:まず、親としての振る舞いがとても重要です。子どもの前で喧嘩をしない、離婚後もできるだけ転校や転居を避けるなど、子どもに余計な負担をかけない工夫を考えてみてください。
それから、お金の問題も無視できません。収入が不安定だと、子どもが塾や習い事に通えなかったり、部活の道具を揃えられなかったりすることもあります。特にシングルペアレントの場合、経済的な基盤がしっかりしていないと、学校外での活動など、子どもにとって必要な体験を提供できなくなるかもしれません。子どもの未来を考えれば、経済面の安定をどう確保するかも重要なポイントになります。
また、再婚を考える方も増えています。今、日本では婚姻の約4組に1組が再婚です。平均寿命が延びたことも影響しているでしょう。ただ、再婚も簡単ではありません。お互いに年齢を重ねていると、双方の親が高齢化していて介護問題が出てくることもありますし、配偶者に連れ子がいる場合には、関係づくりに工夫が必要です。さらに、相手方との親族との関係も複雑になりがちです。再婚すればすべてがうまくいくとは限らない、という現実も受け止める必要があります。
離婚は人生の大きな転機ですが、ただ「別れる」という行動だけで終わらせるのではなく、「その先の未来をどう作っていくか」を考えてほしいと思います。