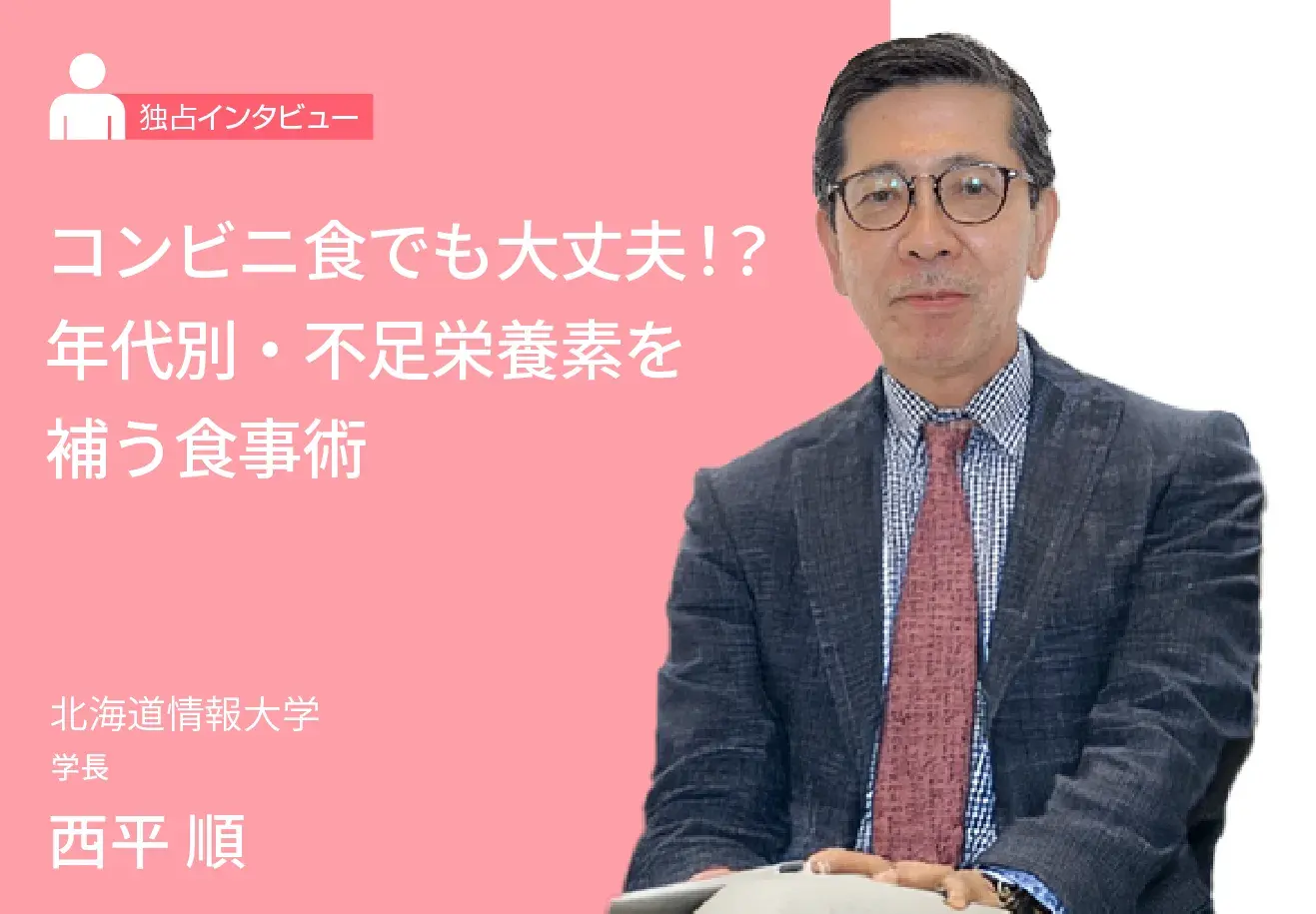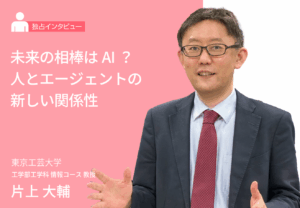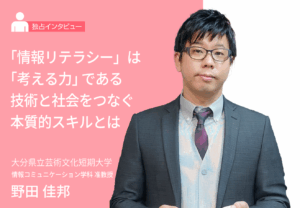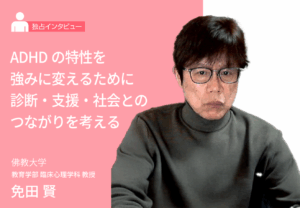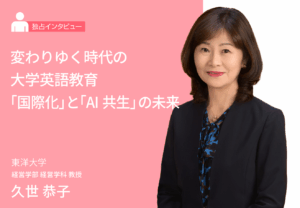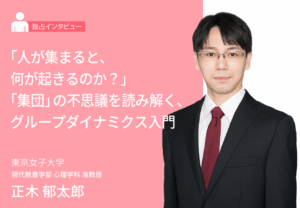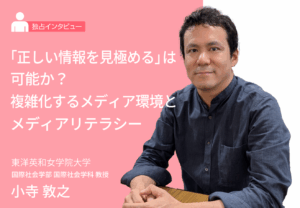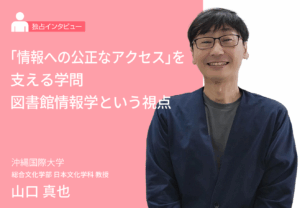私たちの食生活は、便利さを追求するあまり、知らず知らずのうちに栄養バランスを崩しているかもしれません。スーパーやコンビニで手軽に入手できる食品への依存度が高まる中、ビタミンやミネラルの不足が現代人の健康課題として浮かび上がっています。
年齢によって必要な栄養素は異なり、それぞれの世代に適した食生活の知識が必要です。この記事では、北海道情報大学の西平順教授に、世代別の必要栄養素や、日常的な食事での効果的な栄養補給方法について、具体的にお話を伺いました。

西平 順
北海道情報大学 学長
【biography】
現職 北海道情報大学 学長
昭和54年北海道大学医学部医学科卒業、北海道大学医学部内科学第二講座医員。昭和59年~60年米国ウェイクフォリスト大学医学部リサーチフェロー。平成10年北海道大学医学研究科分子医科学助教授。平成18年北海道情報大学教授、平成28年北海道情報大学副学長、令和3年北海道情報大学学長。現在に至る
研究領域(医学博士):炎症、腸管免疫、臨床栄養
医学研究から精密栄養学へ
ナレッジアート(以下KA): まず、西平先生の研究分野について具体的にお聞かせください。
西平氏: 私は医学の分野で研究を続け、これまで臨床研究と基礎研究の両方に取り組んできました。
臨床研究では、患者さんを診察しながら、病気の状態や治療法を研究します。具体的には、血液学、免疫学、糖尿病学を専門とし、患者さんのデータを基にした研究を行ってきました。
一方、基礎研究では、実験室で脂質代謝やタンパク質構造学を中心に研究を進めます。脂質代謝では、コレステロールや中性脂肪が体内でどのように代謝されるかを調べ、タンパク質構造学では、タンパク質の形状や機能を解明することに注力していました。
その後、遺伝子研究の必要性を感じ、分子生物学にも取り組みました。この分野では、遺伝子を対象にした研究を行い、生命現象の分子レベルでの理解を深めます。
その流れで抗体医薬の研究開発にも携わります。つまり、免疫の働きを調節することで病気を治療する薬を開発する分野です。例えば、関節リウマチなどの炎症性疾患を抑える抗体医薬の開発を進めています。抗体医薬の開発では、まず動物実験で抗体の有効性と安全性を確認し、その後、臨床試験で患者さんに投与して効果と副作用を評価します。
現在は、精密栄養学という新しい分野にも取り組んでいます。これは、個々人の遺伝子や代謝の特徴に基づいて、最適な栄養摂取方法を探る研究です。分子レベルでの解析を通じて、食品の機能性を科学的に解明し、健康増進に役立てることを目指しています。
KA:様々な分野の研究を行っていますね。これまでで特に印象に残った研究は何ですか?
西平氏:最も印象に残っているのは、サイトカインの構造解析に関する研究です。サイトカインとは、体内の炎症や免疫反応を調節する重要なタンパク質で、関節リウマチなどの炎症性疾患との関連が知られています。
当時、遺伝子解析技術が急速に発展していた時期で、体内のタンパク質の構造を解明することが重要な研究課題となっていました。多くの生体反応に関わる分子の形状や構造が未解明だったことは、当時の研究の大きな障壁です。
そこで私たちは、まず遺伝子の解析から着手し、その構造を詳しく調べました。この解析結果を基に、大腸菌を使って遺伝子由来のタンパク質を大量生産することに成功しています。この技術の確立は、構造解析を進める上で重要な一歩となりました。
栄養素のバランスが人体に与える影響について
KA:現在は、精密栄養学の研究をされているとのことですが、食事が体に与える影響について教えていただけますか。
西平氏:食事は体に多くの機能をもたらすため、非常に重要です。私たちの体は、主にタンパク質、脂質、糖質などの栄養素で構成されています。これらの栄養素は、私たちの体を作り上げる基本的な要素です。したがって、食事の重要性は広く認識されています。
私たちの体は、人生のさまざまな時期において、それぞれ必要な栄養素を適切に摂取することが求められます。栄養素を過不足なく摂取することが、健康を維持するために非常に重要です。病気を予防したり、体調を整えたりするためには、必要な栄養素をしっかりと摂取することが必要になります。
具体的には、糖質、タンパク質、脂質、ミネラル、ビタミンの5大栄養素をバランスよく摂取することが重要です。これらの栄養素に基づいた理解を深めることが、食事の重要性を理解する上は必要になるでしょう。
最近の研究では、食物繊維の重要性も強調されています。食物繊維は体に吸収されない栄養素ですが、体内の栄養素のコントロールに寄与します。したがって、5大栄養素に加えて食物繊維を含む食事をバランスよく摂取することが、健康維持においては重要です。
KA:もしビタミンやミネラルが不足すると、どのような健康問題が生じるのでしょうか。
西平氏:ビタミンやミネラルは、体の代謝や活性化に必要不可欠です。特にビタミンDは免疫機能や骨の健康に関与しています。しかし、若い世代を中心に摂取量が不足していることが多いのが現状です。ビタミンやミネラルが不足すると、体調不良やストレス、睡眠の質の低下など、さまざまな健康問題が引き起こされる可能性があります。
また、現代の食事パターンでは、調理をほとんど行わずに手軽に食べられる食品が増えています。スーパーやコンビニで販売されている食品は、加工の過程でビタミンやミネラルが失われることがあるため、ビタミンやミネラルが不足しがちになります。このような食事のみに偏ると、必要な栄養素が十分に摂取できず、健康に悪影響を及ぼす懸念があります。
日本人の食生活における現状の問題点と改善策
KA:では、現代の日本人の食生活には問題点がありそうですね。現状の問題点とその問題点に対する改善策について教えていただきたいです。
西平氏:現在の日本人の食生活における問題点は、食事のスタイルにあるでしょう。加工技術が非常に進んでいるため、食品メーカーは多様な加工食品を製造しています。これは一見良いことのように思えますが、過度な加工が行われると、塩分や砂糖などが多くなり、一方ではビタミンや食物繊維などの栄養素が失われてしまいます。
例えば、白米は玄米に比べてビタミンや食物繊維が大幅に減少します。また、通常の食パンも同様に、元々は豊富に含まれている食物繊維が製造過程で失われてしまいます。このような加工食品を多く摂取することで、ビタミンやミネラルが不足してしまうという状況が見受けられます。
したがって、全粒粉や加工されていない玄米など、栄養素をしっかり摂取できる食品を選ぶことが重要です。加工食品は美味しさや手軽さを追求するあまり、栄養素が不足しがちになってしまいます。その結果として、食事を摂っているにもかかわらず、ビタミンやミネラルが欠乏してしまうことが大きな問題となっているといえるでしょう。
このような問題の対策として食品の強化が行われ、ビタミンDやミネラルを添加することが一般的になっています。しかし、それでも添加量が圧倒的に不足しています。したがって、主食であるお米など、毎日食べる食品からしっかりと栄養素を摂取する必要があるでしょう。食事のバランスが重要であるとされているものの、実際には十分な栄養素が摂取できていないのが現状です。
今後は、食事のバランスを取るために、微細ミネラルが豊富に含まれている食品を選ぶことが求められます。また、消費者の食品に対する理解やリテラシーも重要です。健康を維持するためには、食事に対する関心を高め、食材についての理解を深めることも必要になるでしょう。先程も話したように過度に加工されたいわゆる「超加工食品」を含む食事のバランスが問題となっているため、食品の知識に対する啓蒙活動がますます重要になると考えています。
KA:食品に対する理解やリテラシーにも関わることなのですが、必要な栄養素は年齢層により違いはあるのでしょうか。
西平氏:はい、若い世代は体を作るために代謝をしっかりと上げる必要があります。骨格や筋肉をしっかりと作るためには、栄養素のバランスが重要です。特に、タンパク質や骨に必要なビタミン類をしっかり摂取することが求められます。しかし、調査によると、若い人は忙しさから食事を摂る時間が不足していることが多く、スーパーやコンビニなどで手軽に購入できる食品に頼る傾向にあります。したがって、必要な栄養素が不足しがちです。
特に女性の場合、痩せることを重視する傾向があり、体重を減らすことに注力するあまり、栄養バランスが崩れることがあります。栄養バランスが崩れれば、若い女性でも骨粗鬆症のリスクが高まる可能性があります。また、男性は最近、肥満傾向が見られ、若い世代でも糖尿病のリスクが増加しています。これらの問題は、若い世代においても体の虚弱性が現れていることを示しています。
一方、高齢者の場合、体の代謝が低下するため、食事のバランスが特に重要です。高齢者は、筋肉量が減少しやすく、フレール(虚弱)状態に陥ることがあります。運動を行うことはもちろん重要ですが、同時に筋肉を維持するために必要な栄養素であるタンパク質を十分に摂取することが求められます。
まとめると、全体として、若い世代と高齢者の両方において、食事バランスをとることが重要です。不足しやすい栄養素をしっかりと調べ、必要な栄養素を意識的に摂取することが求められます。若い世代は、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルが不足していることが多く、また高齢者は不足しがちなタンパク質をバランスの取れた食事を摂る傾向があります。
また、若い世代の女性は骨が弱くなりやすく、男性は炭水化物の摂取過多による肥満が問題となっています。清涼飲料水などの糖質が多い食品は肥満につながりやすく、甘味料の摂取過多も懸念されています。これらの問題を解決するためには、食事の選択を見直し、栄養バランスを意識することが重要です。
生活習慣病予防のための食生活と遺伝的要因を持つ場合の対策
KA:生活習慣病を予防するための食生活について教えていただきたいです。
西平氏:栄養学において最も重要なのは食事のバランスです。厚生労働省や文部科学省から栄養素の摂取に関する表示や最低必要量が示されています。消費者はその表示を見ながら必要な栄養素を把握することができます。
しかし、現在の食事パターンでは、必要な栄養素を十分に摂取できていないのが現状です。不足している栄養素を補うために、個人の食生活の傾向を把握する必要があります。栄養調査によって、どのような食生活をしていると、どのような栄養素が不足するかがおおよそ把握できるからです。
現在、私たちは食事のバランスを分析するアプリを開発しています。このアプリでは食生活を聞き取ることにより、不足している栄養素を指摘し、適切な食材の摂取についてのアドバイスを提供することが可能です。一般の人々にとって栄養学は複雑で理解が難しい分野です。したがって、個人の生活習慣に基づいたアドバイスを提供できる仕組みが今後重要になるため、現在、研究を含めた社会実装に向けて取り組んでいます。
また、病気を未然に防ぐためにも、栄養素の不足を発見し、必要な食材を具体的に提案することが重要です。私たちが取り組んでいる個別化栄養の考え方では、個人ごとに不足している栄養素を特定し、アプリを通じて具体的なアドバイスを提供します。現在の栄養学は一般的な話にとどまっていますが、今後は科学的なデータに基づいた精密栄養学へと発展していくと考えられます。
KA:生活習慣病の1つとして糖尿病があります遺伝的な要因で生活習慣病にかかりやすい方々が、食生活だけで糖尿病などを予防し続けることは可能なのでしょうか?
西平氏:予防は可能です。私たちは15年から20年近く、食品の機能性研究のためヒトを対象にした食の臨床試験を実施していますが、試験に参加した人々の中には、糖尿病になりやすい遺伝的素因を持つ人々もいます。しかし、臨床試験で糖尿病の性質や食事との関係性についての年1回のレクチャーにより、ヘモグロビンA1Cや空腹時血糖などの数値が一般の人々と同様に改善しています。
生活習慣病は、生活改善によって改善する可能性のある病気です。糖尿病、高血圧、肥満、高脂血症などは、遺伝的な背景があっても、食事による改善が期待できます。単一の遺伝子異常による遺伝病とは異なり、生活習慣の改善により予防や改善につながります。
糖尿病に関して言えば、糖尿病の主な原因は膵臓から分泌されるインスリンの問題です。インスリンは血糖値を下げる働きがあり、筋肉や脂肪にエネルギーを蓄積します。しかし、食べ過ぎが続くとインスリンを分泌する膵臓のベータ細胞が疲労してしまいます。
40歳から50歳になると、インスリンの分泌能力は若い時の半分程度まで低下します。若い時からの過食や、遺伝的に糖尿病になりやすい人は、このベータ細胞の疲労が早く進行する傾向があります。また、欧米人は東洋人と比較して、インスリンを分泌する潜在能力が高く、糖尿病になりにくい傾向があります。しかし、日本人やアジア人は、もともとインスリンの分泌能力が低いため、過食により糖尿病になりやすい傾向があります。
このような人種による違いも考慮しながら、個人の持つ遺伝的背景に応じた食生活や運動についてのアドバイスを提供することが重要になるといえるでしょう。
今後注目される健康食品と栄養素について
KA:食生活の重要性はしっかりと認識しておく必要がありますね。では、今後注目される可能性のある健康食品などはあるのでしょうか。
西平氏:現在、栄養に関する研究は非常に重要な分野となっています。私たちの体は食べたもの(食事)で作られますが、実際にはそれが体内の酵素によって吸収されるだけではなく、腸内細菌の役割が極めて重要であることが最近の研究で明らかになっています。
腸内細菌が栄養吸収に貢献する際、特に食物繊維との関連が注目されています。食物繊維は栄養素として直接吸収されることはありませんが、特定の腸内細菌は食物繊維を分解する能力を有しており、分解反応を通じて腸内環境の改善やエネルギー生成に寄与していることが確認されています。
したがって、今後注目される食品の1つは食物繊維を豊富に含む食品です。食物繊維を十分に摂取するためには、毎日食べる主食に食物繊維を含めることが必要になります。例えば、スーパーやコンビニで販売されているパンは、もともと小麦を原料として食物繊維が豊富でしたが、製造過程でその成分が失われてしまっているため、それを補うため食物繊維を多く含む食品を日常的に摂取することが求められています。特に、大麦などの穀物は食物繊維を豊富に含んでおり、日常的に摂取することで健康を維持する助けになります。
また、腸内細菌を活性化させるためには、ヨーグルトなどの乳製品が重要です。特定の腸内細菌を含む製品が増えており、腸内環境を整えるための「腸活」が注目されています。さらに、最近の感染症の影響で免疫力が低下しているため、ビタミンDの重要性も増しています。ビタミンDは骨粗鬆症の予防だけでなく、免疫機能を高める役割も果たします。ビタミンDを含む食品としては、キノコや乳製品が挙げられます。
また、オメガ3脂肪酸も重要な栄養素です。オメガ3は魚や良質な油に含まれ、動脈硬化の予防に寄与します。これらの栄養素、すなわち食物繊維、ビタミンD、オメガ3脂肪酸は、今後の健康食品としてますます重要になってくると考えられます。これらの栄養素をバランスよく摂取することが、私たちの健康を保つために必要です。