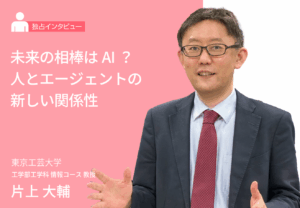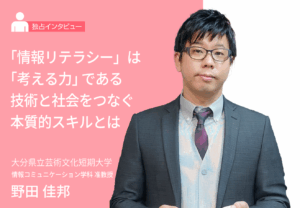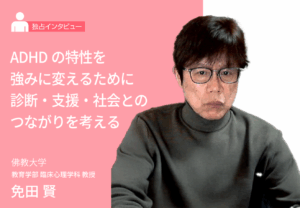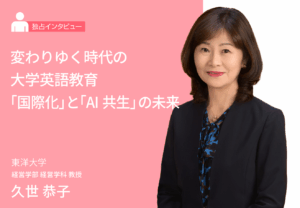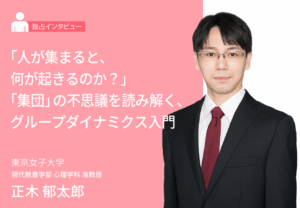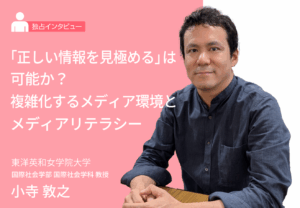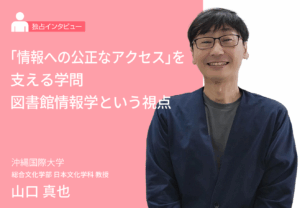ICT(Information and Communication Technology)は若者やビジネスの場で使われるイメージがあるかもしれません。
しかし、実際はICTを学ぶシニアや、シニア向け講座も増えてきています。
そこで今回は、東京情報大学教授の松下孝太郎先生にシニア向けICT教育の実情や今後の課題について、お話を伺いました。

松下 孝太郎
東京情報大学 総合情報学部 教授
【Biography】
神奈川県横浜市生まれ。
横浜国立大学大学院工学研究科人工環境システム学専攻博士後期課程修了 博士(工学)。
現在、(学校法人 東京農業大学)東京情報大学 総合情報学部 教授。
画像処理、コンピュータグラフィックス、教育工学の研究に従事。
教育面では、プログラミング教育、シニアや留学生へのICT教育等にも注力しており、サイエンスライターとしても執筆活動および講演活動を行っている。
ICT教育によりシニア層の余暇はより充実する
ナレッジアート(以下KA):そもそも自分自身、松下先生にシニア向けのICT教育についてお話を伺う前は、「シニア向けのICT教育なんてあるんだ」と思っていました。実際に、こういった教育はどこで受けることができるのでしょうか?
松下氏:シニア向けのICT教育は、意外と身近な場所で受けることができます。
まずお勧めしたいのは、大学の公開講座ですね。多くの大学が地域の方々向けに公開講座を開いており、その中にICTに関する講座が含まれていることがよくあります。
市町村が主催する無料の講座もあります。これは自治体によって異なりますが、比較的多くの地域で開催されており、特に都市部では多くの講座が開催されています。ただし、地方や小規模な自治体では開催されていないこともありますので、お住まいの地域の広報誌や役所のホームページなどで確認するとよいでしょう。
また、カルチャースクールでもシニア向けのICT講座が開かれています。こちらは有料ですが、講師が個人のレベルに応じて丁寧に指導してくれる講座もあるため、基礎からじっくり学びたい方に向いています。
これらが一般的な学習の場ですが、最近ではオンライン講座も増えています。特に、YouTubeやZoomを活用した授業は、シニアの方々が自宅にいながら学べるため、非常に人気が高まっています。
このように、ICT教育を受ける手段はさまざまありますので、ご自身の学びやすい環境を選ぶことが大切ですね。
KA:なるほど、ありがとうございます。それでは、シニアICT教育の目的や意義について教えていただけますでしょうか。
松下氏:シニア層におけるICT教育の目的として、最も大きなニーズは「余暇の充実」です。最近では、ICTを活用して動画を視聴したり、趣味に関する情報を検索したりすることが一般的になっています。例えば、ゴルフを趣味とする方であれば、ゴルフに関する情報をインターネットで調べたり、レッスン動画を視聴したりすることができます。このように、ICTを利用することで余暇をより有意義に過ごせるようになる点が、シニアICT教育の大きな意義の一つだと考えています。
また、私が考えている意義は「異世代間のコミュニケーションの活性化」です。インターネットの普及により、シニア層のICTリテラシーも向上しており、異世代間の交流がより活発になってきています。特に、現在では小学生でもスマートフォンを持ち、インターネットを利用することが一般的です。そのため、オンラインを介した共通の話題が生まれ、世代を超えたコミュニケーションが可能になっているのです。
ご存じの方も多いと思いますが、かつて昭和中期頃までは、祖父母と孫が同居する家庭も多く見られましたが、核家族化の進行により世代間の分断が進んできました。しかし、近年のインターネットや動画コンテンツの普及、さらにはスマートフォンの広がりによって、再び世代間の絆が深まる可能性が高まっていると考えられます。特に、共通の話題を持つことができる点は、異世代間の関係を強化する重要な要素となっています。
KA:シニアがICTを使いこなすことで、余暇を充実させたり異世代とのコミュニケーションが活発になったりするのですね。
松下氏:はい。シニアICT教育の意義は単なる余暇の充実にとどまらず、世代間のつながりを深める新たな役割も担うようになっています。今後も、ICTを活用した世代を超えたコミュニケーションの可能性に注目していきたいと思います。
KA:私の周りのシニア層は、迷惑メールを見極められなかったり、有料アプリであることを知らずに利用したりすることがあります。また、無料解約期間を忘れてしまい、意図せずお金を支払ってしまうケースもあります。こうしたネットリテラシーに関するトラブル防止のための教育は、どの程度行われているのでしょうか?
松下氏:そうですね。私自身はその分野に特化して教えているわけではありませんが、毎回話していることはあります。
迷惑メールに関しては、基本的に怪しいメールが届いても返信しなければ大きな問題にはなりません。ただし、お金に関するメールは特に注意が必要です。例えば、銀行口座へのアクセスを求めるようなメールには絶対に対応しないよう強く伝えています。ネットバンキングに関しても、多要素認証が必要になるため、シニアの方々にはハードルが高く、そもそも利用していない方も多いです。
実際、迷惑メールに中途半端に引っかかってしまうのは40代・50代の方が多く、シニアの方は「そもそも操作が難しくて対応できない」ということもあります。しかし、それを理由に「シニアだから安全」というわけにはいきません。メールに含まれるマルウェアやスパイウェアを不用意に開いてしまうと、自分のパソコンが踏み台となり、加害者になる可能性もあります。そのため、「不審なメールは開かない」という基本を徹底することが重要です。
また、スマホの課金に関してですが、私の講座ではあまりスマホの話はしていません。現在のシニアの方々は、最初から入っているアプリしか使わないことが多く、意図せず課金するケースは少ないように思います。ただし、今後スマホ世代がシニアになっていく中で、アプリ課金に関するトラブルが増える可能性は十分にあります。そのため、スマホの課金に関する注意喚起も強化すべきだと考えています。
今後は、こうしたネットリテラシーの教育も重要になっていくと思います。
世代間のリテラシー格差や端末の使いづらさが課題
KA:では次に、シニアICT教育の現状の課題点と、それに対する改善策について教えていただけますでしょうか。
松下氏:私は約20年にわたり、地域のシニア向けパソコン教室や、本学の公開講座を担当してきました。その中で、シニアICT教育の現状が大きく変化してきたと感じています。
以前は、65歳以上のシニアの方々のICTリテラシーに大きな差は見られませんでした。しかし、現在では65歳、70歳、75歳などと、年齢が少し違うだけでICTスキルに明確な差が生じています。これは、スマートフォンやインターネットの普及により、比較的若いシニアほどリテラシーが高い傾向にあるためです。そのため、シニアICT教育の課題の一つとして、「年齢によって異なる学習ニーズに対応する必要がある」ことが挙げられます。
改善策として、公開講座や地域の講座では、学生アシスタントを配置し、個別対応を行うことが有効です。例えば、私のゼミの学生を補助員として雇い、受講者の質問に直接対応することで、学習の効率を向上させることができます。
KA:個別対応が必要になっているのですね。他に課題はありますか。
松下氏:もう一つの課題として、「端末の操作性と視認性の問題」があります。特に、スマートフォンの普及により、シニア層だけでなく40代以降の社会人層でも、老眼の影響で画面の文字が見づらいという問題が顕在化しています。例えば、レストランでのQRコード決済や、アプリを利用した手続きを行う際に、画面の小ささが障害となることが多いです。
この問題の解決策としては、ICT教育の中で「スマホアプリの基本的な操作方法」を重点的に指導することが重要です。若年層はスマホアプリの操作に慣れていますが、シニア層やシニア手前くらいの層は「アプリを使うこと自体が面倒」と感じる方も多いため、基本的な操作を体系的に学ぶ機会を提供することが必要です。
こうした点を踏まえ、今後のシニアICT教育では、世代間のリテラシー格差や端末の使いづらさに対応したカリキュラムの開発が求められると考えています。
KA:端末の使いづらさに着目したことはなかったのですが、確かにおっしゃる通りですね。
若い人の方がICTリテラシーが高いというお話がありましたが、年齢ではなく、地方と都市部で考えたときに、シニア向けICT教育に違いは生じる可能性があるのでしょうか?
松下氏:そうですね。私自身、地方でのシニア向け講演を依頼されたことはあまりないため、明確な違いを比較するのは難しいのですが、確実にいくつかの差はあると思います。
まず、ICTの必要性が異なるという点があります。例えば、都市部ではキャッシュレス決済やQRコード注文、オンライン予約などが普及しており、シニアの方々もこれらを使わざるを得ない状況が増えています。一方で、地方ではそうしたデジタルツールの導入が遅れているケースが多く、ICTの必要性自体が低いことがあります。
また、学習機会の格差も考えられます。都市部では大学の公開講座、市町村主催の講座、カルチャースクール、民間企業のセミナーなど、多様な学習機会があります。しかし、地方では講座の開催頻度が少なく、学べる環境が限られてしまうことが課題です。そのため、地方のシニア向けICT教育では、オンライン講座を活用するなどの工夫が求められるでしょう。
さらに、地域ごとの生活スタイルの違いも影響します。例えば、都市部のシニアは公共交通機関を利用する機会が多いため、乗換案内アプリの使い方を知ることが重要です。一方、地方では車移動が中心となるため、カーナビの活用やスマートフォンの地図アプリの使い方のほうが重要視されるかもしれません。
このように、地方と都市部ではシニア向けICT教育に違いが生じる可能性があり、地域ごとのニーズに合わせた内容のカスタマイズが重要だと考えています。
遊ぶ感覚から実生活に活きる体験を
KA:では、シニアに対しての効果的なICT教育方法について教えていただけますでしょうか?
松下氏:まず、遊びから始めることが重要です。これは子供たちにも共通していますが、どんな勉強や仕事でも、興味がなければうまくなりません。特にICTの分野では、興味を持たせないと全く習得が進みません。
例えば、国語や社会などの科目は、ある程度強制的に勉強することで身につけることもできます。しかし、ICTは芸術や体育と同じで、自分から積極的に取り組まないと技術が向上しません。頭脳も重要ですが、ある程度職人的な要素も含まれているため、実際に手を動かして学ぶことが不可欠です。そのため、まずは遊びを通じて興味を引くことが大切なのです。
KA:どの世代においても、自ら興味を持って学ぶことは大切ですよね。
松下氏:はい。これはすべての世代に共通する方法ですが、特にシニアに対しては生活の利便性に直結したものを教えることが重要です。
長年この分野に携わってきた経験から、シニアの方々も最初は遊びを通じて興味を持つことが多いですが、小学生などと比べると飽きるのも早い傾向があります。そのため、最初は遊びでも良いのですが、それだけでは続かない方も一定数います。
シニアの方々は、人生経験が豊富で落ち着いており、時間的な余裕もあります。そのため、生活に直結した内容を学ぶことが重要になります。例えば、公開講座などでは、特に女性からのリクエストが多いのですが、「簡単な家計簿の作り方を教えてほしい」という要望がよくあります。
会計ソフトも販売されていますが、家庭のお金の管理くらいであれば会計ソフトほどの高機能は不要です。そのため、広く普及していているExcelで家計簿を作る方法を学びたいというニーズが非常に高いのです。年金収入があり、毎月どのくらいの支出があるのかを把握することは、多くのシニアにとって非常に重要な関心事です。特に、資産を取り崩しながら生活している方々にとっては、残高を管理することが大切になります。
KA:なるほど、確かに実際に活かせる場面が分かれば、学ぶ意欲も湧いてきそうです。
松下氏:また、インターネット関連では、旅行や風景に関する情報への関心が高い傾向があります。これは単なる娯楽ではなく、日々の生活の一環として捉えられています。さらに、電車の時刻表の確認など、日常生活に密接に関わる情報を得る方法を学ぶことも重要です。
このように、シニアに対するICT教育では、単なる遊びだけでなく、生活の利便性に直結する内容を提供することが特に重要だと考えています。
KA:教育方法として、対面授業とオンライン授業というのがあると思いますが、実際に行う際、どちらが効果的だとお考えですか?
松下氏:そうですね。シニアの方ですと、現時点ではやっぱり対面の方がいいとは思います。若者は自分で解決してくれるとは思いますけど、やっぱりシニアになったら手を差し伸べないとなかなか解決できない問題もあると思うからです。
集中力という面でも、若者だけだったら「ちょっとじっくり考えてみるか」っていう子も多いと思うんですけど、シニアの方は「なんかめんどくさいな」って思ってしまって、早く答えが欲しい人も多いでしょう。
このような理由で、シニアの方は先生なり補助学生とか補助員がいて、分からないことをその場で解決できるようにしないと「やめた」ってことになっちゃうと思いますので、シニアに関しては対面の方が教育効果はあると思います。
「個別に」「手厚く」が求められるシニアのICT教育
KA:松下先生はそのシニアICT教育を実際に経験されて、大変だったことや、それをどのように乗り越えたか、成功事例を教えていただけますでしょうか?
松下氏:はい、最近では、先ほどお話ししたように、シニアの方々もある程度のITスキルを持つようになってきました。ただ、世代によってツールの習熟度に差があり、大人数での講座ではその世代間格差が問題になることがあります。
この課題を解決するために、補助学生を配置したり、市の職員の方に協力を仰いだりして対応しています。
かなり前までは、キーボードをほとんど触ったことがない方が多く、どの指でキーを押すのかといった基礎から教える必要がありました。しかし、最近ではPCをある程度経験した方が増えており、そうした状況は改善されつつあります。それでも、年代ごとに異なる課題があり、受講者がどこでつまずいているかを素早く見抜き、適切にフォローすることが求められます。
KA:受講生ひとりひとりを見る体制が求められそうですね。
松下氏:はい、個別対応の重要性を感じています。若い世代の場合、講師が前で説明すれば理解できることが多いですが、シニアの方は集中力や体力の問題もあり、手厚い個別指導が必要になります。また、高齢になると気が短くなったり、面倒に感じたりすることもあります。そのため、単に技術を教えるのではなく、精神的なケアをしながら指導することが重要です。
KA:では、成功事例を教えていただけますか。
松下氏:成功事例としては、成功体験を提供することが非常に効果的でした。シニアの方々は技術的な個人差が大きいため、それぞれに合った簡単な課題を設定し、小さな成功体験を積んでもらうことで自信を持たせることができます。これにより、学習意欲が向上し、自宅でも復習しようという気持ちにつながります。
また、復習の重要性も強調しています。講座の最後には必ず「今日学んだことは可能であれば当日中に復習してください」と伝えています。年齢を重ねると記憶の定着が難しくなるため、当日中に復習することで学習効果が高まります。
これらの工夫により、シニアICT教育の課題を乗り越えてきました。
KA:シニア層が拡大していく中で、受講者が増加すると思います。それでも個別に手厚く指導するための対策は考えていますか?
松下氏:そうですね。確かにシニアの人口は増えていきますが、一方で安心材料もあります。現在のシニア世代は若い頃にパソコンやネットに触れてこなかったため、学習のハードルが若い世代と比較して高いです。しかし、今後シニアになる世代から下の世代は、すでにある程度のデジタルスキルを持っている人が多いので、指導もしやすくなるはずです。
例えば、私の同世代の友人で「スマホがまったく使えない」という人はほぼいません。現在のシニアほど手厚い指導が必要なくなるため、総合的な労力はそこまで増えないと考えています。人数は増えても、一人ひとりのスキルは向上していくので、結果として全体の負担はそこまで変わらないのではないでしょうか。
今後も、シニア層のデジタルリテラシー向上を見据えた教育を続けていきたいと考えています。
最新のICT教育をキャッチアップし実用性を高める
KA:では、最後にこれからシニア向けのICT教育を行う方に対して、アドバイスをお願いいたします。
松下氏:これは、どの世代に対しても共通することですが、まずは「興味を持たせる」ことが最も重要です。「これをやりなさい」と押しつけるのではなく、受講者自身が「やってみよう!」と思えるような授業や講座を展開することが大切です。とはいえ、これは簡単ではなく、講師の経験も問われる部分です。シニアの方々が楽しく学べる環境を整え、適切な題材を用いることで、学習意欲を高めることができるでしょう。
加えて、ICTの進歩は非常に早いため、教える側は常に最新のトレンドを把握することが求められます。例えば、数年前に流行っていたツールが、現在ではほとんど使われていないということはよくあります。YouTubeのように長く続くものもありますが、多くのアプリやサービスは短期間で移り変わるため、時代遅れの内容を教えてしまうと、受講者にとって実用性が低くなってしまいます。
KA:時代の変化に合わせて教える内容が変わってくるのですね。
松下氏:時代の変化で言うと、若者のトレンドを積極的に取り入れることもシニア教育には効果的です。これは単に流行に乗るという話ではなく、世代間のコミュニケーションのきっかけになるためです。若い人が使っているツールを学ぶことで、孫世代との会話が弾んだり、SNSを通じて新しい交流が生まれたりする可能性があります。シニア向けのICT教育は単なる技術習得ではなく、人とのつながりを生み出すものでもあるのです。
KA:若者に限らず、最近のトレンドとしてAI技術、特に生成AIが急速に発展しています。利用者も増えていると思いますが、このような技術をシニア世代に教える際、どのように活用できるとお考えですか?
松下氏:私自身も生成AIをシニアに教えるのは面白いだろうと思っているのですが、いくつかの課題があるのも事実です。
例えば、以前ある出版社の方に同様の質問を受けたことがありますが、生成AIを使おうとすると、まずGoogleアカウントを取得したり、ユーザー登録をしたりといった手続きが必要になります。若者であれば問題なく対応できますが、シニアの方に「Googleアカウントを取ってください」「ログインしてください」とお願いするだけで、多くの方が躓いてしまいます。すでにその段階で「こんな面倒なことならやりたくない」と思ってしまうのです。
また、生成AIの利用には、アカウント認証のためにスマートフォンに通知が送られることもあります。これがシニアの方にとっては大きな壁になりがちです。認証手続きが複雑であることが、現時点での普及を難しくしている要因の一つです。
KA:確かに生成AIを導入するハードルは高そうですね。
松下氏:さらに、生成AIのインターフェースは頻繁に変わります。例えば、プログラミング言語の開発画面などはある程度決まった形がありますが、生成AIはUI(ユーザーインターフェース)などが頻繁に変更される傾向があります。これもシニアの方にとっては混乱の元になります。
もちろん、ChatGPTのようにスタンダードになりつつあるものもありますが、現状ではまだ「Windows」や「MacOS」、「Microsoft Office」のような決定的な標準がないため、変化に対応するのが大変です。
個人的には、シニアの方に生成AIのデモを見せたりして、どのようなものか興味を持ってもらう機会を作っています。実際に見せると「おお!」と驚きながら関心を持ってくれることが多いです。ただ、現状ではシニアの方が一人で家に帰って使いこなせる環境にはまだなっていません。
将来的には、シニア世代にも生成AIを教える社会になるのは間違いないと思います。私自身もいずれその年齢に達することになりますし、そのときには、もっと使いやすい環境が整っていることを期待しています。
#松下孝太郎 #シニアICT #生成AI