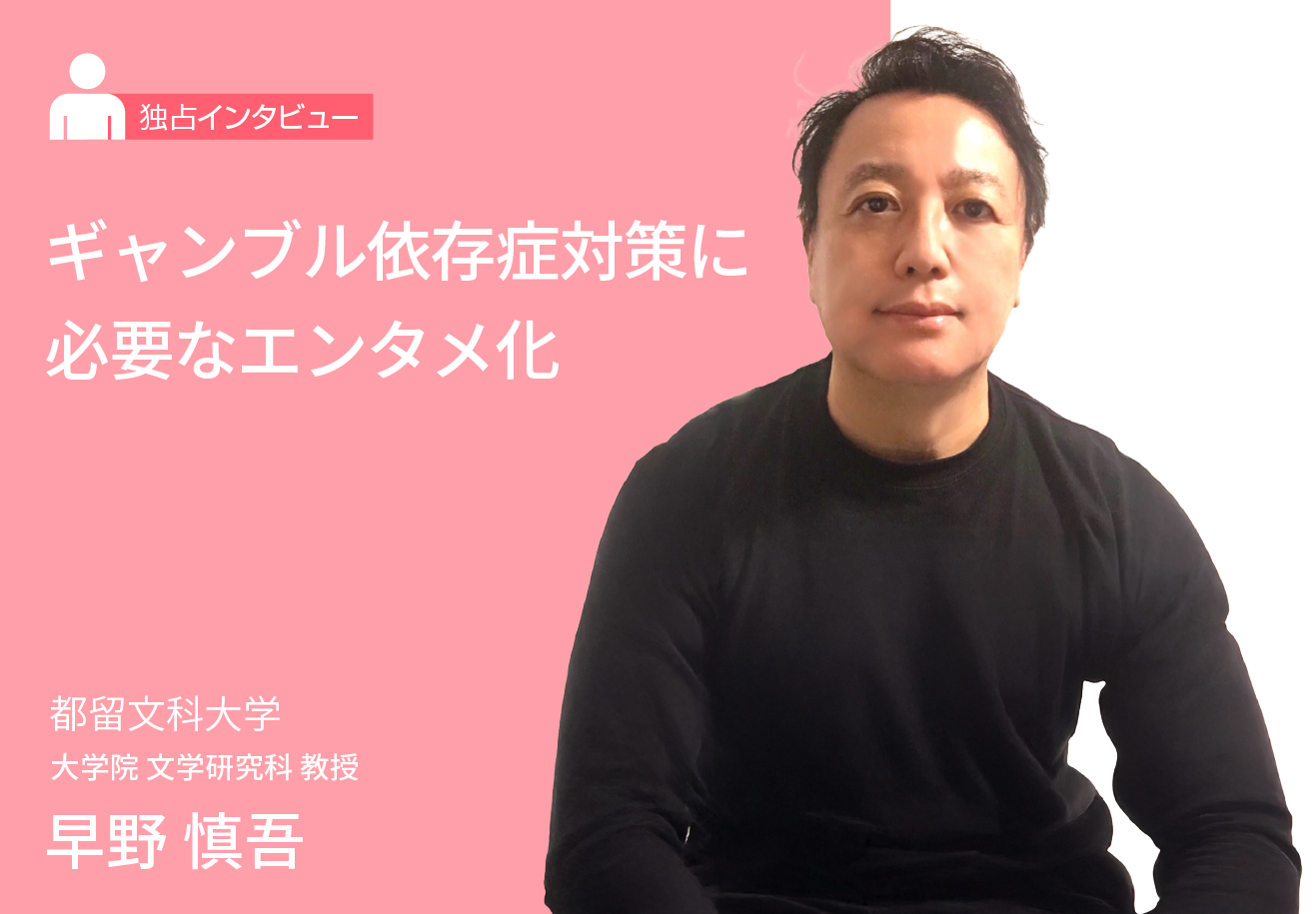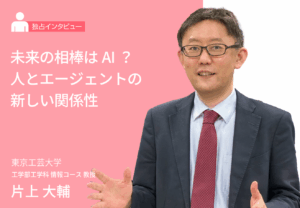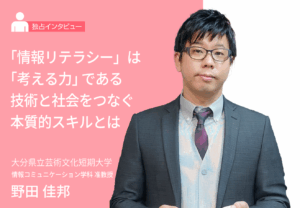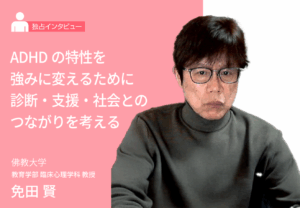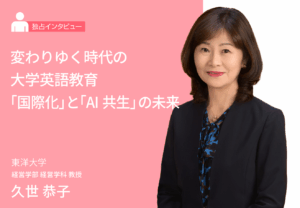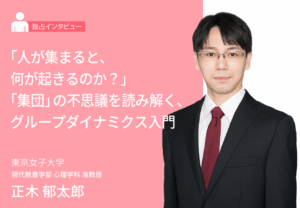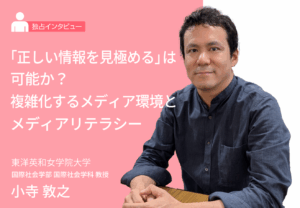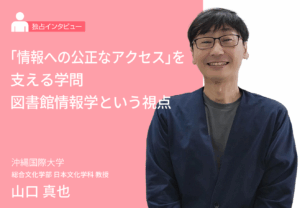「日本には536万人のギャンブル依存症患者がいる」という数字をメディア報道で耳にしたことのある人も多いかもしれません。しかし、その後、より厳密に実施さられた「国内のギャンブル等依存に関する疫学調査」(久里浜調査:調査対象者10,000名、有効回答数は4,685名)によると、ギャンブル依存症が疑われる割合は、過去1年で0.8%(推定70万人)と発表されました。それなのに、いまだに536万人という数値が使われているのが現状です。
この記事では、都留文科大学の早野慎吾教授にギャンブル依存症についての真実を語っていただきました。誤った報道と偏見に覆われてきたギャンブル依存症の実態を、科学的データに基づいて解き明かしていただきます。また、同氏の提案する「ギャンブルのエンターテインメント化」というギャンブル依存症対策の新しいアプローチについても伺っています。
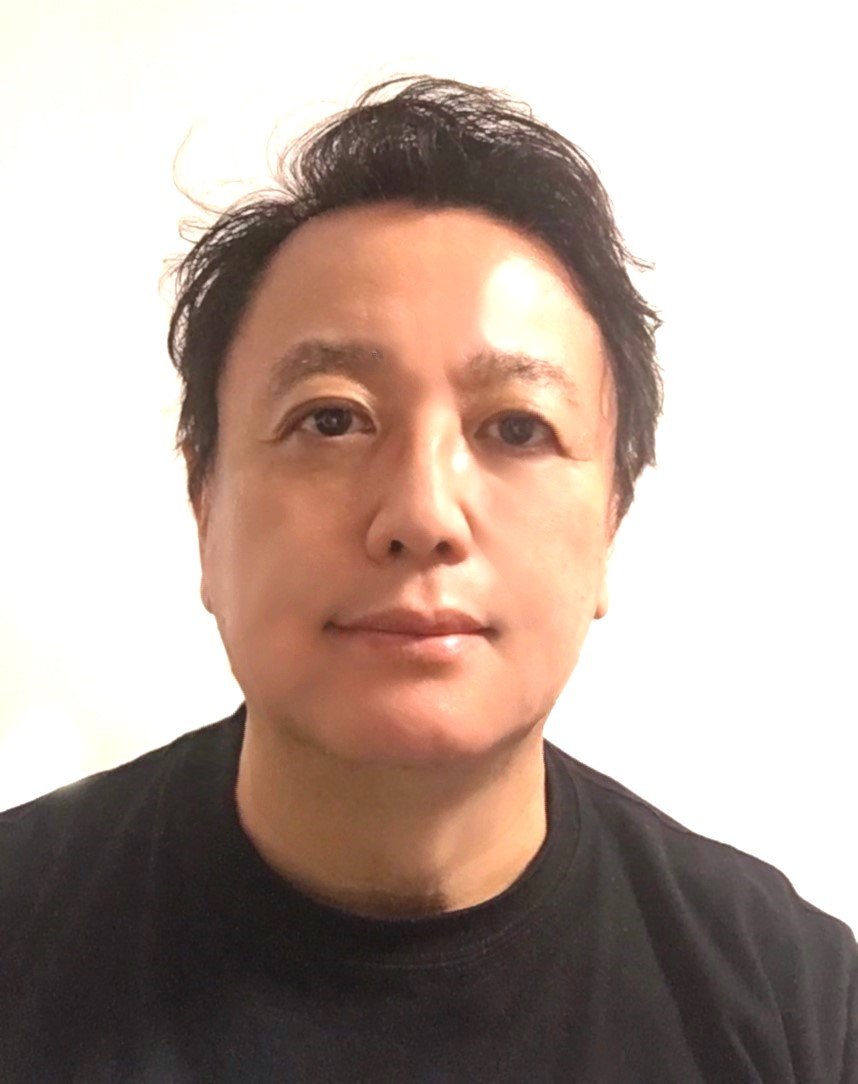
早野慎吾
都留文科大学 大学院文学研究科 教授
【biography】
専門:言語心理学 社会心理学。常磐大学講師、宮崎大学准教授を経て2012年より現職。
The study of differences by region and type of gambling on the degree of gambling addiction in Japan.Scientific Reports.2021 https://doi.org/10.1038/s41598-021-92137-8
Investigating the Effect of Jo-Ha-Kyū on Music Tempos and Kinematics across Cultures: Animation Design for 3D Characters Using Japanese Bunraku Theater.Leonard 55 (5)
The MIT Press.2022 https://doi.org/10.1162/leon_a_02250
A Study on the Effect of Gambling Advertising on Gambling Addiction in Japan.Ars Linguistica 28.2022
言語学から依存症研究へ
ナレッジアート(以下KA):先生の研究分野について具体的に教えてください。
早野氏: 専門は言語心理学、社会心理学です。当初、農芸化学の研究をしていましたが、大学院から言語学を専攻しました。ただし、もっとも得意なことはデータ解析で、どのようにデータを採取してどのように解析するか、そしてデータと結論が合っているかどうかが最大の関心事です。
私は方言学という分野から言語学に入ったのですが、言語使用のもっと深いところにある心理面や社会面の状況を知りたかったので、心理学や社会学の研究成果を積極的に取り入れてきました。共感の言語学をテーマに効果的なコミュニケーションの方法や、感情表現、他者理解などを中心に分析してきました。結局、社会学、心理学、言語学、文化人類学などの複合分野ですので、従来の〇〇学という区分では適切に表現できません。心理学関係の資格も持っているので、心理学者と思っている方も多いと思います。
最近は、ギャンブル依存研究で多方面から声がかかるようになったのですが、ギャンブル依存研究のきっかけは、宝くじ販売店やパチンコ店にできる待機列を見たことです。なぜ、損をするはずのギャンブルに並んでまで参加するのか。手始めにパチンコ宣伝広告と待機列との関係、宣伝広告と依存症との関係について分析してきました。
誤まった数字が作る社会の誤解
KA: では、先生の研究分野のひとつである、ギャンブル依存症研究について教えてください。
早野氏: ギャンブル依存症は、一般的には医学的な問題として捉えられ、治療が重視されています。しかし、日本においては、ギャンブル依存症が疑われる人数の把握や社会調査の方法に多くの課題がありました。
2014年、日本全国に536万人のギャンブル依存症(疑い)がいると発表されましたが、この数字には大きな問題がありました。ギャンブル依存症の定義では、通常、1年間以上ギャンブルを行っていない人はギャンブル依存症とみなされていません。その調査では「過去1年」という条件を外して、すでに回復した人や依存症の定義から外れる人が多数含まれていました。2017年久里浜医療センターによる調査では、ギャンブル依存症(疑い)数は人口の0.8%、推定約70万人と算出されました。この調査はランダムサンプリングによる面接調査で行われています。その後も、久里浜医療センターが調査を実施していますが、郵送やインターネットによる回答方法なので、調査の正確性を考えると2017年の調査を基準とするのがいいと思います。
メディアや政治家たちは、IRカジノに反対する理由として、いまだに536万人という数を引用し続けています。依存症という観点からいえば、行動嗜癖(しへき)のギャンブル依存症よりも、物質依存の薬物依存症やアルコール依存症の方が深刻な社会問題だといえます。たとえば、筑波大学の研究チームがアルコール依存症患者110人に対して、過去の飲酒運転に関する調査を実施しました。その報告では、ほとんどが飲酒運転の経験者であり、6割が何らかの事故を起こしていました。また、半数近くが飲酒運転に危険意識や罪の意識を感じておらず、11.1%が飲酒運転により人身事故を起こしていると報告しています。
警察庁の発表によると2021年における死亡事故率は、飲酒なしの死亡事故が0.75%に対し、飲酒ありの死亡事故は6.92%となっています。アルコール依存による交通事故が起きても、元TOKIOの山口達也さんのような有名人でない限り、マスメディアはほとんど報じていません。先日、泥酔した俳優の吉沢亮さんが間違って隣の部屋に入ってしまった事件が報道されましたが、有名人という特殊な状況があったからだと思います。私の幼少時、酔っ払った隣人が間違えて我が家に入ってくることもあり、母親が文句を言いながら本人の家まで連れて行く光景を何度も目にしています。
私も間違って隣の部屋のドアを開けてしまったこともありますが、様子が違うのですぐに違う部屋であるとわかりました。吉沢さんが依存症なのかどうかはわかりませんが、5分間気が付かなかったことがお酒の怖いところです。お酒は、飲酒運転だけでなくDVの要因にもつながります。酒税やスポンサー料などが入るので、政府やマスメディアがアルコールを問題視しにくいのではないかと勘ぐってしまいます。政治的に利用されて、過剰に問題視されているパチンコとは大きな違いを感じます。
時にマスメディアは、意図的とも思える偏った情報を発信することがあります。例えば、池袋の暴走事故に関する報道です。池袋での高齢ドライバーによる暴走事故では「上級市民」という批判が起こり、メディアは高齢者の免許返納を促す報道を展開しました。10万人あたりの事故件数(令和5年)は、総務省統計局e-statによると85歳以上で519.9、80-84歳で432.6なのに対して16-19歳で1,025.3、20-24歳で589.5となっており、統計的には、若年層の事故の方が多いことがわかります。それなのに、某テレビ局では若年層の「高年層の方は免許返納して欲しい」といった意見を報道していました。確かに、池袋暴走事故は悲惨な事故でしたが、全国で死亡事故が起きているのに、なぜ特定の方だけがいつまでもメディアでさらし者にされるのでしょうか。1つの事例が全体を代表するように報じられるのは偏見を広めることになります。
KA: 先生はギャンブル依存症に関して、どのような調査研究をされているのですか。
早野氏:心理学者や脳科学者を加えてチームを作って、2020年度に492,963人に対して配布し、42,880人(うち過去1年ギャンブル経験あり15,000人)を調査しました。2021年度からは、ギャンブル経験のある15,000人(同一話者)に対して、毎年調査しています。ギャンブル依存状態が、どのように変化するかを確認することが主な目的です。また、大阪府においては、10,000人を対象にIRカジノ関連の調査をしています。
日本では、SOGS(South Oaks Gambling Screen)というギャンブリングスクリーンがよく使われます。他の調査と比較するために、私もSOGSを使用しました。このSOGSで5点以上だとギャンブル依存症が疑われるとされています。
依存症は治らないとの認識が広まっています。確かに治らない人もいますが、薬物依存症やアルコール依存症と違って、大多数は自然回復しています。私の調査でもSOGSが5点だった人の70%は2年後に4点以下になっており、重度と言われる10点以上でも35%は2年後には4点以下になっています。回復した人で相談や治療を受けた人は全体の1%未満なので、回復している人のほとんどは自然回復です。
3年間の変化状態から、自然回復が見込めずに治療が必要と思われたのは、一回でもギャンブル依存症が疑われた人の6.5%でした。久里浜医療センター2017年の調査結果から概算すると、約45,000人(70万人×0.065)となりますので、536万人の100分の1以下ということになります。割合でいうと0.8%(久里浜調査)のうちの6.5%(早野調査)、つまり全体の0.052%となります。4年目の調査で自然回復が見込めない人の割合はさらに下がっているので、長期的には、6.5%より下がると思います。
厚労省関連の調査では、ギャンブル依存症が疑われる割合だけを発表しているだけで、何%が実際にギャンブル依存症と診断できて、そのうち何%に治療が必要という最も重要な情報はまったく報道されていません。あおるだけあおって、肝心の情報は発信していないのです。そして、依存症関連で起きた事件の悲惨さを広めています。新型コロナ禍において体温37度以上の人数を新型コロナ感染者疑いと報道するようなものです。
KA:そのような偏った情報ばかりが広まると、人々が誤った偏見を持ちやすくなりますね。
早野氏:その通りです。ギャンブル依存症疑いが536万人と言った後に、ギャンブル依存は借金地獄や犯罪も引き起こすと報道すれば、536万人がまるで犯罪者予備軍のように聞こえます。
世界中でギャンブルが存在し続けている理由を根本的に考えることなく、批判だけが先行しています。
ギャンブルをなくすことができないことは、歴史が証明しています。近年、ギャンブルは、禁止するのでなく、管理することが最も効果的であることがわかってきました。ギャンブルを必要とする人も少なからずおり、その人たちにギャンブルをやめさせようとしても、不法賭博に移行するだけなので、管理できるギャンブルで対応する方が効果的なのです。
大阪IRカジノ計画に関連して、維新の会がギャンブル依存症の原因をパチンコと違法オンラインカジノだと主張し、2022年に大阪市議会でその法案が可決されました。しかし、この主張には科学的データによる裏付けが全くありませんでした。データを示さない感情論の意見が可決されるということ自体が問題です。議会で感情論が優先されれば、メディアに誘導されることになるし、デマも広まります。
2014年の調査では、調査関係者が日本で依存症者が多い理由について「パチンコが身近にあるから」という憶測を述べたことでパチンコ批判が広がりました。ギャンブル事情や調査方法が異なるので、日本のギャンブル依存症の数は、多いとも少ないとも言えないのが実情です。SOGS調査で0.8%であれば、ギャンブル依存大国などということはありません。それに、一番身近なギャンブルは参加者数、店舗数から見ても宝くじです。そのことを指摘したことで、パチンコへの批判は抑えられるようになりました。還元率は、宝くじ45%、公営ギャンブル75%、パチンコ85%なので、パチンコがもっともライトで遊びやすいことがわかります。この状態で、官は批判しないが民は批判するマスメディアも間違っています。
このように、社会学的な視点から見ると、ギャンブル依存症に関する議論には、科学的根拠の不足や政治的な偏り、メディアの偏向報道など、多くの課題が存在することが明らかになっています。
ギャンブル依存症の真実をデータで紐解く
KA:様々な課題がありそうですね。先ほどの法案が可決に際し、科学的データによる裏付けが全くなかったという点について詳しく教えていただけますか?
早野氏:大阪市では、データを示さずにパチンコ・パチスロを違法カジノと同様に扱っています。また、大阪府はシンガポールのギャンブル依存対策をモデルにすれば、ギャンブル依存症例が減ると説明しています。シンガポールでは、カジノを設置する際にギャンブル依存対策でギャンブル依存症が減ったとする報告もありますが、カジノ解禁後に60%増加したという報告もあります。元データにあたって、どの調査がより客観的で信頼できるかを確認する必要があります。
カジノでのギャンブル依存対策では、成功した例がないという多くの研究報告があります。また、シンガポールと日本では、ギャンブル事情も異なりますから、単純にシンガポールを模倣すればギャンブル依存対策ができると考えるのは、大きな間違いです。
また、私の調査では、パチンコとカジノでは客層には違いがあり、パチンコ参加者の8割は年収600万円以下の層であり、大阪IRカジノ参加希望者の8割は年収800万円以上の裕福層です。それに、パチンコ参加者の多くはカジノ参加料に6,000円支払うなら、パチンコに使いたいと思っているのです。詳しくは次の研究報告をご覧ください。https://doi.org/10.34356/0002000149
カジノが富裕層向けのギャンブルとして認識される一方で、パチンコは一時的なストレス解消の手段として利用されることが多いのです。先の調査では、パチンコはもっともやめやすく(つまり依存症になりにくく)、やめた場合、最も回復率が高いことも示しています。これは、パチンコが一時的な娯楽として利用されることが多く、生活状況が改善されると自然に参加頻度が減少するためだと考えられます。
一方で、競馬や競艇などの公営ギャンブルは、より本格的なギャンブル愛好者に支持される傾向があります。パチンコでの1日の負け(損失)は最大で10万円程度で還元率が85%です。それに対して、公営ギャンブルの賭け金は青天井(無制限)で還元率も75%ですから、公営ギャンブルの方がはるかに危険なわけです。大阪府が進めるギャンブル等依存症対策は、カジノを含む統合型リゾート(IR)の導入を見据えたものですが、各ギャンブルの性質の違いを十分に考慮した政策設計が求められるでしょう。パチンコだけを敵視しても、有効なギャンブル依存対策はできません。感情論で進める政策は、状況を悪化させるだけです。
KA:ギャンブルの種類により、依存度などの傾向は異なるのでしょうか?
早野氏:ギャンブル依存症は、「やめたくてもやめられない」状態を指しますが、私が実施している全国調査では、ギャンブル依存になりやすいギャンブルとそうでないギャンブルがあります。一番依存症率が低いのは宝くじですが参加者数が多いので実数としては多くなります。一番依存症率が高いのはオートレースですが、参加者が少ないので実数は少なくなります。パチンコは、参加者が多いので実数はある程度多くなりますが、やめる割合が多く、やめた場合の回復率が高いのが特徴です。
現在、パチンコ業界が縮小化していますが、その弊害も大きいのです。パチンコ業界は地方経済や雇用において重要な役割を果たしてきました。競馬場などではオンライン投票の普及により、人員削減が進んでいますが、パチンコ店は接客や運営に多くのスタッフを必要とするため、地域社会における雇用の維持に寄与しています。また、娯楽の少ない地域では、娯楽を提供し、社交場としての機能も果たしています。パチンコを非難している人たちが代替の娯楽や社交場を提供してくれるならいいのですが、非難だけして提供はしませんから。
社会的な課題として、薬物依存症やアルコール依存症は、ギャンブル依存症よりも深刻な影響を及ぼすとされています。ギャンブル依存問題も大切ですが、薬物依存症やアルコール依存症は、健康や社会生活に直接的な被害をもたらすため、優先的に対策を講じるべきです。しかし、現状ではギャンブル依存症が注目を集めており、科学的根拠に基づかない偏見や誤解に基づく規制が行われています。
政治とメディアが作るギャンブル依存症のイメージ
KA:一口にギャンブルといっても様々な種類があり、それに対する依存度の傾向も規制の方法も多岐にわたりますね。そもそも、ギャンブルが存在するから依存するのであって、ギャンブル自体がなければ、ギャンブル依存もなくなるのではとも考えてしまいます。
早野氏:ギャンブルは日常生活に溶けこんでいます。小学校で余った給食をじゃんけんで得るのもギャンブルです。トランプ、じゃんけん、すごろくなど、すべてギャンブルです。すごろくなどは平安時代から行われている歴史のあるギャンブルです。ギャンブルは最も単純に優越感と解放感を得られる娯楽で、そこに物や金銭が加わるとその優越感や開放感が強まるのです。すべての先進国で、ギャンブルを禁止した経緯がありますが、成功した例はありません。最終的には管理・統制する方向に向かっています。
令和元年東京都の依存症相談件数を例に挙げると、以下のように報告されています。
- アルコール依存症が5000件
- 薬物依存症が1181件
- ギャンブル依存症が296件
このデータから、ギャンブル依存症の相談件数は他の依存症と比べて少ないことがわかります。しかし、ギャンブル依存症は社会的注目度が高く、「無限に資金を投入できる」という特徴を問題視する声もあります。しかし、アルコール依存症や薬物依存症は、飲酒運転や薬物乱用による重大な事故や犯罪が引き起こされる可能性があり、ギャンブル依存症よりも深刻な社会問題といえるでしょう。水原一平元通訳や三菱UFJ貸金庫事件などは、ギャンブル関連でも、極めて特殊なケースと言えます。
アルコールやギャンブルに限らず、楽しいと感じることには依存がつきものです。恋愛、性行為、買い物、ゲームなども依存症になる可能性があります。依存症は、アルコールやギャンブルだけの問題ではありません。また、パチンコだけを問題視して規制をかけるのは、愚の骨頂です。実際、パチンコ規制(主に出玉規制)をしたことで参加者は大幅に減りましたが、依存症者数が減ったという報告はありません。そろそろ、これまでの規制が間違いであったことに気づくべきです。パチンコは厳しく規制されているのに対して、宝くじは1枚で何千万円もの当選金を得られる可能性があるにもかかわらず、ほとんど規制されていません。このような偏った状況を改善し、全てのギャンブルに対して公平な規制を行うことが求められます。宝くじなどは、売上金で社会貢献していることを積極的にアピールしていますが、まず、すべきことは、ギャンブル依存症者の支援です。そのためには、ギャンブル依存症疑いの人数でなく、支援が必要な人数を算出して、その人数に見合った資金援助をする必要があるのです。
エンターテインメントとしてのギャンブルの可能性
KA:先生はギャンブル依存症に対してどのように取り組んでいけばいいとお考えなのでしょうか。
早野氏:ギャンブル依存症対策として、業界全体が目指すべき重要な方向性は「エンターテインメント化(エンタメ化)」と私は考えています。
Scientific Reportsに私が行った全国調査の結果を発表したのですが、人口密度と依存症の関係性が明らかになり、都市部よりも地方でギャンブル依存の割合が高い傾向が示されています。この結果は、従来「都市部の方が依存症になりやすい」と考えられていた見解を覆すものです。地方では娯楽の選択肢が少ないため、ギャンブルに依存しやすい傾向があると考えられます。具体的には、カラオケ、音楽鑑賞、キャンプなどの娯楽をしている人はギャンブル依存率が低いということがわかりました。これらのデータは、娯楽の多様性がギャンブル依存症の予防につながる可能性を示しています。都市部では娯楽施設が充実しているため、ギャンブルに依存しにくい環境が整っています。
KA:なるほど、エンターテインメント化は面白い発想ですね。エンターテインメント化により、どの程度依存度に違いが出るのでしょうか。
早野氏:例えば、公営ギャンブルの中では、競馬の依存症率が低い一方でオートレースは極めて高い。この違いは、中央競馬がエンタメ化を積極的に進めていることが原因と考えられます。中央競馬では一昨年からカップルや家族で楽しめるイベントを提供するなど、幅広い層をターゲットにした施策が行われています。一方で、オートレースは従来型のギャンブラーが中心であり、エンタメ化が進んでいないのが現状です。結果として、競馬では娯楽として参加している人の割合が多く、オートレースは少ないといえます。
パチンコ・パチスロ奨学金の理事をやっている関係で、同じ理事の韓裕さん(マルハン東日本カンパニー社長)と話す機会が何度かあり、マルハンがパチンコ業界をエンタメ化する「パーパス」というプロジェクトを進めていることを知りました。担当者の西眞一郎さんが説明をしてくれたのですが、私が考えるギャンブル依存症対策の方向性と一致していました。パチンコ業界は、公営ギャンブルと違って一枚岩ではないのですが、業界大手のマルハンがその気になったことは大きな進歩だと思います。これに、全日遊連や都遊協などの組織が積極的に参加しているので、5年後の状況が楽しみです。私としては、データを取って解析を進めます。
KA:エンターテインメント化が難しいギャンブルはあるのでしょうか。
早野氏:やはり、パチンコですね。パチンコのエンターテインメント化には課題が多く、現状では既存客の奪い合いが中心となっています。新規顧客を増やすためには、数時間を1,000円程度で楽しめるような手軽なゲーム性を提供し、ライトユーザーを増やす戦略が重要だと思います。ライトユーザーが増えることでのめりこみを抑制する雰囲気が生まれます。心理学では、バンドワゴン効果、スノッブ効果などが指摘されていますが、多数派に引きずられるということです。
ライトユーザーを増やすためには、メーカーが遊技機の値段を下げることが最重要です。遊技機の値段はユーザーから得なければならないのだから、ライトユーザーが楽しむことはできなくなります。それと、パチンコを管轄している警察庁ですが、遊技台の有効期限3年(延長3年)というのは、エコ、経済、エンタメのすべての観点からマイナスです。自動車の車検のように、検査を通過すれば何年でも使える状況が必要です。遊技台の入れ替えが早ければ、その分ユーザーから回収しなければならないのだから、手軽に遊べる状況がつくりにくくなるのです。古い台を残すことができれば、各店舗の個性も出せて多様化していきます。
中央競馬は、様々な施策を通じてエンタメ化に成功しています。一方で、パチンコ業界も業界全体でエンタメ化を推進すること、そして、地域ごとの娯楽環境の充実がキーになると考えています。
今後学生に求められる能力とは
KA:最後に、起業を目指す学生へのアドバイスについてお聞かせください。
早野氏:私が起業に関するアドバイスができるとは思えません。ただし、大学教員のなかでは、企業とのつながりが多い部類に入るので、現代社会で、学生に求められる能力についてお話します。
特に文化系の学生は、受験勉強で記憶中心の学習を行う傾向がありますが、インターネットが普及した現在では、単なる記憶の価値は大きく低下しています。それよりも、得られた情報を判断する能力や、情報から未知の問題を解決する能力の方が重要だと思います。
例えば、私の授業では試験問題を事前に提示します。そして、回答には、パソコン、図書館、生成AIなど何を使用してもいいと指示しています。自分の得意なコンテンツを活用して、答えを導き出すのです。重要なのは、これらの手段を活用して得た情報の正確性を見極め、さらにその情報をもとに適切に解答をだすことです。卒業論文においても、テーマはある程度の自由を与えますが、評価は科学的データの使用と、そのデータと結論の整合性を評価基準としています。
また、学生よりも大学教育にはいくつかの課題があると考えています。そのひとつが教員のアップデート不足です。文系分野では、自分が大学院時代に学んだ状況をそのまま継続している人が多く見られます。従来の方法に固執する傾向が強く、これが教育の停滞を招いていると考えられます。四字熟語や古典の知識不足を嘆く意見も教員から聞かれますが、私は知識をどのように活用して、将来に対処していくかが重要だと考えています。
しかし、教員のアップデートが期待しにくい現状では、学生自身が主体的に知識の応用方法を模索する必要があります。学生には、現在学んでいることが社会でどのように活用できるかを常に考えながら学習することをおすすめします。
重要なのは、学んだ知識をどのように更新・アップデートし、実際の課題解決にどのように活用していくかということです。それに伴い大学教育の本質は、単なる暗記学習を促すことではなく、将来起きるであろう問題に対処する能力養成に重点を移す必要があると考えています。