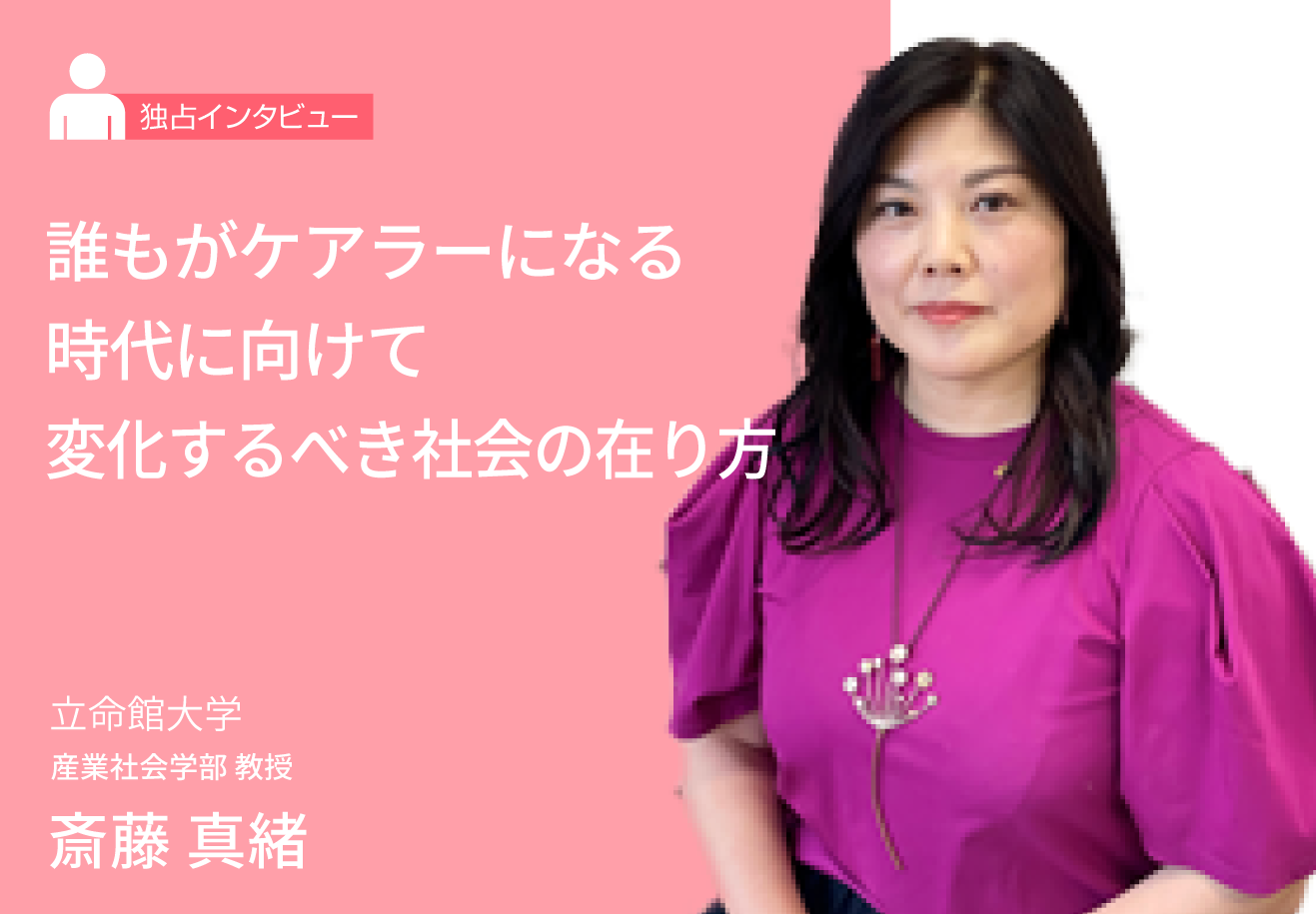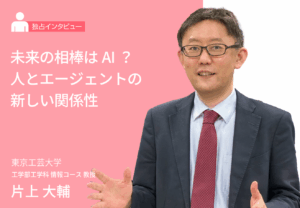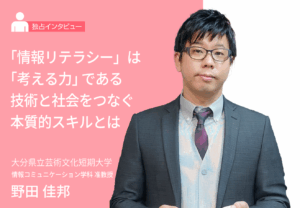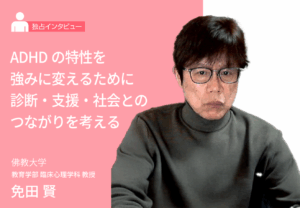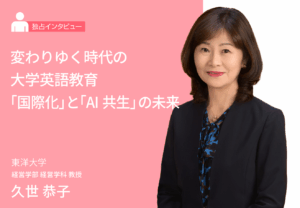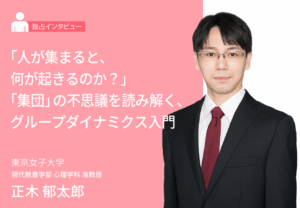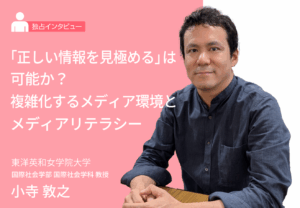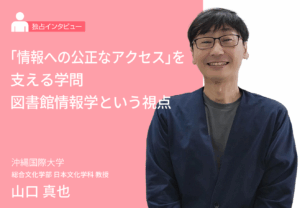日本は、世界でも類を見ないスピードで少子高齢化が進行しています。厚生労働省の発表によると、2024年の出生数は72万988人と、1899年の統計開始以来、過去最少を記録しました。また、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2070年には65歳以上の人口が全体の38.7%を占めると見込まれています。
こうした人口構造の変化に伴い、家族のケアを担う子どもや若者、いわゆる「ヤングケアラー」や「若者ケアラー」の存在が社会的に注目されつつあります。
そこで今回は、立命館大学産業社会学部で家族社会学を専門とされる斎藤真緒教授にお話を伺いました。

斎藤 真緒
立命館大学 産業社会学部 教授
【biography】
立命館大学産業社会学部教授。博士(社会学)。専門家族社会学。思春期保健相談士。
日本家族社会学会所属。
「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」副代表
JST-RISTEX研究事業「ケアの加藤に寄り添い、ケアラーの社会的孤立・孤独を予防する包括的支援システムの構築」代表
主著:
斎藤真緒、2025、「ケアするーケアはジェンダーから自由になれるのか」伊藤公雄・牟田和恵・丸山里美編『ジェンダーで学ぶ社会学{第4版}』世界思想社
斎藤真緒、2023、「ヤングケアラーはどんな「問題」なのか―ケアラー支援との接続に向けた視座―」『子ども学』11号斎藤真緒、2022、「あらためて、ヤングケアラー『ブーム』を問うー問題の射程と次元の再考のために」『現代思想2022年11月号 特集ヤングケアラー:家族主義的福祉・貧困の連鎖・子どもの権利・・・』
『子ども・若者ケアラーの声からはじまる―ヤングケアラー支援の課題』(共著、クリエイツかもがわ、2022年3月)
ヤングケアラー・若者ケアラーの現実
ナレッジアート(以下KA): 「ヤングケアラー」、「若者ケアラー」の定義について教えて下さい。
斎藤教授:一般には、ヤングケアラーは18歳未満、若者ケアラーはおおむね30歳までの若者で、家族などのケアを担う人を指します。昨年、法制度にも位置づけられ、支援も整備されました。 私は、年齢で区切らず、子ども期から若者期にかけてケアに関わる人を広く捉えるために8年ほど前から「子供・若者ケアラー」という言葉を使っています。
KA: 先生がヤングケアラー、若者ケアラーの研究を始められたのは 2017年頃ということですが、何かきっかけがあったのですか。
斎藤教授:もともと私は、家族介護全般に関心があり、特に妻や親を介護する男性介護者に関する実態調査や支援活動に取り組んでおりました。研究する中で、家族の介護の形が大きく変わりつつあるということは強く感じており、「ヤングケアラー」という存在も知っていたものの、その当時は研究対象として強く意識していたわけではありませんでした。
転機となったのは、私が担当していた大学1年生の学生が、実際にヤングケアラーだったことです。その学生は祖母の介護のために通信制高校に転校し、介護と学業の両立という負担により、最終的に高校卒業までに5年を要しました。さらに、大学に入学できたのも、祖母を看取ってからでした。言葉として知っていた「ヤングケアラー」が、子どもや若者の進路や人生設計にこれほど大きな影響を与えるという現実を、この学生との出会いを通じて初めて実感し、ヤングケアラーの研究へと踏み出す大きなきっかけとなりました。
KA: 先ほど若者ケアラーとヤングケアラーは年齢により区別されるというお話がありましたが、年齢以外の違いはなんでしょうか。
斎藤教授:主に、ケアの内容や対象に違いがあることが国の調査などを通じて明らかになってきています。例えば、ヤングケアラーの主なケア対象は「年の離れた兄弟姉妹」が多いのに対し、大学生ケアラーでは「母親(特に精神疾患)」「祖母」「兄弟姉妹」の順に変わってきます。これは、ライフステージの変化とともに、ケアの役割や対象が変化することを示しています。幼少期は兄弟の世話が多くても、成長とともにその必要性が減る一方、親や祖父母の介護が新たに生じます。つまり、家族という単位では、ケアは断続的に発生しうるものであり、誰もがいつかケアラーになる可能性があるということです。
また、18歳以降の若者ケアラーはヤングケアラーと違い、法的に「成人」と見なされるため、支援の現場でも大人としての役割を期待されがちです。その結果、進学や就職、将来設計などに大きな影響を受ける人も少なくありません。
ケアラーのキャリア形成
KA: 先ほどのお話に関連して、ヤングケアラーや若者ケアラーとしての経験は、将来的なキャリア形成や人生観に具体的にどのような影響を与え得るのでしょうか。
斎藤教授: まず、勉強に割く時間や友人との時間が十分に取れないといった点は、統計的に明らかになっています。ケアや家事が日常にあることで、子どもたちの生活が制約されているのは間違いありません。
一方、将来的に進路やキャリアを考える際にも大きな影響があります。特に精神疾患や障害を抱えた家族のケアは、長期にわたることが多く、当事者たちは今後もケアが続いていくことを前提とした将来設計をせざるを得ません。 例えば、「全国転勤がある仕事は無理かもしれない」「家を離れることができない」「海外で活躍する夢も諦めるしかない」といったように、夢や目標自体を“ケアがある前提”に適応させてしまう傾向があります。そうした中で「自分のやりたいことをあきらめるのは仕方ない」と感じている若者ケアラーは少なくありません。
KA:そういった状況に置かれているケアラーが自分の将来を切り開いていくために必要なことはなんでしょうか。
斎藤教授:「自分の夢を大切にする力」を小さな頃から育むことが重要だと強く感じます。
自分の夢を実現するためには、「これは譲れない」「どうしてもやりたい」という意思を表明し、時には対立を乗り越える力が必要です。しかし、ヤングケアラーや若者ケアラーの多くはとても優しく、家族のために自分を犠牲にしてしまう“いい子”が多いんです。その優しさゆえに、自己主張が苦手で、意見が対立したときには譲ってしまいがちです。
だからこそ、学校の中で「自分の意見を言葉にして伝える力」を育むことが非常に重要だと思っています。この点に関しては、学校の先生方への研修などでもよくお話しさせていただいております。家庭ではどうしても我慢を強いられる場面が多いため、学校という場でこそ、そうした力を意識的に身につけてほしいです。そしてそのような力は一度教えたからできるものではなく、日常の中で何度も経験を重ねながら育てていく必要があると考えています。
つまり、ケアと向き合いながらも自分の人生を切り拓いていくためには、夢をあきらめないこと、夢とケアを両立するにはどうすればいいかを考える力、必要な支援や情報を得るために、自ら声を上げられる力が必要になってきます。
KA: 日常的にケアが発生することによって、キャリアの形成や選択にどうしても影響が出てしまうのが現状だと思いますが、彼らは結果的にどういった職業に就く傾向が見られるのでしょうか。
斎藤教授: 日本では明確なデータはありませんが、海外ではいくつか事例があります。例えばイギリスの調査では、約4分の1のヤングケアラーが、看護や福祉といった「ケアに関わる分野」を進路として選んでいることが分かっています。
つまり、ケアの経験がマイナスに働くだけでなく、それを自分の将来やキャリアにポジティブに生かそうとする人たちもいるということです。ただし、すべての人がそうであるわけではなく、その選択を無理に勧めるのも適切ではないと思っています。
自主的な選択とは別に、特に就職活動においてケアラーであることがハンディキャップになる場面もあります。例えば、大学のキャリアセンターなどでよく求められる「ガクチカ」(学生時代に力を入れたこと)をPRする際、ケアがあることで課外活動やアルバイト、留学などの一般的な経験が積みにくく、「語れることがない」と感じる学生も少なくありません。
だからこそ私が強く感じているのは、支援の在り方として、若者ケアラーにサービスを届けるだけでなく、企業側の「評価のものさし」そのものを見直すことが重要だということです。
例えばイギリスでは、若者ケアラーが自ら「ケアを通じて身につけたスキル」をSNSなどで発信する取り組みが行われました。そこでは、「マルチタスクが得意」「忍耐強い」「人の話をよく聞ける」など、ケア経験を通じて培った力をポジティブに表現しています。日本ではどうしても「ヤングケアラー=かわいそうな子」というイメージが先行しがちですが、彼らが持つ潜在的な力を、企業も社会も正当に評価していくべきだと思います。わかりやすい「ガクチカ」だけで判断するのではなく、多様な経験や背景を持つ学生たちのポテンシャルを、もっと柔軟な視点で見てほしいと思います。
ケアラー支援政策の現状と課題
KA: お話を伺って、学校だけでなく、国や企業、自治体も含めた包括的なサポートが必要だと感じました。現在、若者ケアラーに対する支援政策には、どのようなものがあるのでしょうか?
斎藤教授: 現時点で国が示している支援メニューはいくつかあります。まず一つは、「ピアサポート」の場の提供です。同じような経験を持つ若者たちが出会い、交流できるような場に対して、予算をつけて整備するというものです。最近ではオンラインによるピアサポートも広がりを見せており、経済的・時間的制約から移動が難しく、自宅から出づらい状況にあるケアラーの心の支えとなる大きな役割を果たしています。ただし、「家族にバレたくないので声は出せない」「聞くだけで参加している」といったケースも多く、すべての人にとって安心できる支援の場にはまだなっていないのが現実
です。従来の対面型のピアサポートに関しても、自治体ごとの対応に差があり、実施できていない地域も多いため、すべての若者ケアラーが平等にアクセスできる状況ではありません。
もう一つは、「ヘルパー派遣事業」です。これは、家事を担うヤングケアラーのいる家庭に対して、必要に応じてヘルパーを派遣できるようにするという支援です。以前は福祉の対象とされていませんでしたが、「ヤングケアラー」として認められることで支援の対象に含まれるようになりました。しかし、こちらも自治体によって対応状況にばらつきがあります。
また、今年度からは、特に若者ケアラーに焦点を当てたキャリア支援や進路支援の取り組みも拡充されています。ただ、これについては積極的に取り組む自治体はまだ少ない印象です。その背景には、年齢区分の制度上の壁があります。18歳未満であれば「児童福祉法」の対象となり、虐待防止などの文脈で関係機関が連携し、情報共有を行う仕組みがあります。この仕組みに「ヤングケアラー」という課題も乗せることが可能です。しかし、18歳を超えるとこの体制は適用外となり、支援から急に切り離されてしまいます。つまり、18歳までなら自治体が把握・対応できても、それ以降は「もう大人だから自分でなんとかしてね」という扱いになってしまうのが現状です。
そのため、18歳以上の若者ケアラーが「どんな支援が受けられるのか」を知る手段が非常に限られており、支援制度が存在していても情報が本人に届いていないことが多いです。実質的に、自力で探すしかないという状況が続いています。
また、全体を通して言えることは、地域間格差が大きな障壁となっていることです。支援制度が整いつつあるとはいえ、実際に取り組めている自治体とそうでない自治体の差は大きく、法律ができた今でも、そのギャップは依然として存在しています。
KA: まだ課題は多いということですね。支援制度やアクセスが限られる中で、ケアラーとしての立場が人生の様々な側面に大きな影響を持つことがよく理解できました。このようなストレスによって性格が内向的になったり、うつ病などの精神的な不調を引き起こすケースもあるのでしょうか。
斎藤教授: はい、それは実際に非常に多いと思います。ヤングケアラーに限らず、年代を問わず多くのケアラーがメンタル不調を抱えているというのは、さまざまな調査でも指摘されています。
私が関わってきたヤングケアラーの中にも、自分自身が精神疾患を発症してしまったり、強いストレスからさまざまな不調を抱えている方が少なくありません。その結果、例えば学業の継続が難しくなったり、友人関係を築くのが困難になったり、さらには就職後に離職してしまうといったケースも見られます。
だからこそ、メンタルヘルスへの支援は非常に重要だと感じています。しかし現状、日本ではその分野に十分な予算がついているとは言えません。高額なカウンセリング費用がネックになって、支援を受けたくても受けられないヤングケアラーも多くいます。「無料でカウンセリングを受けたい」「精神的なサポートをもっと気軽に受けられるようにしてほしい」といった声は、実際に数多く寄せられています。 経済的な支援とメンタルヘルス支援がセットで提供されることが、今後の課題の一つだと感じています。
誰もがケアラーになり得る時代に向けて──ケアラー支援のこれから
KA: ヤングケアラー・若者ケアラーを取り巻く状況について、今後どのような変化や傾向が見込まれるか、ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。
斎藤教授: まず一つは、ケアラーの数が今後さらに増える可能性が高いということです。国の調査によると、学校のクラスに1〜2人の割合でヤングケアラーがいると言われています。これは決して少なくない数字であり、実際に多くの子どもたちが何らかのケアを担っていることがうかがえます。
背景として、かつてのように「両親がそろい、母親が専業主婦で家庭のケアを担う」といった形の家族は減少しており、代わりに限られた家族構成員が仕事とケアの両方を担う家庭が増えてきています。例えば、ひとり親家庭では親が病気になると、子どもが即座にケアの担い手になりやすくなりますし、両親がそろっていても共働きであれば、祖父母の介護が若者に委ねられるケースもあります。さらに少子高齢化が進む中で、今後は誰もが潜在的にケアラーになりうる時代に入っていくと思います。
つまり、これまでヤングケアラーは“特別な立場”と見られてきましたが、今後は人生のどこかで誰もがケアに関わる可能性があるという前提で、ケアを担う人への支援が制度的にもっと広がっていく必要があります。
また、精神疾患やひきこもり、不登校など、従来の介護や育児とは異なる「多様なケアの形」が増加しており、それらが長期化する傾向にもあります。こうした新たなケアの課題に社会全体でどう対応していくかが、今後の重要な論点になるでしょう。
KA: 今後、よりケアの問題が一般化していく可能性が高いのに対し、すでに多くの課題が指摘されている従来の支援モデルでは対応しきれないのではないかという風に感じました。現在行われてる支援に加えて、今後どのような視点が必要になるとお考えですか。
斎藤教授: まず、支援のあり方そのものについて課題があると感じます。現在の支援モデルは、「子どもが担っているケアや家事を取り除くこと」を前提に組まれていますが、それだけでは不十分ではないかと思います。例えば、進学などを機に実家を離れ、一人暮らしを始めたとしても、家族との関係は続いていきます。実際、多くの若者ケアラーが、実家に残る家族のことを気にかけながら、後ろ髪を引かれるような思いで日々を過ごしています。 つまり、「目の前の負担をなくせば支援は終わり」ではなく、家族との関係性や距離感とどう向き合っていくかといった、より長期的な視点での支援が必要です。
また、法律上は支援の対象が30代までとなっていますが、それ以降の世代も課題を抱え続けています。例えば、40代・50代の人たちも家族のケアと仕事の両立に悩んでおり、最近では「ビジネスケアラー」という言葉も使われるようになってきました。 こうした現状を踏まえると、ヤングケアラー支援を「年齢」で区切るのではなく、あらゆる世代のケアラーを包括的に支援していく枠組みが必要だと思います。
さらに、支援が届きにくいのは「目に見えるケア」だけではありません。感情的なケアや将来的な不安を抱えながら生きている「潜在的なケアラー」も多くいます。例えば、兄弟に障害がある、自分が一人っ子で高齢の両親と暮らしている、といった背景を持つ学生の中には、「将来自分が親の面倒をみることになる」と、すでに進路選択に制限を感じている人もいます。
そういった、「まだケアラーではないが、将来的にそうなる可能性が高い若者たち」も含めて、ケアと自分の人生・キャリアを両立できるような社会の仕組みを抜本的につくっていくことが、本当の意味でのヤングケアラー支援に必要な視点だと考えています。
病気や障害そのものはなくせなくても、「ケアがあるから夢を諦めなければならない」という状況は、社会の仕組み次第で変えることができると思います。ケアラーを支える仕組みづくりが、今後より社会全体に広がっていくといいなと思います。
引用:
–少子高齢化はどれくらい進むの?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター