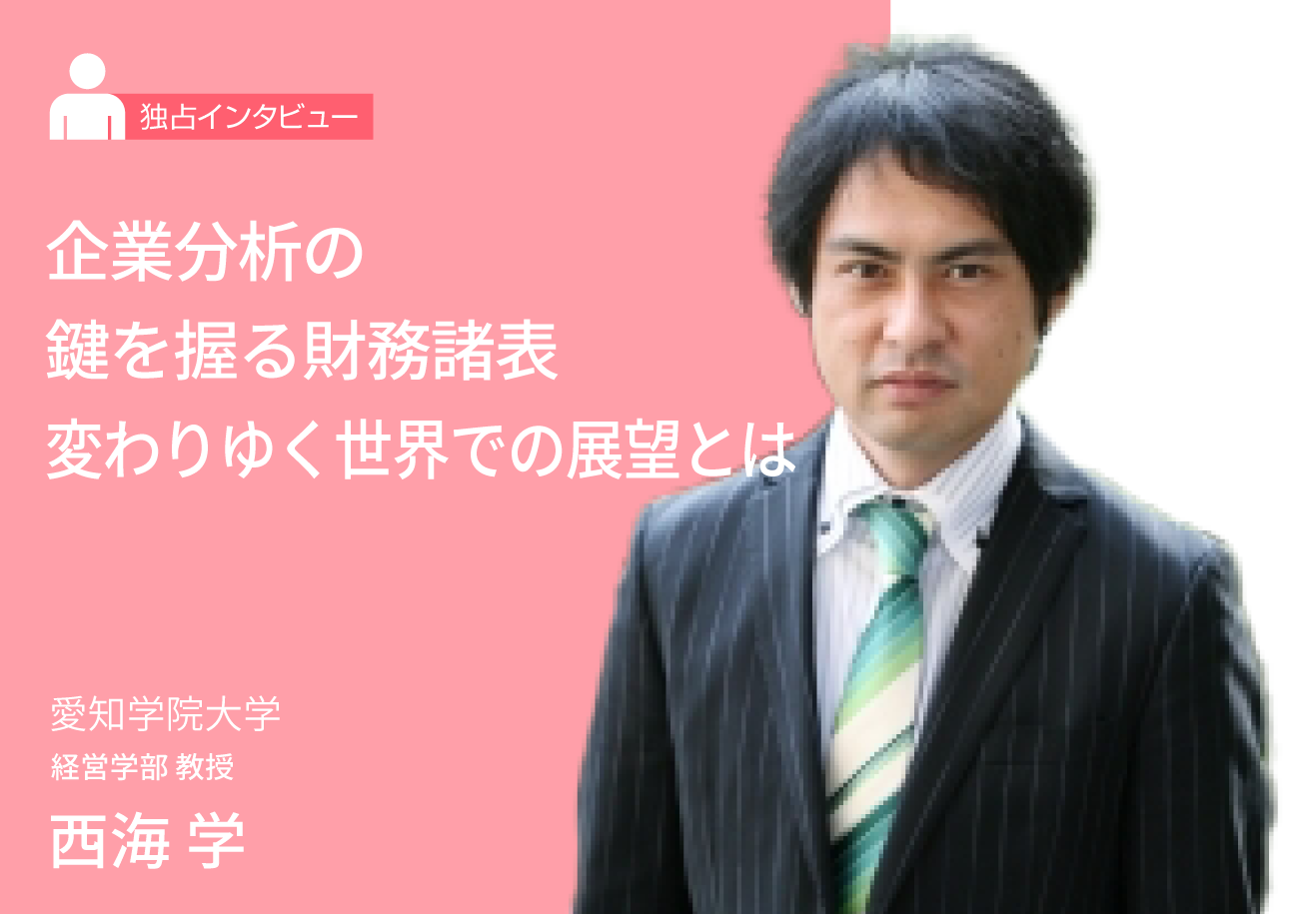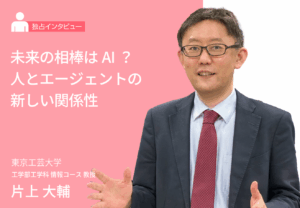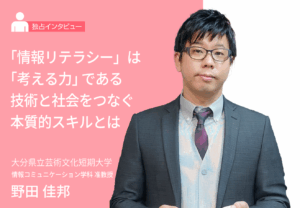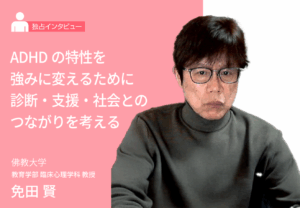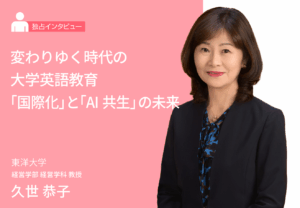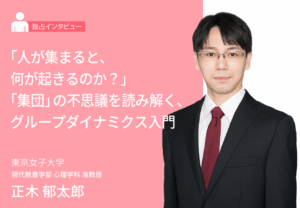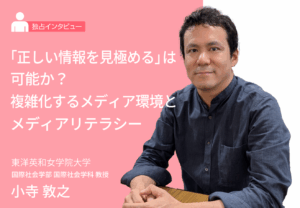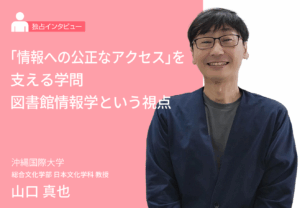現代のビジネスにおいて、企業の健全性や成長性を読み解くうえで欠かせないのが「財務諸表」です。
しかし、多くの人にとって、損益計算書や貸借対照表といった言葉は難しく感じられ、具体的に何がわかるのか、どのように活用すべきかが分かりにくいものでもあります。
そこで今回は、愛知学院大学の西海学先生に財務諸表が企業活動をどのように映し出すのか、また、時代の変化や国際化に伴って会計基準がどう変化してきたのか、お話をうかがいました。

西海 学
愛知学院大学 経営学部 教授
【biography】
1971年 横浜市生まれ
2004年 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士課程後期修了
博士(経営学)
2004年 福井工業大学工学部専任講師
2008年 愛知学院大学経営学部専任講師(准教授、教授歴任)
2014年 University of Victoria 客員教授
2016年 愛知学院大学経営学部教授
財務諸表の基本構成と役割――貸借対照表・損益計算書を中心に
ナレッジアート(以下KA):まず最初に、そもそも財務諸表とはどういったものかについて教えていただけますか?
西海氏: 財務諸表は、企業の状況が現在どうなっているかを外部の人に報告するための資料です。 「諸表」とあるように複数の表で構成されていて、メインとして開示されるのは「貸借対照表」と「損益計算書」の2つです。
貸借対照表は、企業の現状、たとえば現金をどれくらい保有しているか、投資資産や負債がどれだけあるか、株主からの投資額がいくらあるかなどを示すものです。最近では「財政状態計算書」と表示されることもありますが、基本的には同じものを指します。
もう一つの損益計算書は、企業がどれだけの利益を上げたかという経営成績を示す表です。
この2つが財務諸表の中心ですが、補足的に開示されるものもあります。たとえばキャッシュフロー計算書。企業が黒字でも現金が不足していると問題が起こるため、これを使ってキャッシュの流れを示しているのです。
また、株主資本等変動計算書もあります。貸借対照表は決算日時点の静的な情報ですが、それだけでは株主の持ち分が1年間でどう変化したかが分かりません。その変動を補足的に示すのがこの表です。
KA:特に大切なのは「貸借対照表」と「損益計算書」の2つでよろしいでしょうか。
西海氏:はい、この2つが最も重要な財務諸表で、昔から必ず開示することが求められています。
さらに、財務諸表には「個別財務諸表」と「連結財務諸表」の2種類があります。現在では連結財務諸表が主流です。
個別財務諸表は企業単体の情報を示すもので、たとえばトヨタの個別貸借対照表や個別損益計算書は、トヨタ自動車単体の情報だけを載せています。
一方、連結財務諸表は企業グループ全体の情報を示します。トヨタグループで言えば、トヨタ自動車のほかに、ダイハツ、日野自動車、デンソー、トヨタ合成などの子会社、関連会社を含めた全体の状況を表します。現在はこちらが主に利用されています。
KA:財務諸表と一口に言っても、さまざまな種類があるのですね。ちなみに、最近よく聞く「決算書」という言葉は、財務諸表に含まれるのでしょうか?
西海氏: はい、「財務諸表」という言い方は、金融商品取引法や会社法などの法律の文脈で使われる、少し堅い表現です。一方、「決算書」というのは、もう少し日常的でくだけた表現です。基本的には、財務諸表と決算書は同じものと考えて問題ありません。
ただし、決算書と呼ばれるものの中には、財務諸表以外の報告書も含まれることがあります。たとえば、環境に関する取り組みを報告する書類や、経営者の見解を示す「MD&A(経営者による分析と説明)」などです。
そのため、「決算書」という言葉の方が、やや幅広く、漠然とした表現になっていると言えます。
財務諸表はなぜ作成される?資金調達における重要性
KA: では、財務諸表を作成する目的について教えていただけますでしょうか?
西海氏:財務諸表っていう名前からある程度推察できると思うのですが、「財務」を英語で言うとファイナンスです。基本的に財務諸表っていうのは、資金調達、つまりファイナンスの目的で開示されるものです。そういう目的を持って開示するので、「ファイナンシャル・ステートメンツ」っていう呼び名がついています。
企業はまず、設立して経営活動を行うには当然、経営資金が必要になります。会社を設立する時には株式を発行して資金調達を行いますし、設立後には追加的に株式を発行したり、金融機関からお金を借りたり、あるいは証券市場を通じて社債を発行するなどして資金を調達するわけです。
その時に、企業に投資しようとしている投資家や、貸し付けをしようとする金融機関が企業の状況を全く把握できないと、投資家は「株式をいくらで買えばいいのか」がわからないですし、銀行なども「どのくらいの利率で貸し付けるのが適正なのか」を判断できません。そうなると、当然企業側は資金調達ができなくなってしまいますし、資金がなければ経営を継続することも難しくなります。
ですから、企業としては、投資家や金融機関に対して「我が社は今こういう状況です」「財政状態はこうで、これまでの業績はこうです」という情報を伝える必要がある。そのために財務諸表を作成して、彼らが「この株価が妥当だな」とか、「このくらいの利回りが適正だな」と推定できるようにするわけです。KA:財務諸表というのは、企業が資金を調達するために必要な情報を、投資家や金融機関に提供する目的で作成されているものなのですね。
簿記から財務諸表へ――作成の基本プロセスと必要な知識
KA:では次に、財務諸表を作成する方法について教えていただけますでしょうか?
西海氏:財務諸表を作成するにあたって企業会計の基本となる原則があります。それが「企業会計原則」と呼ばれるものです。この企業会計原則の中に「一般原則の二」という項目があり、そこに「正規の簿記の原則」というものが定められています。これは、すべての取引について正確な会計帳簿を作成しなければならない、というものです。
つまり、財務諸表を作る際には、その元となるデータを、きちんと簿記で記録した帳簿に基づいて作成しなければならない、ということになります。したがって、財務諸表を作成する上での最も基本的な部分は「簿記」になります。簿記によって、企業の日々の経営活動をしっかり記録していくことがまず必要です。
この簿記の記録を1年間継続し、年度が終わった時点で、そのデータを基に「財務諸表」、つまり「貸借対照表」と「損益計算書」を作成する流れになります。
KA:愚弟的に簿記の例を挙げてもらってもよろしいですか。
西海氏:例えば、3,000円で商品を売った場合は、左側に「現金3,000円」、右側に「売上3,000円」と記録します。このような記録を日々積み重ねていくのですが、データを集計するにあたって、詳細をダラダラ書いても経営の妨げになるので、簿記ではできるだけ簡潔に記録することが基本です。
「現金が入ってきた」といった場合は、左側に「現金」とだけ記録しますし、「商品を誰々に売り上げました」という取引も、詳細には書かず、単に「売上」と記録します。
こうした取引の内容は「勘定科目」と呼ばれます。勘定科目は、それぞれ異なる性格を持っていて、基本的には5つに分類されます。それが「資産」「負債」「資本」「費用」「収益」の5つです。
次のステップとして、簿記で記録してきた内容を、これらの勘定科目に分類していきます。中でも、比較的わかりやすいのが「損益計算書」です。損益計算書は、「収益」と「費用」に関する勘定科目の金額を集計し、収益から費用を差し引いた「利益」を算出するためのものです。
一方、「貸借対照表」は、残りの「資産」「負債」「純資産(資本)」に関する情報をまとめて作成する、という流れが基本的な財務諸表の作成方法になります。
KA:例えば、簿記には3級や2級といった資格があると思います。そうした資格を取得すると、実際に財務諸表を作成できるようになるんですか?
西海氏:日商簿記の検定などでは、日々の簿記の記録だけでなく、最終的に財務諸表の作成までが範囲に含まれています。実際の企業で使われているような勘定科目ほど複雑ではありませんが、財務諸表を読むために必要な知識は、日商簿記3級の勉強を通して得られると考えて問題ありません。試験勉強を進めていけば、最終的には財務諸表を作成するところまで到達できるようになっているのです。
KA:ありがとうございます。簿記を学んでいない人が会計ソフトなどを使っても、財務諸表を作成することは可能なのでしょうか?
西海氏:もちろん可能です。会計ソフトに日々の経営取引を入力すれば、ソフトの方で自動的に簿記処理を行ってくれます。また、そのソフトには貸借対照表や損益計算書を作成するためのプログラムも組み込まれていますので、基本的には問題なく作成できます。
そのため、簿記の知識がなくても使えますが、入力されたどの取引データがどのように財務諸表上表現されているかは、わかっている方がもちろん良いと言えますので、簿記の知識があった方が望ましいのは確かですね。
財務諸表の実生活での活用法――投資・就職活動への応用
KA:続いて、財務諸表の勉強後、日常生活への生かし方について教えていただけますでしょうか。
西海氏:財務諸表を利用する人――、メインの利用者はやっぱり投資家だと思います。一番この利用に向く場面っていうのはどこかといったら、株式投資をするような場面ではないでしょうか。
あとは、大学三年生とか四年生が就職活動をするときに、その企業に行くにあたって企業分析をする場面も挙げられます。いくつか内定をもらって迷ったときに、どの会社が将来性があるのかなっていうことを判断する際にも、使える知識でしょう。
ただ、先ほども申しあげたとおり、一番のメインは、投資家が投資意思決定をするときに、その判断材料の一つとして使うことかなと思います。
KA:具体的に財務諸表の中でも、特にどういったところを重点的に見れば株取引に役立つことができるんでしょうか?
西海氏:例えば、ソフトバンクの貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を例に挙げてみます。 「BS」が貸借対照表、「PL」が損益計算書、「CF」がキャッシュフロー計算書を指しています。
まずは一番メジャーな貸借対照表から見てみましょう。貸借対照表は左側に資産の部があり、これは企業がどう資金を運用しているかを表しています。一方、右側には資金調達の方法や株主の持分などが載っています。簡単に言えば、左側が「お金をどう使ったか」、右側が「どう集めたか」を示しているというイメージです。
株式投資で注目したいのは、まず「資本合計(純資産合計)」です。ソフトバンクの貸借対照表では、資本合計が約3兆9000億円となっていて、これは株主全体の持ち分を示しています。この数字を発行済株式数で割れば、一株あたりの株主持分が分かります。この資本の金額を使った指標に「PBR(株価純資産倍率)」があります。
KA:PBRとは、どのような指標なのでしょうか?
西海氏:PBRは株価と資本合計の比率で、これが1を超えていれば株式市場は企業価値を帳簿上、記録上の株主の持分より高く評価しているということになります。逆に1を下回る場合は、市場がその企業の帳簿上の価値を信用していないということですね。
ソフトバンクの場合、PBRは3.06です。つまり、市場から非常に高く評価されていることを意味します。
ちなみに、業種別の平均PBRを見てみると、銀行業で0.4、情報通信業で2.3ほどです。ソフトバンクは情報通信業なので、業種平均よりも高いPBRです。つまり、それだけ企業価値が高いと見られているということですね。
ただし、PBRが高いということは、株価がすでに高いという可能性もあり、投資利回りはそれほど期待できないかもしれません。このように、PBRを見ることで、その企業の市場評価や投資価値を比較検討することができるようになるのです。
KA:続いて、損益計算書(PL)について教えていただけますか。
西海氏:ソフトバンクのPLには、売上総利益(粗利)、営業利益、純利益などが記載されています。
売上総利益は「売上総利益」または「粗利」と呼ばれ、販売による利益のことです。営業利益は、営業活動のみでどれだけ利益が出るかを示します。これらを売上高で割ると、粗利率や営業利益率、純利益率といった利益率が出るのです。
粗利率が高い企業は、他のコストが多少増えても利益を残しやすく、またインフレなどの外部からの影響を比較的受けにくい傾向があります。今のように物価が上昇しやすい時代では、粗利率が高い企業の方が安定しています。
また、株式投資でよく使われる指標に「ROE(自己資本利益率)」と「ROA(総資産利益率)」があります。
KA:これらはどういった指標なのでしょうか?
西海氏:ROEは株主の持分に対してどれだけ利益を出せているかを示すもので、目安は10%です。ソフトバンクの場合、ROEは15%なので、株式投資の観点から見ると非常に魅力的です。
一方、ROAは企業が保有する資産に対する利益率で、目安は5%。ソフトバンクのROAは3.8%とやや低めです。これは、設備投資などに大きな資金を使っているものの、利益率がそこまで高くないことを意味します。
つまり、ソフトバンクは薄利多売のようなビジネスモデルで、規模で利益を出している企業だと考えられます。経営効率は高くないかもしれませんが、規模で安定的に利益を稼得しており、株式投資の利回りは十分期待できるだろう、ということ考えられます。
こうした財務指標を実際の企業で比べてみたり、簡単な計算をしてみたりすることで、教科書で学ぶよりもずっと実践的に理解できますし、財務諸表の読み方にも慣れていくと思います。
財務情報の限界と課題は「情報の鮮度」と「開示頻度」のギャップ
KA: 財務指標における課題点と、その課題に対する改善策について教えていただけますでしょうか?
西海氏:まず、財務指標が開示されるタイミングについてですが、基本的には年に一度、年次決算としてまとめられます。これに加えて、四半期ごと、つまり年に3回の四半期決算も開示されており、合計で年4回、財務諸表が公開されています。
ただ、実際に最も活用されているのは年次決算の情報で、四半期決算の情報は、あくまで年次決算を補完する程度の位置づけになっているのが現状です。たとえば、株価を推定する際や、企業のファンダメンタルを分析する際も、投資家は年次決算の情報を主に参照しています。そのため、企業側からは「四半期決算を開示する必要が本当にあるのか」といった声も挙がっており、これがひとつの課題となっています。
もう一つの課題は、財務情報の開示頻度と株式市場の情報ニーズとのギャップです。株価や利回りなどの情報は、証券市場が動いている限りリアルタイムで変化していきますが、財務諸表という主たる企業情報は年に一度しか開示されません。
たとえば、10月30日に企業の株価を評価しようとした場合、その時点で利用できる最新の財務情報は、3月31日時点の年次決算になります。つまり、半年以上前の情報に基づいて評価を行わなければならないわけです。この間に企業の経営状況が変化している可能性も高く、時間が経つほど、財務情報の信頼性や精度は下がってしまいます。
このような不確実性を補うために四半期決算が存在するのですが、それでもあくまで四半期ごとですし、情報の「鮮度」という点で問題が残っています。
KA:なるほど、ありがとうございます。こういった課題に対して、何か改善策はあるのでしょうか?
西海氏:かつては会計処理をすべて手書きで行っていたため、頻繁に財務諸表を作成することは現実的ではありませんでした。しかし現在では、さまざまな会計ソフトを活用することで、日々の取引をデータ化し、蓄積していくことが可能になっています。
これにより、年次決算レベルの情報を、簡易的な四半期決算よりも精度の高い形で、もっと頻繁に開示できる可能性が高まっています。実際にXBRL(extensible business reporting language)というXMLを応用した財務諸表など企業情報の開示のためのコンピュータ言語が開発・導入され、ここ10年、あるいはもっと前から、研究の分野ではこうした方向性について議論されています。
KA:こういった動きは、企業にどのような影響をもたらすのでしょうか。
西海氏:企業側としては、頻繁に情報を開示すると、細かい取引の内容や経営の戦略的な要素まで外部に知られてしまう恐れがあります。たとえば、「このやり方で利益を出している」といった企業の強みが露呈すれば、競合に真似されてしまうリスクがあるのです。その結果、企業の利益機会が減り、業績が悪化してしまう可能性もあるため、企業としては頻繁な情報開示には慎重にならざるを得ません。
その一方で、情報開示が遅れることで、株式市場が企業の本来の価値を正確に評価できず、本当は業績が改善している企業の株価が上がらなかったり、逆に業績が悪化している企業に高い株価がついてしまったりするリスクもあります。これは市場の効率性を損なう要因になります。
したがって、企業秘密とのバランスをとりつつ、ある程度タイムリーに、かつ精度の高く、連続性のある情報を開示していく必要がある、というのが現在の課題と考えています。
KA:ありがとうございます。財務状況を社内で作成する際、投資家にとって魅力的に見せようとして、情報を都合よくごまかすようなこともあり得るのではと思うのですが、社内で作成された財務諸表の正確性を判断する仕組みはあるのでしょうか?
西海氏: 企業が自ら「これは正確です」と言ったとしても、それはあくまで自己評価ですので、第三者が完全に信頼するのは難しいですよね。実際に過去には不正会計の事例も数多く存在します。
そこで、作成された財務諸表が適正であることを保証する役割を担うのが公認会計士です。財務諸表が作成されると、公認会計士が企業に入り、機密情報に触れながら内容を確認し、「この情報に問題はない」と判断された場合に監査報告書を発行し、適正意見を出します。そして企業はこの監査報告書を財務諸表とともに開示することになります。監査法人、公認会計士は、もし、会計情報が一部問題がある場合は、限定付適正意見、会計情報が不適切である場合は不適正意見を表明し、さらに重要な監査手続が実施できなかったり、意見表明のための合理的な基礎が得られなかった場合は、意見不表明とします。
つまり、現代の財務諸表では、公認会計士がその適正性を保証する仕組みがしっかりと整備されています。基本的にはすべての上場企業が、監査報告書とセットで適正な財務情報として開示していますよ。
会計基準の国際化と今後の展望――IFRSの広がりと各国の対応
KA:では、財務指標における今後の展望について教えていただけますでしょうか?
西海氏:財務諸表は、会計のルールに従って作成されます。20世紀から21世紀の初めぐらいまでは、各国で会計のルールがそれぞれ定められていました。日本だと、先ほど申し上げた企業会計原則が主な基準になります。アメリカにはアメリカの基準があり、イギリス、ドイツも同様に独自の基準があるのです。
当然、ルールが異なると「日本のルールだからたまたま当期純利益が多く見えるのでは?」「アメリカの基準にしたら違う結果になるのでは?」といった指摘が出てきます。逆に、「アメリカの基準だから資産が多く見えるけれど、ドイツの基準で作成したらそうは見えないかもしれない」といった具合です。
KA:このような指摘が出てきたのは、やはり国際化が進んだからでしょうか?
西海氏:はい、その通りです。かつては日本の投資家は日本の株式に、アメリカ人はアメリカの株式に投資するといった具合に国内に閉じた投資が主流でしたが、今ではアメリカ人が日本企業に投資したり、日本人が中国やアメリカの企業に投資することが一般的になっています。
たとえば、各国で独自の会計基準がある場合には、トヨタとドイツのフォルクスワーゲンを比較する際、トヨタは日本基準で、フォルクスワーゲンはドイツ基準で財務諸表を作成しています。もし見かけは似ている企業だったとしても、基準が異なると比較にならないので、似た傾向にある企業だとは判断しきれません。そこで、「同じ基準で作らないと正確な比較ができない」ということで、国際会計基準が生まれ、国際財務報告基準(IFRS)へ発展してきました。
現在、EU諸国、カナダ、オーストラリア、東南アジア諸国、そして東アジアでは韓国など、多くの国がIFRSを採用してきています。 IFRSに基づいた財務諸表であれば、国が異なっても比較がしやすくなります。
KA:たしかに、問題は解決しそうですね。
西海氏:ただし、それに対して独自の会計基準を維持している国もあります。それがアメリカと日本です。理由としては、ニューヨーク証券取引所や東京証券取引所が世界的にも大規模な市場であることが挙げられます。特にニューヨーク証券取引所は非常に大きいため、アメリカ企業の特性を反映できる自国の会計基準を使うほうが望ましいと考えられます。
実際、IFRSは「全世界で通用する汎用的な基準」として作られているため、アメリカの企業を表現するには不十分な面もあります。そうした背景から、アメリカは基本的に自国の会計基準を使っていますが、希望すればIFRSを使ってもいいという柔軟なスタンスも取っているようです。
日本もアメリカと同様の立場です。特に日本は商慣行などに特殊な点があり、それらを踏まえた日本独自の会計基準を使ったほうが、日本企業の実態をより適切に表現できると考えられています。ただし、海外で資金調達を行う場合、たとえばヨーロッパで資金を集めるような企業に対してはIFRSを、アメリカで資金調達をするならアメリカ基準を使用した方が合理的だと考えられ、実際にそれは認められています。
KA:日本企業は柔軟に基準を変えているのですね。
西海氏:結局のところ、これらはヨーロッパとアメリカの経済力に左右される部分も大きいです。ヨーロッパ経済が活況になれば、IFRSの使用を求める圧力が高まりますし、アメリカ経済が優勢になれば、IFRSのプレゼンスが低下するという現象が繰り返されています。
それでも、日本企業の中でもIFRSを採用する企業は増えていますし、アメリカの企業でも採用例は出てきています。今後の展望としては、会計基準が完全にIFRSに統一されるとは思いませんが、財務諸表の作成においては、IFRSを参考にしたり、その考え方を取り入れたりする流れが進んでいくのではないかと考えています。
実用的な視点から学びを深める方法がおすすめ
KA:最後に、財務諸表を勉強しようという方に対して、何かアドバイスをお願いできますか?
西海氏:まず、財務諸表に興味を持つきっかけとして多いのは、簿記の資格を取りたいという理由と、株式投資をやってみたいので企業情報を読めるようになりたいという理由、この2つのパターンが主だと思います。
簿記の資格を目指す方は、資格試験向けのテキストが出版されていますので、それに従って勉強するのが一番効率的だと思います。きちんと体系立てて書かれていますし、その通りに進めれば合格に近づけるはずです。
一方、株式投資に興味があって財務諸表を学びたいという方は、財務諸表の基本構造を知って、その上でいくつかある財務指標の見方を身につけることが大切です。財務諸表の中に出てくる指標が何を意味しているのか、それを理解しながら読み取る練習をしていくと良いと思います。財務諸表の基本的な構造を理解するには、初学者は簿記3級の内容を学ぶことが良いと思います。もし財務諸表の知識が全くない初学者は、財務諸表の基本的な構造を理解するために、遠回りになる気がするかもですが、簿記3級の内容から学ぶのが良いと思います。
財務諸表を学ぶ際、会計学の教科書などを読むと、非常に細かいことまで書かれていて、全部覚えなければいけないような気がして、嫌になってしまうかもしれません。でも、実際には枝葉の話が多かったりもします。それに、先ほどお話ししたように、IFRSのように会計基準自体も経済の変化に合わせて変わっていきます。ですので、今覚えたことが数年後には使えなくなっている、ということも十分にあり得ます。
だからこそ、まずは「財務諸表が何を示しているのか」という基本をしっかり押さえることが重要です。そのためには簿記3級程度の知識をまず得て、そのうえで、実際の財務指標を見ながら「そこから何がわかるのか」ということを、遊び感覚でもいいので楽しみながら考えていく。そういう学び方が、結果的に一番力になるのではないかと思います。