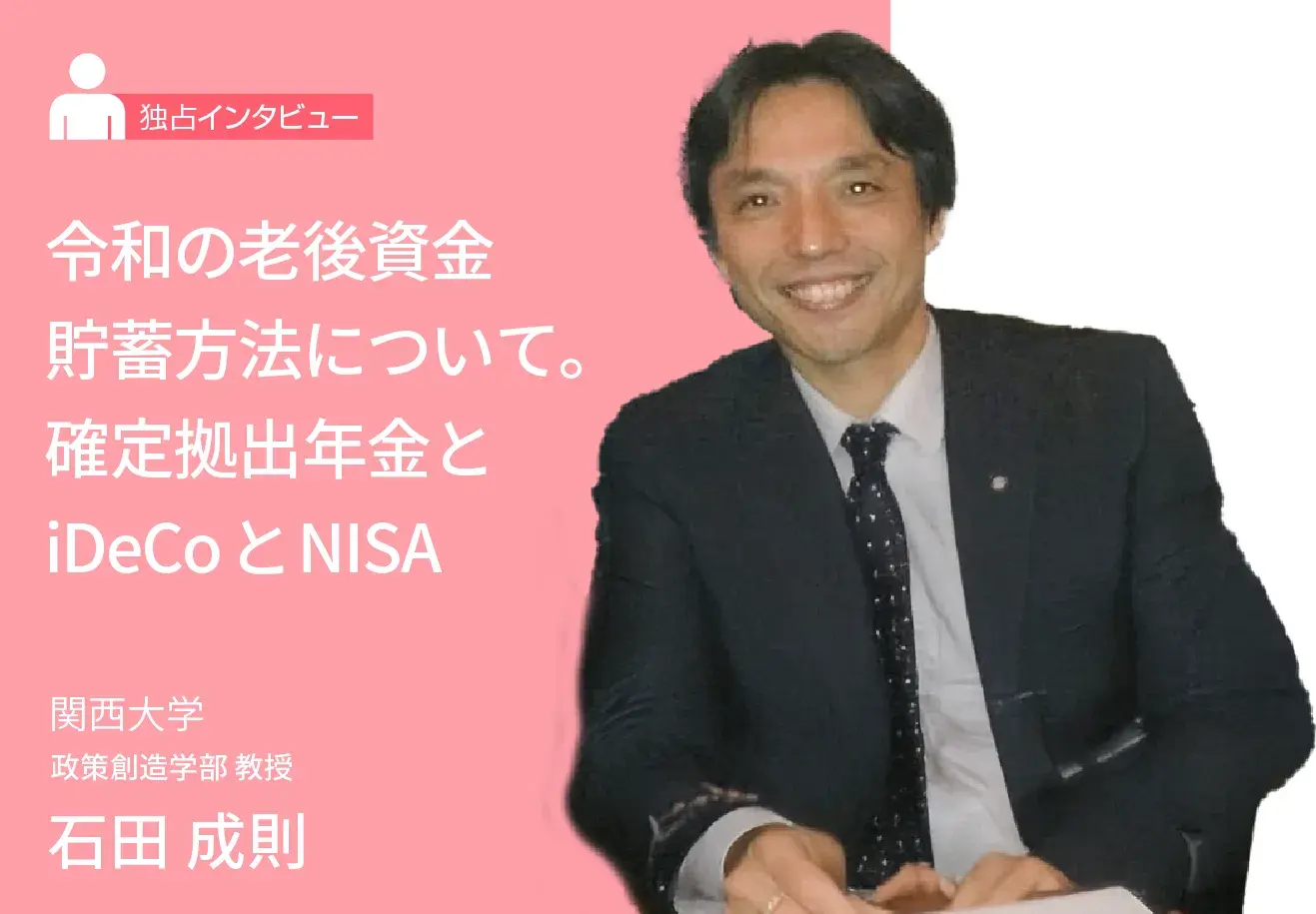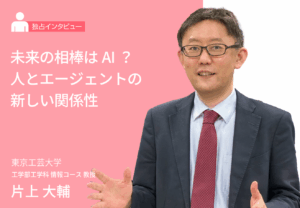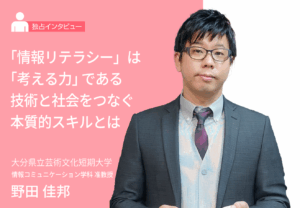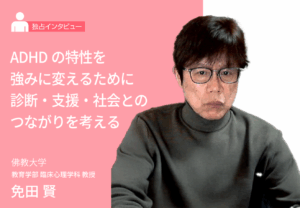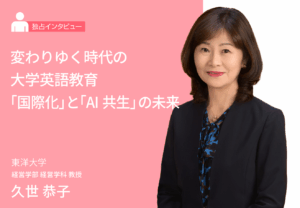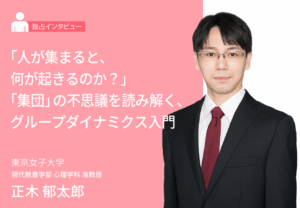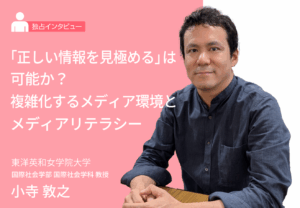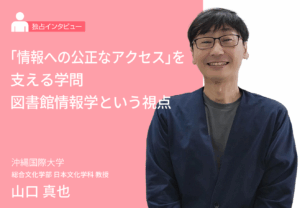昨今では老後の資金を自助によって準備する社会に変わってきていて、確定拠出年金やiDeCoなどに関心が高まっています。
確定拠出年金は、企業年金のうち確定給付企業年金に相当しないもので仕組みが大きく異なります。
本稿では、これまでの確定給付企業年金との違いや個人型の確定拠出年金であるiDeCoとの違い、投資行動として混同されがちな確定拠出年金とNISAとの目的面での比較などを、関西大学の石田教授に伺いました。

石田 成則
関西大学 政策創造学部 教授
【biography】
関西大学政策創造学部教授。社会保障論、福祉政策論、損害保険論担当。1991年慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程修了、その後1991年から2015年まで山口大学経済学部に勤務。2015年に関西大学政策創造学部に移籍し、現在に至る。この間、1996年9月から10ヶ月、文部科学省在外研究員として英国ヨーク大学経済関連学部に赴任。2009年商学博士(早稲田大学)
確定拠出年金とは
ナレッジアート以下KA):まず初めに、確定拠出年金というのはどういったものでしょうか?
石田氏:確定拠出年金とは、私的年金の1つで2001年の10月から制度導入されています。この確定拠出年金は、従来型の企業年金である確定給付年金に加えて新たに導入をされた制度です。確定拠出年金では、加入者である従業員が毎月一定の金額を掛け金として積み立て、そしてその積立金を加入者自らが運用し、元本と運用収益を老後に受け取る仕組みになっています。そのため、老後に受け取る受給金額は、運用の成績によって変動するという特徴があります。
この制度が導入された理由は以下の二点です。
第一に、公的年金の財政が非常に厳しくなり、従来の仕組みを続けていくと若い人たちの負担が重くなってしまうという懸念があったためです。そのため、2004年に大きな改革が行われ、従来の公的年金の仕組みが、給付率固定型から保険料率ないしは保険料水準固定型に変えられました。
この公的年金の改革によって、将来的に定年退職者が受け取ることになる年金額は徐々に下がっていくことになります。この下がっていく年金の部分を、従来の確定給付型の企業年金に加えて、確定拠出型の企業年金で補っていく。そして、所得代替率つまり働いている時の平均収入の8割を国の年金と私的年金、主に企業年金で確保するという目的で、この制度が導入されました。
併せて、経済のグローバル化や企業経営の国際化という時代の中で、だんだんと労働者・働く人たちの中における流動層が増えているという現状を考えなければなりません。従前の終身雇用制度とは違い、多くの労働者が転職を経験する社会になってきたわけです。
企業側としても、国際競争に打ち勝つため、人件費が高い正社員の数を減らし、非正規雇用と呼ばれる労働流動層の従業員の割合を増やすようになりました。
また、働く側としても、終身雇用が前提ではなくなったことで一つの会社に長く勤めたとしても将来的な給料があまり上がらない社会となったことから、自身の給料を増やすため、より良い処遇を求めて転職をするということが一般的となりました。
従来型の確定給付企業年金では、残念ながら転職をしてしまうと老後に貰える年金額がガクッと減ってしまいます。すなわち、長期勤続者が優遇される仕組みになっています。
これに対して、非正規雇用の方もそうですが、短期的に転職する人にも不利にならないように、確定拠出年金が導入されました。
この確定拠出年金は、仕組み上、自らの口座に毎月掛け金を積み立てていくことになります。そして、一つの会社から別の会社に移る場合には、その積立金の入金された口座ごと、つまり元本と運用収益を一緒に別の会社に移すことができます。こういう仕組みのことをポータビリティないしは年金携行性と呼んでいます。従来型の確定給付企業年金にはなかった、こうしたポータビリティ・年金携行性といった特徴があるのが、確定拠出年金ということになります。
KA:ありがとうございます。確定拠出年金の掛け金の負担割合と受給開始年齢について教えてください。
石田氏:はい。まず受給開始年齢については、60歳以降で具体的な年齢を従業員側で選択するというように定められておりまして、60歳以前にはこれまで積み立てた元本と運用収益を引き出すということはできないことになっています。これも特徴の一つですね。
確定拠出年金の掛け金の負担割合については、従業員側と雇用者側とが相談をした上でそれぞれの拠出額を決めることになっています。ただし、従業員側の拠出の方法は給料からの天引きという形になり、天引きされた額がご自分の確定拠出年金の口座に入金されるという仕組みです。
確定拠出年金の問題点と改善策
KA:ありがとうございます。次に、確定拠出年金の問題点とそれに対する改善策について教えていただけますでしょうか?
石田氏:課題点は運用面と制度面に分けることができます。
まず運用面ですが、確定拠出年金では自らの掛け金を運用する必要がありますが、この点については個人が利用しやすいかどうかといった点ではリスクがあります。運用がうまくいけば老後資金を多く得ることができますが、運用に失敗をしてしまうと残念ながら老後資金が目減りしてしまう、こういう危険性があり、大きな課題になっています。
この課題については、確定拠出年金の宿命ということになっていますが、リスクを低減させた金融商品を選択することが可能となっています。従来の確定給付企業年金と確定拠出年金の特徴を併せ持ったハイブリッド型の年金であるキャッシュバランスプランと呼ばれている商品が登場しています。
このキャッシュバランスプランでは、従業員個々が口座を持つことでポータビリティを持たせて転職をした時にも不利にならない仕組みになっています。
また、資金を管理する企業側が運用の責任も持つことで、最低限の老後資金を確保できるような仕組みになっています。よって、運用成績が良くないような状況でも企業側が一定の老後資金の保証をしてくれるというメリットが、このキャッシュバランスプランにはあります。
しかし、欠点もあります。この仕組みは、企業側が常に最低保証のために資金を持っている必要があるため、ある程度財務体力がある大きな企業でなければ導入することが難しくなっています。残念ながら、企業の多くを占める中小企業では、こういったプランはまだ普及しておりません。
次に、制度上の課題点です。大きく二点あります。
一点目は、今お話ししたように中小企業になかなか普及していないということです。財務体力がある大企業では確定拠出年金を導入することができても、財務体力がない中小企業では導入することが難しいという事情があります。
制度上の二点目の課題点は、自ら積み立てたお金であっても残念ながら60歳になるまで引き出すことができない点です。急な資金ニーズに応えることができないということで、これは大きなデメリットになっています。
これについては、日本に確定拠出年金を導入する際に参考としたアメリカの制度、いわゆる401(k)プランですけれども、この401(k)プランでは、60歳になる以前にも例えば教育資金や 災害時の資金や医療介護のための資金であれば引き出すことができるという柔軟性を持っています。こういった柔軟性があることで、401(k)プランはかなりアメリカ国内で普及しています。
残念ながら、日本で確定拠出年金があまり受け入れられていない背景には、60歳まで資金を引き出すことができないという窮屈さがあると考えています。今後、この緊急時の資金調達のための引き出しを容認することによって、我が国でも確定拠出年金の加入者が大きく増えることが期待できると思っています。
KA:ありがとうございます。中小企業においては普及が難しいというお話でしたが、加入者数や普及率はどれぐらいの割合になりますでしょうか?
石田氏:現在の加入者数は、およそ830万人程です。国内の全労働者ということで言うと正規も非正規も合わせると6000万人ぐらいの方がいますので、まだ15%にも満たないということになります。まだまだ加入率の向上のためには制度改善の余地があると考えられます。
KA:ありがとうございます。確定拠出年金を導入している企業の従業員は、加入をしないという選択も自由に取れるでしょうか?
石田氏:日本においてはできません。
この確定拠出年金は、労使の協約によって導入をするということになっており、労働組合がある企業であれば組合が同意し、組合がない場合には従業員の代表者と合意の上で導入するということになっています。そして、会社が導入をしている場合には必ず全ての従業員が加入するという仕組みになっています。
これはアメリカの仕組みとは少し違っていてアメリカでは自由に加入するかしないかということを選択できますが、日本では選択できません。
KA:ありがとうございました。確定拠出年金とiDeCoとの違いについてお教えいただけますでしょうか?
石田氏:はい。制度上の仕組みが大きく異なります。iDeCoは、個人型の確定拠出年金です。これまで私がお話してきたのは企業型の確定拠出年金ですので、確定拠出年金には2種類あるということになります。確定拠出年金の保険者となる企業、これを母体企業と呼んでいますが、iDeCoの場合は母体企業が保険者になるのではなくて国民年金基金連合会というところが一括して運用しているという仕組みになります。ここが大きな違いです。
そのため、個人型の確定拠出年金は、企業型の確定拠出年金と同時に加入するということはできない仕組みとなっています。
よって、企業型の確定拠出年金に加入していない人が、主にこの個人型の確定拠出年金に加入しているということになるため、加入者の種別というか加入者が全然違うと考えていただいたらいいかと思います。
すなわち、このiDeCoという制度の加入者については企業年金が無い会社の方か自営業者の方々が主だったため、加入者が少なくて10万人 から20万人という程度で推移しておりましたが、制度改革がありまして加入者が増えました。専業主婦の方、公的年金では第3号被保険者と呼称している専業主婦の方と、それから従来はこういった年金がなかった公務員の方に対象を広げました。この改革で、現在ではおよそ350万人が加入しているという状況になっています。
掛け金の負担の違いという点では、企業型の確定拠出年金の方は会社が掛け金を負担してくれるという仕組みですが、個人型の確定拠出年金では完全に個人が拠出をすることになります。
掛け金の引き出しという点では、60歳まで引き出すことができないという点は個人型だろうが企業型だろうが同様です。老後の資金を形成するために導入された制度設計ということが理由です。
確定拠出年金における今後の展望
KA:ありがとうございました。では、確定拠出年金における今後の展望について教えていただけますでしょうか?
石田氏:はい。従来の企業型に加えて個人型の企業年金を導入したというのが1つの大きな制度改革になっていますが、この改革によって加入者数が非常に増加しています。
ただし、中小企業ではなかなか企業型の確定拠出年金を導入することもできず、また中小企業に勤めている従業員の方は、あまり給料が高くないということもあって、老後に備えるということがなかなかできない状況でした。
そこで、2018年に新しい制度が導入されました。これはiDeCo+(イデコプラス)という制度です。制度の違いとしては、先ほどの個人型の確定拠出年金では、加入者は自分が掛け金を出してその掛け金だけを運用することになりますので、少額の資金しか運用できない、よって結果的に運用収益もあまり大きくないということが欠点でした。ところが、iDeCo+では、従業員の掛け金と同額まで企業側が掛け金を拠出することが可能となりました。
こうした制度改革により、今後ますます個人型企業型含めて確定拠出年金の普及につながっていくことが期待されています。
KA:ありがとうございます。掛け金の設定について、だいたいこのくらいの掛け金を月々拠出すれば老後資金として安心だというような目安の額はございますか?
石田氏:目安となるかは分かりませんが平均値としては、最も多い層が2万円程度ということになります。例えば、毎月1万円ずつ積み立てるということになると1年間で12万円ですね。5年間で60万円、30年間で360万円ということになるわけです。一番多い層が2万円程度ということになりますので、30年で600万円ぐらいというのが平均的な数値になります。
国としては、掛け金負担の上限の枠として55,000円というのを決めていまして、それ以下であれば税金は一切かからないですね。また、運用収益にも一切税金負担がないというメリットがありますが、この上限の月々負担額が55,000円程度ということになっています。そして、55,000円を積み立てた場合は30年間でだいたい1800万円程になります。
国としては、30年で1800万円ぐらいのお金を積み立てて欲しいと考えているところかと思いますが、残念ながら平均でもその半分にも満たないというのが現状になっています。
確定拠出年金への加入を検討している方に向けたアドバイス
KA:ありがとうございます。確定拠出年金への加入を検討している方に対してアドバイスをお願いしてもよろしいでしょうか?
石田氏:はい。確定拠出年金については、いくつかの種類があるということをまず理解をする必要があると思います。そして、ご自分の会社で導入しているかどうか、まずそれを調べる必要があります。もし導入されている場合には、基本的には加入するということが 義務になります。
ご自分の会社が企業型の確定拠出年金を導入しているのかどうか、導入しているとしたら掛け金はいくらぐらいでどのように資金が今たまっているのか、まずそういうことを確認するということをおすすめします。
その後、お勤めの会社に導入されていない場合や、専業主婦や公務員の方は、個人型の確定拠出年金iDeCoに加入するということができます。
しかし、自ら資金を運用していくことが求められますので、なかなかハードルが高いと思われます。そこでiDeCoです。特に、これまで投資信託などを買っている方々はこのiDeCoに加入することによって税の優遇措置を受けられることになります。掛け金に対しても運用収益に対しても税金がかけられないということで、非常に有利な金融商品になるわけです。ですから、従来から金融商品を購入していたという人にとっては加入の意味は非常に大きいと思います。
あとは、金融商品を運用するので、金融機関の窓口の人と相談することになりますが、知識がなければ商品の選択を適切にはできませんし、金融機関に推奨されるものを鵜呑みにする形となってしまいます。また、月々の運用実績もレポートとしてお手元に送付されると思いますが、それをしっかり確認しなければいけません。そういう意味では、ご自分でしっかり金融や株式市場の動きなどに関心を払って勉強をすることも大事かと思います。
そもそも、ご自分が確定拠出年金に加入しているのか、どの種類の年金に加入しているのか、こういったことにこれまで関心が無くて分からなかったという方は、所属の会社の総務や人事の関係部署に確認してみてください。
我が国では、自分が一体どれくらいの掛け金を月々負担しているのか分からないという方も結構いらっしゃるんです。ですので、現在は国の方で年金ダッシュボードというものを作って、個人の年金の支給開始年齢や貰える年金額など公私年金の具体的な情報を一纏めにして周知する方法を構想しています。ちなみに、欧米諸国ではこうした年金情報を国民に対して郵送で情報提供しています。その点日本はまだまだ遅れておりますので、今後早急に整備していく必要があるかと思います。
KA:ありがとうございます。では最後に、政府により税制優遇されて運用商品も選べるっていう点ではNISAもありますがNISAとiDeCoの違いを教えていただけますでしょうか?
石田氏:はい。NISAとiDeCoは目的が違っています。
iDeCoの場合は、老後の資産形成が目的であり、より長期にお金を運用するということになります。ですので、金融商品も基本的には長期的な保有を目的とした商品が中心になってきます。
また、優遇措置の額は、月々55,000円で年間66万円までです。
対してNISAは、年間 240万円(つみたて枠は別に120万円)の優遇措置と非常に大きな金額になります。ただし、今は撤廃されていますが、従来は期間が決められていて、その中でまた別の金融機関に預けることになるため、短期的な資金を増やす目的で行うものになります。例えば、住宅の購入資金であるとか、あるいは子供の教育資金であるとかですね。
短期に資金を増やすのか、それとも老後資金を積み立てるのか、このようにNISAとiDeCoは目的が違うため、運用の手段も変わってくるということを考えて頂きたいです。