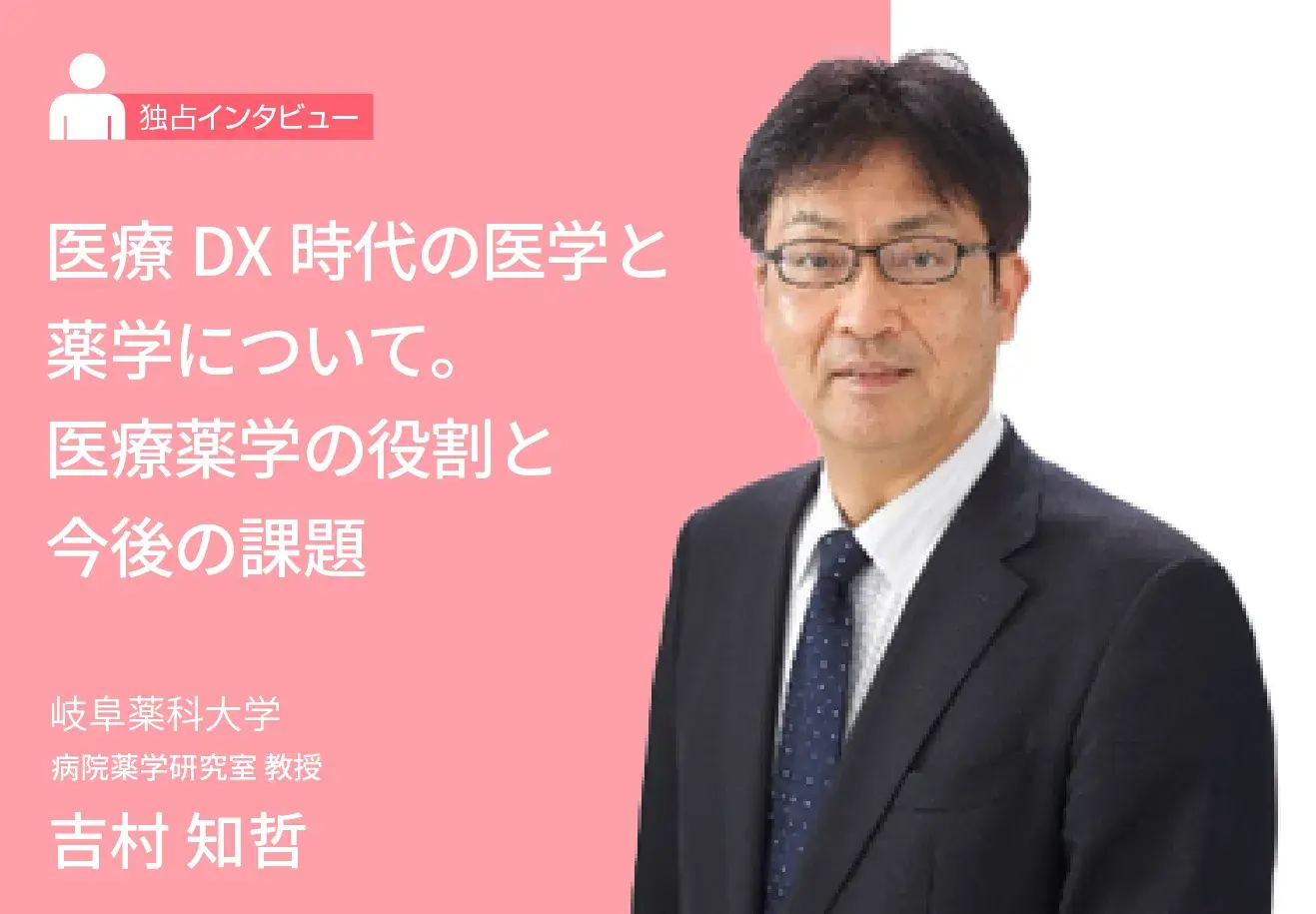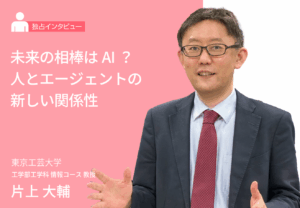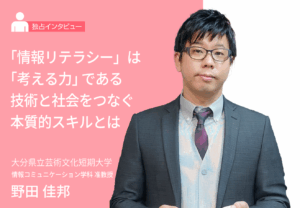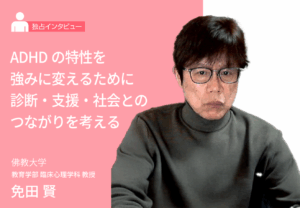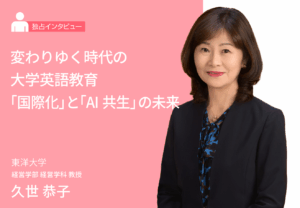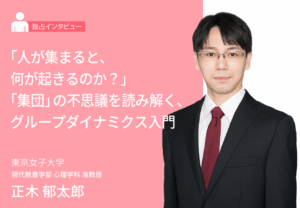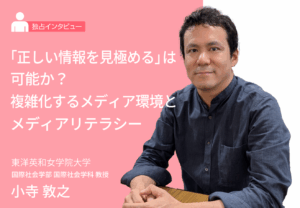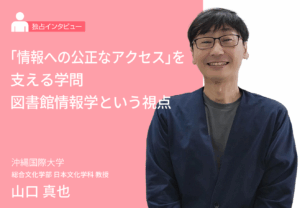医療にもDX化の波が押し寄せ、医学や薬学においてもビッグデータ解析を活用した新たな患者さんへのアプローチが広がっています。特に、患者さんの個別ニーズに応じた治療を支援する分野として、医療薬学が注目されています。
AIや機械学習による患者さん個人に合わせた医療の提供やデジタルヘルスの技術の進展、
医療機関による正しい情報の発信など、医療や薬学を取り巻く環境が激変しています。
そこで今回、医療薬学が抱える課題や今後の展望について、専門家である岐阜薬科大学の吉村教授にお話を伺いました。

吉村 知哲
岐阜薬科大学 病院薬学研究室 教授
【biography】
●学歴・職歴等
1985年3月 岐阜薬科大学 卒業
1987年3月 岐阜薬科大学大学院博士前期課程 修了
1987年4月 大垣市民病院薬剤部 入職
2015年4月 大垣市民病院 薬剤部長
2017年4月 大垣市民病院 院長補佐、通院治療センター副センター長(兼務)
2023年4月 岐阜薬科大学 実践薬学研究推進センター長 病院薬学研究室 教授
現在に至る
●資格等
・1997年 学位[博士(薬学)]取得
・日本医療薬学会認定がん指導薬剤師
・日本医療薬学会認定がん専門薬剤師(2007年~2019年)
・日本医療薬学会 医療薬学指導薬剤師・専門薬剤師
●書籍
・「がん薬物療法副作用管理マニュアル」第3版,医学書院,2024
・「がん専門・認定薬剤師のためのがん必須ポイント」第5版, じほう, 2023
・「薬剤師のための栄養療法管理マニュアル」,医学書院,2023
・「検査値と画像データから読み解く 薬効・副作用評価マニュアル」,医学書院,2022
・「検査値×薬物療法のマネジメントスキルを強化する ハイリスク薬フォローアップ」,じほう,2022
・「薬剤師が実践すべき副作用へのロジカルアプローチ」,南江堂,2021
など
医療薬学とはどんな学問か
ナレッジアート(以下KA):まず初めに、「医療薬学」 というのはどういった学問なのかについて教えていただけますか?
吉村氏:医療薬学とは、名称の通り医療と薬学を融合させた学問分野であり、患者さんに適切な薬物治療を提供するための学問です。この分野は多岐にわたり、薬物の効果検証、副作用のメカニズムの解明、適切な薬物治療を通じた患者さんの健康支援を目的としています。加えて、薬の設計や製造、臨床研究、患者指導や教育までを幅広くカバーしています。特に、薬剤師は、医師や看護師と共に、「チーム医療」の一員として重要な役割を果たします。単に薬を提供するだけでなく、適切な薬物療法の基盤を築くことも医療薬学の大きな役割です。
医療薬学の研究分野は多岐にわたりますが、特に薬物治療の最適化においては、薬物動態学(ファーマコカイネティクス pharmacokinetics, PK)と、薬力学(ファーマコダイナミクス pharmacodynamics, PD)を組み合わせて解析するPK/PDの概念が重要です。個々の患者さんに適した治療を提供するために、副作用の防止や薬物相互作用のメカニズム解明にも取り組んでいます。
また、患者さんの治療への理解を深めるためにコンプライアンス(医療従事者の指示通りに治療を受けること)やアドヒアランス(治療方針の決定に賛同し、より積極的に治療を受けること)を向上させるための教育も重視されています。
加えて、医療経済学の観点から、薬物治療の費用対効果を考慮し、患者さんの医療費負担軽減も視野に入れた研究も進められています。
このように、医療薬学は多様な分野を横断しながら医療に貢献する学問になります。
KA:ありがとうございます。医療薬学という分野は、大学教育においては医学部と薬学部、どちらの研究分野になりますでしょうか?
吉村氏:基本的には薬学の領域に属します。医学でも薬物治療学を通して薬学と関連する内容を学びますが、薬学においては薬物動態や薬物相互作用などをより深く研究します。医学部では主に薬の臨床応用に重点を置き、薬学部では薬の作用メカニズムや動態を詳細に研究するという違いがあります。
医療薬学の知識の日常生活への活かし方
KA:ありがとうございます。医療薬学の知識を日常生活へ応用する方法について教えていただけますか?
吉村氏:これは医療薬学というより薬剤師の知識ということになるかもわかりませんが、 健康増進や適切な薬の選択、使用方法のアドバイスなど、日常生活において多くの場面で活用できます。
例えば、がん患者さんが標準治療(手術や抗がん剤治療)以外の民間療法などを検討することがあります。世間には根拠不明な情報が多く、例えば、「この薬を飲んだらがんが消えた」といった怪しい情報も流れています。実際に、私も知人から民間療法の是非について相談を受けたことがありました。こうした場合、科学的根拠(エビデンス)が最も重要であり、安全性や費用面を考慮すると標準治療を受けることを推奨します。
また、市販薬の選択にも知識が役立ちます。表示されている薬の成分を確認し、症状に適した薬を選ぶことで、より効果的な治療が可能です。
副作用の早期発見や対応も重要です。例えば、めまいや発疹が現れた場合、直ちに服薬を中止し医療機関を受診する判断ができます。
さらに、薬物相互作用の知識も有益です。処方薬同士の相互作用は医療機関でチェックが可能ですが、サプリメントや食品との相互作用は見落とされがちです。例えば、納豆を食べるとワルファリンの作用が減弱するため併用は禁忌です。このような知識により、事故を未然に防ぐことが可能です。
また、生活習慣病予防のための食生活改善や、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の予防にも役立ちます。消毒薬の選択一つをとっても、全てのウイルスや菌に有効なわけではなく、適切な知識が必要です。
さらに、災害時の対応も重要です。災害時などの緊急時には医療機関で通常の薬が手に入らない可能性がありますが、医療薬学の知識があれば適切な薬の管理や代替策を講じることができます。
このように、医療薬学の知識は日常生活のさまざまな場面で役立ちます。
KA:ありがとうございます。民間療法やエビデンス不十分な治療方法や治療薬を勧められた方へのアドバイスが可能とのお話ですが、そのような薬や治療法を勧めてくる人はSNSを通じて広めているのでしょうか?
吉村氏:そうですね。情報の入手経路にはさまざまなケースがありますが、がん患者さんには年配の方も多いため、SNSよりもダイレクトメールや知人からの伝聞・紹介といったケースが多いように見受けられます。例えば、「知り合いから、この鉱石の成分中のミネラルを摂取したらがんが根治したと聞いた」といったケースですね。
もちろん、インターネット経由での情報入手も多いです。特に、インターネット検索をすると、さまざまな情報が掲載されており、その中には根拠不明の怪しい情報も含まれています。中には、「病院で提供される標準治療は悪だ」と断定するウェブサイトも見受けられます。そういったサイトには、「抗がん剤治療は副作用ばかりで寿命を縮めるだけ」といった内容が書かれていることもあります。そのような情報を信じてしまい、民間療法を選択するケースもあります。現在、真偽不明の情報が氾濫している状況です。
こうした中で、科学的根拠のある情報を正しく判断し、適切に選択できることが私たちの強みだと考えています。
KA:ありがとうございます。では、フェイクニュースが溢れている中で患者さんが正しく情報を得るには、どういったことが大事かと思いますか?
吉村氏:はい。現在、インターネットやSNS上には真偽不明の情報が氾濫しており、患者さんや一般の方々が正しく情報を取捨選択することは簡単ではありません。医学や薬学の基礎知識が前提として必要になるためです。
そのため、そうした知識を持つ専門家が正しい情報を発信・紹介することが重要だと思います。例えば、「このサイトは信頼性が高い」と薬剤師が紹介する、あるいは、薬剤師会や医療機関が正しい情報を発信するプラットフォームを構築するなど、環境を整備することが第一歩となるでしょう。
その上で、患者さんや一般市民、お子様向けに情報リテラシー教育を実施し、キャンペーンを通じて正しい薬の使い方を啓発することも大切です。こうしたキャンペーンを通じて、先ほど述べた信頼性の高いサイトやプラットフォームの周知を図ることが重要だと考えます。
また、医療従事者側の教育も欠かせません。正確な治療方法や薬品情報の発信を行うためには、発信者側への教育・啓発も必要になるでしょう。
医療薬学の抱える課題とその改善策
KA:ありがとうございます。では医療薬学の現状における課題点とその課題に対する改善策について教えていただけますでしょうか?
吉村氏:はい、現状の課題として以下の4点を挙げます。
1. 医療・薬物療法の個別化を進める上での障害
現在、医療の個別化が進んでおり、患者さんの個々の体質や症状に特化した薬を処方する流れとなっています。しかし、それを進めていく上での障害もあります。
個別化医療を実現するためには、患者さんの体質や遺伝的背景、生活環境などを把握する必要があります。当然、副作用の程度も患者さんごとに異なります。
しかし、病院ではがんをはじめ多くの疾患において標準治療がガイドラインに基づいて提供されており、ある程度画一的な治療が行われます。そのため、患者さんごとに最適な治療とは限らないケースもあるのです。
改善策として、薬物ゲノム学の活用が挙げられます。患者さんの遺伝情報を基に薬の選択や投与量を最適化することが可能です。
また、医療ビッグデータやリアルワールドデータの活用も有効でしょう。電子カルテや医療データベース、レセプトデータ等を解析し、治療効果を評価することで、より適切な薬物療法の選択につなげられます。
さらに、AIや機械学習を導入し、個別の患者さんのプロファイルに基づいた最適な治療計画を提案する医療DXの進展も期待されています。
2. 薬剤耐性菌の増加
感染症に対する抗菌薬や抗生物質が効かなくなる薬剤耐性菌の増加は世界的な問題となっています。
2050年には薬剤耐性菌による死者が1,000万人に達すると予測されています。2013年中にがんで亡くなった方は年間820万人であり、このままではその頃にはがんの死者よりも薬剤耐性菌による死者の方が多くなると予測されています。
薬剤耐性菌増加の原因は、抗菌薬の不適切な使用や過剰使用が薬剤耐性菌の発生を助長しているとされています。そして、それに対抗できる新薬の開発ペースも、耐性菌の変化のペースに追い付いておりません。
改善策として、現在できることとしては、抗菌薬の適正使用の推進があげられます。
そのために、薬剤師をはじめとする医療従事者への教育が必要です。抗菌薬の処方に関して、投薬の効果がないと見受けられる病気に対しては、むやみに使用しないことが最も重要です。例えば、小児科などでは、かつて風邪に対して頻繁に処方されていた抗菌薬が、現在では適正な使用に限ろうとする動きが広がってきています。
また、耐性菌の監視システムも稼働し始めており、全世界で耐性菌の分布や傾向を継続的にモニタリングする研究が始まっています。
さらに、新薬の開発についても、公的資金を投入することで耐性菌に効果のある抗菌薬の開発を強化することが求められます。このような取り組みを進めながら、薬剤耐性菌の増加に対処していく必要があるのではないでしょうか。
3. ポリファーマシーの問題
ポリファーマシーとは、「Poly(多くの)」+「Pharmacy(調剤)」を組み合わせた造語で、多剤併用を意味します。高齢者は複数の疾患を抱えていることが多く、それに伴い多くの薬を服用しているケースが一般的です。病状に対して対症療法的に薬剤を処方すると、多剤併用(ポリファーマシー)の状況を招きやすくなり、薬物同士の相互作用や副作用のリスクが高まる可能性があります。高齢化社会の進展とともに、この問題がより注目されるようになっています。
また、服薬のスケジュールも複雑化するという問題があります。例えば、Aという薬は朝に服用し、Bという薬は寝る前に服薬するといったスケジュールになると、先に述べたアドヒアランスやコンプライアンスの観点でもマイナスとなり、患者さんの医療や投薬治療への理解が低下する要因となります。理解が低下すれば、過剰使用にも繋がりかねません。
ポリファーマシーの問題に対する改善策としては、無駄な薬を減らすということが最も重要です。処方の適正化が求められます。処方する医師や薬剤師も含め、「チーム医療」として医療従事者全員で患者さんに寄り添い、例えば現在処方されている薬が本当に症状の改善に繋がるのかをダブルチェックすることや、不必要な薬がないかを精査する体制を構築することが重要です。
また、別の改善点としては、デジタルツールの活用も有効だと考えられます。例えば、患者さんがスマートフォンアプリを用いて薬の服用スケジュールを管理することで、飲み忘れを防ぐことができます。
従来のアナログな方法としては、お薬カレンダーに服用予定の薬を小袋に分けて貼付するという方法があります。しかし、出先に持っていくことを忘れるケースがありました。その点、スマートフォンアプリを活用すれば、服薬スケジュールの管理が容易になり、リマインダー機能を使って服用を通知することが可能になります。
もちろん、ご高齢の方でスマートフォンを使いこなせない方には、従来のアナログも有効です。しかし、医療のDX化の波に乗ってデジタルツール活用することはアドヒアランス向上のための一助になるでしょう。
4. 薬品情報の氾濫と信頼性
インターネットやSNS上では薬に関する情報が氾濫しており、中には不正確な情報に基づいて薬が使用されるケースも見られます。この問題は、先に述べたがん治療だけでなく、若者の間にも影響を及ぼしています。例えば、「オーバードーズ(OD)」の問題があります。これは、風邪薬や咳止め薬などを一度に大量に服用する行為のことですが、非常に大きな社会問題となっています。
この薬品情報に関する問題の対策としては、信頼性の高い情報の発信が重要です。医療機関や医療従事者による信頼性の高い情報源を紹介すること、また、医師や薬剤師、医療機関によるプラットフォームを構築し、患者さんや一般利用者に正しい情報を発信することが求められます。
さらに、患者さん向けの情報リテラシー教育の実施や、正しい薬の使い方を啓発するキャンペーンイベントの開催も有効です。こうしたイベントを通じて、信頼性の高い情報サイトやプラットフォームの周知を図ることも解決策の一つとなるでしょう。
KA:ありがとうございます。適正な薬の処方に関するご質問ですが、オンライン診療が普及していっている中で不適切な薬の処方が行われるケースも見受けられますが、そういったことを防止するための案があれば教えていただけますでしょうか?
吉村氏:オンライン診療は非常に効率的で有用かと思います。新型コロナウイルス感染症の影響で一気に普及しましたが、血液検査やバイタルサインの測定が不要な診療であれば、オンライン診療を活用するのは妥当だと考えます。
適正な薬の処方が行われなかったという点については、オンライン診療そのものの問題というよりも、保険適用外の診療に起因するケースが多いのではないでしょうか。例えば、糖尿病治療薬をダイエット目的で保険適用外で入手するケースがあります。確かに割高にはなりますが、購入は可能です。しかし、そのような場合、もし副作用が生じても救済措置を受けることができません。例えば、糖尿病治療薬には急性膵炎などの重篤な副作用のリスクがありますが、安易に購入する人も少なくありません。同様に、美容整形などの分野でもこのようなケースが見られます。こうした状況では、薬剤師が介入できないのが現行制度の限界です。こうした危険性について、正しい情報を発信していくことが重要だと考えています。
KA:ありがとうございました。現状の薬の処方の問題という点では、薬自体の流通量が減っていて処方箋を薬局に持って行っても薬が取り寄せになってしまうケースが増えてきております。そういった問題について、解決策や改善策等がございましたらお聞かせいただけますでしょうか?
吉村氏:現在、日本国内では薬の安定供給に関する問題が深刻化しています。特に、ジェネリック医薬品の供給が大幅に減少していることが大きな要因です。数年前、一部のジェネリック医薬品メーカーが適切な製造工程を遵守していなかったことが発覚し、厚生労働省から行政処分を受けました。大手メーカーも対象となり、その影響で国内の生産体制が縮小してしまいました。一方で、先発医薬品の供給には大きな問題は発生していませんが、ジェネリック医薬品の供給不足により、多くの医療機関や薬局で影響が出ています。
この問題の解決策として、国内の製造体制の強化や、海外メーカーからの安定した供給確保が求められます。また、薬の供給状況をリアルタイムで把握できるシステムを整備し、医療機関と薬局が連携して迅速に対応できるようにすることも重要です。
医療薬学の今後の展望
KA:ありがとうございました。最後のご質問になりますが、医療薬学の今後の展望についてお教えいただけますでしょうか?
吉村氏:はい。医療薬学の展望を課題やその改善策を踏まえて、以下の5点について触れたいと思います。
1. 個別化医療の推進
医療の個別化が進む中で、患者さんのライフスタイルや遺伝情報を考慮したオーダーメードの薬物療法が主流となっていくと考えます。そのためには、医療ビッグデータの活用が不可欠です。日常生活における健康データを解析することで、より効果的な医療や薬物選択が可能になり、個別化医療の推進が加速するでしょう。
2. AIを活用したデジタルヘルス技術の進化
AI技術は、患者さんごとに最適な処方を提案し、薬物相互作用のリスクを予測するなど、医師や薬剤師の診療をサポートする役割を担うようになります。さらに、ウェアラブル端末を用いた薬効のモニタリングや副作用の検知、電子薬歴システムによる一元管理も普及するでしょう。
また、デジタル治療薬(デジタルセラピューティクス)も注目されています。例えば、アメリカでは、ADHD(注意欠陥多動性障害)の治療用アプリが認可されています。このアプリでは、ゲームを通じて患者さんの注意力を向上させることが可能です。さらに、認知行動療法を基盤とした薬物依存症治療プログラムや、2型糖尿病患者向けの血糖値モニタリングアプリなども開発されています。今後、医療薬学においてもデジタル技術の活用がますます進むと予想されます。
3. リアルワールドデータの活用
AI技術の進展に欠かせない医療ビッグデータの活用が、個別化医療の進展をさらに加速させると考えます。リアルワールドデータの活用は、薬物の実際の効果を検証するという点でも重要です。
4. 再生医療とバイオ医薬品の発展
再生医療や遺伝子治療といった新しい治療法が次々と登場しています。従来の医薬品とは異なるメカニズムを持つため、薬剤師や研究者も新たな知識や経験を蓄積する必要があります。
5. チーム医療における薬剤師の役割拡大
私自身、病院で薬剤師として36年間勤務しましたが、当初は調剤が主な業務でした。しかし現在では、患者さんへの指導やサポートを積極的に行い、「チーム医療」の中での役割が拡大しています。
さらに、専門薬剤師制度が導入され、がんや感染症など特定の疾患に応じた専門的な薬剤師の需要が高まっています。薬剤師がより重要な役割を担うようになるため、適正な診療報酬の確保も今後の課題と考えます。
医療薬学を勉強中の方や検討している方へのアドバイス
KA:ありがとうございます。では最後に、医療薬学を勉強している方や医療薬学にご興味がある方へのアドバイスをお願いしてもよろしいでしょうか?
吉村氏:はい、医療薬学の具体的な内容についてはこれまでお話ししたとおりですが、根本的には「科学的な探求」と「人類への貢献」という二つの要素があると考えています。科学に対する探究心と、人の健康に貢献したいという使命感、これこそが、医療薬学の魅力ではないでしょうか。
また、勉強する上では目的意識を持つことが非常に重要です。
例えば 、「新薬開発研究に携わりたい」「入院患者さんの薬物療法をサポートしたい」といったように、どのような形で医療薬学に関わりたいのかを明確にすることで、学ぶべき領域が自然と絞り込まれていきます。医療薬学には多様なアプローチがあるため、自分がどの分野に貢献したいのかを考えることが、学びの指針となるでしょう。
実際、医療薬学には臨床薬学、薬剤学、薬物動態学、薬物相互作用の研究など、幅広い分野が含まれています。その中で自分が最も興味を持てる分野を見つけることが、学びのモチベーションを維持する上でも、将来的に実践的なスキルを身につける上でも、とても大切です。また、自分のリサーチクエスチョン(研究課題)を見つけ、それを深掘りしていくことも重要です。大きな目標を持って研究に取り組むことで、より実りのある学びにつながるはずです。
何より、医療薬学は、薬を通じて人々の健康を支える重要な学問です。科学的な視点と実践的なスキルを兼ね備え、多くの人の健康と生活の質向上に貢献できる、非常にやりがいのある分野だと思います。
ぜひ、医療薬学に興味を持ち、学びを深める人が増えていくことを願っています。