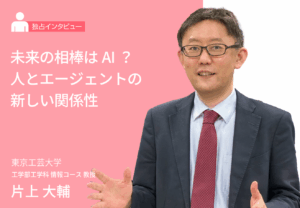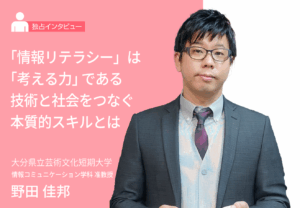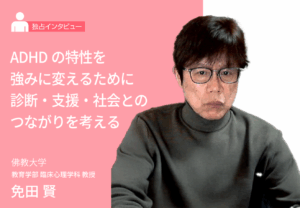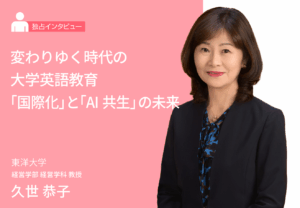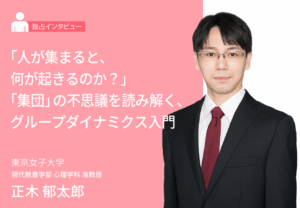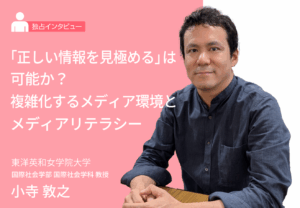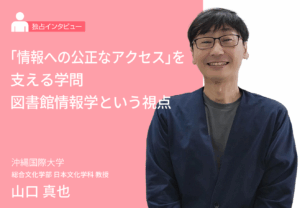日本の実質賃金は、2023年に前年比マイナス2.5%を記録しました。この数字は、私たちの給料が上がっているにもかかわらず、生活が楽にならない現状を如実に表しています。なぜこのような事態が起きているのでしょうか。
この記事では、マクロ経済学の視点から、賃金と物価の関係性を紐解きます。また、実質賃金の低下が私たちの暮らしに与える影響の理解と対策についても、大東文化大学の郡司大志教授からお話を伺っています。
マクロ経済学は遠い話のように感じるかもしれませんが、物価上昇や賃金の問題は、私たちの日常生活に直結しています。マクロ経済の仕組みを理解することで、家計の管理から資産運用まで、より賢明な判断を後押ししてくれるでしょう。

郡司 大志
大東文化大学 経済学部 教授
【biography】
大東文化大学経済学部教授。法政大学経済学部経済学科卒。法政大学大学院社会科学研究科経済学専攻博士後期課程修了。博士(経済学)。日本学術振興会特別研究員(PD)、東京国際大学経済学部客員講師(一号)などを経て、現職。専門はマクロ経済学、金融政策、金融論。主な著書に『マクロ経済学への招待』新世社(2024年11月)、主な論文に “Impact of the Kuroda Bazooka on Japanese households’ borrowing intentions,” Japan and the World Economy 69, 101240, 2024(単著)、“Did the BOJ’s negative interest rate policy increase bank lending?” The Japanese Economic Review 76, 91-120, 2025(単著)、“Do reserve requirements restrict bank behavior?” Forthcoming in the Review of Financial Economics(三浦一輝氏との共著)がある。
マクロ経済学とは?データから見える経済の全体像
ナレッジアート(以下KA): まず最初に、マクロ経済学とはどのような学問なのか教えていただけますか?
郡司氏: マクロ経済学とは、個人や企業といった個別のデータではなく、それらを集計したデータを分析する学問です。例えば、個人の消費額を調査して、それを国全体で集計すると「家計最終消費支出」というデータが得られます。このような集計データをもとに、経済全体の動きを分析するのがマクロ経済学です。
具体的には、失業者を集計して「失業者数」を出し、そこから「失業率」を計算します。また、物の値段を集計して「物価水準」を求め、それを基に「インフレ率」を算出します。こうしたデータを分析することで、経済の問題点が浮き彫りになります。
例えば、失業率が上がれば労働市場に問題があることが分かりますし、インフレ率が上昇すれば物価が上がり、国民生活に影響が出ることが分かります。現在の例で言えば、インフレ率が高くなり、物の値段が上昇している状況を分析するのがマクロ経済学の役割です。また、問題を特定した後、その解決策や政策を検討することもマクロ経済学の重要な役割です。
KA: マクロ経済学と似た言葉で「ミクロ経済学」というものを耳にしたことがあります。この二つにはどのような違いがあるのでしょうか?
郡司氏: ミクロ経済学は、個別の経済主体や市場を分析する学問です。経済主体とは、経済活動を行う個人や企業のことを指します。ミクロ経済学では、個人や企業の行動や意思決定、さらには特定の市場の動きを分析します。一方、マクロ経済学は、これらの個別データを集計して、経済全体を分析する点が大きく異なります。
KA: 私たちが日常生活の中でマクロ経済の動向を感じられる場面はあるのでしょうか?
郡司氏: 日常生活でマクロ経済を直接実感することはあまり多くありません。ただし、ニュースなどで発表される経済データを通じて、「今の経済状況はこうなっているのか」と感じることはあると思います。
例えば、物価が上がっているというニュースを見れば、それがインフレ率の上昇を意味していると理解できます。また、失業率が高いという報道を見れば、労働市場に問題があることが分かります。このように、マクロ経済の動向は、日常生活の中で間接的に感じることが多いといえるでしょう。
KA: つまり、マクロ経済学は主に政策を考える人たちにとって重要な学問ということですね。
郡司氏: その通りです。マクロ経済学は、政府や中央銀行などの政策担当者が、経済の問題を把握し、適切な政策を立案するために役立つ学問です。
日本経済の課題 実質賃金の低下と物価上昇の狭間で
KA: 次に、マクロ経済学の視点から見える現状の課題点と、それに対する改善策について教えてください。
郡司氏: マクロ経済学では「実質」という言葉をよく使います。これは、物価の変動の影響を取り除いた値を指します。最近よく耳にする「実質賃金」もその一例です。
私たちが手にする賃金は「名目賃金」と呼ばれますが、名目賃金の上昇率からインフレ率を引くと「実質賃金の上昇率」が得られます。つまり、賃金の増加と物価の上昇のどちらが大きいかを示す指標です。
この値がプラスであれば生活が豊かになりますが、マイナスであれば物価の上昇が賃金の増加を上回り、生活が苦しくなります。実際、日本ではここ数年、実質賃金の上昇率がマイナスとなっており、国民生活が厳しい状況にあります。
2023年の速報値では前年比マイナス2.5%でした。これは、前年よりも実質的に2.5%賃金が下がったことを意味します。2024年のデータはまだ出ていませんが、同様にマイナスになる可能性が高いと予想されています。この課題を解決するには、以下の2つの方法があります。
- 名目賃金を上げる
賃金そのものを上昇させる必要があります。具体的には、労使交渉で高い賃上げを求めたり、最低賃金を引き上げたりすることが考えられます。ただし、インフレ率を上回る賃上げが必要です。 - インフレ率を下げる
インフレ率を下げるためには、消費者物価指数(CPI)を低下させる必要があります。2023年11月の速報値では、CPI総合指数の前年比は2.9%の上昇、日銀が目標とする生鮮食品とエネルギーを除いた指数は2.4%の上昇と、いずれも高い水準にあります。
インフレ率を下げるための代表的な手段は金融政策です。例えば、日銀が金利を引き上げることで、民間部門の資金調達を抑制し、景気を冷やして物価を下げる方法があります。また、政府が電気やガス料金への補助金を出すなど、個別の財に対する物価対策を講じることも有効です。
KA: 日本の実質賃金が下がっているとのことでしたが、世界的に見た場合、実質賃金の上昇や下降はどのような状況になっているのでしょうか?
郡司氏: 世界的には実質賃金は上昇傾向にあります。一方で、日本は長年実質賃金が上がらない状況が続いており、ここ数年ではマイナスに落ち込んでいます。したがって、他国と比較して大きく遅れをとっているのが現状です。
インフレ率を下げることは可能か?
KA:現在の日本は世界に比べて物価が低い状況だと思います。そのような状況でインフレ率を下げることは可能なのでしょうか?
郡司氏: 良い質問ですね。確かに日本の物価水準は長年低いままでしたが、この2~3年で上昇傾向にあります。すべての物価を含めた「総合指数」はかなり高い水準にあります。したがって、現在は物価を抑えようとしていますが、日銀が目標とする前年比2%の物価水準に収めることが課題となっています。
ただし、物価を抑えるのは非常に難しい状況です。日本は資源を輸入に頼っているため、資源価格が上昇する中で物価を抑えるのは困難です。物価を下げるためには、需要を抑える必要があります。具体的には、景気を抑制して物の需要を減らし、価格を下げるという方法です。
日銀が注目しているのは、生鮮食品やエネルギーを除いた物価指数です。これらを除いた商品やサービスの価格を前年比2%の上昇率に収めることを目指しています。
KA: 経済はグローバル化が進み、日本独自の経済圏では完結しない状況です。世界との価格差や影響を考慮すると、インフレ率を無理に下げるよりも、インフレ率が上がることに備える方が重要ではないかと感じます。先生はどのようにお考えでしょうか?
郡司氏: その点については、政府が対応すべき課題だと思います。例えば、小麦や資源など個別の財に対して補助金を出したり、税金を下げたりすることが考えられます。
一方で、日銀が行うのは政策金利を操作して経済全体の需要を調整することです。これは間接的な方法であり、具体的な価格対策は政府が担うべきだと考えます。
KA:日銀が政策金利を上げ下げして調整していくこともあると思いますが、簡単に金利を上昇させることは可能なのでしょうか?
郡司氏: 日銀がターゲットとする金利については、上げ下げは可能です。日銀は目標とする金利を厳密にコントロールできます。ただし、その影響が経済全体に広がるかどうかは別問題です。日銀が直接コントロールできるのは、設定した目標金利のみです。
KA: そうすると、経済の状況を考慮しながら金利を調整しなければいけないということですね。
郡司氏: その通りです。日銀はインフレ率という目標を掲げ、その達成のために金利を操作しています。しかし、インフレ率が目標に達したとしても、例えば失業率が高くなるといった副作用が生じる可能性もあります。したがって、慎重な調整が必要です。
KA: 日銀が今後金利を上昇させた場合、どのような影響が考えられるのでしょうか?
郡司氏: 金利が上がると、債券価格が下がるため、資産価格全体が下落する可能性があります。また、株式市場にも影響が及ぶでしょう。私たちの生活に直接影響する点としては、預金金利が上がる一方で、住宅ローンの金利も上昇し、借り入れが難しくなることが挙げられます。
インフレ率2%目標の真相 政策決定の舞台裏
KA: 次に、マクロ経済における今後の展望について教えてください。
郡司氏: 現在、日銀はインフレ率の目標を年率2%と設定し、それに基づいて政策を実行しています。先ほどもお話ししましたが、日銀が参照しているインフレ率は現在2.4%と、目標をやや上回っています。したがって、少し引き締めた金融政策を行えば、目標達成が見えてきている状況です。ただし、2つの問題点があります。
- 2%の目標が日本経済にとって高すぎる可能性
この目標は2013年に設定されました。当時、安倍政権が発足し、黒田東彦氏が日銀総裁に就任したタイミングで掲げられたものです。しかし、仮に2%の目標が達成できたとしても、10年もの歳月がかかっています。この間、賃金の上昇が十分に進まなかったことを考えると、2%という目標が日本の経済力に対して高すぎるのではないかという疑問が生じます。今後、この目標をどう見直すかが重要な課題となるでしょう。 - 金融政策でインフレ率をコントロールできる限界
過去10年間、日銀は2%の目標を掲げながらも達成できない時期が続きました。このことから、金融政策だけで物価水準を短期間で変えるのは難しいのではないかという見方もあります。今後、日銀の政策実行能力がさらに問われることになるでしょう。
2%のインフレ目標はどのように決められたのか?
KA: 2%の目標はどのように決められたのでしょうか?
郡司氏: 良い質問です。2%の目標は、他国のインフレ目標を参考にして設定されたものです。つまり、日本経済の体力や状況を十分に考慮して決められたわけではありません。
では、なぜ他国が2%を目標にしているのかというと、「高すぎず低すぎず」という漠然とした基準で決められています。実際、経済学的にも2%が最適であるという明確な根拠は示されていません。日本も他国を参考にして2%を採用したというのが実情です。
KA: 時代によって物価や価値観も変わると思います。過去に設定された目標が正しいとは限らないので、その都度目標を見直すべきではないでしょうか?
郡司氏: おっしゃる通りです。経済の状況や体力を考慮して、2%という目標が適切かどうかを検討し、その都度見直すことは重要だと思います。ただし、どの水準が適切なのかを測る方法がまだ確立されていないのが現状です。したがって、現時点では他国を参考にして2%を目標にしているに過ぎません。
今後、より良い方法が確立されれば、国ごとに適切な目標を設定できるようになるかもしれませんが、まだ発展途上の部分が大きいと言えるでしょう。
KA: もしインフレ率が上昇していく場合、個人としてできることは、どのようなことがあるのでしょうか?
郡司氏: インフレ率が上昇した場合、個人でできることは限られています。インフレは経済全体の問題であり、個人の力で直接的に解決することは難しいからです。
ただし、インフレに対応するためにできることとしては、以下のような行動が考えられます。
- 資産運用:インフレ率に近い運用益を目指して資産を運用すること。例えば、株式やETFなどのリスク資産を活用する方法があります。
- 賃上げの要求:労働組合に加入し、賃上げを求める活動を行うことも1つの手段です。
インフレ時の投資先の選択肢
KA: 今後インフレ率が上昇していく場合、投資先としてはどのようなものが良いのでしょうか?
郡司氏: もし、インフレ率が安定して2%を超えるような時代になれば、それに見合う利子率の商品が出てくるはずです。例えば、かつて日本では定期預金だけでもインフレ率を上回る金利が得られた時期がありました。しかし、現在は日銀が金利を低く抑えているため、安定運用できる商品がほとんどありません。
したがって、現状ではリスクを取って株式やETFなどで運用するしかないかもしれません。ただし、日銀が金利を引き上げ、2%を超えるような金融商品が出てくれば、選択肢は広がるでしょう。
KA: ただ、現在、円安が進んでいます。このような状況で金利を維持することは可能なのでしょうか?また、現状を維持することで悪化する可能性はないのでしょうか?
郡司氏: 現在の円安水準は、日銀が低金利政策を続けていることが大きな要因とされています。日銀が金利を引き上げれば、円安が改善する可能性があります。
金利水準を経済力に見合った適切なレベルに設定することで、金融商品の金利や為替の水準も安定してくるでしょう。ただし、金利を引き上げることで景気に与える影響も考慮する必要があります。
理論を実践に マクロ経済学の生活への活かし方
KA: では、マクロ経済学で学んだことを、どのように私たちの日常生活で活かせるのかについて教えてください。
郡司氏: マクロ経済学は、学んだからといって直接的に生活に活かすのが難しい学問です。例えば、総理大臣や日銀総裁のような立場であれば、学んだ知識を政策に直接反映させることができますが、一般の人々にとっては、学んだことをすぐに実行に移す機会は少ないでしょう。したがって、マクロ経済学を「間接的に」活かす形になります。
選挙での活用
例えば、選挙の際に政党が発表するマニフェストを評価する際に役立ちます。マクロ経済学の視点から、その政策が経済にどのような影響を与えるのかを考え、効果が期待できるかどうかを判断することができます。今年は参議院選挙も予定されていますが、そのような場面でマクロ経済学の知識を活用して、より良い選択をすることが可能です。
住宅ローンの選択
住宅ローンを組む際にも、マクロ経済学の知識が役立つかもしれません。例えば、変動金利と固定金利のどちらを選ぶべきかを判断する際に、日銀の金融政策を考慮することができます。日銀が金利を引き上げる可能性が高いと予想される場合、固定金利を選ぶことで将来的な金利上昇のリスクを回避できるかもしれません。一方で、金利が低い状況が続くと見込まれる場合は、変動金利を選ぶのも一つの選択肢です。
このように、住宅ローンの金利方式を選ぶ際には、安易に低金利の変動型を選ぶのではなく、日銀の動向を注視しながら慎重に判断することが重要です。
投資における活用
さらに、個人投資家として資産運用を行う際にも、マクロ経済学の知識が役立つ場面があります。例えば、株価や為替レートがどのように変動するかを予測する際に、経済指標や金融政策の動向を参考にすることができます。
ただし、金融市場はニュースが出るとすぐに価格が変動するため、個人が市場よりも早く情報を得て取引を行うことは現実的ではありません。
したがって、金融市場に「勝つ」ことを目指すのではなく、市場がニュースに過剰反応しているのか、あるいは反応が鈍いのかを見極めることで、利益を得るチャンスを見つけることができるかもしれません。
マクロ経済学の間接的な効果
このように、マクロ経済学は直接的に生活に影響を与えるわけではありませんが、知識を活用することで、生活に大きな影響を与えるマクロ経済の変動に対応する力を養うことができます。選挙での判断、住宅ローンの選択、資産運用など、さまざまな場面で間接的に役立つ学問と言えるでしょう。
経済学への入り口 ミクロからマクロへの学びの道筋
KA: そもそもなのですが、先生がマクロ経済の研究をしようと思った理由は何でしょうか?
郡司氏: マクロ経済は、個人レベルでは政策を直接実行することが難しい分野ですが、経済全体がダイナミックに動いていく様子を調べられる点に魅力を感じました。私が所属していたゼミでは、ミクロ経済学とマクロ経済学の両方を学んでいましたが、ミクロ経済学を学んでいた時よりも、マクロ経済学を学んだ時にそのダイナミックさに面白みを感じました。政策が実施され、それによって経済全体がどのように動くのかを考えることが非常に興味深く、研究を始めるきっかけになっています。
ミクロ経済とマクロ経済の関係性
KA: ミクロ経済学を学んだとしても、マクロ経済の視点がないと、ミクロ経済を実質的に理解することは難しいと思います。いかがでしょうか?
郡司氏: おっしゃる通りです。ミクロ経済学を考える際にも、経済全体がどのように動くのかを考慮する必要があります。ミクロ経済学では、他の要因を固定して個別の経済主体(消費者や企業)がどのように行動するかを分析しますが、マクロ経済が動いた場合に何が起こるのかを考えることも重要です。
つまり、ミクロ経済学を学ぶ際にも、マクロ経済の視点を一部取り入れることで、より深い理解が得られるということです。
KA: 先生は、マクロ経済とミクロ経済のどちらから学ぶのが良いと思いますか?
郡司氏: どちらかと言えば、まずはミクロ経済学から学ぶのが良いと思います。ミクロ経済学は、マクロ経済学を学ぶ際にも必要になる基礎的な考え方を含んでいます。
個人や企業がどのようなメカニズムで行動するのかを理解した上で、マクロ経済学を学ぶと、経済全体の動きがより分かりやすくなるでしょう。
学びの順序とその理由
KA: より身近なものから学び、その仕組みを理解するためにマクロ経済学を学ぶということですね。
郡司氏: そうですね。個別の市場を集計していくとマクロ経済になります。ですから、まずは個別の市場や経済主体について学び、その次にそれらを集計した全体像を学ぶという順番が良いでしょう。
KA: 先生はマクロ経済を学んで、何か得をしたとか、考え方が変わったということはありますか?
郡司氏: マクロ経済学で特に面白みと感じたのは、ミクロで起こる行動が、必ずしもマクロで同じ方向に動くとは限らないという点です。
例えば、みんなが貯蓄をしようとして節約をすると、個人レベルでは最適な行動になります。しかし、マクロの視点で見ると、みんなが節約をすることで消費が減り、結果的に賃金も減少してしまい、貯蓄ができなくなるという現象が起こります。
このように、マクロで考えると、みんなが同じ行動を取ると逆効果になる場合もあります。また、個別に最適な行動を取ることが、必ずしも全体にとって良い結果をもたらすとは限らないという点に気付かされました。これがマクロ経済学の面白いところです。
KA: なるほど。それは何にでも当てはまることですね。木を見て森を見ずというように、個別のことばかり見ていると方向性を間違えてしまうと思います。マクロ経済学に興味はあるのですが、言葉だけを見ると難しそうに感じてしまいます。
郡司氏: そうですね。確かにマクロ経済学は難しそうに見えるかもしれませんが、身近なところから疑問を持つことで、学びやすくなると思います。
経済学を学ぶ最初のステップ
KA: 経済学を学んだことのない人が最初に学ぶとしたら、どのようなアプローチが良いのでしょうか?
郡司氏: ミクロ経済学から入るのが良いと思います。例えば、「リンゴを食べるかミカンを食べるか」といった身近な選択から始まり、それが徐々に市場全体の話に広がっていきます。そして、市場全体で何が起こるのか、取引をどのようにすれば効率的なのかを学んでいきます。このように、身近な疑問からスタートし、徐々に広い視点を持つことで、経済学への理解が深まると思います。
KA: 先生の話を聞いていると、経済学は学問としてだけでなく、生活に活かせる知恵を学ぶような学問でもあると思えてきました。
郡司氏: その通りです。例えば、ミクロ経済学では、金利が上がった時にどのような行動を取るべきかを考えます。金利が上がれば貯蓄を増やそうとする人もいれば、資産が増えた分を使おうとする人もいます。
このように、個人の行動は一律ではなく、性格や状況によって異なります。ミクロ経済学では、人が合理的に行動する場合にどのような選択をするのかを分析します。これは、性格分析に近い部分もあり、心理学に似た面白さがあります。
KA: そう考えると、経済学は学問としてとっつきにくいものではなく、実際は結構取り組みやすい学問なのかもしれませんね。
郡司氏: そうですね。心理学に似ている部分もありますが、心理学より少し硬い学問です。ただ、人や企業の行動が「どのような仕組み」で動いているのかを学ぶためのものだと考えると、意外と親しみやすいのかもしれません。