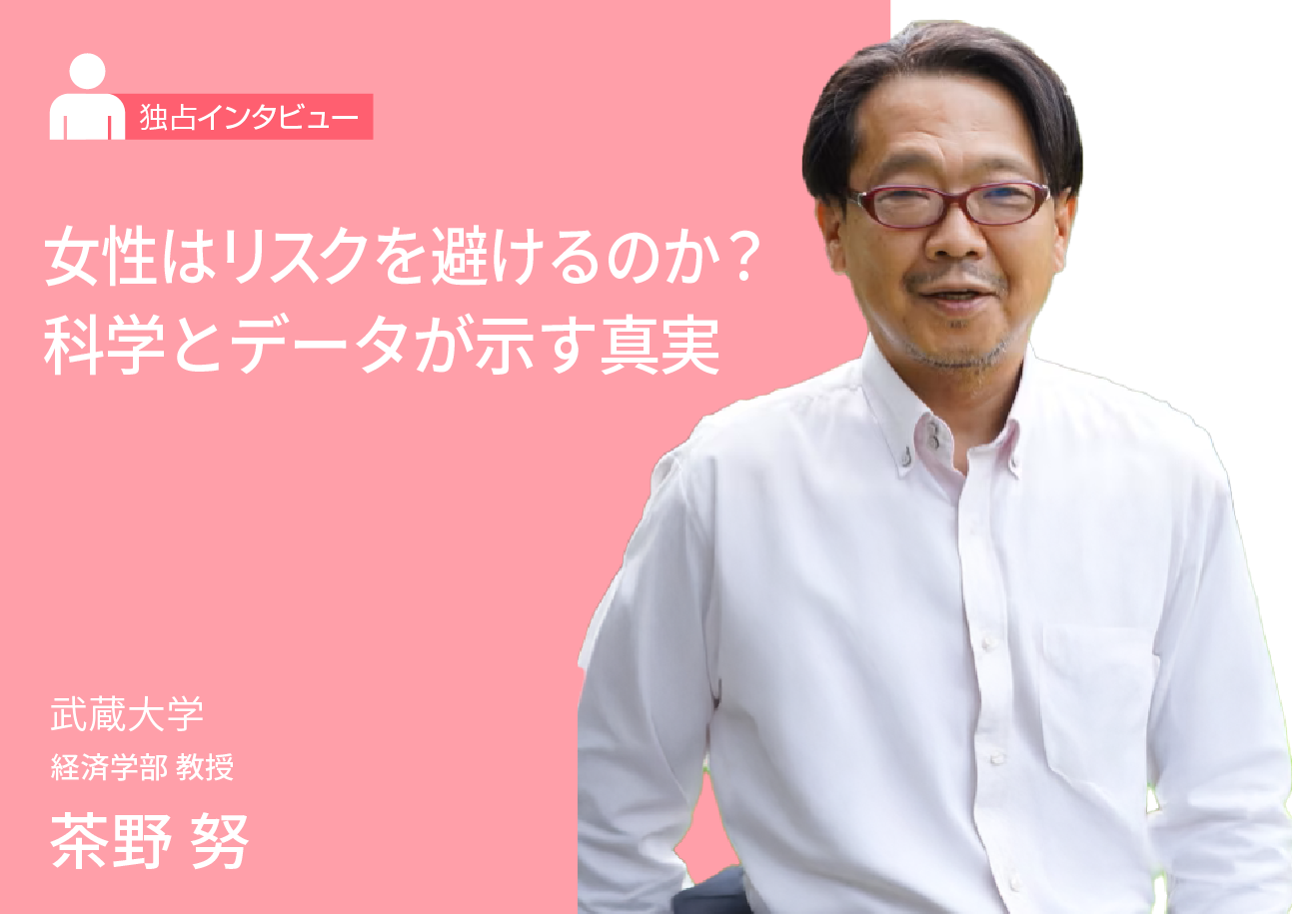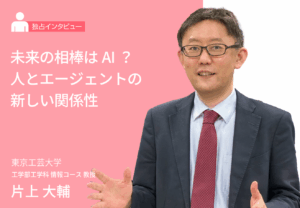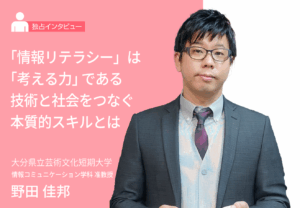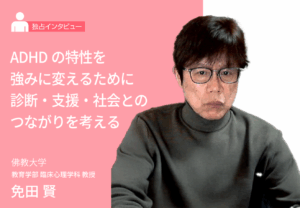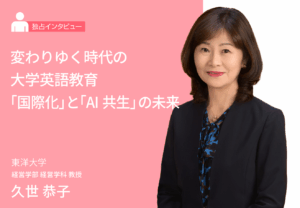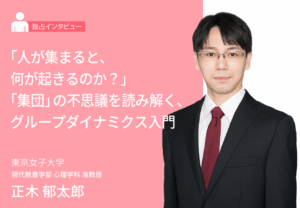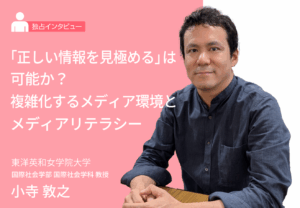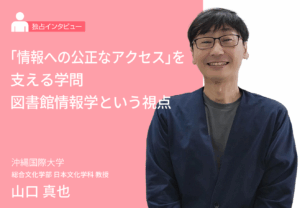「女性は男性よりも慎重だ」というイメージは、多くの人に共有されています。しかし、それは本当に科学的な根拠に基づいているのでしょうか?
社会学、心理学、経済学など、さまざまな分野の研究がこの問いに挑んできましたが、結果は一様ではありません。例えば、女性はリスクを避ける傾向が見られる一方で、現実の投資行動ではその差はさほどでもない(統計的に有意ではない)との実験データもあります。
この記事ではリスク回避行動における男女差について、武蔵大学の茶野努教授にお話を伺いました。神経伝達物質や遺伝要因といった脳科学の観点も交えながら、性別による意思決定の違いとその背景を探ります。
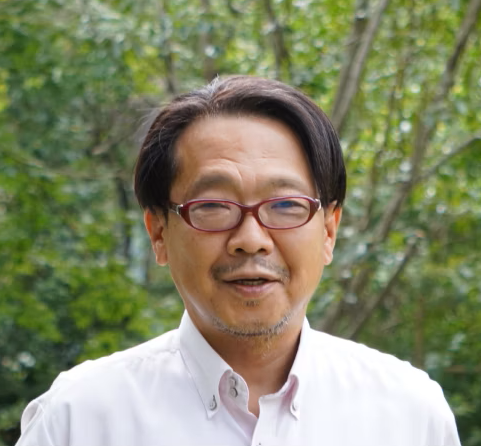
茶野 努
武蔵大学 経済学部 教授
【biography】
〇学歴
1987/03 大阪大学 経済学部卒業
1999/03 大阪大学大学院 国際公共政策科博士課程修了 博士(国際公共政策)
〇職歴
1987/04 住友生命保険相互会社(入社)
1990/04 (株)住友生命総合研究所(出向)
1999/04〜2001/03 九州大学 経済学部 客員助教授
2008/09 ~ 武蔵大学 経済学部 教授
リスク回避研究の3つの視点
ナレッジアート(以下KA):はじめに、リスク回避における男女の違いについて教えてください。
茶野氏:まず、既存研究のアプローチ方法として、以下の3つに大別されます。
- 社会学的なアプローチ
- 心理学的なアプローチ
- 経済学的なアプローチ
既存の社会学や心理学の研究では、リスク回避に関して男女差があるとし、女性の方がリスク回避的であるという仮説を支持する研究が多いです。女性の方がアルコールや薬物の依存になりにくく、核戦争や産業汚染、汚染廃棄物に対するアレルギーのようなものも強いことからも、このことは容易に想像できるでしょう。
また、違法薬物や犯罪行為に手を染める女性は男性よりも少ない傾向があるため、社会学的、心理学的な研究では、女性の方がリスクを避けるという結論が多くなっています。
一方で、経済学的なアプローチでは、投資をした時や保険に加入した時の行動を分析対象とするため、より狭い範囲で女性のリスク回避的な傾向を捉えようとしています。
経済学的な視点では、女性の方がリスク回避的であるという結果にはならない場合があります。
実験から見えるリスク回避の男女差
KA:経済学的な視点では、男女のリスク回避の違いをどのように調べているのでしょうか?
茶野氏:男女のリスク回避の違いを調べる研究には、大きく分けて2つのアプローチがあります。1つは「実験経済学」と呼ばれる分野で行われる実験的な方法、もう一つは実際の行動データを分析するフィールド研究です。
実験経済学にも、「抽象的なギャンブル実験」と、投資や保険加入のように、ある環境的文脈下でのリスキーな意思決定に関する実験(「環境的文脈実験」)の二つのアプローチがあります。
抽象的な実験の例には、以下のようなものがあります。
選択肢1:赤玉10個と白玉10個が入った壺から1つ玉を取り出し、その色を当てると1000円がもらえる。
選択肢2:赤玉と白玉が合計20個入った壺から1つ玉を取り出し、その色を当てると1200円がもらえる。ただし、赤玉と白玉の具体的な数は不明。
この実験では、条件2は条件1よりもリスクが高そうにみえる選択肢です。このような抽象的な多くの実験で、女性は男性よりもリスクを避ける傾向があるという結果が得られています。
KA:具体的にはどのような違いが見られるのでしょうか?
茶野氏:環境的文脈実験においては、例えば、10万円を渡して、それを債券(リスクが低い)、株式(リスクが高い)、またはそれらが混ざった投資商品に振り分ける実験を行います。このような実験では、女性のリスク回避的な傾向が弱まることがわかっています。
このような実験では、抽象的なギャンブルのような設定ではなく、より現実的な金銭感覚を伴う判断を求めます。その結果、女性がリスクを避ける傾向が、抽象的な実験ほど顕著ではなくなるのです。
一方、フィールド研究では、実際の保険加入や株式投資の個票データを分析します。興味深いことに、抽象的な実験では女性がリスク回避的であるという結果が多いのに対し、実際の投資行動や保険加入行動を分析すると、必ずしも同じ傾向が見られないことがあります。
私が生命保険文化センターのデータを用いて行った研究では、年齢や所得といった要素をコントロールした上で男女の保険加入状況を比較しました。その結果、女性が男性に比べてより高い保険料を支払っているという事実はなく、「女性の方がリスク回避的で保険に積極的に加入する」という仮説は支持されませんでした。
つまり、これまでの研究を総合すると、「女性は男性よりもリスク回避的である」と断定することは難しいと言えます。抽象的なギャンブルの実験では女性がリスクを避ける傾向が強く見られる一方で、実際の投資や保険加入の場面ではその傾向が弱まる、あるいは見られないこともあります。
この違いは、状況や文脈によってリスクに対する態度が変わることを示唆しています。例えば、知識や資産の額、結婚状況、家族構成といった要因がリスク選好に影響を与える可能性があります。しかし、こうした要素を十分に考慮した研究はまだ少なく、さらなる調査が必要です。
リスク回避傾向と社会的認識
KA:なぜ女性の方がリスク回避的な傾向があると考えられるのか、その要因について教えてください。
茶野氏:女性がリスク回避的であると考えられる理由については、いくつかの仮説がありますが、必ずしも明確な結論が出ているわけではありません。
女性は「優しい」「おとなしい」というイメージが社会的に広く共有されています。このようなステレオタイプの見方が、女性がリスクを避ける傾向があるという認識を生む可能性があります。実際には、こうしたイメージが必ずしも行動に直結するわけではありません。
また、心理学的な研究では、女性が極端な犯罪行為や危険な行動に関与する割合が男性よりも低いことが指摘されています。したがって、女性がリスク回避的であるという印象を受けやすいのかもしれません。ただし、これがすべての状況に当てはまるわけではありません。
投資行動や保険加入行動においては、男女間で大きな差が見られない場合も多々あります。多くの人は合理的に考えて行動するため、性別による違いが顕著に現れないこともあります。
例えば、「女性はリスクを避けるために株式投資をしない」「保険に多く加入する」というイメージがあるかもしれませんが、統計的な分析では必ずしもそのような傾向は確認されていません。
男女差があると考えられる背景には、社会的・文化的な性別による役割分担が影響している可能性があります。たとえば、男性は外で働いて、女性が家を守るといったことが、女性にリスク回避的なものを求めるのかもしれません。女性がリスク回避的であるという認識は、社会的なイメージや一部の心理学的要因に基づくものであり、すべての状況に当てはまるわけではありません。
KA:投資行動における失敗で男女間に差はあるのでしょうか。
茶野氏:リスク回避やリスク選好に関して、男女間でいくつかの傾向が見られますが、統計的に有意な差があるとは言い切れません。
男性は、リスクの高い投資(例:株式や為替取引)に積極的に取り組む傾向があり、一獲千金を狙うような行動が見られます。大きな利益を得る可能性がある反面、失敗するリスクも高まります。
ただし、男女間でリスク選好やリスク回避に違いがあるように見える場合でも、統計的に有意な差が確認されることは少ないです。多くのケースでは、個人の知識や経験、経済状況、文化的背景が意思決定に大きく影響を与えています。
男女を問わず、リスクに対する行動は合理的な判断に基づくことが多く、性別による違いよりも、個々の状況や環境が失敗例に影響を与えると考えられます。
脳科学から見るリスク選好の仕組み
KA:では次に、遺伝とリスク回避の関連性について教えてください。
茶野氏:脳内の神経伝達物質としては、主に以下の3つが関与しています。
- ドーパミン
喜びや快楽の情報を伝える役割を持ち、人が積極的に行動する際に重要な役割を果たします。ドーパミンが多く分泌されると、積極的な意思決定やリスクを取る行動が促進される傾向があります。 - ノルアドレナリン
恐怖や驚きといった感情を伝える神経伝達物質です。危険を察知し、慎重な行動を取る際に重要な役割を果たします。 - セロトニン
ドーパミンやノルアドレナリンの働きを調整し、精神を安定させる役割を担います。セロトニンが不足すると、情緒が不安定になり、不安やうつ、パニック障害などを引き起こす可能性があります。また、セロトニンの低下は女性ホルモンの分泌減少と関連しており、更年期の女性が情緒不安定になる一因とされています。
ドーパミンは、人が積極的に行動する際に重要な役割を果たします。例えば、ドーパミンの分泌が活発な人は、投資や新しい挑戦といったリスクを伴う行動を取りやすい傾向があります。一方で、セロトニンが不足して情緒が不安定になると、不安を感じやすくなり、安定志向が強まることが分かっています。
また、ドーパミンの受容体には、D1、D2、D3、D4、D5の受容体があり、これらはそれぞれ異なる役割を持ち、ドーパミンが結合することで脳内に電気的な反応を引き起こします。D5受容体は興奮性を担う受容体で、D1受容体よりも10倍ほどドーパミンとの親和性が高いとされています。
研究によると、D5受容体の遺伝子に異常がある場合、リスクを取る行動や投資の積極性が高まる可能性が示唆されています。この分野の研究は2000年代に入って急速に進められており、遺伝的要因がリスク回避やリスク選好にどのように影響を与えるかが注目されています。
遺伝子が示すリスク許容度の個人差
このD5受容体遺伝子には、DRD4 7Rという変異型が存在します。この変異型は「冒険家遺伝子」と呼ばれており、この遺伝子を持つ人は、積極性や冒険心が強い傾向があると言われています。例えば、歴史的に見ても、未知の土地を目指して航海に出た探検家たちのような行動が、この遺伝子の影響を受けている可能性があると考えられています。
この遺伝子多型を持つ人は、ドーパミンの働きに対する感受性が低いため、通常よりも強い刺激を求める傾向があります。その結果、リスクを伴う行動を取ることで、快感や満足感を得ようとするのです。
他にも、セロトニンの働きを弱めるセロトニントランスポーター遺伝子も存在しています。セロトニントランスポーター遺伝子には、SS型とLL型という2つの主要な型があります。
- SS型(短い型)
この型は「心配性の遺伝子」とも呼ばれ、セロトニンの働きが弱くなるため、不安や悲観的な傾向が強くなるとされています。SS型を持つ人は、リスクを避ける行動を取りやすい傾向があります。 - LL型(長い型)
一方で、LL型を持つ人はセロトニンの働きが強く、不安を感じにくい傾向があります。そのため、リスクを取る行動に対して積極的である可能性があります。
セロトニントランスポーター遺伝子の型の分布には、人種によって違いがあります。
アジア人(日本人を含む)はSS型を持つ割合が高いとされ、一般的にリスク回避的な傾向が強いと考えられます。一方で、アフリカ人およびアメリカ人はLL型を持つ割合が高い傾向があり、リスクを取る行動に対して積極的である可能性があります。これらの違いは、文化的な行動や経済活動(例えば株式投資)にも影響を与える可能性があります。
DRD4 7R(冒険家遺伝子)を持つ人は、リスクを取る傾向が約25%高いとされています。例えば、ギャンブルや投資などのリスクを伴う行動に積極的であることが確認されています。
セロトニントランスポーター遺伝子のSS型を持つ人は、リスク回避的な傾向が約28%高いとされています。不安や悲観的な感情が行動に影響を与えるため、リスクを避ける選択をすることが多いとされています。
これらの結果は、ドーパミンとセロトニンのバランスがリスク行動に大きな影響を与えることを示唆しています。ドーパミンが多い人はリスクを取る行動に積極的であり、セロトニンが少ない人は不安を感じやすく、リスク回避的になる傾向があります。
また、男女間でのドーパミンやセロトニンの働きの違いについては、まだ明確な結論は出ていません。ただし、いくつかの研究では、男性の方がドーパミンの働きが強く、リスクを取る傾向がある可能性が示唆されています。
例えば、東京大学の研究では、線虫を用いた実験で、オスの線虫がメスと結合するために活発に運動する際、ドーパミンの分泌が多いことが確認されています。この結果から、人間でも男性の方がドーパミンの働きが強く出る可能性があることが推論できます。
ただし、これらの研究はまだ初期段階であり、男女間のリスク行動の違いが遺伝的要因によるものかどうかを断定するには、さらなる研究が必要です。
投資行動における時間軸の重要性
KA:ドーパミンの多い人は積極的にリスクをとる傾向があるとおっしゃっていましたが、例えば「長期投資」においてもその傾向はあるのでしょうか?
茶野氏:良い質問ですね。これまでお話しした実験は、主に短期的な投資行動を分析するものでした。短期的な投資では、ドーパミンが多い人は、投資を宝くじやギャンブルのように捉え、高揚感を得るために行動している可能性があります。
一方で、長期的な投資については、まだ十分なデータがありません。長期投資では、短期的な高揚感ではなく、合理的な判断がより重要になるため、また違った結果になる可能性があります。この点については、統計データや実験を通じて検証する必要があります。私自身もこの質問を受けて初めて考えた点で、今後の研究課題として非常に興味深いテーマだと思います。
KA:では、女性と男性それぞれに適した資産運用方法について教えてください。
茶野氏:結論から言うと、男女差による「適した資産運用方法」というものには、現時点では大きな違いはないと考えています。
遺伝子研究が進むにつれて、男性の方がリスクを取る傾向があるという可能性が示されるかもしれませんが、現時点ではその根拠は十分ではありません。むしろ、資産運用に影響を与えるのは、性別よりも以下のような要素です。
- 投資や金融に関する知識
- 資産の額
- 結婚状況や家族構成
- 住宅所有の状況
これらの要素を考慮しながら資産運用を行うことが重要です。例えば、金融知識を深め、専門家のアドバイスを受けながら、自分の状況に合った投資を行うことが大切になるでしょう。
また、男女の違いよりも、ライフサイクルに応じた資産運用を考える必要があります。例えば、結婚前はある程度リスクを取ることができるかもしれませんが、結婚後はリスクを抑える必要が出てくる場合があります。多くの研究でも、結婚後や子供ができた後は、リスクを取る余裕がなくなる傾向があることが示されています。
したがって、若い頃には株式投資などを通じて積極的に資産を増やし、結婚後や家族が増えた後は、保守的な投資に切り替えて老後資金を貯める、といった戦略が有効かもしれません。このように、ライフステージに応じて資産運用の方針を変えることが重要です。
KA:では、最後にどのような専門家のアドバイスを聞くのが良いのでしょうか?
茶野氏:そうですね。中立的な立場の専門家に相談するのが良いと思います。例えば、特定の金融機関の営業担当者は、自社の商品を売り込むことが目的の場合があります。したがって、ライフプランナーやファイナンシャルプランナーといった、顧客の立場に立ってアドバイスをしてくれる専門家に相談するのが良いでしょう。
また、投資で成功している先輩や知人の話を聞くのも参考になります。様々な人の意見を聞きながら、自分の知識を深めていくことが重要です。株式投資などは知識がないと難しいため、まずは基本的な知識を身につけることが必要になるでしょう。
さらに、現在の日本は世界的にみて超低金利の状況にありますので、国内だけでなく海外も含めた国際分散投資を検討する必要があります。株や債券だけでなく、金などの資産にも注目することが重要です。資産運用では、リスクを分散させることが基本ですので、様々な選択肢を検討しながらバランスよく投資を行うことが求められます。
まとめ
リスク回避における男女差については、社会学、心理学、経済学の視点から多角的に研究されています。一般的に、女性は男性よりもリスクを避ける傾向があるとされますが、その傾向は状況や文脈によって異なります。
抽象的な実験では女性がリスク回避的である結果が多く見られる一方で、実際の投資や保険加入行動では男女差が認められない場合もあります。また、脳科学の視点では、ドーパミンやセロトニンといった神経伝達物質がリスク選好に関与しており、これらの働きが個人のリスクテイクあるいはリスク回避行動に影響を与えることが分かってきています。しかし、男女間の違いについては、いまのところ明確な結論が出ていません。