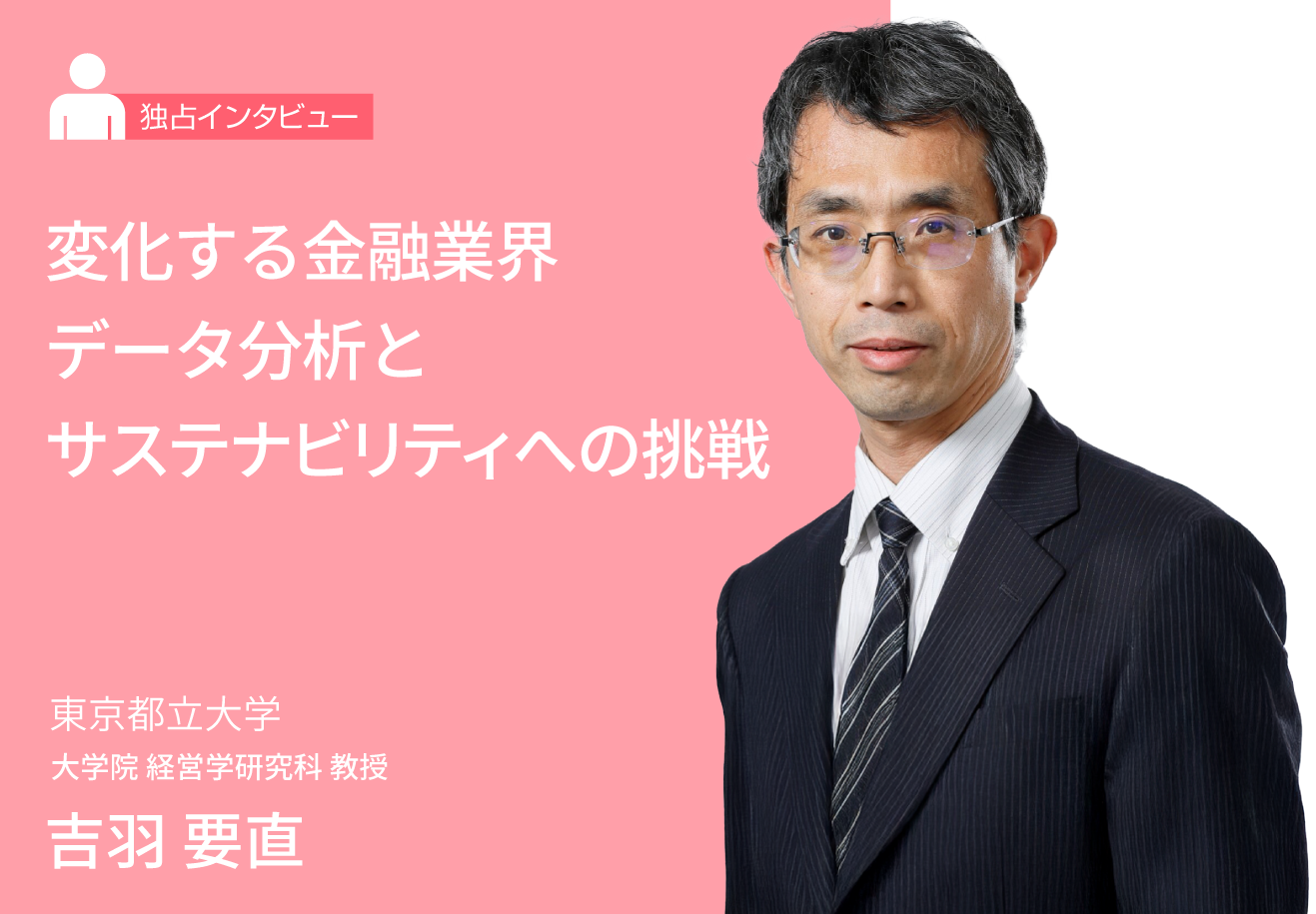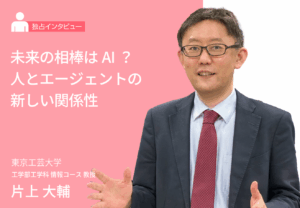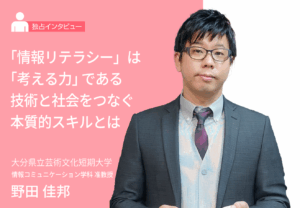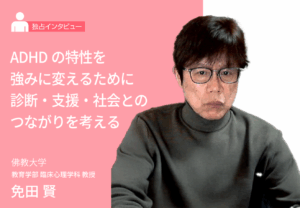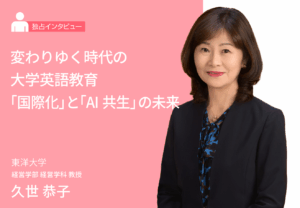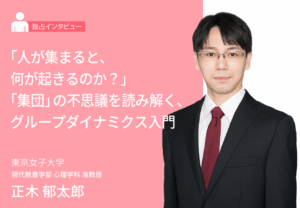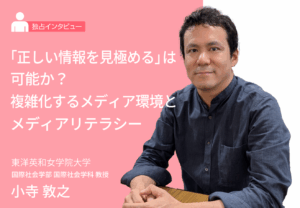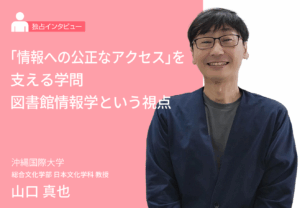新NISA等の新制度の施行により、より多くの人々が気軽に投資の世界へ足を踏み入れることができる時代へと突入しています。そして近年、金融業界においても、大きな変化が生じつつあります。
金融業界の基礎から今後の展望まで、吉羽先生にお話を伺いました。

吉羽 要直
東京都立大学 大学院 経営学研究科 教授
【biography】
1993年東京大学大学院工学系研究科修士課程修了後、日本銀行に入行。調査統計局、金融研究所、金融機構局企画役、金融研究所ファイナンス研究グループ長などを経て、2021年東京都立大学大学院経営学研究科(ファイナンスプログラム)教授。2006年から統計数理研究所リスク解析戦略研究センターで客員教員(現在に至る)。2011年に総合研究大学院大学で博士(統計科学)を取得。所属学会は、日本統計学会、日本ファイナンス学会、日本金融・証券計量・工学学会。
応用数学の知識を活かした日本銀行でのキャリア
ナレッジアート(以下KA):現在は東京都立大学にて経営学教授を勤められている吉羽先生ですが、元々は日本銀行に勤められていたと伺っております。先生のご経歴を伺ってもよろしいでしょうか。
吉羽氏:私は学生時代、東京大学の理科一類に所属していました。理科一類は入学時点では学部が決まっておらず、2年生の後半で学部を選ぶことになります。その際、もともと金融業界に興味があったことから、経済学部を選ぶことを考えていました。
しかし、学んでいく中で、「数学をさらに深めた方が良いのではないか」と感じ、応用数学の分野で修士課程まで進むことにしました。
複数の金融機関も検討しましたが、広範な調査や分析を行っている日本銀行であれば、応用数学の知識が活かせるのではないかと考え、最終的に日本銀行を選びました。
市場のストレス状態におけるリスク管理研究
KA:では、吉羽先生が現在研究している分野について詳しく教えて頂けますか。
吉羽氏: 簡単にいうと、リスク管理に関する研究をしています。主なテーマは、※1ポートフォリオを組んだ際のリスクをどのように把握するかです。
株式やその他の資産といった各要素がリスクファクターとして確率的に変動する中で、それらを統合してポートフォリオ全体のリスクを評価する際に、特に市場の状況が悪化した「ストレス状態」では、資産価格も同様に下落する傾向にあります。このような状況を正確に捉えるためのモデリングを中心に研究を進めています。具体的には、接合関数(コピュラ)を活用し、特に※2裾(テール)での依存性が強くなるモデルに焦点を当てています。
一般的に、多資産変動のリスク管理には多変量正規分布が使われることが多く、接合関数で言えば「正規接合関数」がその代表例です。しかし、この手法では資産変動間の依存性、特に市場価格が下落した際の依存性が弱くなるという問題があります。実際の市場では、むしろ下落するときほど依存性が強くなります。この点を考慮しないと、リスクを過小評価してしまう恐れがあります。
そのため、私は市場価格が下落時に強く依存し合う状況を適切に捉えられるモデルを研究しています。接合関数を用いて、裾での依存性を強調するようなアプローチを開発することで、実際の市場状況により近いリスク評価を実現することを目指しています。
※1複数の資産を組み合わせて構成された投資の集合体
例:
| 資産クラス | 割合 | 特徴 |
| 株式 | 50% | 高リスク・高リターン |
| 債券 | 30% | 安定した収益、低リスク |
| 現金 | 10% | 流動性が高く、緊急時に対応可能 |
| コモディティ | 10% | インフレに対するヘッジ手段 |
※2統計分布の端の部分、特に確率密度関数や分布関数の極端な値
リーマンショック以降のリスク管理
KA:昔と現在を比較して、リスク管理にはどのような変化がありましたか。
吉羽氏:2008年から2009年のリーマンショック以前には、資産価格の依存関係を多変量正規分布に基づく「正規接合関数」を用いて分析するのが一般的でした。例えば、証券化商品(住宅ローン担保証券など)の評価にもこの手法が広く使われていました。
しかし、このアプローチでは資産価格が下落する際の依存性が弱く評価されてしまうため、特にストレスがかかる市場環境では、実際のリスクが過小評価される傾向があったのです。
具体例として、証券化商品におけるシニアトランシェ(最も安全とされる部分)の評価があります。
当時は、シニアトランシェは多変量正規分布に基づく「正規接合関数」に基づいた評価では多くの住宅ローンが同時にデフォルトする可能性は極めて低く、デフォルト損失はほとんど生じないと評価されて、簡単に作られていました。しかし、リーマンショックのような金融危機が発生すると、資産価格が一斉に下落し、ポートフォリオ全体が大きな損失を被りました。その結果、本来なら安全とされるシニアトランシェにも損失が発生してしまうという状況が生まれたのです。この問題は大きな批判を招きました。
こうした背景を受けて、金融危機以降、リスク管理のアプローチにはいくつかの変化が見られるようになりました。私のように、極端な市場環境での資産価格の依存性を正確に捉えようとする研究に取り組む人もいれば、過去のデータに頼る従来の手法では不十分だと考え、より「未来を見据えた」視点が重視する人も出てきました。具体的には、過去のデータ分析に加えて、仮想的なシナリオを構築して評価を行う「シナリオ分析」や「フォワードルッキング(前向き思考)」の手法が普及しました。
リーマンショック前後で、リスク管理は大きく変化したと言えるでしょう。
金融業界で求められるスキルセット
KA:金融業界ではどのような人材が求められているのでしょうか。
吉羽氏:最近では、金融業界に限らず、多くの業界でデータサイエンスのスキルが非常に重視されています。データ分析、例えば深層学習を用いて把握した過去の行動パターンなどをもとに、マーケティングや具体的な戦略を立てるといった能力のニーズはさまざまな業界で高まっています。
KA:マーケティングのスキルが重要になってきているということですが、金融の知識と比べた際、どちらを重視すべきでしょうか。
吉羽氏:どちらも重要ですが、まずは基本的な経済学やファイナンスの知識をしっかりと身につけることが大切だと思います。特にミクロ経済学やマクロ経済学、金融の入門といった基礎的な内容は、金融業界で働く上で欠かせません。その上で、データサイエンスやマーケティングのスキルやテクニックを身につけるとさらに強みになるのではないでしょうか。
KA:それらの知識を身につけるためには、具体的にどのように学ぶのが効果的でしょうか。
吉羽氏:金融に関しては、大学で使われるような基本的な教科書を読むのが良いでしょう。また、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格勉強も役立ちます。資産運用に興味があるなら、証券アナリストの勉強をするのもおすすめです。また、実際の市場で取引を体験してみるのもよいと思います。ただし、まずは基礎から始めることが大切です。データ分析力に関しては、関連する本を読んで、具体例を応用しながら分析を試してみるとよいと思います。実践を通して学ぶことで、スキルが身につきやすくなります。
金融業界におけるスキルの汎用性と人材流出
KA:現在の金融業界における課題は何ですか。
吉羽氏:一つには、人材の確保が挙げられます。特にデータサイエンスのスキルを持つ人材の需要に関しては、どの業界でも高まりを見せており、以前よりも確保が難しくなっています。また、せっかく人材を集めても、離職率が比較的高いという別の問題もあります。以前は、金融業界で身につけたスキルが他の業界ではあまり使われないということもあり、全く異なる分野に転職するケースは少なく、独立する場合でも、金融関連の仕事を続けることが一般的でした。しかし、現在では全く異なる業界に移ることも珍しくありません。金融業界でデータサイエンスや深層学習といった汎用性の高いスキルを学んだ人材が、全く異なる業界に転職して活躍する例も増えています。例えば、アナリストのスキルを持つ人が、同様の分析手法を活用しながら異業種で成功するケースもあります。金融業界が相対的に魅力を失っている側面があると言えるかもしれません。このような動きが今後も続くかは不明ですが、現状としてはこうしたトレンドが見られます。
KA:個人的には、新NISAなど、投資関連の分野への関心は高まっているように感じるのですが、金融業界全体としては違った状況があるのですね。
吉羽氏: ええ。確かに、投資に関しては関心が高まっているように思いますが、それが金融業界への就職意欲に直結しているとは言えません。「貯蓄より投資」という考え方が啓蒙されつつありますが、それ以外の金融ジャンル、特に保険や伝統的な金融サービスへの関心は以前ほど高くないように感じます。
また、※3サステナブルファイナンスも大きな課題です。我々は気候変動対策の一環として定められた※4ネットゼロを、2050年までに達成しなければなりません。融資先企業が脱炭素化を進めるためには、CO2排出を抑える設備への移行が必要であり、金融機関も、こうした取り組みを支援する必要があります。また、投資においても、脱炭素の取り組みを進めている企業により投資することが求められています。金融機関自身は直接のCO2排出量が少ないものの、取引先企業が排出する分(スコープ3)もカウントされてしまうため、融資先企業の環境改善に取り組む必要があります。
※3環境、社会、ガバナンス(ESG)の観点を考慮しながら行われる資金調達や投資活動
※4温室効果ガス(特にCO₂)の排出量を実質的にゼロにすること
金融業界の未来:変わりゆく業界の中でやりがいを見つける
KA:金融業界における今後の展望について教えてください。
吉羽氏:今後、金融業界ではデータを活用した分析の重要性がさらに高まると考えています。
また、環境問題に対応するためのコンサルティング的な役割への需要も増加するでしょう。そのため、金融業界はこれまでの「資金を融資するだけ」という従来のイメージから、より幅広いサービスを提供する方向へと変化しています。このトレンドは今後もしばらく続くのではないかと見ています。
KA:最後に、金融業界への転職や就職を考えている方々へ、アドバイスをお願いします。
吉羽氏: 金融業界は、昔と比べて大きく変化してきています。その中で、取り組むべき課題はたくさんありますが、同時にやりがいのある魅力的な仕事も数多く存在します。自分にとって「これだ」と思えるやりがいを見つけ、それに向かって努力を重ねていくことが大切です。ぜひ、自分の可能性を信じて、一歩踏み出してみてください。