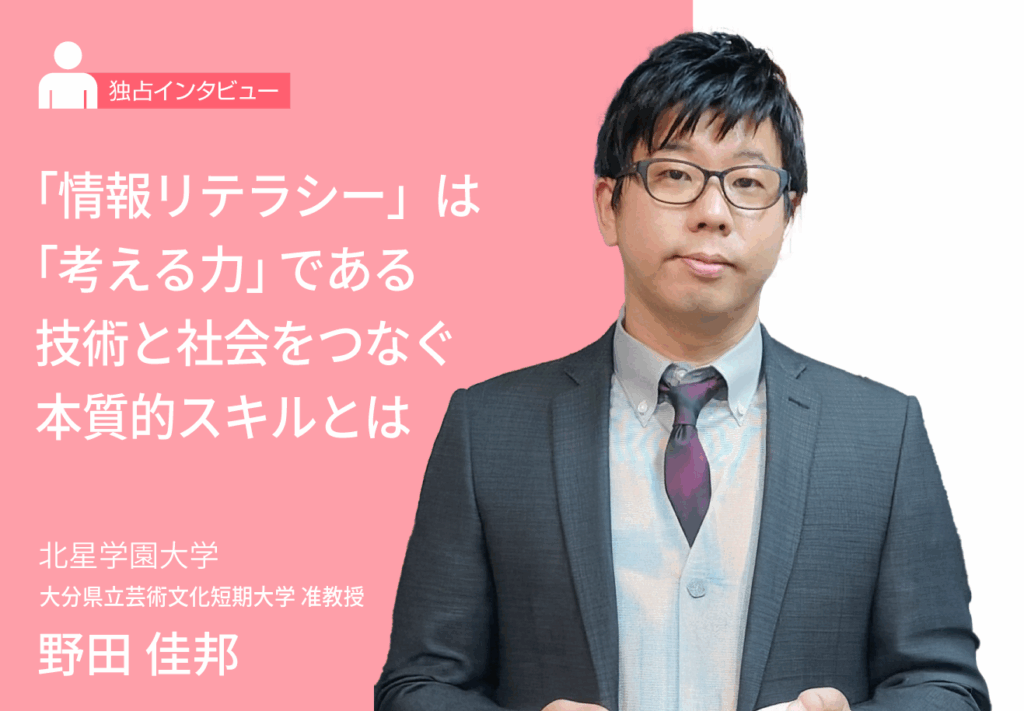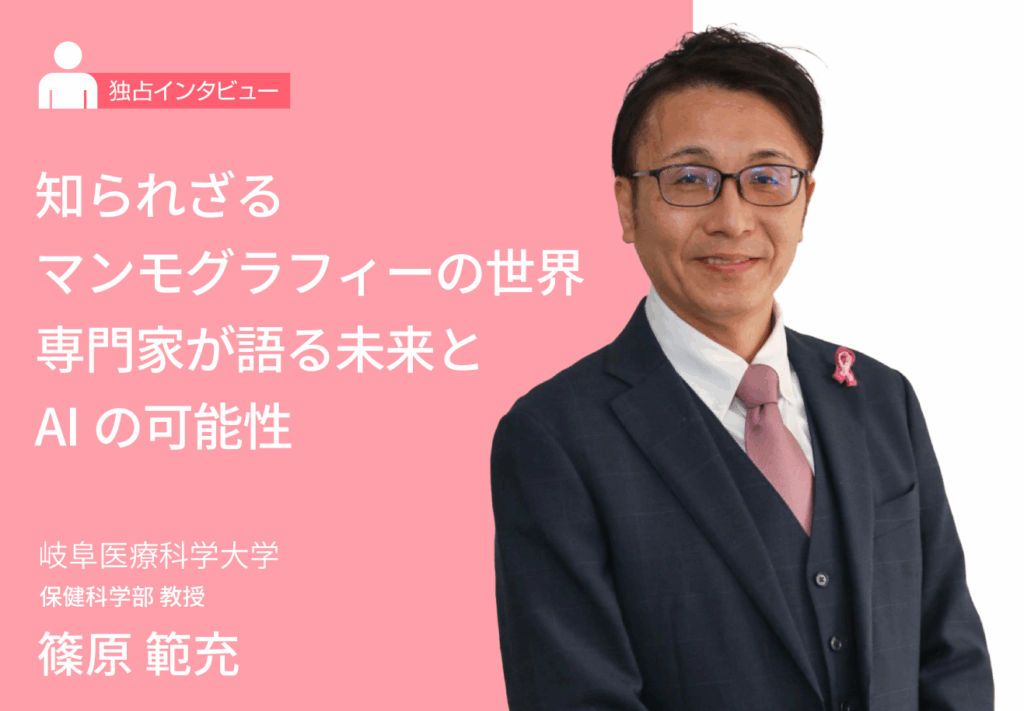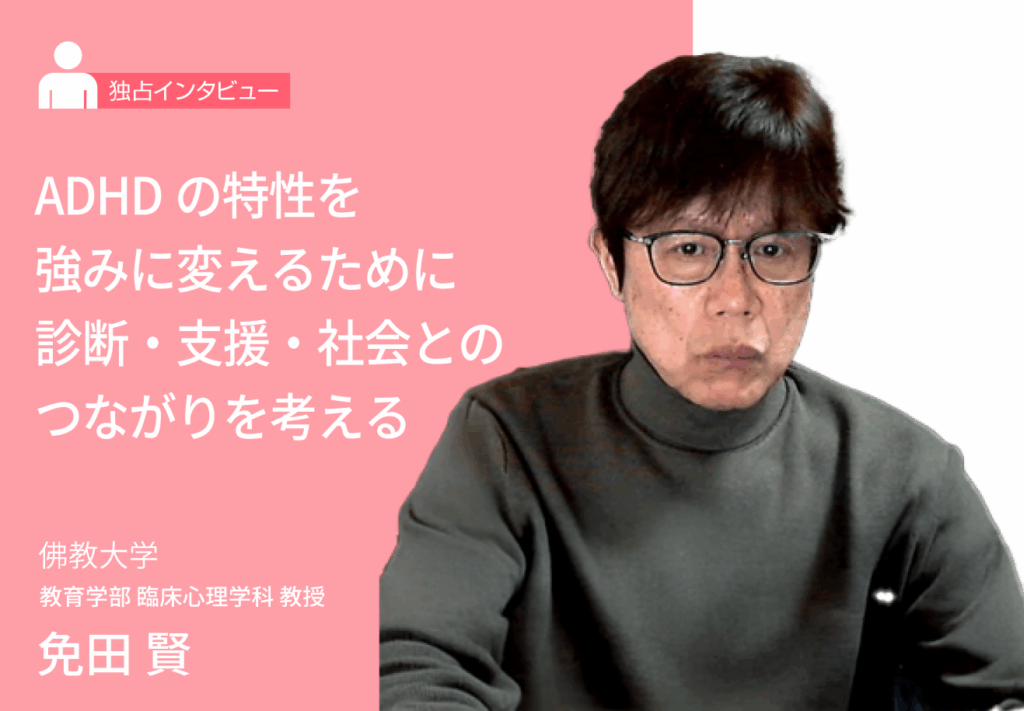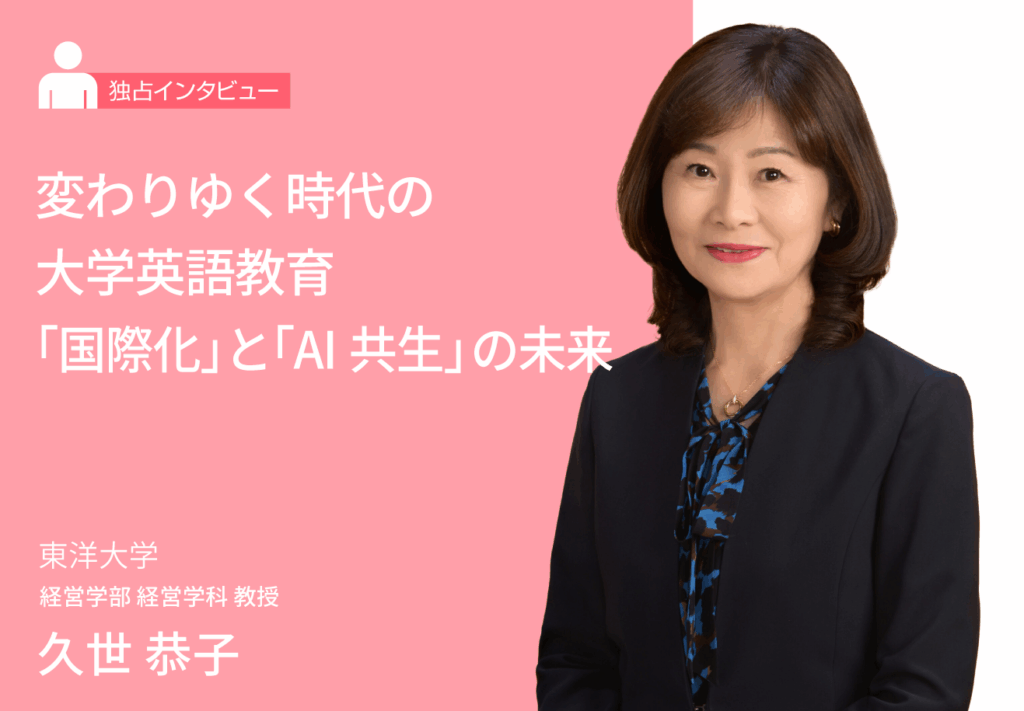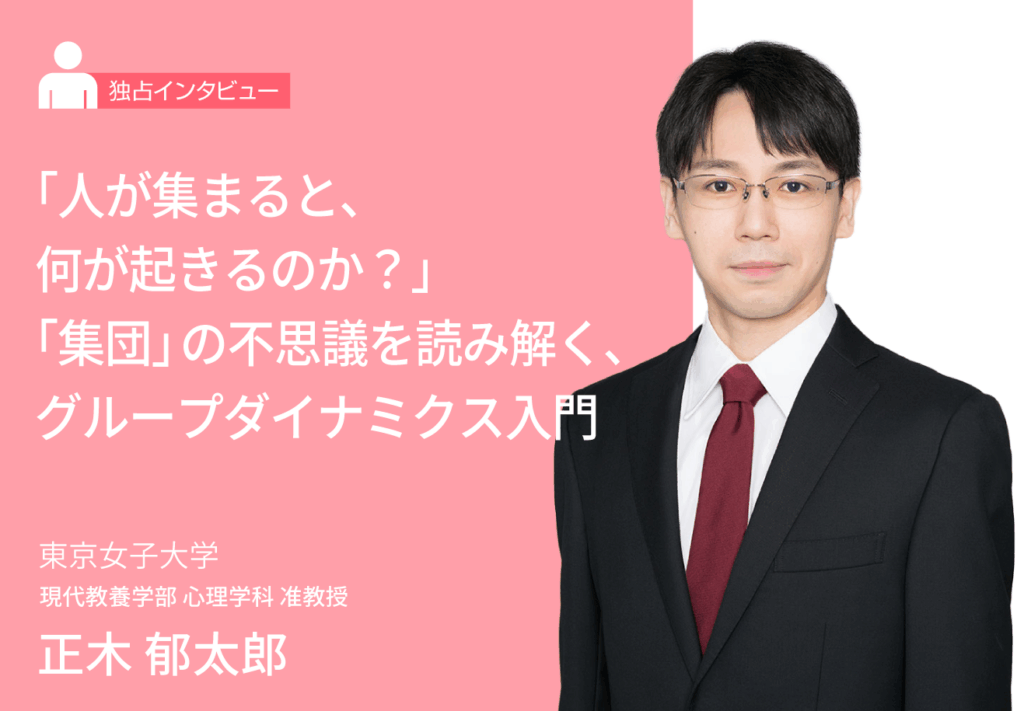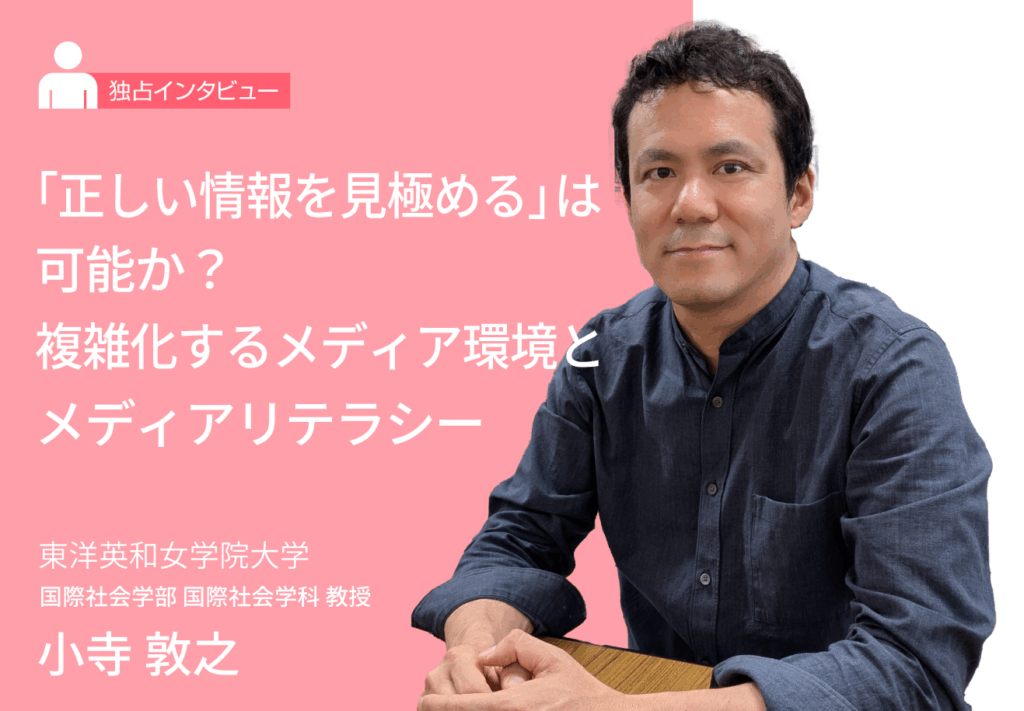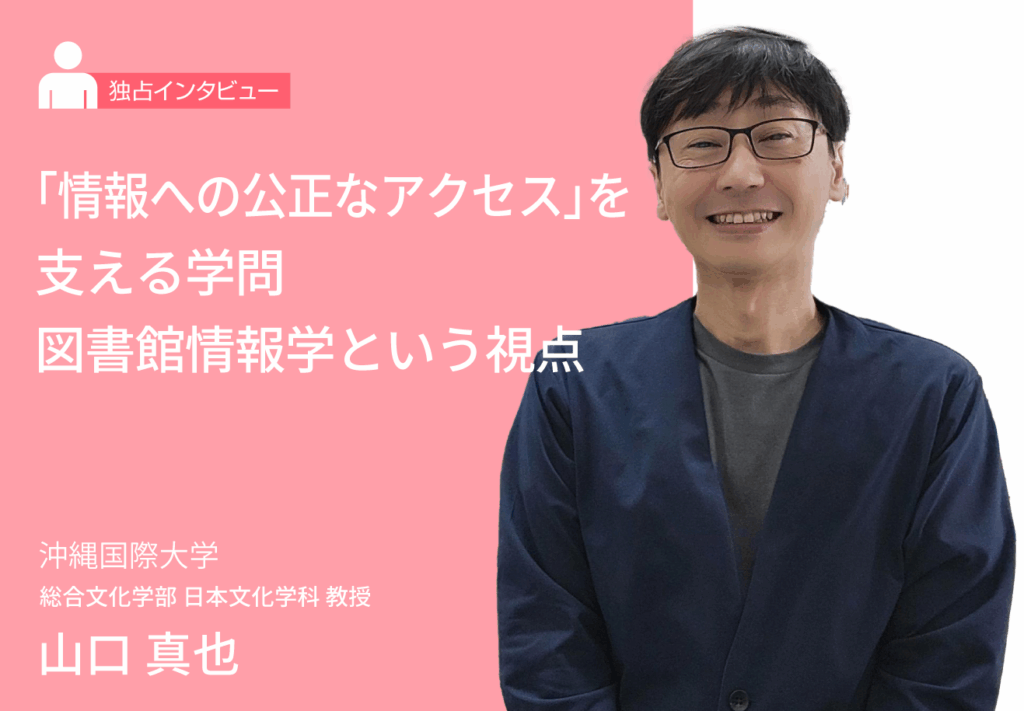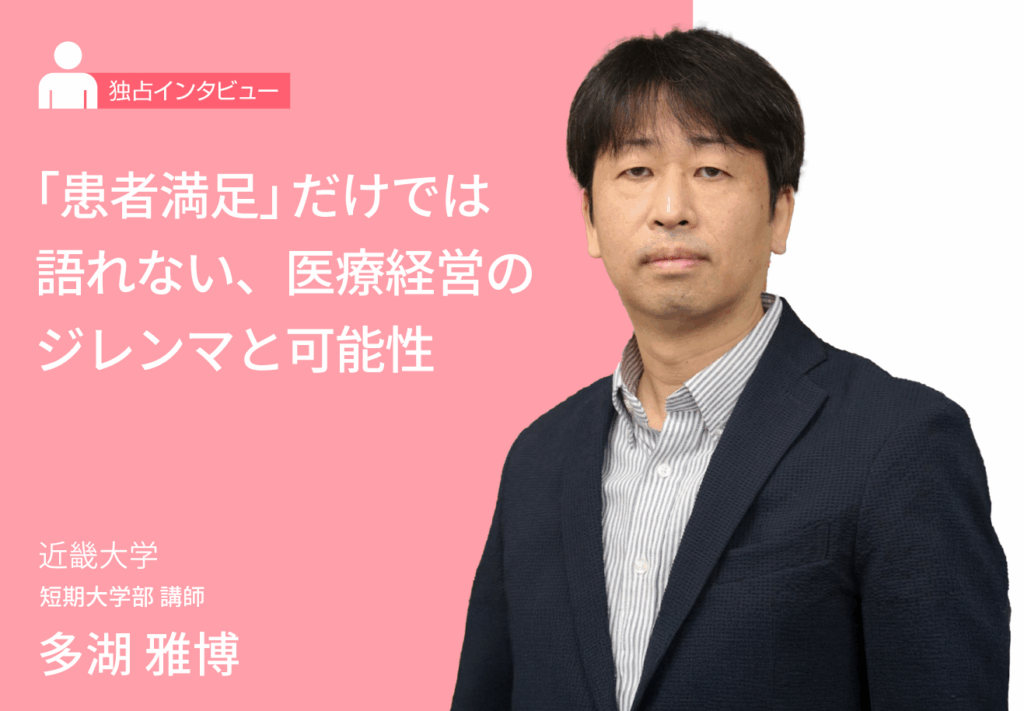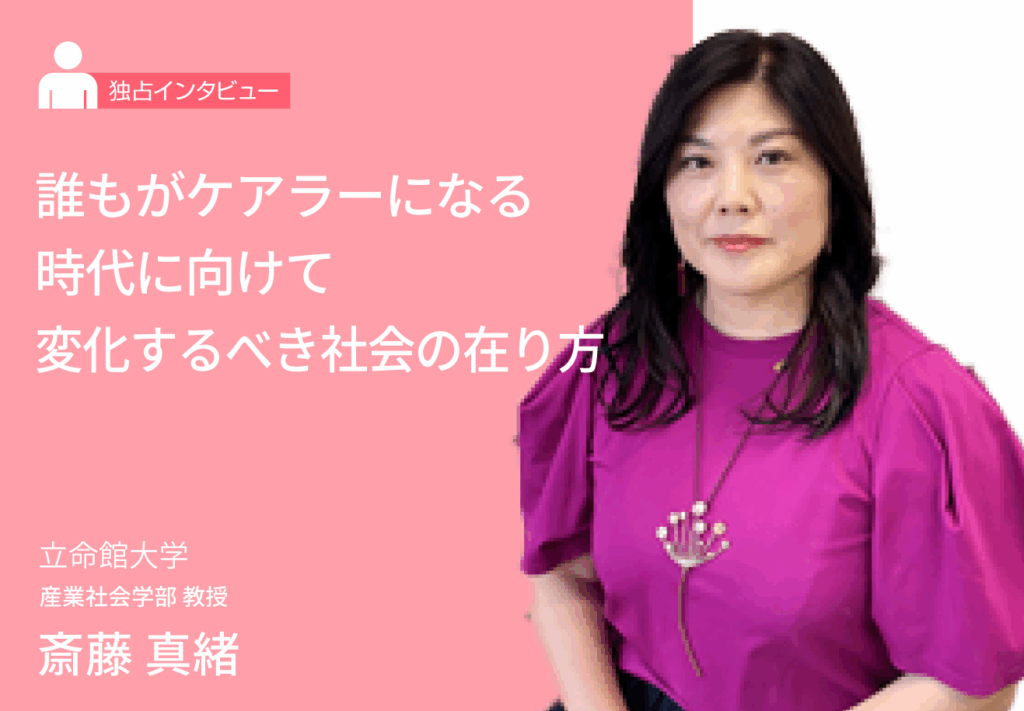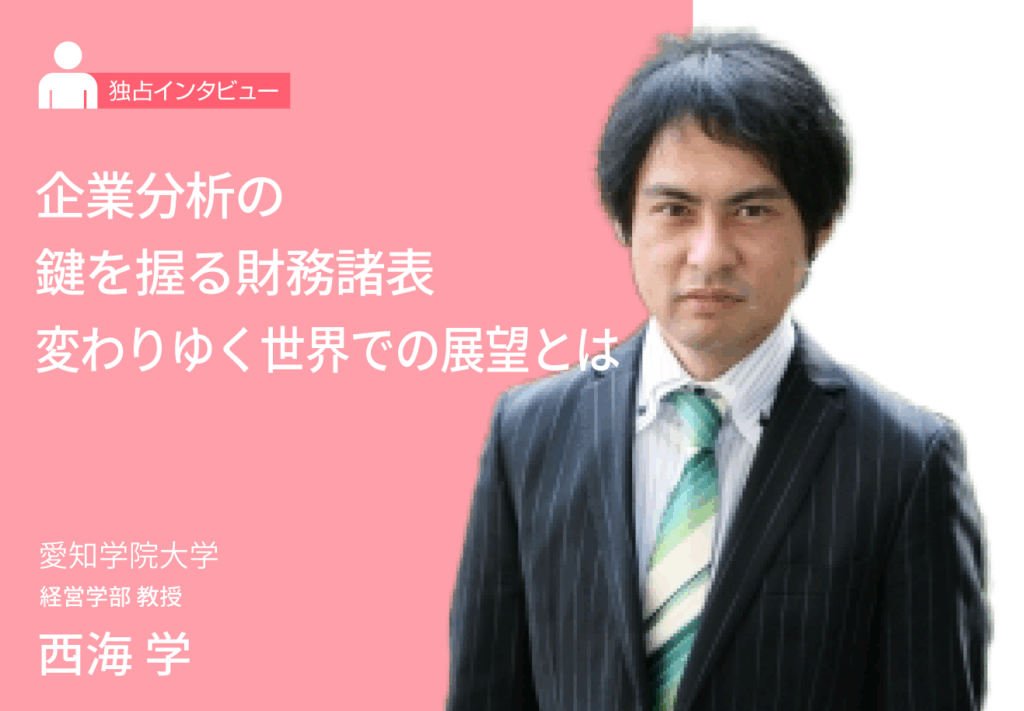インタビュー– category –
-

「情報リテラシー」は“考える力”である——技術と社会をつなぐ本質的スキルとは
SNSやAIの急速な普及にともない、「情報をどう扱うか」が個人の生活にも社会全体にも大きな影響を与える時代になりました。 私たちは日々、膨大な情報にさらされ、何を信じ、何を選ぶかを無意識に問われています。そんな現代において必要とされるのが、「... -

知られざるマンモグラフィーの世界|専門家が語る未来とAIの可能性
乳がんは、特に40代から50代の働き盛りの世代にとって、向き合うべき重要な健康課題です。早期に発見できるかが、その後の治療の可能性を広げることになります。 しかし、「痛そう」「放射線が心配」といったイメージから、乳がん検診の中心的な役割を果た... -

ADHDの特性を強みに変えるために──診断・支援・社会とのつながりを考える
子どもから大人まで、さまざまなライフステージで影響を及ぼす発達障害。なかでもADHD(注意欠如・多動症)は、集中力の持続が難しかったり、衝動的な行動をとったりと、日常生活において「ちょっとした生きづらさ」につながることがあります。 しかし一方... -

変わりゆく時代の大学英語教育──“国際化”と“AI共生”の未来
現代社会において、英語は単なる外国語の一つにとどまらず、国境を越えて人と人をつなぐ「共通語」としての役割を強めています。特に大学教育の現場では、グローバル化の進展やAI技術の急速な発展を背景に、従来の語学教育の枠を超えた新しいアプローチが... -

「人が集まると、何が起きるのか?」――“集団”の不思議を読み解く、グループダイナミクス入門
私たちは日々、誰かと一緒に働き、話し合い、意思決定をしています。しかし、家族、学校、職場、友人関係といった集団の中で「なぜこの空気になるのか」「なぜあの人の発言で場が動いたのか」といった現象に、改めて疑問を抱いたことはないでしょうか? 「... -

「正しい情報を見極める」は可能か?──複雑化するメディア環境とメディアリテラシー
情報があふれ、何を信じるべきか分からない──そんな混迷の時代に求められるスキルとして、メディアリテラシーが注目されています。 しかし、メディアリテラシーを身につけるとはどういうことでしょうか。そしてこれは複雑化する情報社会を生き抜く処方箋に... -

「情報への公正なアクセス」を支える学問──図書館情報学という視点
図書館の本の並べ方という、一見すると単なる整理術のようにも思えるこの行為が、実は一つの学問の出発点であることをご存じでしょうか。 情報があふれる現代において、私たちは「必要な情報に、誰もが、等しく、たどり着ける」環境づくりを求められていま... -

“患者満足”だけでは語れない、医療経営のジレンマと可能性
少子高齢化、医療財政の逼迫、医療人材の確保と定着など、現代の日本の医療現場は、かつてない課題に直面しています。 そうした中で、今あらためて注目されているのが「医療経営」という視点です。 今回は、近畿大学の多湖雅博先生に、医療経営の基本的な... -

誰もがケアラーになる時代に向けて──変化するべき社会の在り方
日本は、世界でも類を見ないスピードで少子高齢化が進行しています。厚生労働省の発表によると、2024年の出生数は72万988人と、1899年の統計開始以来、過去最少を記録しました。また、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2070年には65歳以上の人口が... -

企業分析の鍵を握る財務諸表—変わりゆく世界での展望とは
現代のビジネスにおいて、企業の健全性や成長性を読み解くうえで欠かせないのが「財務諸表」です。 しかし、多くの人にとって、損益計算書や貸借対照表といった言葉は難しく感じられ、具体的に何がわかるのか、どのように活用すべきかが分かりにくいもので...