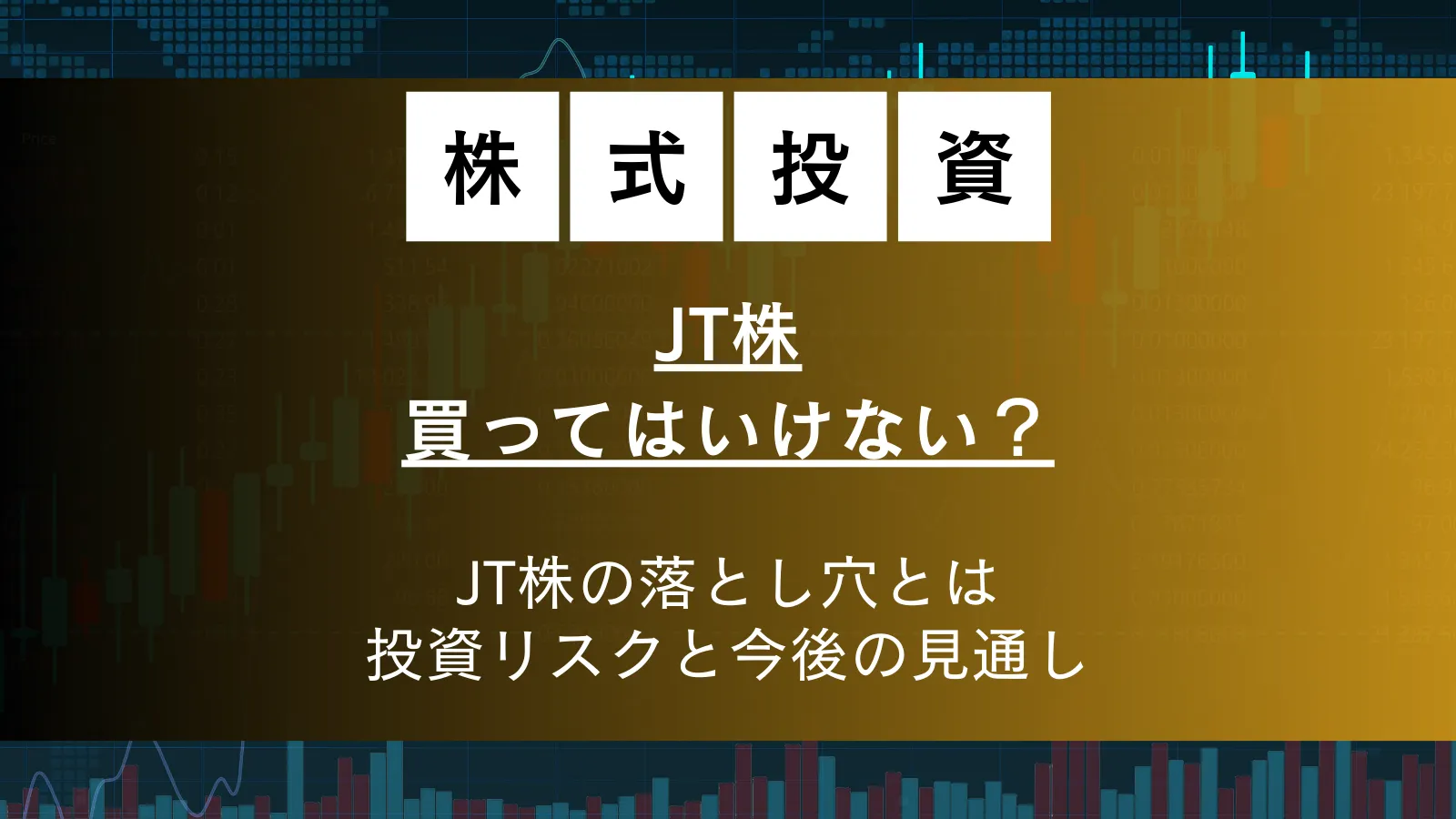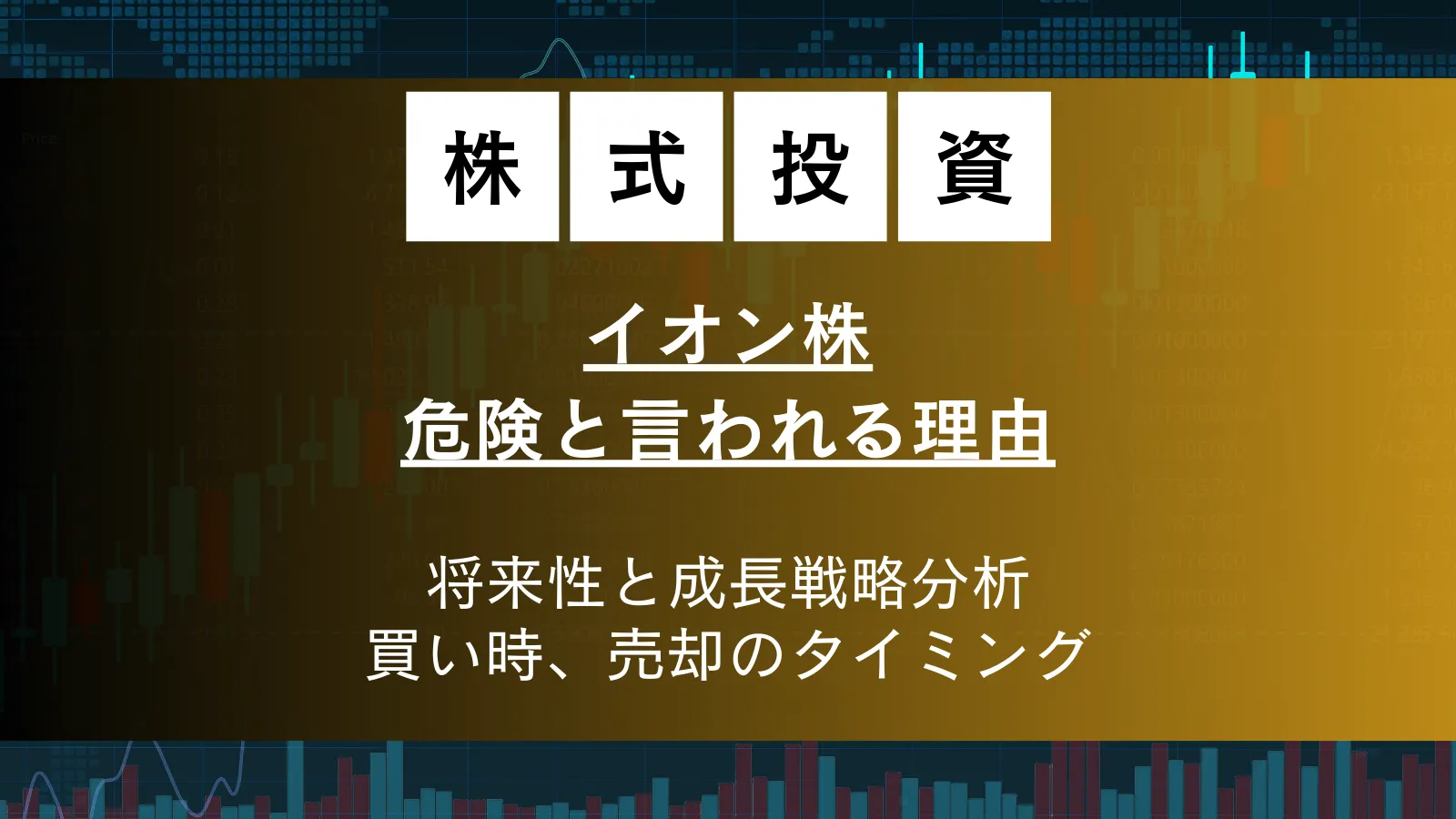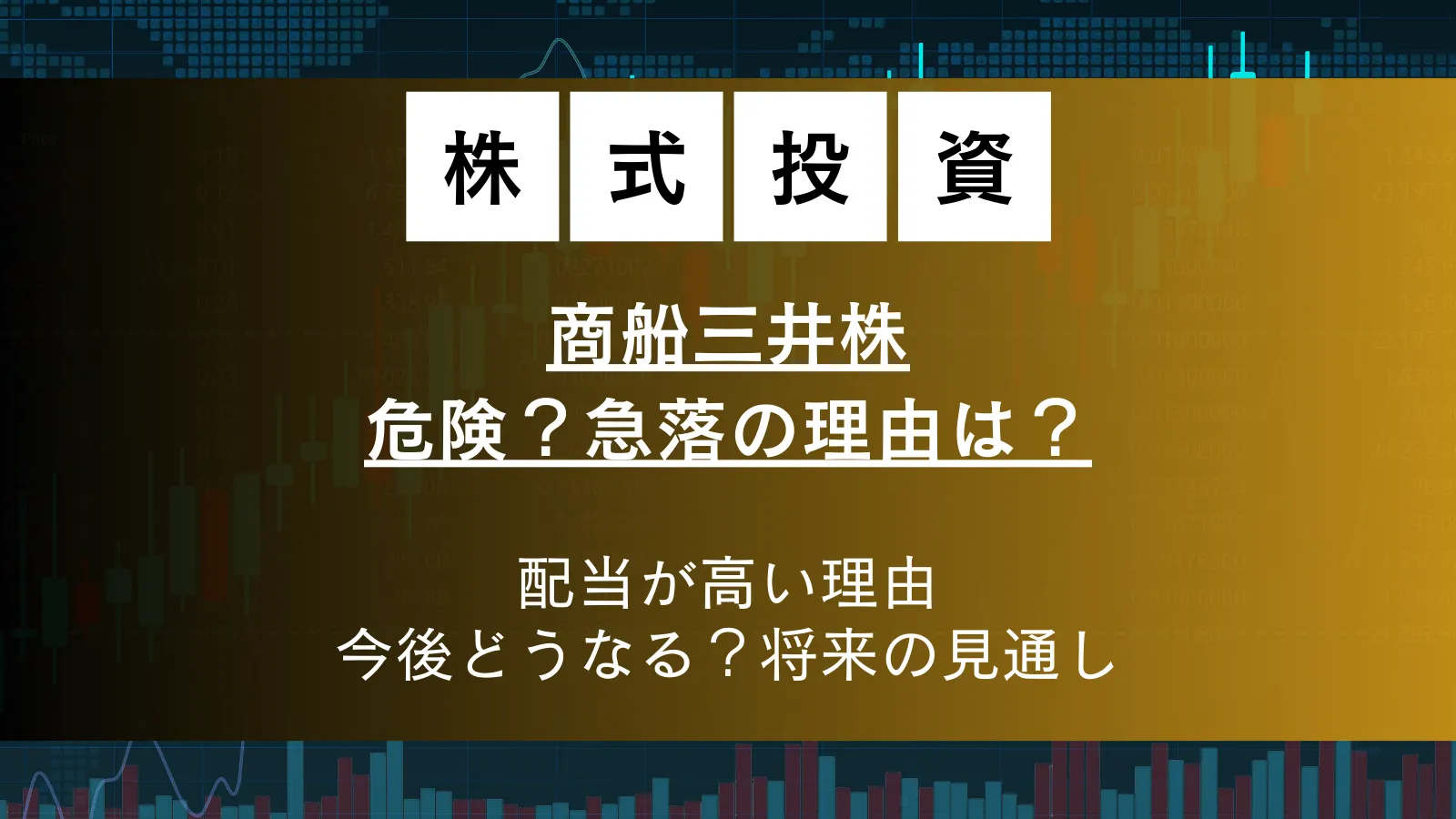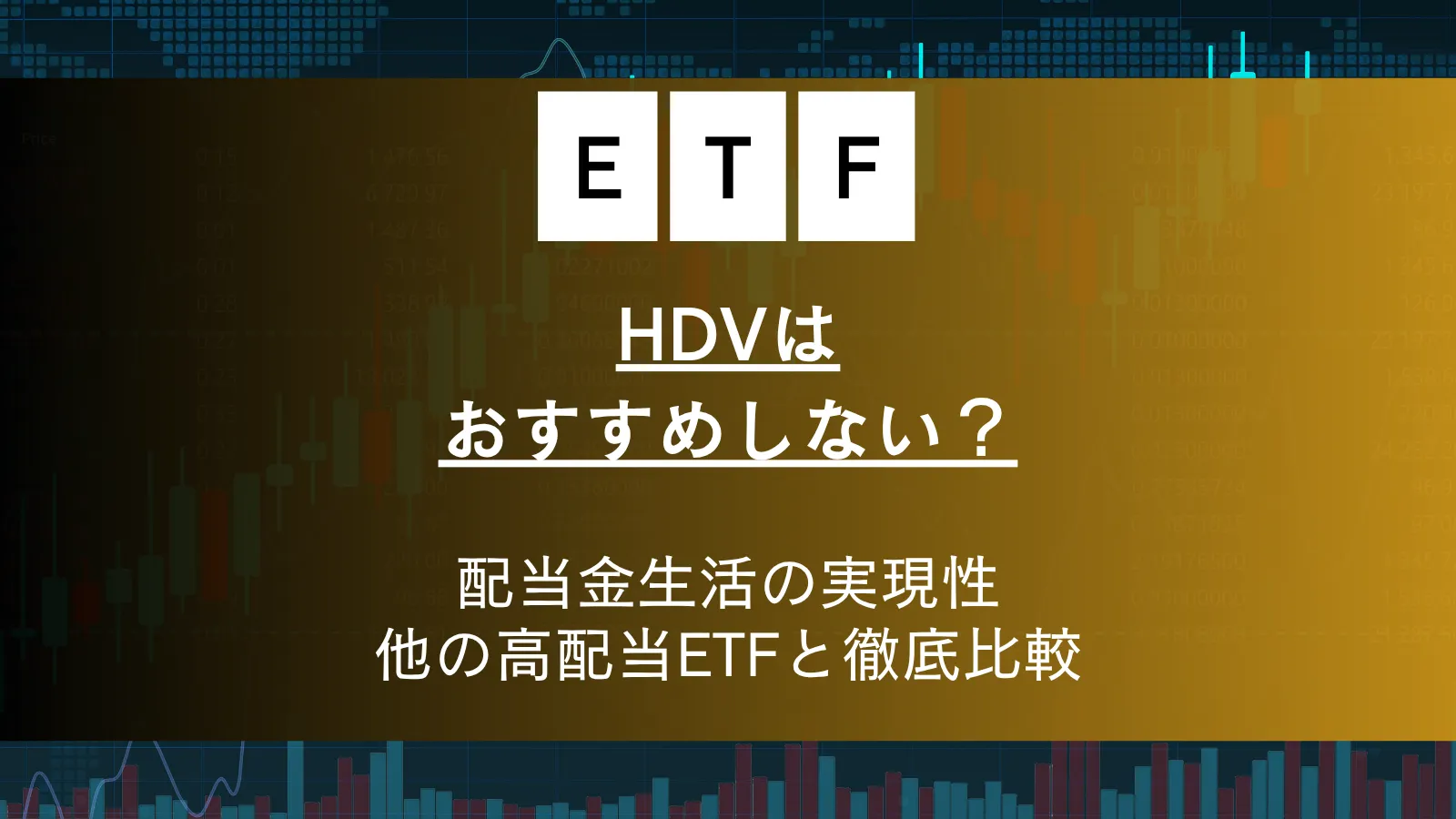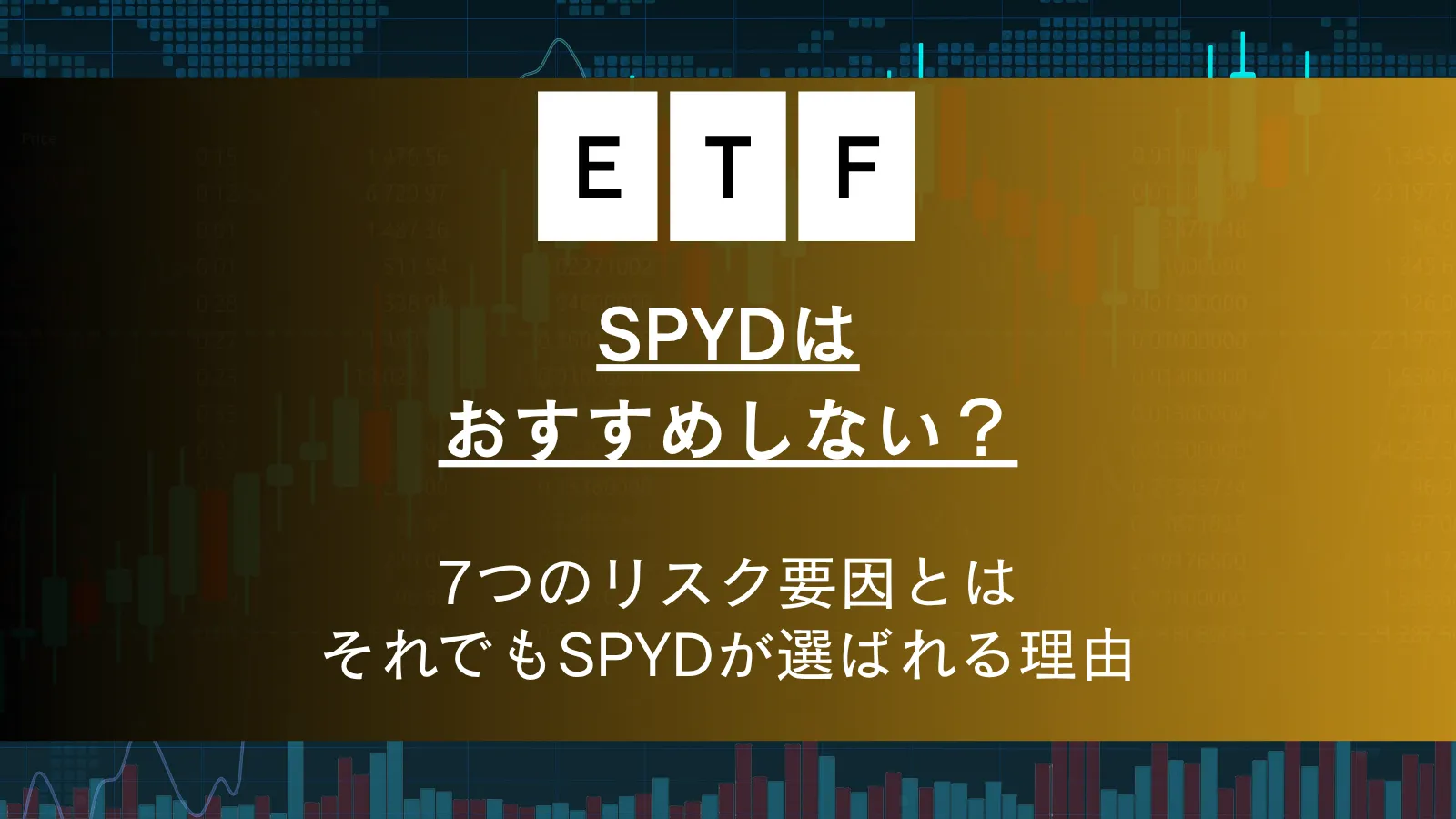「VYMはおすすめしない」との声を耳にしますが、本当にそうでしょうか?確かに配当利回りは2.39%と高配当ETFとしては物足りない水準です。
同じ米国高配当ETFのSPYD(4.44%)やHDV(3.21%)と比較しても、VYMの配当利回りは2.39%と最も低く、配当収入だけを重視する投資家には物足りないかもしれません。
さらに、米国ETFならではの二重課税問題や為替リスク、配当の自動再投資ができないなど、VYMには多くのデメリットが存在します。
一方で、年利12%以上の実績を持つヘッジファンドなら、VYMの課題をすべてクリアできます。詳しくはプロが運用するヘッジファンドをご確認ください。
この記事では、VYMをおすすめしない理由を詳しく解説し、メリット・デメリットを比較しながら、どんな人に向いているかを明らかにします。
VYMへの投資で後悔しないために、最後までしっかりと確認していきましょう。
VYMよりも高い資産成長を目指したい方は、おすすめ代替投資先2選をご覧ください。年利10%以上の実績を持つプロ運用ファンドを詳しく紹介しています。
投資目的別:VYMをおすすめする人・おすすめしない人の特徴
VYMへの投資を検討する前に、自分の投資目的と合っているかの確認が大切です。
VYMには明確なメリット・デメリットがあり、投資目的によって向き不向きが大きく分かれます。
どんな人におすすめできて、どんな人にはおすすめしないのか、具体的な特徴を整理してみましょう。
>>先にVYMの基本情報について知りたい方は、こちらをご覧ください
VYMをおすすめする人の特徴
VYMは安定した配当収入を長期的に得たい人におすすめです。
- 定年退職後の生活費の一部として配当金を活用したい方
- 給与以外の収入源を作りたいサラリーマン
- リスクを抑えた運用をしたい投資初心者
- 米国企業の成長に長期的に投資したい方
VYMは572銘柄への分散投資により個別株のような大きな値下がりリスクを避けられ、年4回の配当を定期的に受け取れます。特に定年退職後の方にとっては、年金を補完する安定収入源として活用できるでしょう。また、サラリーマンの方なら給与とは別の収入の柱を作ることで、経済的な安心感を得られます。
投資初心者の方には、個別株選びの難しさや銘柄選定の手間を省ける点も魅力です。VYMは米国の優良企業で構成されているため、アメリカ経済の成長とともに資産を増やしていける長期投資に適したETFといえます。
ただし、配当利回り2.39%では本格的な配当収入には不十分です。
より高い収益性を求める方は、年利17.35%(2024年度実績)という圧倒的なパフォーマンスを誇り、3ヶ月ごとの運用報告で透明性も確保されたAction合同会社のような代替投資先も検討してみましょう。
VYMをおすすめしない人の特徴
一方で、VYMをおすすめしないのは短期間で大きな利益を狙いたい人です。
- デイトレードやスイングトレードで利益を上げたい方
- 税金の手続きが面倒だと感じる方
- 高配当を重視する方
- 資産を最速で増やしたい若い世代の方
VYMの値動きは緩やかすぎて、短期売買には適していません。デイトレードやスイングトレードで利益を狙うなら、もっと値動きの激しい個別株やレバレッジETFを選ぶべきでしょう。また、米国ETFは確定申告が必要になるため、税務処理に慣れていない方には負担になります。
さらに、配当利回り2.39%はSPYD(4.44%)やHDV(3.21%)と比較して低く、高配当を求める投資家には物足りない水準です。
資産を最速で増やしたい若い世代の方には、VYMよりは成長株ETFやヘッジファンドのほうが目的に合っているでしょう。
具体的には、アクション合同会社、ハイクアインターナショナルなどの選択肢があります。
時間を味方につけられる若いうちは、もっとアグレッシブな運用も選択肢に入れてよいはずです。
投資目的に合わせたVYMの活用方法
VYMは単独で投資するより、ポートフォリオの一部として活用するのがおすすめです。
たとえば、資産の30%をVYMのような安定型、50%をS&P500のような成長型、20%をオルタナティブ投資に配分するると、リスクを抑えながら着実に資産を増やすバランス型のポートフォリオが構築できます。
年齢によって配分を変えるのも賢い方法です。若いうちは成長重視で運用し、年齢とともにVYMの比率を高めていくと、ライフステージに応じた資産形成が可能になります。
たとえば50代になったら配当重視に切り替える戦略も有効でしょう。
また、配当金の使い道を明確にするのも重要です。
生活費に充てるのか、再投資するのか、それとも趣味や旅行に使うのか。目的を明確にするとVYMへの投資はより価値ある選択へと変わるはずです。
VYMをおすすめしない7つの理由を徹底解説
VYMは米国高配当ETFとして人気がありますが、「VYMはおすすめしない?」と疑問を持つ声があるのも事実です。
その理由を理解した上での投資判断が重要です。
投資目的によっては、VYMをおすすめしないケースが多いのが実情です。
ここからは、VYMをおすすめしない理由を7つに分けて詳しく見ていきましょう。
投資を検討している方は、デメリットをしっかり理解する必要があります。
理由①VYM配当利回りは高配当ETFの中では物足りない水準
VYMの配当利回りは2.39%と、高配当ETFとしては物足りない水準です。
同じ米国高配当ETFのSPYD(4.44%)やHDV(3.21%)と比較すると、VYMが最も低い配当利回りとなっています。
高配当を重視する投資家にとっては、この差は決して小さくありません。
| ETF名 | 配当利回り | 3年トータルリターン | 構成銘柄数 |
|---|---|---|---|
| VYM | 2.39% | 13.62% | 572銘柄 |
| SPYD | 4.44% | 7.55% | 約80銘柄 |
| HDV | 3.21% | 8.81% | 約80銘柄 |
ただし、配当利回りが低い分、3年トータルリターンではVYMが13.62%と比較対象の中で最も高くなっています。
VYMは、配当だけでなく株価の値上がり益も含めた総合的なリターンにおいて、優れたパフォーマンスを示しています。
配当重視か、トータルリターン重視かで選択が変わってくるでしょう。
高配当を重視する投資家には、この配当利回りの低さこそがVYMをおすすめしない最大の理由となります。
配当重視なら、年利17.35%(2024年度実績)という高水準な配当実績を持つAction合同会社もおすすめです。
理由をさらに深掘りし、高配当ETFの「罠」について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
理由②大きなキャピタルゲインは期待できない
VYMの構成銘柄は成熟した大企業が中心のため、株価の大幅な上昇は期待しにくい特徴があります。
高配当株は一般的に成長段階を過ぎた企業が多く、配当に利益を回す分、事業への再投資が少なくなります。その結果、株価の上昇余地は限定的になりがちです。
実際、S&P500と比較すると、3年トータルリターンではS&P500が26.23%、VYMが13.62%とS&P500が大きく上回っています。
過去10年・20年といった長期スパンで見ても、成長株中心のS&P500やナスダック100の方が高いリターンを出してきた実績があります。
株価の値上がりを重視するなら、VYMよりも成長性の高い投資先を選ぶべきでしょう。
将来の売却益で大きな利益を得たい方や、積極的にリスクを取って高いリターンを狙いたい方には、成長株ETFや個別成長株への投資がおすすめです。
VYMはあくまで配当収入を重視する投資家向けの商品であり、大きなキャピタルゲインを期待できない点がVYMをおすすめしない理由となります。
資産の大幅な成長を狙うなら、年利17.35%の実績を持つアクション合同会社のようなヘッジファンドが効果的です。
株価成長を重視した投資信託の選び方については、こちらの記事が参考になります。
理由③米国の税金と確定申告の手間がかかる
VYMのような米国ETFに投資すると、配当金に対して日米で二重課税されることがあります。
まず米国で10%の源泉徴収税が差し引かれ、さらに日本でも約20%の税金がかかります。
つまり、何もしないと配当金の約30%が税金で持っていかれます。
二重課税を回避するには、確定申告で「外国税額控除」を申請する必要があります。
確定申告をしないと、配当金が大幅に減ってしまうので注意が必要です。
毎年の確定申告は手間がかかりますし、税務の知識も必要になります。
投資初心者にとっては、外国税額控除申請の煩雑さがVYMをおすすめしない理由の一つになるでしょう。
理由④短期的な資産形成には適していない
VYMは配当重視のETFなので、短期間で資産を大きく増やしたい人には向いていません。
なぜなら、VYMの魅力は長期保有による配当の積み重ねにあるからです。
短期売買で利益を狙うなら、値動きの大きい成長株やレバレッジETFのほうが効率的でしょう。
また、配当金を受け取ってしまうと、その都度税金が引かれます。
複利効果を最大限に活かせない点も、資産形成においてはデメリットになります。
1~2年といった短期間での運用を考えている方や、できるだけ早く資産を増やしたい方は、VYM以外の選択肢を検討したほうがよいかもしれません。
理由⑤為替変動リスクと手数料負担を考慮する必要がある
VYMは米ドル建ての商品なので、円高になると為替差損が発生するリスクがあります。
たとえば、1ドル150円で購入したVYMが、売却時に1ドル130円になっていたら、それだけで約13%の損失です。
配当利回りが2.39%程度なので、数年分の配当が吹き飛んでしまう計算になります。
さらに、米ドルへの両替時には為替手数料もかかります。
往復で1~2%程度の手数料を考えると、実質的なリターンはさらに低くなってしまいます。
為替リスクを避けたい投資家や、手数料を抑えたい方には、日本の高配当株やETFへの投資も選択肢として検討する価値があるでしょう。
あるいは、為替リスクや両替の手間が一切かからない国内ファンドのAction合同会社(2024年度実績 年利17.35%)なら、国内にいながら高水準なリターンだけに集中できます。
理由⑥配当の自動再投資ができず複利効果を活かしにくい
VYMの大きなデメリットの一つが、配当金の自動再投資ができない点です。
投資信託なら配当を自動的に再投資して複利効果を最大化できますが、ETFでは配当金は現金で受け取るしかありません。
手動で再投資しようとすると、その都度売買手数料がかかり、少額の配当では手数料負けしてしまうリスクもあります。
複利効果を最大限に活かしたい投資家にとって、自動再投資ができない点はVYMをおすすめしない大きな理由の一つです。
理由⑦金融セクター偏重により景気変動の影響を受けやすい
VYMは金融セクターが21.15%と最も高い比率を占めています。
金融セクターは景気敏感セクターであり、リーマンショック(2008年)やコロナショック(2020年)のような経済危機時には大きく下落する傾向があります。
実際、コロナショック時にVYMは約-35%下落し、回復にも時間がかかりました。金融セクターの比率が高いのは、不況時のリスクを意味します。
一方、SCHDはヘルスケアセクターが13.21%と分散が効いており、HDVはエネルギーセクター24.28%と異なるリスク特性を持っています。
景気変動に強いポートフォリオを目指すなら、セクター配分の偏りが少ない投資先や、Web3事業と実業への分散投資でリスクヘッジを図るAction合同会社も検討する価値があるでしょう。
VYMのメリット:おすすめしないと言われても魅力はある
ここまでVYMをおすすめしない理由を見てきましたが、決して悪い投資先ではありません。
むしろ、投資目的がマッチすれば非常に優れたETFといえます。
ここからは、VYMの魅力的なメリットを4つご紹介しましょう。
メリット①少額から分散投資を始められる
VYMの大きな魅力は、1株から購入できる手軽さにあります。
2026年1月時点の株価は約146ドルなので、日本円にすると約2.3万円程度から投資を始められます。
まとまった資金がなくても、米国の優良企業572社に分散投資できるのは大きなメリットです。
個別株で同じような分散投資をしようとすると、数百万円以上の資金が必要になります。
少額から始めたい投資初心者にとって、VYMは最適な選択肢の一つといえるでしょう。
少額から手軽に始められるとはいえ、投資に「安全」はつきものです。リスクを抑えながら資産を増やすための安全な投資方法について、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
メリット②500以上の銘柄に自動で分散される
VYMは572銘柄に及ぶ、圧倒的な分散効果を誇ります。
同じ高配当ETFのSPYDやHDVは約80銘柄なので、VYMの分散度は群を抜いています。
多くの銘柄に分散されていれば、個別企業の業績悪化による影響を最小限に抑えられます。
セクターも金融、産業、ヘルスケアなど幅広く分散されています。
リスクを抑えた運用を心がけたい投資家にとって、500以上の銘柄への分散効果は大きな安心材料になるはずです。
リスクを抑えた運用とさらなる分散効果を求めるなら、VYMとは異なるアプローチで絶対収益を追求するヘッジファンドもおすすめです。
メリット③安定した配当金収入を得られる
VYMは四半期ごとに配当金が支払われるため、年4回の定期収入を得られます。
配当利回り2.39%と控えめながら、定期的なキャッシュフローは魅力です。
しかも、長期的には増配傾向にあるため、将来的な配当金の積み増しが見込まれます。
リタイア後の生活費の一部として、あるいは再投資の原資として、安定した配当収入は投資家にとって心強い味方になるでしょう。
メリット④経費率0.06%の低コストで運用できる
VYMの経費率はわずか0.06%と、ETFの中でもトップクラスの低さです。
100万円投資しても年間600円しかコストがかからない計算になります。
アクティブファンドなら1~2%の信託報酬がかかるので、VYMの低コストは驚異的です。
長期投資において、コストの差は最終的なリターンに大きく影響します。
低コストで米国高配当株に投資したいなら、VYMは最有力候補になるでしょう。
VYMの7つのおすすめしない理由を理解した上での賢い活用法
ここまでVYMのメリット・デメリットを詳しく見てきましたが、7つのデメリットを正しく理解した上で適切に活用すれば、VYMは優れた投資先となり得ます。
デメリットを弱点として避けるのではなく、特性として理解し活用すると、VYMの真価を引き出せるでしょう。
VYMの7つのデメリットを逆手に取った4つの実践的な活用戦略をご紹介します。
戦略① 配当利回りの低さを補う:高配当ETFとの組み合わせ戦略
VYMの配当利回り2.39%は、SPYD(4.44%)やSCHD(3.92%)と組み合わせると配当収入を大幅に向上できます。
VYMの強みである572銘柄への分散効果を活かしつつ、他の高配当ETFで利回りを補完する戦略です。
たとえば、配当重視型ポートフォリオとして以下のような配分が考えられます。VYMを50%、SPYDを30%、SCHDを20%とすると、平均配当利回り約3.2%を確保しながら、VYMの分散効果でリスクも抑えられます。
| ETF | 配分 | 配当利回り | 役割 |
|---|---|---|---|
| VYM | 50% | 2.39% | 安定性・分散の中核 |
| SPYD | 30% | 4.44% | 高配当の補完 |
| SCHD | 20% | 3.92% | 増配期待 |
| 合計 | 100% | 約3.2% | バランス型 |
この戦略がおすすめなのは、以下のような人です。
- 配当収入を重視したいが、リスク分散も重要視する
- VYM単体では配当利回りに物足りなさを感じる
- 複数のETFを組み合わせる手間を惜しまない
- 年間30万円以上の配当収入を目指したい
ただし、それでも配当利回り3%台では物足りない方は、年利実績17.35%のアクションのような代替投資先も検討する価値があります。
戦略② 自動再投資不可を逆手に取る:定期キャッシュフロー確保戦略
VYMは配当の自動再投資ができませんが、「定期的な現金収入を得られる」メリットとして活用する発想の転換が有効です。
特に退職後や副収入を求める投資家にとって、年4回の確実な配当は心強い収入源になります。
自動再投資されない特性を活かし、配当金の使い道を事前に決めておくと効果的です。
生活費の補填として給与以外の安定収入源にする、趣味・旅行資金として罪悪感なく使える楽しみにする、緊急予備資金として現金として確保できる安心感を得る、あるいは手動で再投資してタイミングを自分で判断するなど、様々な活用方法が考えられます。
| 使い道 | メリット |
|---|---|
| 生活費の補填 | 給与以外の安定収入源 |
| 趣味・旅行資金 | 罪悪感なく使える楽しみ |
| 緊急予備資金 | 現金として確保できる安心感 |
| 手動で再投資 | タイミングを自分で判断 |
この戦略がおすすめなのは、以下のような人です。
- 定年退職後で年金を補完する収入が欲しい
- 給与以外の定期的な副収入を確保したい
- 複利効果よりも現在のキャッシュフローを重視
戦略③ 為替リスクを分散する:国内資産とのバランス運用
VYMは米ドル建てのため、円高時には為替差損が発生するリスクがあります。為替リスクを軽減するには、国内資産(日本株・日本国債・円預金など)とバランスよく組み合わせる戦略が有効です。
たとえば、VYM(米国株)を30%、日本高配当株を30%、S&P500を20%、日本国債/預金を20%での配分が考えられます。この配分なら、円高時には日本資産が、円安時には米国資産が利益を生むため、為替変動の影響を相殺できます。
| 資産クラス | 配分 | 役割 |
|---|---|---|
| VYM(米国株) | 30% | ドル建て・高配当 |
| 日本高配当株 | 30% | 円建て・為替ヘッジ |
| S&P500 | 20% | ドル建て・成長期待 |
| 日本国債/預金 | 20% | 円建て・安全資産 |
この戦略がおすすめなのは、以下のような人です。
- 為替変動リスクを最小限に抑えたい
- 円高・円安どちらでも安定した運用を目指す
- 米国資産と日本資産の両方に投資したい
- 国際分散投資でリスクヘッジしたい
為替リスクを完全に排除したい場合は、為替リスクや両替の手間が一切かからない国内ファンドのAction合同会社(2024年度実績 年利17.35%)のような代替投資先も選択肢となります。
完全に円建てで運用できるため、為替変動を気にせず純粋なリターンだけに集中できます。
戦略④ 年代別の最適配分:ライフステージに応じたVYM活用法
VYMは年齢やライフステージによって最適な活用方法が異なります。若いうちは成長重視、年齢とともに配当重視へシフトしていくのが基本戦略です。
| 年代 | VYM配分 | 成長株配分 | 現金・債券 | 運用方針 |
|---|---|---|---|---|
| 30代 | 10〜20% | 70% | 10% | 成長最優先 |
| 40代 | 30〜40% | 50% | 20% | 成長と配当のバランス |
| 50代 | 40〜50% | 30% | 30% | 配当へシフト |
| 60代〜 | 50〜60% | 10% | 40% | キャッシュフロー重視 |
30代は時間を味方につけられる年代なので、S&P500などの成長株を70%、VYMを20%程度に抑えて長期的な資産成長を優先します。
40代は家族のライフイベントに備え、VYMを30〜40%に増やして配当収入を確保しながら成長も狙います。
50代は退職後を見据えてVYMを40〜50%まで高め、年間100〜200万円の配当収入で年金を補完します。
60代以降はVYMを50〜60%として定期的なキャッシュフローを最大化し、月額20〜30万円の安定収入を確保します。
この戦略なら、年齢に応じて自然にリスクを下げながら、安定した配当収入を確保できます。
VYMとは?米国高配当ETFの基本情報をわかりやすく紹介
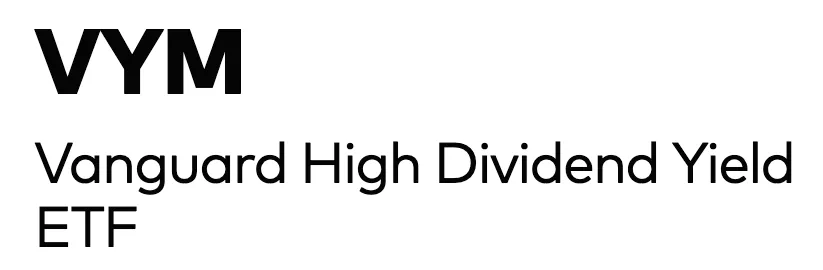
ここまでVYMのメリット・デメリットを見てきましたが、改めてVYMの基本情報を整理しておきましょう。
VYMの正式名称は「Vanguard High Dividend Yield ETF」で、世界最大級の運用会社であるバンガード社が提供する米国高配当ETFです。
2006年11月から運用が始まり、すでに18年以上の実績があります。
経費率は0.06%と非常に低く、投資家にとって魅力的なコスト設定になっています。
VYM配当利回りは2.39%で、配当金は年4回、3ヶ月ごとに支払われるため、定期的な収入を求める投資家から人気を集めています。
VYMの構成銘柄とセクター配分を詳しく解説
VYMは現在572銘柄で構成されており、米国市場の中でも配当が平均以上の企業に投資しています。
上位10銘柄を見てみると、ブロードコム(8.69%)、JPモルガン・チェース(4.06%)、エクソンモービル(2.35%)といった大型優良企業が並んでいます。
セクター配分では金融セクターが21.15%と最も多く、次いでハイテク17.52%、ヘルスケア13.21%と続きます。
特定のセクターに偏りすぎない分散投資が実現されているのが特徴です。
しかし、先述のとおり、金融セクターが最も高い比率を占めている点には少し注意は必要です。
構成銘柄は成熟した大企業が中心なので、急激な成長は期待できませんが、配当利回り2.39%の安定した配当収入を狙いやすくなっています。
VYMの利回り・増配率と他ETFとの比較
2026年最新のデータでVYMの利回り・増配率を他の高配当ETFと比較してみましょう。
| ETF名 | 配当 利回り | 3年 リターン率 | 5年 増配率 | 暴落時 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 2.39% | 13.62% | 3.84% | -8~10% |
| SPYD | 4.44% | 7.55% | 4.42% | -15~18% |
| HDV | 3.21% | 8.81% | 1.95% | -8~10% |
| SCHD | 3.92% | 6.45% | 9.23% | -10~12% |
この比較から明らかになるのは、VYMは配当利回りでは最も低い一方、3年トータルリターンでは13.62%と4つのETFの中で最も高いパフォーマンスを示しています。
配当利回りは低めですが、株価の値上がり益を含めた総合的なリターンでは優れた成績を収めているのがわかります。
VYMの配当利回りと分配実績
気になる配当利回りですが、2026年1月時点で2.39%となっています。
「あれ?高配当ETFなのに3%未満?」と思われるかもしれませんね。
実はVYMは高配当ETFの中では配当利回りが中程度の位置づけなんです。
過去の分配実績を見ると、安定して四半期ごとに配当が支払われており、長期的には増配傾向にあります。
SPYDやHDVと比べると配当利回りは低めですが、その分、トータルリターン(配当+値上がり益)では優れたパフォーマンスを示しています。
配当だけでなく、株価の成長も含めた総合的なリターンを重視する投資家には適しているでしょう。
ただし、配当利回り2.39%では本格的な配当収入には不十分です。
より高い収益性を求める方は、年利17.35%(2024年度実績)を達成したAction合同会社のような代替投資先も検討してみましょう。VYMと比較して7倍以上という高水準な利回りを実現しており、少ない資金でも効率的に資産形成を目指せます。
FTSE High Dividend指数と運用方針
VYMはFTSEハイディビデンド・イールド・インデックスへの連動を目指して運用されています。
この指数は、米国市場で平均以上の配当利回りを持つ企業を集めており、REITは含まれていません。
運用方針としては、高配当銘柄への投資を通じて、市場平均を上回る配当収入の獲得を目指しています。
ただし、配当利回りだけでなく、企業の財務健全性も考慮されているため、無理な高配当を出している企業は除外される仕組みです。
インデックス運用のため、アクティブファンドのような高い手数料はかかりません。
長期投資を前提とした、コストを抑えた運用が可能になっています。
VYMの配当金支払日と権利落ち日はいつ?
VYMは年4回(3月、6月、9月、12月)の四半期配当を実施しています。配当金を受け取るには、権利落ち日の前営業日までにVYMを保有している必要があります。
2025年の実績と2026年の予定スケジュールは以下の通りです。
| 配当月 | 権利落ち日 | 支払日 |
|---|---|---|
| 2025年3月 | 3月21日 | 3月25日 |
| 2025年6月 | 6月20日 | 6月24日 |
| 2025年9月 | 9月19日 | 9月23日 |
| 2025年12月 | 12月19日 | 12月23日 |
| 2026年3月 | 3月20日(予定) | 3月24日(予定) |
購入タイミングの注意点として権利落ち日の2営業日前(権利付き最終日)までに購入を完了する必要があります。
米国株式は決済に2営業日かかるため、配当を受け取りたい場合は早めの購入を心がけましょう。
また、配当金は支払日(権利落ち日から約4営業日後)に証券口座に入金されます。米国株式特有の決済サイクルを理解し、余裕を持ったスケジュールでの購入が重要です。
VYMの運用シミュレーション:配当金の積み上げ効果を検証
実際にVYMに投資したら、どれくらいのリターンが期待できるのでしょうか?
500万円を投資した場合のシミュレーションを通じて、配当金の積み上げ効果を具体的に見ていきます。
積立投資と一括投資、それぞれのパターンで検証してみましょう。
5年間運用した場合のリターンを検証
まずは5年間の運用でどうなるか見てみましょう。
配当利回り3%と仮定してシミュレーションします。
積立投資の場合(毎月8.3万円×60回=総額498万円)
- 投資元本:498万円
- 受取配当金:約39万円
- 5年後の評価額:537万円(資産成長率7.88%)
一括投資の場合(500万円を最初に投資)
- 投資元本:500万円
- 受取配当金:75万円
- 5年後の評価額:575万円(資産成長率15%)
一括投資の方が、より多くの配当金を享受できます。
5年間で75万円しか増えないのは、時間に対するリターンが低すぎます。
同じ500万円・同じ5年間でも、2024年度実績(年利17.35%)のAction合同会社なら、この利回りが継続したと仮定すれば1,100万円以上(+600万円超)に成長する計算になります。
VYMとの差額は500万円以上。効率的な資産形成を考えるなら、高実績を誇る代替投資先との比較は必須です。
10年間運用した場合のリターンを検証
次に10年間の長期運用ではどうなるでしょうか。
時間をかけるほど配当の威力が発揮されます。
積立投資の場合(毎月4.17万円×120回=総額500万円)
- 投資元本:500万円
- 受取配当金:約77万円
- 10年後の評価額:577万円(資産成長率15.4%)
一括投資の場合(500万円を最初に投資)
- 投資元本:500万円
- 受取配当金:150万円
- 10年後の評価額:650万円(資産成長率30%)
10年間では一括投資なら元本の30%に達する配当金を受け取れる計算です。
長期保有による配当の積み上げ効果がはっきりと表れていますね。
VYMの積み上げ効果に物足りない方は、ヘッジファンドとの詳細な比較結果をご確認ください。VYMとは桁違いの成長が期待できます。
配当金の再投資による複利効果を検証
配当金の再投資による複利効果を検証すると、ETF特有の大きな構造的デメリットが浮き彫りになります。
投資信託であれば配当を自動的に再投資できるため複利効果を最大限に活かせますが、VYMのようなETFでは配当金を現金で受け取るしかありません。
手動で配当を再投資する場合、その都度売買手数料がかかる問題も見逃せません。
特に少額の配当では手数料負けが生じ、長期的には運用効率を押し下げる要因となります。
複利効果を重視する投資家にとって、売買手数料がかかる点はVYMをおすすめしない重要な理由の一つです。
資産の最大化を目指すのであれば、配当再投資型の投資信託や、そもそも配当を出さずに内部で成長を続ける成長株ETFのほうが、税務上も手数料面でも有利な選択肢となるでしょう。
VYMと他の高配当ETF(SPYD・HDV・SCHD)を徹底比較
米国高配当ETFを選ぶ際、VYM以外にもSPYD、HDV、SCHDなどの選択肢があります。
それぞれ特徴が異なるため、どれを選ぶべきか迷ってしまいますよね。
4つのETFを様々な角度から比較して、あなたに最適な高配当ETFを見つけるお手伝いをします。
VYMをおすすめしない理由が分かる配当利回り・増配率比較
まずは最も気になる配当利回りと増配率から比較してみましょう。
| ETF名 | 配当 利回り | 5年平均 増配率 | 配当頻度 |
|---|---|---|---|
| VYM | 2.39% | 3.84% | 年4回 |
| SPYD | 4.44% | 4.42% | 年4回 |
| HDV | 3.21% | 1.95% | 年4回 |
| SCHD | 3.92% | 9.23% | 年4回 |
配当利回りだけ見るとSPYDが4.44%と最も高く、VYMは2.39%と最も低い水準です。
一方、増配率ではSCHDが9.23%と圧倒的に高く、長期的な配当成長を最も期待できます。SPYDも4.42%と堅実な増配を続けています。
VYMは配当利回り・増配率ともに控えめで、高配当を求める投資家にはVYMをおすすめしない理由となります。572銘柄による高い分散効果はありますが、配当収入を重視するなら他のETFの方が魅力的です。
ETFの2〜5倍の配当が期待できる投資商品もあります。
4つのETFを比較しましたが、いずれも配当利回りは5%未満です。配当収入を最優先するなら、年利17.35%(2024年度実績)という圧倒的なパフォーマンスを記録したAction合同会社のような投資先も検討する価値があるでしょう。
構成銘柄とセクター分散を比較
次に、分散投資の観点から構成銘柄数を見てみましょう。
| ETF名 | 構成 銘柄数 | 上位セクター | 特徴 |
|---|---|---|---|
| VYM | 572銘柄 | 金融 (21.15%) | 最も分散が効いている |
| SPYD | 約80銘柄 | 不動産 (21.30%) | REITの比率が高い |
| HDV | 約75銘柄 | 生活必需品 (27.06%) | セクター偏重が目立つ |
| SCHD | 約100銘柄 | エネルギー (19.3%) | 質の高い銘柄に厳選 |
VYMの572銘柄は圧倒的で、リスク分散を重視する投資家には最適です。
SPYDはREIT比率が高いため、不動産市場の影響を受けやすい点に注意が必要です。
ETFを選ぶ際、セクター構成は非常に重要です。特にSPYDの不動産(REIT)比率が高いリスクについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
トータルリターンとボラティリティを比較
配当だけでなく、値上がり益も含めたトータルリターンも重要です。
| ETF名 | 3年 リターン | ボラ ティリティ | 最大下落率 (過去5年) |
|---|---|---|---|
| VYM | 13.62% | 中 | -15% |
| SPYD | 7.55% | 高 | -35% |
| HDV | 8.81% | 中 | -20% |
| SCHD | 6.45% | 低 | -12% |
VYMは配当利回り2.39%と低めながら、トータルリターンでは13.62%と最も高い成績を記録しています。
一方、SCHDは配当利回り3.92%で6.45%とやや劣りますが、ボラティリティが低く、最大下落率も-12%と4つの中で最も小さいため、リスクとリターンのバランスが取れた運用ができています。
SPYDは配当利回りこそ高いですが、値動きが激しく、トータルリターンも劣っています。
安定性を最優先するならSCHD、リターンとのバランスを取るならVYMが適しているでしょう。
投資スタイル別のおすすめETFを比較
最後に、投資スタイルに応じたおすすめETFをまとめます。
| 投資スタイル | おすすめ ETF | 理由 |
|---|---|---|
| 配当重視型 | SPYD | 最高水準の配当利回り |
| 安定運用型 | VYM | 572銘柄による抜群の分散効果 |
| バランス型 | SCHD | 利回りと成長性の両立 |
| セクター集中型 | HDV | エネルギーセクターへの投資 |
どのETFも一長一短があるため、自分の投資目的に合わせて選ぶ必要があります。
複数のETFを組み合わせるのも有効な戦略でしょう。たとえば、VYMで安定性を確保しつつ、SPYDで高配当を狙うといった組み合わせが考えられます。
HDVは約80銘柄と構成銘柄数が少なく、エネルギー・ヘルスケア・生活必需品などのディフェンシブセクターに集中投資する特徴があります。景気後退期に強い反面、成長性では他のETFに劣る傾向があるため、市況に応じて使い分けると良いでしょう。
複数のETFを組み合わせる際、HDVの特性への理解が大切です。HDVの注意点や、おすすめしない理由については、こちらの記事で詳しく解説しています。
VYMの買い方:購入手順を解説
VYMは米国ETFのため、日本の証券会社を通じて購入します。
楽天証券・SBI証券・マネックス証券などの主要ネット証券で取り扱いがあり、新NISA(成長投資枠)でも購入可能です。
VYMを購入する具体的な手順
VYMを購入する基本的な流れは以下の通りです。
- 証券口座を開設する
ネット証券で口座開設を行います。新NISAを利用したい場合は、NISA口座も同時に開設しましょう。 - 日本円を米ドルに両替する
VYMは米ドル建てのため、証券口座内で円を米ドルに両替します。為替手数料は証券会社によって異なります(1ドルあたり0~25銭程度)。 - VYMのティッカーシンボルで検索
取引画面で「VYM」と検索し、銘柄情報を確認します。 - 購入数量と注文方法を選択
購入株数を入力し、成行注文または指値注文を選択します。米国市場の取引時間は日本時間の23:30~翌6:00(夏時間は22:30~翌5:00)です。 - 注文を確定する
注文内容を確認し、発注します。約定後、2営業日後に決済が完了します。
新NISA(成長投資枠)を利用する場合は、注文時に「NISA口座」を選択すると、配当金や売却益が非課税になります。ただし、年間投資枠は240万円までとなります。
VYM購入時に知っておくべき注意点
VYMを購入する際は、以下の点に注意が必要です。
- 為替手数料がかかる
- 為替リスクがある
- 米国市場の取引時間に注意が必要
- 配当金に二重課税がかかる
- 最低購入金額が必要
特に注意すべきは為替手数料と為替リスクです。円から米ドルへの両替時に証券会社によって異なる手数料が発生し、往復の両替で1~2%のコストがかかる場合もあります。
また、VYMは米ドル建てのため、円高になると為替差損が発生します。1ドル150円で購入し、130円になった場合、約13%の損失となるため注意が必要です。
さらに、配当金には米国で10%、日本で約20%の二重課税がかかります。外国税額控除を利用すれば一部取り戻せますが、確定申告が必要になります。米国株式市場は日本時間の深夜に開いているため、リアルタイムで取引したい場合は時間帯にも注意しましょう。
VYMの低利回りに物足りなさを感じるなら「ヘッジファンド」「プライベートデット」
「VYMはおすすめしない」結論に至った方へ、代替案をご提案します。
配当利回り2.39%では物足りない投資家向けに、年利10%超の実績を持つヘッジファンドとプライベートデットファンドが注目されています。
ヘッジファンドやプライベートデットファンドは成功報酬制を採用しており、運用成果を上げなければ収入を得られない仕組みです。
つまり、投資家とファンドの利害が一致しているのが最大の特徴といえるでしょう。
- 成功報酬制
利益が出た時のみ手数料発生
(VYM:運用成績関係なく経費率0.06%) - 高い透明性
運用方針・実績を詳細開示
(VYM:四半期報告のみ) - 圧倒的実績
年利10%以上の実績
(VYM:配当利回り2.39%)
1位:アクション – 年利17.35%の圧倒的実績

アクションは2024年度に年利17.35%の驚異的な成績を達成した新進気鋭のヘッジファンドです。
エンゲージメント投資を通じた企業価値向上の独自手法で、VYMの配当利回りを大幅に上回るリターンを実現しています。
| 比較項目 | アクション | VYM |
|---|---|---|
| 2024年実績 | +17.35% | +2.39%(配当のみ) |
| 手数料体系 | 成功報酬型 | 固定0.06% |
| 運用戦略 | 事業投資+Web3 | パッシブ運用 |
| 分散投資 | 複数事業への配分 | 米国株式のみ |
500万円を投資していれば、86.75万円のリターンを得られた計算になります。
2024年度実績は驚異の年利17.35%
アクションの最大の魅力は、その圧倒的な運用実績です。2024年度に年利17.35%の高いリターンを達成し、日本国内のヘッジファンドの中でもトップクラスの成績を残しています。
投資信託の年利3~5%、VYMの配当利回り2.39%と比較すると、アクションの実績は桁違いの高リターンを実現しています。
もちろん、設立間もないファンドのため長期的な実績はこれからですが、初年度の成果は資産を大きく増やしたい投資家にとって注目に値するでしょう。
- 2024年度実績17.35%
日本国内ヘッジファンドの中でもトップクラス - 2025年度想定12〜17%
安定的に高い水準のリターンを目指す運用方針 - 金融業界30年以上の経験
実力ある運用チームによる高度な投資判断 - 透明性の高い情報開示
役員陣や実績を公式サイトで公開、四半期レポートも実施 - 最低投資額500万円から
比較的参入しやすい金額設定
運用を担うのは、金融業界で30年以上の経験を持つ古橋弘光氏率いるプロフェッショナルチームです。役員陣の経歴や運用実績を公式サイトで公開するなど、透明性の高い運営姿勢も投資家からの信頼を集めています。
多角的な事業投資でリスク分散
アクションのもう一つの特徴は、複数の事業領域に分散投資している点です。
一つの投資手法に依存せず、複数の事業分野に資金を配分して、リスクを分散させながら高いリターンを追求しています。
- 事業投資
暗号資産担保融資、再生可能エネルギー、大型建築施工、先端技術開発(NEDO) - 余剰資金・ファイナンス
流動性確保、短期事業資金貸付、新規案件への迅速対応 - Web3事業
BTC・ETHマイニング、ブロックチェーン技術活用
多角的なアプローチにより、ある投資が不調でも他の投資でカバーできる体制を構築しています。
事業投資を中核としながら、Web3や短期ファイナンスなど多様な投資機会を追求して、安定性と収益性を両立させているのです。
VYMで米国高配当株に投資しながら、日本市場でも高いリターンを狙いたい方や、配当ETFとは異なる投資戦略でポートフォリオを多様化したい方にとって、アクションのような個人投資家が参加できる国内ヘッジファンドは有力な選択肢となるでしょう。
ただし、出資した資金は原則1年間のロックアップ期間があるため、余剰資金での投資が推奨されます。興味がある場合は、公式サイトから無料面談を申し込んで詳しい説明を受けてみましょう。
アクション合同会社について詳しくは下記の記事も参考にしてください。
2位:ハイクアインターナショナル – 年利12%固定の安定運用
プライベートデットファンドは、企業への事業融資を通じて安定収益を狙う運用手法です。
国内では「ハイクアインターナショナル」が代表的な存在で、年間12%(固定)の配当を実現しています。
| 項目 | ハイクア インターナショナル | VYM |
|---|---|---|
| 期待利回り | 年12%(固定) | 2.39%(変動) |
| 手数料 | 完全無料 | 年0.06% |
| 配当頻度 | 3ヶ月毎3% | 四半期配当 |
| 最低投資額 | 500万円 | 制限なし |
| 運用の安定性 | 事業融資で安定 | 株価変動の影響大 |
年利12%固定の高利回り
ハイクアの最大の特徴は、年利12%の高水準固定リターンを目指している点です。
投資信託の年利3~5%や定期預金の0.1%と比較すると、圧倒的に高い利回りを実現しています。しかも株式市場の値動きに左右されない安定した収益構造を持つため、長期的な資産形成に適しています。
株式投資と異なり、企業が売上を出せば利息が得られるため、リターンまでの過程がシンプルで直接的です。
市場の値動きに一喜一憂する必要がなく、3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回の分配金が支払われる定期的なキャッシュフローも大きなメリットとなっています。
- 市場変動に左右されない
株価暴落時でも安定した利回りを確保 - 株価変動リスクがない
事業融資型なので株式市場の影響を受けない - 定期的なキャッシュフロー
3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回の分配金 - シンプルな収益構造
企業の売上から直接利息を得る仕組み - 高い透明性と信頼性
投資先の事業内容が明確で追跡可能 - 最低投資額500万円から
ポートフォリオに組み込みやすい金額設定
代表者が情報開示に積極的で、出資前に無料面談が可能、出資後も事業報告会があるなど透明性も高い運営体制となっています。
投資判断に必要な情報がしっかりと提供される環境は、投資家にとって大きな安心材料といえるでしょう。
ベトナム市場の成長性
ハイクアが投資対象とするベトナムは、アジアの中でも特に高い成長率を誇る新興国です。
年間6〜7%の経済成長を継続しており、若い労働力と政治的安定性が経済発展を後押ししています。
投資先の「SAKUKO Vietnam」は、ベトナム国内で確固たる事業基盤を築いており、ベトナム成長市場の恩恵を直接受けられる環境にあります。
先進国市場が成熟し、日本経済も低成長が続く中、ベトナムのような成長市場への投資は、ポートフォリオ分散の観点からも有効な戦略です。
- 高い経済成長率
年間6〜7%の安定した成長を継続中 - 若く活力ある労働力
平均年齢約32歳、人口約1億人の内需拡大の潜在力 - 製造業の集積地
「世界の工場」として外資企業の進出が活発化
国内の投資信託や株式だけでなく、成長市場への分散投資を検討している方にとって、ハイクアは魅力的な選択肢となるでしょう。
VYMの配当利回り2.39%に物足りなさを感じている方や、米国株式市場以外への分散投資を検討している方にとって、ハイクア・インターナショナルのような個人投資家が参加できる国内プライベートデットファンドをポートフォリオに組み込むのは有効な戦略と言えるでしょう。
まずは無料の資料請求で詳細な投資条件をご確認ください。年利12%の安定した固定リターンを実現する投資モデルの仕組みや、ベトナム市場の成長性について詳しく知れます。
ハイクアインターナショナルについて、詳しくは下記の記事も参考にしてください。
投資額別シミュレーション比較
実際の投資額で比較すると、代替投資先の優位性がより明確になります。
| 運用先 | 500万円 (5年後) | 1000万円 (5年後) | 2000万円 (5年後) |
|---|---|---|---|
| VYM | 約580万円 | 約1,160万円 | 約2,320万円 |
| ハイクア | 約880万円 | 約1,760万円 | 約3,520万円 |
| アクション | 約1,086万円 | 約2,172万円 | 約4,344万円 |
※VYMは配当+株価成長を含めた年利3%で試算。ハイクアは年利12%固定、アクションは2024年実績17.35%が継続した場合の試算
差額を見れば、「VYMはおすすめしない?」と疑問を持たれる理由が明確に理解できるでしょう。
VYMをおすすめしない理由に関するよくある質問
VYMに関してよく寄せられる質問をまとめました。
投資を検討している方の参考になれば幸いです。
まとめ
「VYMはおすすめしない?」の疑問に答えるため、以下のデメリットを解説してきました。
- VYM配当利回りが2.39%と高配当ETFの中では低めである
- 配当の自動再投資ができない
- 大きなキャピタルゲインが期待できない
- 税金手続きが煩雑 など
しかし、572銘柄への分散投資による安定性や、0.06%の低コストで運用できる点、13年連続増配の実績は大きな魅力です。
本格的に資産を増やしたい方には、17.35%超の実績があるアクションや、年利12%のハイクアインターナショナルといったヘッジファンドをおすすめします。
アクションやハイクアは最低投資額500万円~1000万円と高額ですが、VYMとは比較にならない高いリターンを期待できます。
ヘッジファンドに興味を持たれた方は、まずは年利17.35%実績のあるアクションから検討を始めてみてはいかがでしょうか。
投資に正解はありません。VYMの安定性を取るか、ヘッジファンドの高成長性を取るか、自分の目的やリスク許容度に合わせて最適な投資先選びが成功への第一歩となるでしょう。