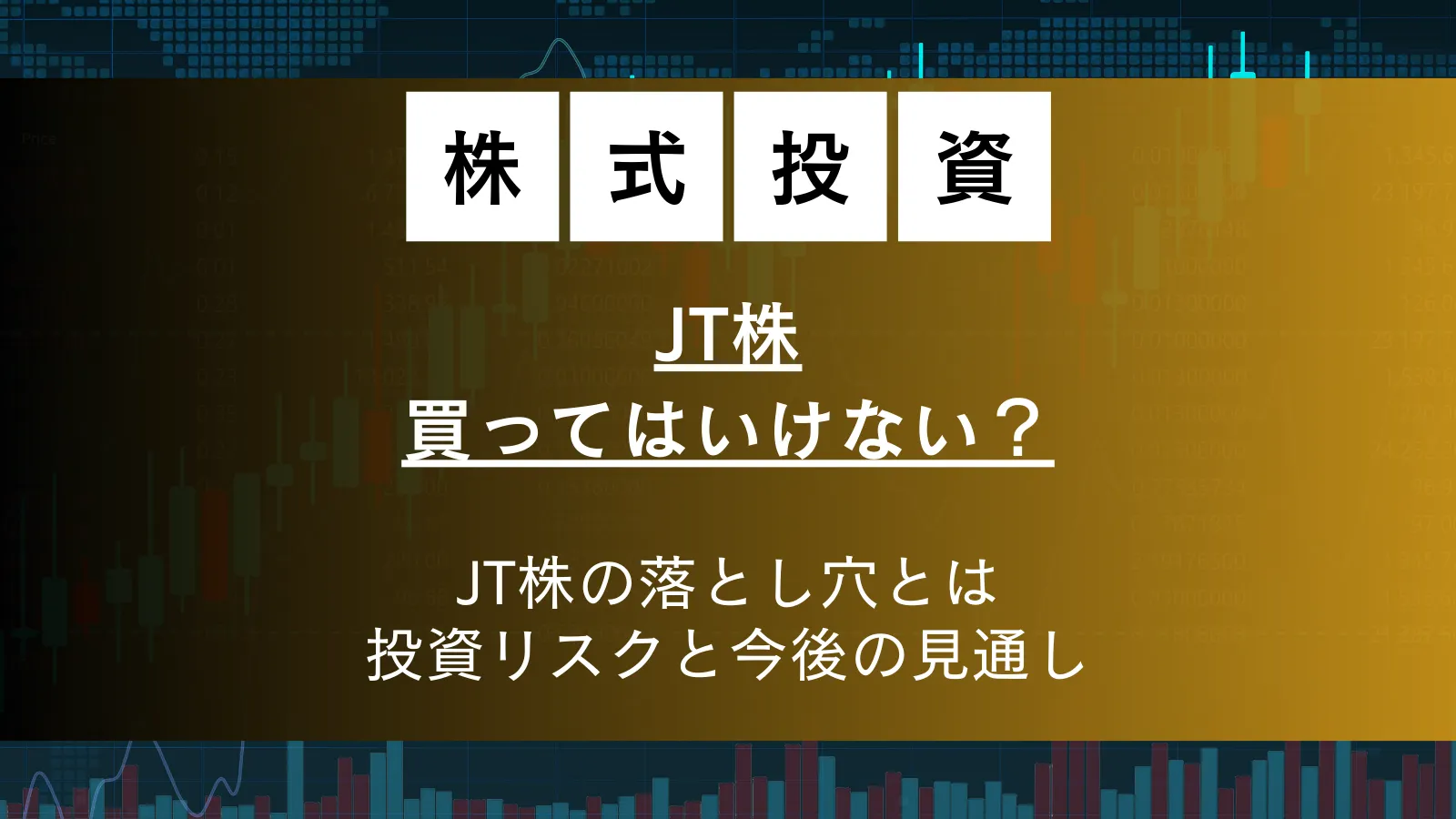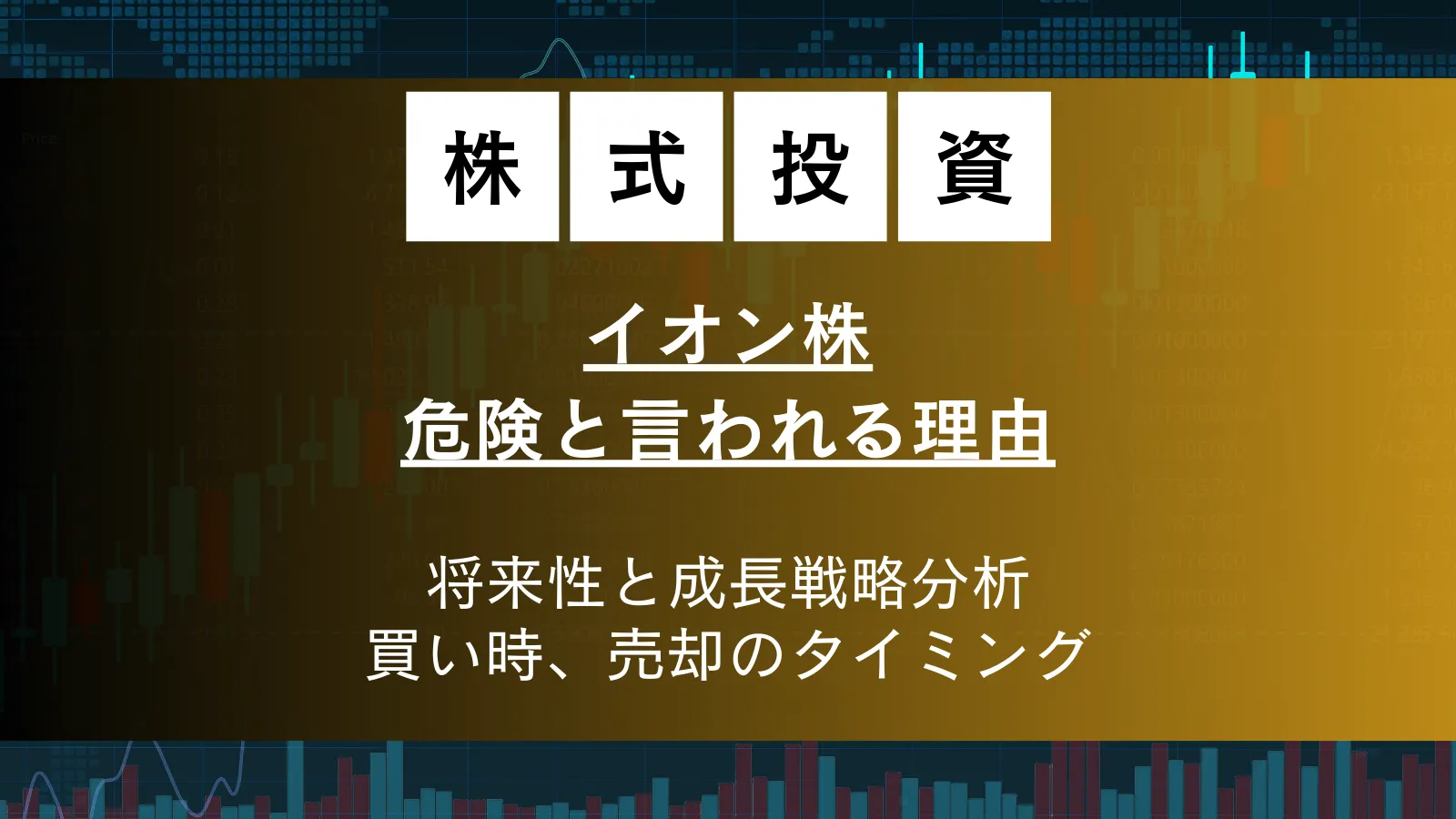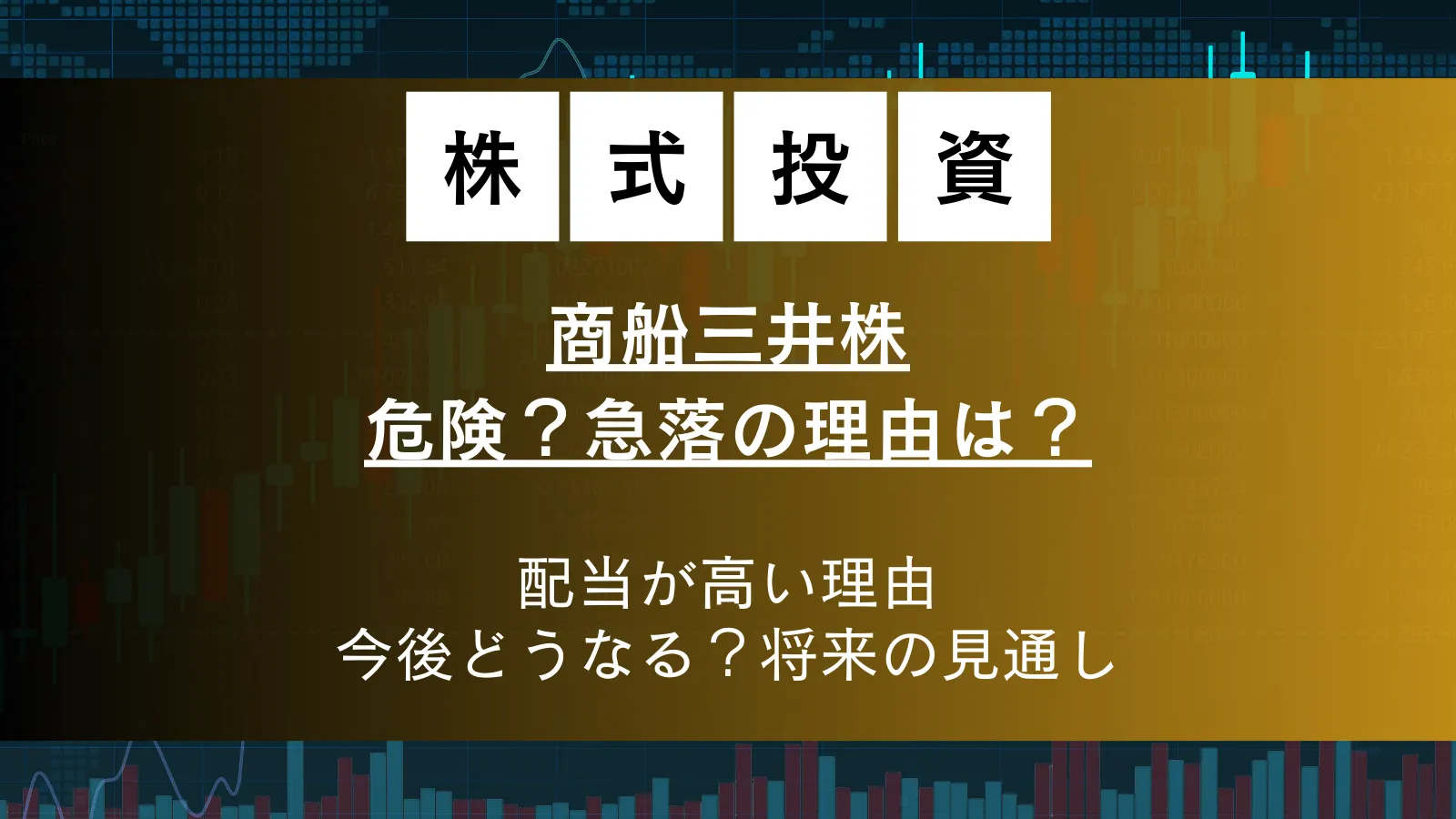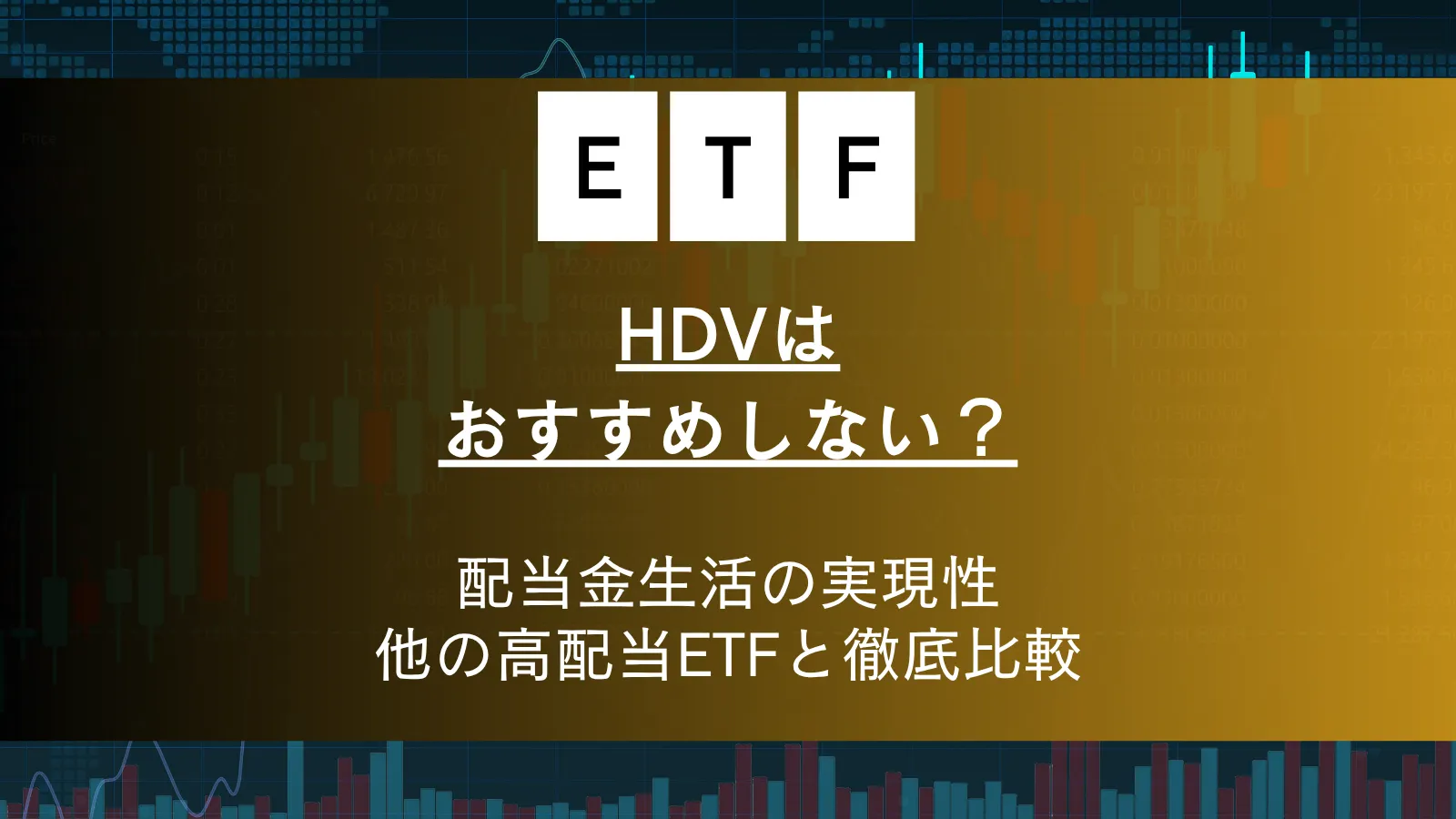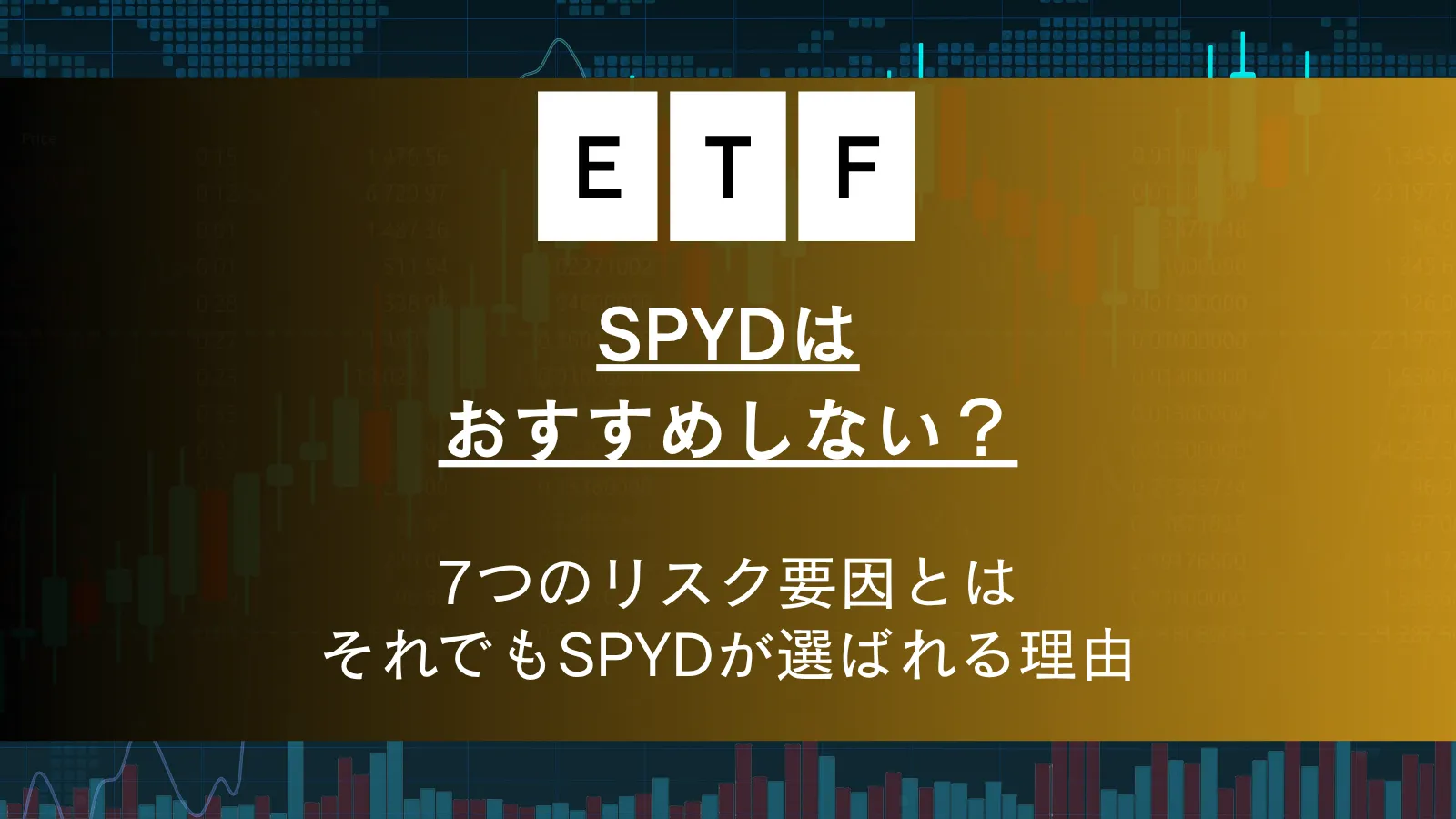VIG(バンガード米国増配株式ETF)について「おすすめしない」という声を聞いたことはありませんか?
実際、投資家コミュニティでは「VIGはおすすめしない」「配当利回りが低すぎる」といった否定的な意見が目立ちます。
特に配当利回りが約1.58%と他の高配当ETFと比べて明らかに低いことが、多くの投資家を失望させているのです。
しかし、VIGには10年以上連続増配という厳格な選定基準があり、安定性を重視する投資家から支持されているのも事実です。
この記事では、VIGをおすすめしないと言われる理由を徹底的に検証し、メリットやデメリット、他のETFとの比較まで詳しく解説していきます。
VIG(バンガード米国増配株式ETF)の基本情報と特徴
VIG(バンガード米国増配株式ETF)は、バンガード社が運用する米国の増配株に投資するETFです。
S&P US Dividend Growers Indexという指数への連動を目指しており、単なる高配当株への投資とは一線を画しています。
最大の特徴は10年以上連続で増配を続けている企業のみを投資対象にしている点でしょう。
この厳しい基準をクリアした約300銘柄で構成されています。
経費率はわずか0.06%と、数あるETFの中でもトップクラスの低コストを実現しています。
ただし、2026年時点での分配金利回りは1.58%程度にとどまっており、高配当を期待する投資家からは物足りないという声も聞かれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用会社 | バンガード社 |
| 設定日 | 2006年4月 |
| 経費率 | 0.06% |
| 分配金利回り | 約1.58% |
| 構成銘柄数 | 約300銘柄 |
| 連動指数 | S&P US Dividend Growers Index |
VIGは増配の継続性を最重視するため、財務体質が健全で業績が安定した企業が中心となります。
このような特性から、配当狙いというより長期的な資産形成を目指す投資家に適したETFといえるでしょう。
VIGをおすすめしないと言われる5つの理由
ネット上では「VIGはおすすめしない」「やめとけ」という否定的な意見が散見されます。
実際に投資家たちがVIGに対して不満を持つ理由は何なのでしょうか。
ここでは主要な5つの理由を詳しく見ていきましょう。
配当利回りの低さが投資家を失望させる
VIGへの批判で最も多いのが、配当利回りの低さです。
| ETF | 配当利回り(2026年) |
|---|---|
| VIG | 1.58% |
| QYLD | 11.97% |
| JEPI | 7.54% |
| SPYD | 4.45% |
| VYM | 2.38% |
退職後の生活費として配当収入を期待している投資家や、定期的なキャッシュフローを求める人にとって、VIGの利回りは物足りないでしょう。
「せっかく投資するなら、もっと高い配当がほしい」というのが正直な感想かもしれません。
VIGの低利回りに不満を感じる方は、年利10%以上を目指す高利回り投資も検討する価値があるでしょう。
株価の高さが投資の障壁となる
VIGの株価は2026年時点で約218ドル(約33,000円)となっています。
これは初心者投資家にとってかなり高いハードルといえるでしょう。
米国ETFは1株単位での購入が基本なので、毎月の積立投資をするにも相当な資金が必要になります。
さらに、ドルコスト平均法での定額積立も困難です。
ETFの性質上、決まった金額での購入ができないため、投資計画が立てにくいという問題があります。
少額から始めたい投資家にとって、VIGの高い株価は大きな壁となっているのが現実です。
厳しすぎる銘柄選定基準が問題となる
VIGの選定基準である「10年以上連続増配」というルールは、あまりにも厳格すぎるという批判があります。
一度でも配当を減らした企業は、たとえ優良企業であっても容赦なく除外されてしまうのです。
コロナ禍のような特殊な状況で一時的に配当を維持できなかった企業も、問答無用で投資対象から外されることになります。
実際、フェデックスやディズニーといった有名企業も、配当減額により除外された後、株価が大きく上昇したケースがありました。
「一回の失敗で終わり」という厳しすぎるルールが、かえって投資チャンスを逃しているのではないでしょうか。
高配当銘柄を除外する方針が不満を生む
VIGは意図的に上位25%の高配当企業を除外する方針をとっています。
これは「過度に高い配当を出す企業はリスクが高い」という考えに基づいているようです。
しかし、高配当を求める投資家からすれば、わざわざ高配当銘柄を避けるETFに投資する意味が見出しにくいのも事実でしょう。
短期的な配当収入を重視する人にとって、この方針は理解しがたいものかもしれません。
「高配当がほしいのに、なぜ高配当銘柄を除外するの?」という素朴な疑問は当然といえます。
成長性と配当のバランスが中途半端になる
VIGは成長株と高配当株の中間的な位置づけとなっており、どちらの魅力も中途半端という指摘があります。
2026年最新データを見ると、5年トータルリターンではVYM(14.40%)やSPYD(13.64%)に対してVIGは12.47%と、同じ配当系ETFの中でも劣後しています。
株価の上昇を狙うならグロース株ETFの方が期待できますし、配当とリターンの両方を狙うなら現時点ではVYMの方が効率的です。
VIGの「どっちつかず」な特性が、投資家を悩ませる要因となっています。短中期(5年)のパフォーマンスでは他の選択肢に見劣りし、超長期(10年以上)での増配効果を待つ必要があるためです。
投資の目的を明確にしたい人にとって、VIGのポジショニングは曖昧に感じられるかもしれません。
より明確な収益目標を持ちたい方は、プロが運用する年利10%超の投資手法との比較も参考になります。
安定性×低コストで注目のVIGの投資メリット
ここまでVIGの欠点ばかり見てきましたが、実は多くのメリットも存在します。
特に長期投資を考える人にとって、VIGの持つ強みは見逃せません。
ここでは主要な5つのメリットを詳しく解説していきましょう。
長期的な安定性が確保されている
VIGの最大の魅力は、なんといっても優れた安定性にあります。
10年以上連続で増配を続けている企業だけで構成されているため、財務基盤がしっかりした優良企業への投資が可能となるのです。
増配を長期間継続するには、安定した業績と健全な財務状況が不可欠です。
つまり、VIGの構成銘柄は自然と「倒産リスクの低い安全な企業」が集まることになります。
投資初心者でも安心して長期保有できるという点で、VIGは優れた選択肢といえるでしょう。
業界最低水準の経費率が魅力的である
バンガード社の強みである低コスト運用は、VIGでも健在です。
経費率はわずか0.06%と、業界でもトップクラスの低さを誇ります。
| ETF | 経費率 | 100万円運用時 の年間コスト |
|---|---|---|
| VIG | 0.06% | 約600円 |
| VYM | 0.06% | 約600円 |
| JEPI | 0.35% | 約3,500円 |
| PFF | 0.46% | 約4,600円 |
| QYLD | 0.61% | 約6,100円 |
- 複利効果を最大化
経費が少ないほど再投資に回せる金額が増える - 30年で数百万円の差
0.06%と0.61%では約165万円の差 - 毎年確実に発生
市場の上下に関係なく必ず引かれるコスト - 見えないコスト
基準価額から自動的に差し引かれるため気づきにくい
長期投資において、この経費率の差は最終的なリターンに大きな影響を与えます。たとえば100万円を30年間運用した場合、経費率の差だけで数十万円から百万円以上の違いが生まれることもあるのです。
優れた分散投資効果が期待できる
VIGは約300銘柄で構成されており、リスク分散の面でも優れています。
一つの企業が減配したり、業績が悪化したりしても、全体への影響は最小限に抑えられるのです。
個別株投資では、このレベルの分散投資を実現するのは困難でしょう。
VIG一つ買うだけで、米国の優良企業300社に分散投資できるのは大きな魅力です。
投資初心者や、個別株の分析に時間をかけられない人にとって、この分散効果は心強い味方となります。
増配による長期的な資産成長が見込める
VIGは短期的なリターンでは他のETFに劣るものの、増配による長期的な複利効果が期待できます。
5年トータルリターンではVYM(14.40%)に対してVIG(12.47%)と約2ポイント劣後していますが、VIGの真価は年率約8%という高い配当成長率にあります。
連続増配企業は基本的に成長力があり、10年、20年という超長期スパンでは株価上昇と増配の相乗効果が期待できるとされています。
ただし、現時点での実績データは5年分しかないため、この仮説が実証されるには今後のパフォーマンスを注視する必要があります。
下落相場での強い耐性を持っている
市場が下落する局面で、VIGは他のETFより下落率が低い傾向があります。
連続増配企業は財務基盤が安定しているため、市場の混乱時でも比較的安定したパフォーマンスを示すのです。
2022年の下落局面では、VOOが-23.0%下落したのに対し、VIGは-19.1%の下落にとどまりました。
この差は一見小さく見えるかもしれませんが、長期投資においては大きな違いとなります。
リスクを抑えながら着実に資産を増やしたい投資家にとって、VIGの下落耐性は重要なメリットといえるでしょう。
VIGと高配当ETFの比較一覧表
VIGの真の実力を見極めるため、人気の高配当ETFと最新データで比較してみましょう。
配当利回りだけでなく、実際の運用成果である5年トータルリターンや経費率など、投資判断に欠かせない指標を一覧にまとめました。
| ETF名 | 配当利回り | 経費率 | 5年トータル リターン | 構成銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 1.58% | 0.06% | 12.47% | 約300 |
| VYM | 2.38% | 0.06% | 14.40% | 約400 |
| SPYD | 4.45% | 0.07% | 13.64% | 約80 |
| HDV | 3.12% | 0.08% | 12.24% | 約75 |
| QYLD | 11.97% | 0.61% | 8.26% | 約100 |
| JEPI | 7.54% | 0.35% | 10.36% | 約100 |
最新データを見ると、VIGの配当利回りは1.58%と確かに控えめです。
しかし注目すべきは、5年トータルリターンでVYMが14.40%と最高値を記録している点です。VIGは12.47%と2番目のSPYD(13.64%)に次ぐ3位となっています。
一方、最も配当利回りが高いQYLD(11.97%)は、5年リターンが8.26%と最下位レベルです。これは「高配当=高リターン」ではないことを示しています。
経費率では、VIGとVYMがともに0.06%と最低水準を維持しており、長期投資におけるコスト優位性が際立ちます。
VYMとの詳細比較
VYM(バンガード米国高配当株式ETF)は、VIGと同じバンガード社が運用する人気の高配当ETFです。
2026年最新データでは、配当利回りがVYMの2.38%に対してVIGは1.58%と、約0.80ポイントの差があります。
さらに注目すべきは、5年トータルリターンでもVYMが14.40%とVIGの12.47%を上回っている点です。この結果は、「VIGが総合パフォーマンスで必ず勝る」という従来の評価を覆すものといえます。
VYMは約400銘柄と分散度も高く、配当・リターンの両面でバランスの取れた選択肢として再評価されています。
現時点のデータでは、短中期(5年)ならVYM、超長期(10年以上)の増配成長を狙うならVIGという選択が妥当でしょう。
一方で、VYMにも注意すべき点があります。VYMのデメリットや隠れたリスクを知りたい方は、こちらの徹底解説記事もご覧ください。
SPYDとHDVとの詳細比較
SPYD(S&P500高配当株ETF)とHDV(iShares高配当ETF)は、どちらも配当重視型のETFです。
配当利回りを見ると、SPYDが4.45%、HDVが3.12%と、VIGの1.58%の約2〜3倍の水準となっています。
興味深いのは5年トータルリターンです。SPYDは13.64%とVIGの12.47%を上回るパフォーマンスを記録しています。一方、HDVは12.24%とVIGとほぼ同水準です。
つまり、過去5年間に限れば「高配当ETFの方がリターンも配当も高い」という結果が出ています。ただし、SPYDは約80銘柄と集中度が高く、景気変動による値動きの大きさには注意が必要です。
長期投資においては、5年という短期データだけでなく、10年以上の実績や下落耐性も考慮すべきでしょう。VIGの真価は、市場の浮き沈みを経た超長期で発揮される可能性があります。
長期視点では高配当ETFのリスクも検証が必要です。HDVの配当利回りの限界や、さらにSPYDをおすすめしない理由も確認しておきましょう。
VIGの実際の運用パフォーマンスを検証
数字で見るVIGの実力はどの程度なのでしょうか。
ここでは過去の運用実績から、VIGの本当のパフォーマンスを検証していきます。
過去5年間のトータルリターンを分析
VIGの5年間のトータルリターンは12.47%という成績を記録しています。
これは100万円を投資していたら、5年後には約162万円になっている計算です(年平均リターン約12.5%)。
| ETF | 5年リターン | 100万円 →5年後 |
|---|---|---|
| VYM | 14.40% | 約197万円 |
| SPYD | 13.64% | 約185万円 |
| VIG | 12.47% | 約162万円 |
| HDV | 12.24% | 約161万円 |
同じ配当系ETFと比較すると、VIGは3位という結果です。トップのVYMとは約35万円の差が生まれており、「トータルリターンで優位」という従来の評価は、少なくとも直近5年間では当てはまりません。
ただし、これは5年という比較的短い期間のデータです。VIGの増配戦略が真価を発揮するのは10年、20年という超長期とされており、今後の追跡が必要です。
短中期でより高いリターンを求める方には、年利10%以上の実績を持つファンドという選択肢もあります。
ボラティリティとリスク調整後リターンを評価
投資のリスクを示すボラティリティの面でも、VIGは優れた特性を示しています。
価格変動の幅が比較的小さく、安定した値動きが特徴的です。
リスク調整後リターンで評価すると、VIGの魅力がより明確になります。
つまり、取ったリスクに対して得られるリターンの効率が良いということです。
安定志向の投資家にとって、この低ボラティリティは大きな魅力となるでしょう。
配当成長率の推移を確認
VIGの配当は着実に成長を続けています。過去10年間の平均配当成長率は年率約8%という高い水準を維持しています。
| 投資年 | 初期利回り | 5年後YOC | 10年後YOC |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 1.58% | 2.32% | 3.41% |
| 年間成長率 | — | 8.0% | 8.0% |
現在の配当利回りは低くても、この成長率が続けば将来的には魅力的な配当収入が期待できます。たとえば、今1.58%の利回りでも、10年後には購入価格に対して3.41%の利回りになる可能性があるのです。
YOC(Yield On Cost)の観点から見れば、早期に投資した人ほど有利になる仕組みといえるでしょう。
VIGが向いている投資家・向いていない投資家の特徴
VIGは万人向けのETFではありません。
投資目的や資金力によって、向き不向きがはっきり分かれます。
自分がどちらのタイプに当てはまるか、確認してみましょう。
VIGをおすすめできる投資家の条件
VIGが最も適しているのは、20年以上の超長期的な資産形成を目指す投資家です。
5年という短中期ではVYMやSPYDに劣後するデータが出ていますが、年率約8%の配当成長が長期間続けば、トータルでの優位性が期待できます。
- 20年以上の超長期投資を前提にできる
- 短期リターンより増配による複利効果を重視
- 市場の浮き沈みに動じないメンタルの強さがある
- 低ボラティリティと安定性を最優先する
- 配当額より配当成長率に魅力を感じる
個別株分析に時間をかけられない人や、投資初心者でも安心して保有できるのがVIGの魅力です。ただし、「今すぐ高リターン」を求める人には不向きであることを理解すべきです。
VIGを避けるべき投資家の特徴
高い配当収入を最優先する投資家には、VIGはおすすめできません。
1.58%程度の利回りでは、生活費の足しにするには物足りないでしょう。
少額から投資を始めたい人にも不向きです。株価が約218ドル(約33,400円)と高いため、まとまった資金が必要になります。
5〜10年程度の中期投資を考えている人も要注意です。現在のデータでは、この期間ならVYMやSPYDの方が配当・リターンともに優れているためです。
短期的な利益を求める投資家にとっても、VIGの成長スピードは遅すぎるでしょう。
このような投資家には、市場環境に左右されにくい絶対収益型投資が適しているかもしれません。
VIGより高リターンが期待できる資産運用方法
VIGの安定性は魅力的ですが、もっと高いリターンを求める投資家もいるでしょう。
ここでは、VIGを上回る収益が期待できるオルタナティブ投資について紹介します。
オルタナティブ投資の魅力
オルタナティブ投資とは、株式や債券といった伝統的資産以外への投資を指します。
不動産、コモディティ、プライベートエクイティ、ヘッジファンドなどが代表例で、従来の株式・債券とは異なるリターン源泉を持つのが特徴です。
オルタナティブ投資の最大の魅力は、株式市場との相関が低く、分散効果が高い点にあります。
- 分散効果
株式市場の下落時もポートフォリオ全体を守る - 高い収益性
VIGの1.58%を大きく上回る年利8〜20%も可能 - インフレ対策
不動産やコモディティは物価上昇に強い - 絶対収益追求
市場の上下に関係なく利益を狙える商品も
たとえば不動産投資信託(REIT)なら、賃料収入による3〜5%の安定配当が期待できます。金や原油などのコモディティは、インフレ対策としても有効です。
VIG一本に頼るより、これらの資産クラスを組み合わせることで、リスクを抑えながら高いリターンを狙える可能性があります。
以下では、特におすすめの2つを具体的なファンド名とともに紹介しましょう。
プライベートデットファンド
プライベートデットファンドは、オルタナティブ投資の中でも安定性と高利回りを両立できる選択肢です。
非上場企業への融資で年利8~12%の安定収益を狙います。銀行融資を受けにくい成長企業や中小企業に直接融資することで、高い金利収入を得る仕組みです。
株式市場の変動に左右されにくく、毎月または四半期ごとに安定したインカムゲインが期待できます。VIGの配当利回り1.58%と比べると、5〜7倍以上の収益性があるのは大きな魅力でしょう。
| 項目 | プライベートデット | VIG |
|---|---|---|
| 期待利回り | 8〜12% | 1.58% |
| 収益の安定性 | 高い(契約ベース) | 中(市場次第) |
| 市場変動の影響 | 小さい | 大きい |
| 最低投資額 | 500万円〜 | 約33,000円 |
| 流動性 | 低い | 高い |
機関投資家向けの商品でしたが、最近は個人投資家向けのファンドも増えてきています。その中でも特に注目されているのが「ハイクアインターナショナル」です。
ハイクアインターナショナル
| 運用会社 | 合同会社 ハイクア・インターナショナル |
|---|---|
| 設立 | 2023年 |
| 本社所在地 | 日本(大阪) |
| 主な投資対象 | SAKUKO VIETNAM (ベトナム企業) |
| 主な投資戦略 | 事業融資 |
| 年間期待利回り | 年利12% |
| 最低投資金額 | 500万円 |
| 運用の相談 | 資料請求・面談 |
| 公式サイト | ハイクア・インターナショナル |
ハイクア・インターナショナルは年利12%の固定リターンを目標とする、安定性を重視したヘッジファンドです。
ベトナムの成長企業「SAKUKO Vietnam」への事業融資により、市場変動に左右されにくい収益構造を実現しています。
- 年利12%固定の高利回り
市場変動に左右されない安定収益 - 株価変動リスクがない
事業融資型なので株式市場の影響を受けない - 高い透明性と信頼性
投資先の事業内容が明確で追跡可能 - 成長市場での運用
ベトナムは年間5~6%の経済成長を継続中 - 定期的なキャッシュフロー
3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回の分配金 - 最低投資額500万円から
他のヘッジファンドより参入しやすい
最低投資額が500万円とヘッジファンドとしては比較的低く、ポートフォリオに組み込みやすいのが特徴です。
株式投資と異なり、企業が売上を出せば利息が得られるため、リターンまでの過程がシンプルで直接的です。
代表者が情報開示に積極的で、出資前に無料面談が可能、出資後も事業報告会があるなど透明性も高いと言えます。
VIGのような公募ETFと比べると流動性は低くなりますが、安定した高利回りを求める投資家にとっては検討に値する選択肢といえるでしょう。
まずは無料の資料請求で詳細な投資条件をご確認ください。年利12%の安定した固定リターンを実現する投資モデルの仕組みを詳しく知ることができます。
ハイクアインターナショナルについて詳しくは下記の記事も参考にしてください。
ヘッジファンド
ヘッジファンドは、オルタナティブ投資の中でも最も高いリターンを狙える選択肢です。
年利10~20%のリターンを狙える投資先として、富裕層や機関投資家を中心に注目されています。
市場の上下に関係なく収益を追求する「絶対収益型」の運用が特徴で、株式の売り(ショート)やデリバティブ、裁定取引など、高度な投資戦略を駆使します。
| 項目 | ヘッジファンド | VIG |
|---|---|---|
| 期待リターン | 10〜20% | 1.58%+値上がり |
| 下落相場での対応 | プラスも可能 | マイナスになる |
| 運用戦略 | 多様(ロング・ショート等) | 株式ロングのみ |
| 最低投資額 | 500万円〜 | 約33,000円 |
| 透明性 | 低い | 高い |
2022年の株式市場下落局面では、多くのヘッジファンドがプラスのリターンを達成し、VIG(-19.1%)との大きな差を見せました。
プロの運用チームが市場の歪みを見つけ出し、VIGでは不可能なレベルの収益を目指します。日本の個人投資家でも投資可能なファンドの中で、特に実績のある「アクション」を紹介します。
アクション

| 運用会社 | Action合同会社 |
|---|---|
| 設立 | 2023年 |
| 本社所在地 | 日本(東京) |
| 主な投資対象 | 日本株・事業投資・Web3事業・ファクタリングなど |
| 主な投資戦略 | ・株式の成長投資戦略 ・エンゲージメント、アクティビスト投資戦略 ・ポートフォリオ投資戦略 |
| 利回り | 17.35%(2024年度実績) |
| 最低投資金額 | 500万円 |
| 運用の相談 | 面談 |
| 公式サイト | アクション |
2024年に年利17.35%の実績を残したアクション合同会社は、より高いリターンを求める方におすすめです。
- 圧倒的な運用実績
(※2024年度は年利17.35%) - 金融業界経験30年以上の実力ある運用チーム
- 多角的な投資でリスク分散
(株式、不動産、債券、ファクタリング、Web3事業など) - 最低投資額500万円から
- ロックアップは1年間あり
アクション合同会社は、バリュー株投資に加え、事業融資、Web3、ファクタリング、ESGなど多様な投資戦略を採用し、年間12〜17%以上(2024年度実績は+17.35%)のリターンを目指すヘッジファンドです。
最低投資額が500万円とヘッジファンドとしては比較的低く、役員陣や実績を公式サイトで公開するなど透明性が高いのが特徴です。
出資した資金は1年間のロックアップ期間があるため、余剰資金での投資が推奨されます。
VIGのような公募ETFと比べると透明性も低くなりますが、絶対収益を追求し市場の上下に左右されたくない投資家にとっては、魅力的な選択肢といえるでしょう。
興味がある場合は、公式サイトから無料面談を申し込むことで詳しい説明を受けてみましょう。
アクション合同会社について詳しくは下記の記事も参考にしてください。
VIGの将来性と今後の投資戦略
VIGへの投資を検討する上で、将来性は重要な判断材料となります。
現在の低い配当利回りが将来どう変化するか、市場環境の変化にどう対応できるか、詳しく見ていきましょう。
将来的な高配当化への期待度を検証
VIGの最も注目すべき点は、将来的な高配当化への期待です。
現在は配当利回り1.58%、5年リターンも12.47%とVYMに劣っていますが、年率約8%の配当成長が続けば、長期的には逆転する可能性があります。
YOC(Yield On Cost)という考え方で見ると、早期に投資した人ほど有利になります。
| 投資時期 | 初期利回り | 10年後YOC | 20年後YOC |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 1.58% | 3.41% | 7.35% |
| 年間成長率 | — | 8.0% | 8.0% |
たとえば今100万円投資して、配当が年8%ずつ成長すれば、20年後の実質利回りは約7.35%まで上昇する計算です。
ただし、これはあくまで「年8%の増配が20年間続く」という楽観的シナリオです。現時点では、5年スパンでVYMに劣後している事実を直視すべきでしょう。
超長期保有を前提とし、短中期のパフォーマンス劣後を受け入れられる投資家のみ、VIGの将来性に賭ける価値があるでしょう。
20年待てない方や、より確実な収益を求める方は、年利10%以上の安定運用を実現する投資手法も比較検討してください。
市場環境変化への対応力を分析
市場環境が変化しても、VIGは比較的安定したパフォーマンスを維持する傾向があります。
| 市場環境 | VIGへの影響 | 理由 |
|---|---|---|
| 金利上昇局面 | 相対的に安定 | 成長株より影響小 |
| 金利低下局面 | 追い風 | 配当株への注目高まる |
| インフレ環境 | プラス | 価格転嫁力のある企業が多い |
| 景気後退期 | 下落耐性高 | 財務健全性の高い企業構成 |
金利上昇局面では成長株が売られやすくなりますが、VIGの連続増配企業は相対的に安定しています。
どのような市場環境でも一定のパフォーマンスが期待できる点は、VIGの大きな強みといえるでしょう。
よくある質問
VIGに関してよく寄せられる質問をまとめました。
投資判断の参考にしてください。
まとめ
VIGが「おすすめしない」と言われる最大の理由は、配当利回りの低さ(1.58%)と株価の高さ(約218ドル)、そして短中期リターンの物足りなさにあります。
2026年最新データでは、5年トータルリターンがVYM(14.40%)やSPYD(13.64%)に対してVIGは12.47%と劣後しており、「トータルリターンで優位」という従来の評価は見直しが必要です。
しかし、VIGには見逃せないメリットもあります。0.06%という業界最低水準の経費率、約300銘柄による優れた分散効果、そして年率約8%という高い配当成長率です。
VIGは万人向けのETFではありません。高配当を求める人や5〜10年の中期投資を希望する人には不向きですが、20年以上の超長期で増配効果を享受したい投資家には検討の価値があります。
- 5〜10年の投資期間
VYMまたはSPYDの方が実績面で優位 - 20年以上の超長期
VIGの増配効果に期待できる可能性あり - 配当重視
VYM、SPYD、HDVが選択肢 - 増配成長重視
VIGの独自性が活きる
最終的には、あなたの投資期間、目的、リスク許容度に応じて判断することが大切です。
VIG以外の選択肢も知りたい方は、年利8〜17%を目指すオルタナティブ投資の詳細もご確認ください。