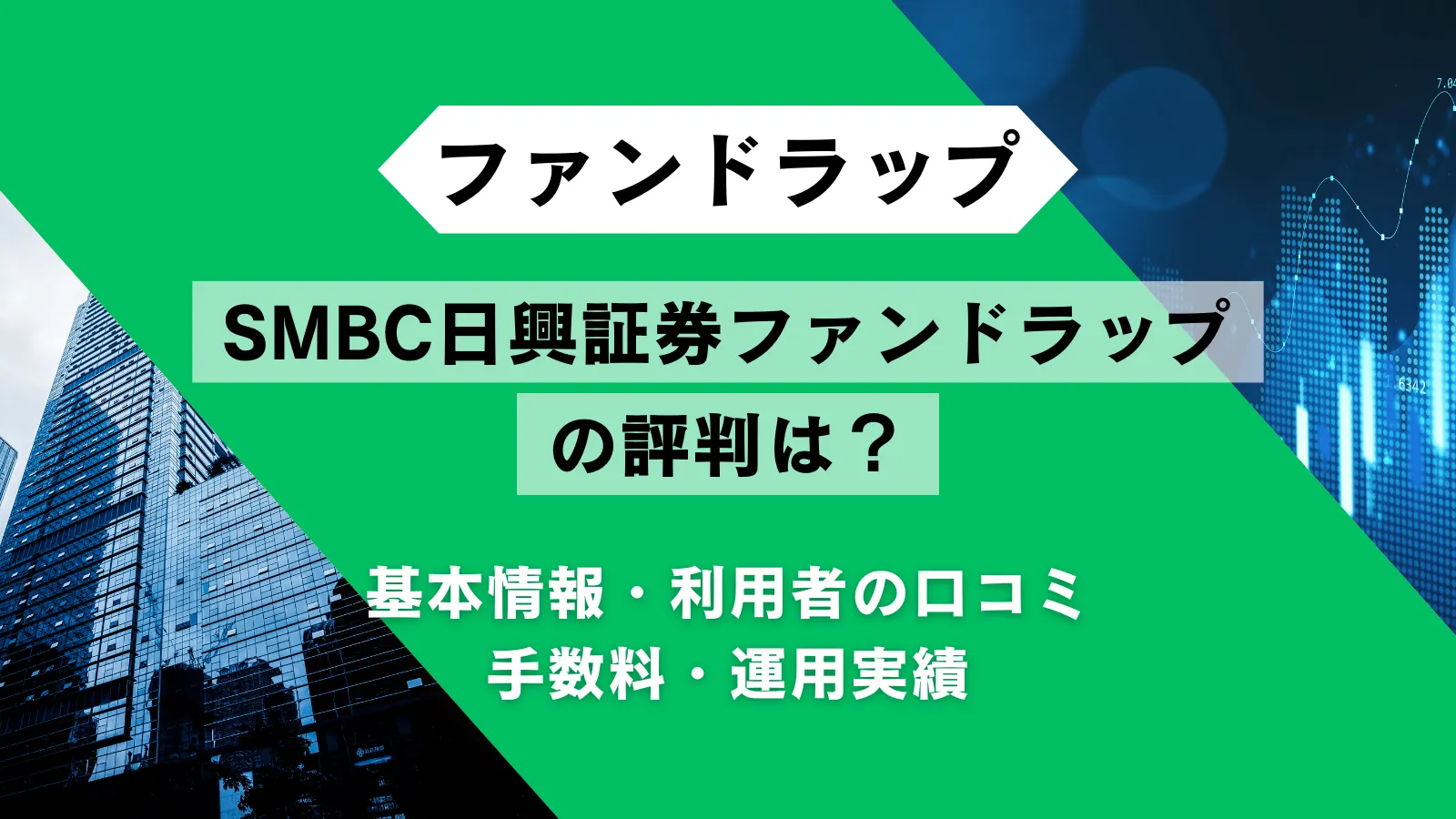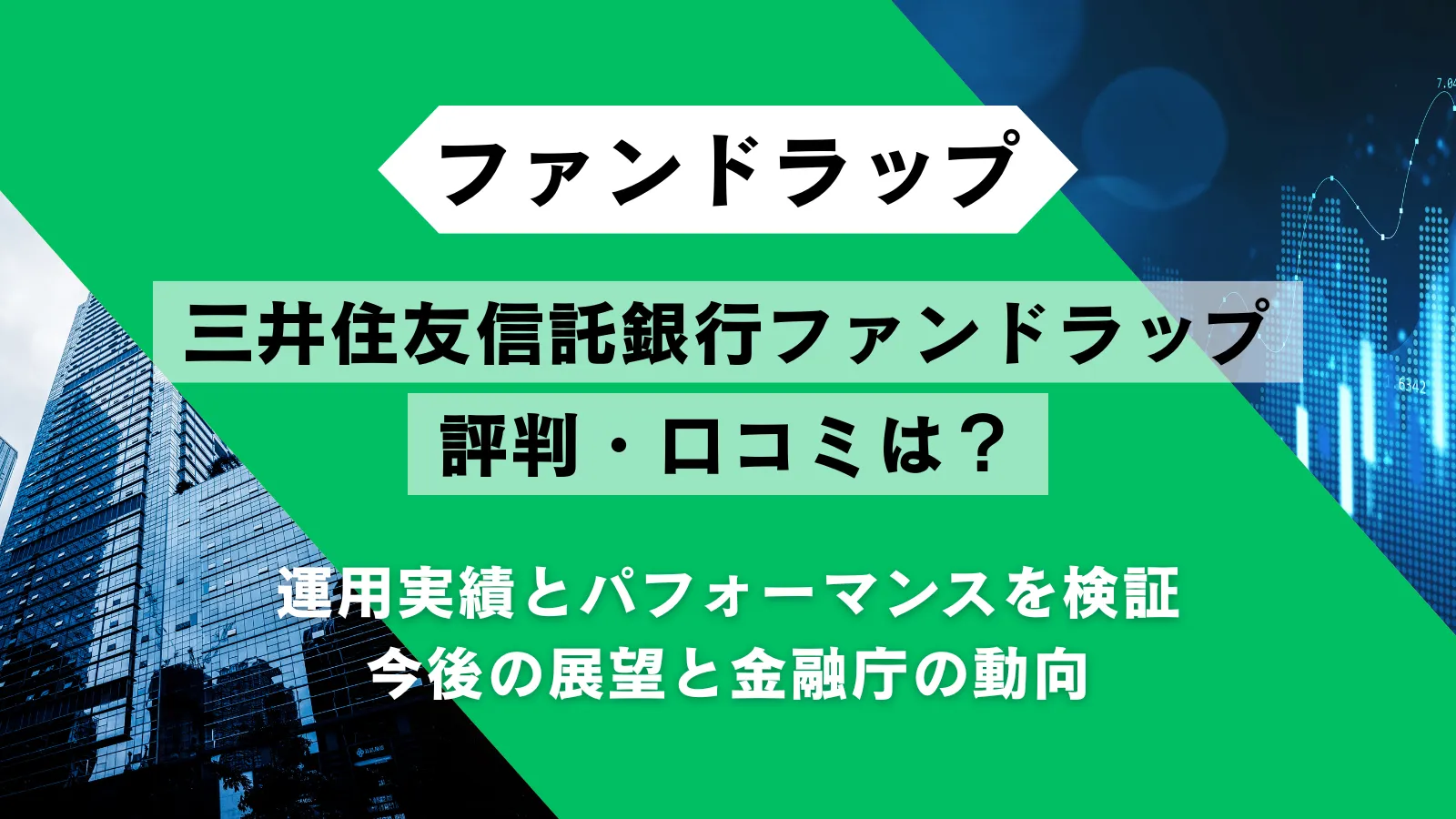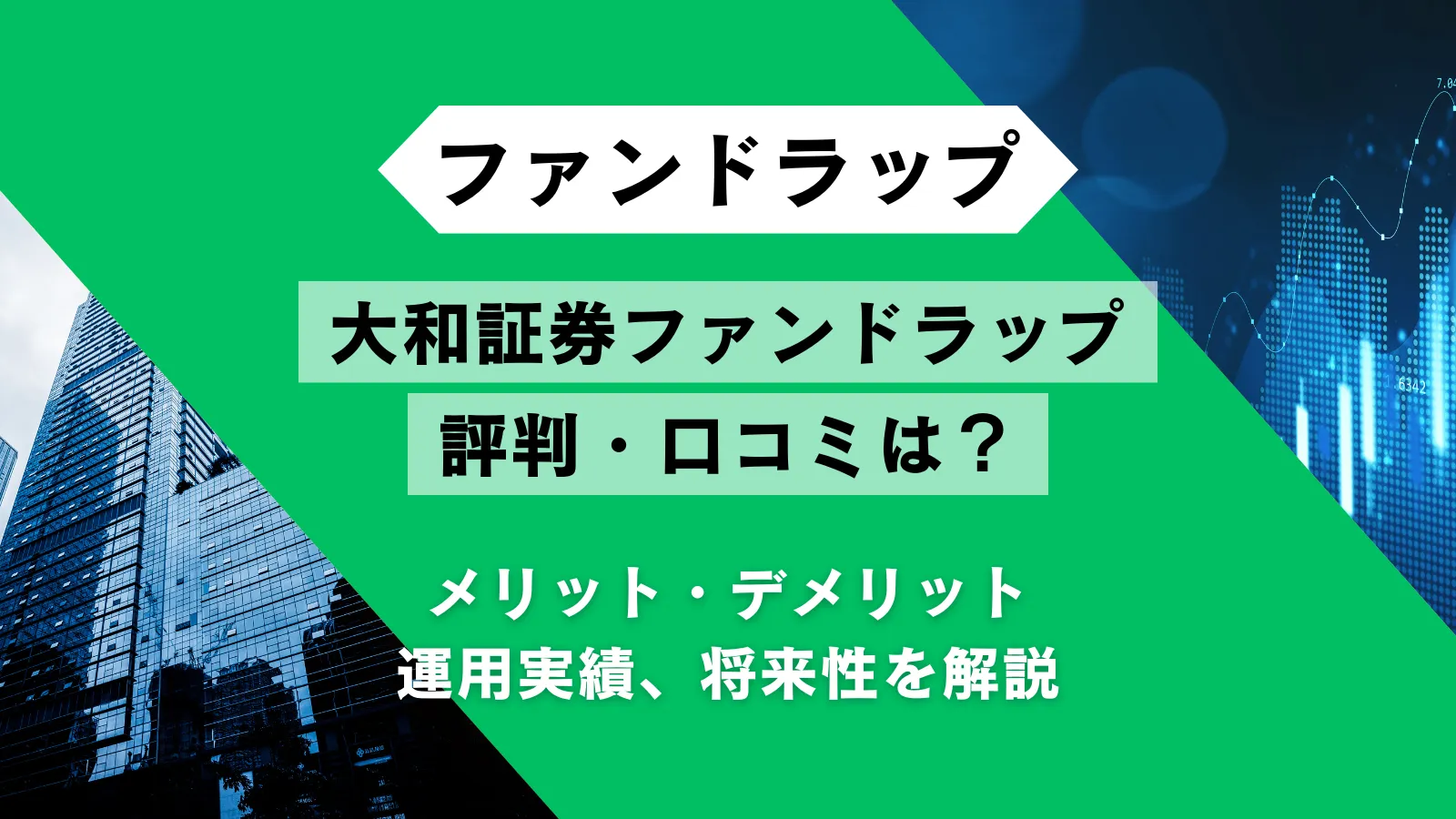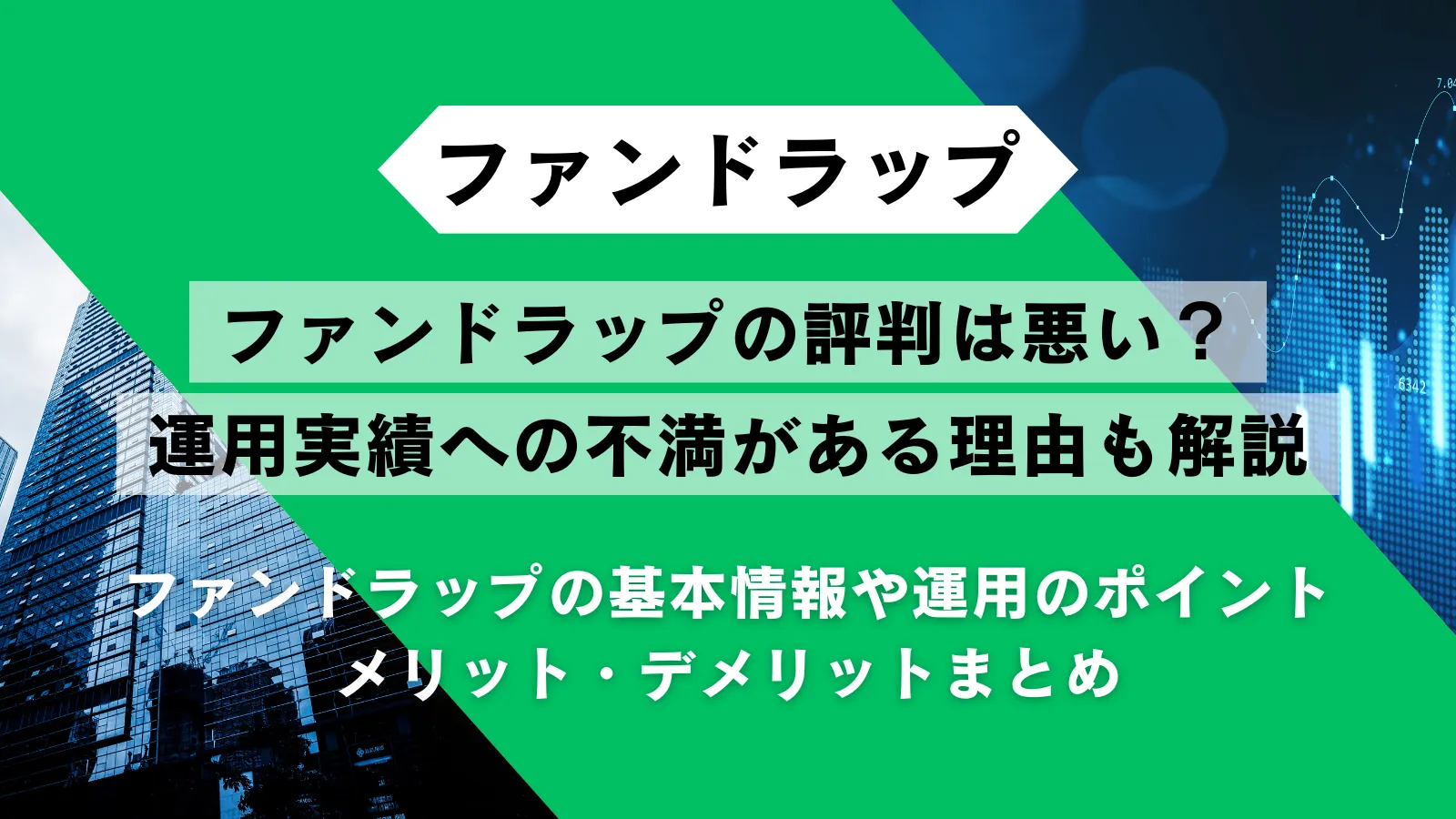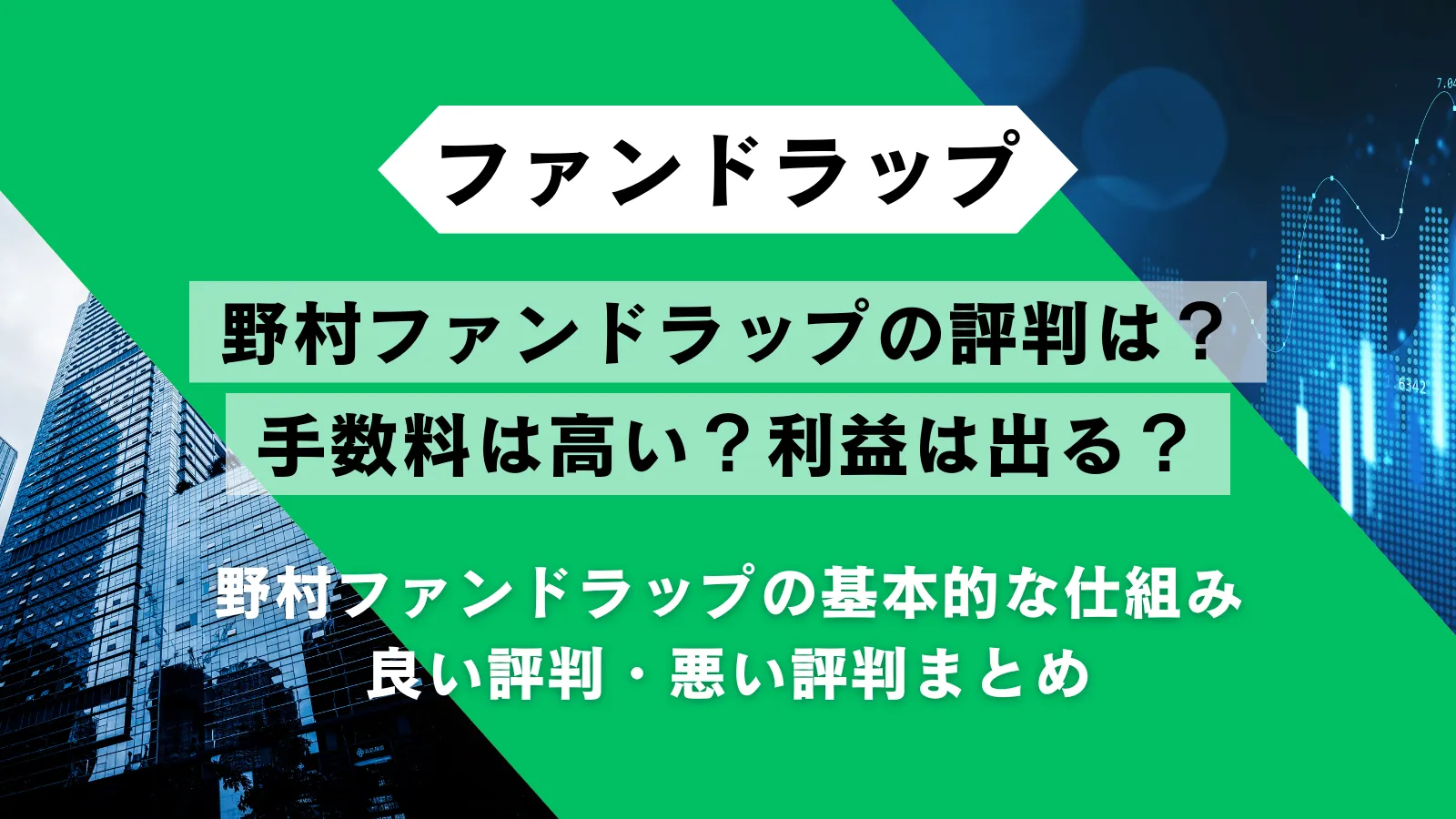「資産運用を専門家に任せたい」「最適なポートフォリオで長期的な資産形成を目指したい」とお考えの方へ。
SMBC日興証券が提供する日興ファンドラップは、お客様一人ひとりの投資方針に基づき、プロが資産配分の決定から運用・管理までを一貫して行う包括的なサービスです。
本記事では、仕組みや種類、手数料体系といった基本情報に加え、SMBCファンドラップとの違い、さらには実際の評判・口コミ、メリット・デメリットまで徹底解説します。
野村證券や大和証券など他社商品との比較や、投資額別のシミュレーションも交え、日興ファンドラップがあなたの資産運用に適しているかをわかりやすくご紹介します。
日興ファンドラップとは?基本情報と仕組みをわかりやすく解説
日興ファンドラップは、SMBC日興証券が提供する投資一任サービスです。
プロの運用担当者があなたの代わりに資産運用を行ってくれるため、投資経験の浅い方でも安心して始められるでしょう。
この章では日興ファンドラップの基本情報について、以下の3点から詳しく見ていきます。
日興ファンドラップの仕組みとは?
日興ファンドラップは、顧客一人ひとりの投資方針に合わせて資産運用をサポートするサービスです。
担当者があなたのリスク許容度や運用目的をヒアリングし、最適な運用プランを提案してくれる仕組みになっています。
運用開始後は投資判断から売買タイミングまで、すべての管理業務をプロに任せられるのが特徴です。
日興ファンドラップの主な特徴を以下の表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用会社 | SMBC日興証券株式会社 |
| サービス開始 | 2006年 |
| 最低投資金額 | 300万円 (1万円単位) |
| 運用管理費用 | 最大1.32% (税込) |
| 購入時手数料 | なし |
| 運用対象 | 世界の株式 債券 オルタナティブ等 |
| 運用モデル | 標準モデル セレクトモデル |
2026年時点での運用資産は5.03兆円を突破しております。
長期的な資産形成を目的とした商品設計となっているため、購入時手数料がかからない点も魅力でしょう。
日興ファンドラップとSMBCファンドラップの違いを比較
SMBCファンドラップと日興ファンドラップは名前が似ていますが、実は異なるサービスです。
どちらもSMBC日興証券が運用を担当していますが、販売窓口や投資対象に違いがあります。
両サービスの主な違いを比較表で確認してみましょう。
| 項目 | 日興ファンドラップ | SMBCファンドラップ |
|---|---|---|
| 販売窓口 | SMBC日興証券 | 三井住友銀行 |
| 最低投資金額 | 300万円 | 300万円 |
| 運用管理費用 | 最大1.32% (税込) | 最大1.54% (税込) |
| 基本モデル数 | 標準モデル7種類 セレクトモデル3種類 | 6種類 |
| 投資対象 | 世界中から厳選された 約100本のファンド | SMBCファンドラップ専用14本の 投資信託および日興MRF |
日興ファンドラップは直接販売を行っているため、SMBCファンドラップと比べて運用管理費用が安く設定されています。
投資対象についても、日興ファンドラップは世界中から厳選したファンドに分散投資できる一方、SMBCファンドラップは専用ファンドに限定される違いがあります。
また、日興ファンドラップでは総契約金額3,000万円以上から利用できる「プライベート・プレミアム・セレクション」という富裕層向けコースも用意されています。
手数料の低さと運用の柔軟性を重視するなら、日興ファンドラップの方が適しているといえるでしょう。
日興ファンドラップの種類と特徴
日興ファンドラップには「標準モデル」と「セレクトモデル」の2種類があります。
標準モデルはリスク許容度に応じて7段階(R1〜R7)から選べる運用スタイルで、世界中から厳選された約100本のファンドに分散投資します。投資初心者や長期運用を重視する方に適しています。
一方セレクトモデルは、専用ファンドから自分で投資対象を指定できるタイプです。安定・成長・積極の3段階から選ぶ形式で、市場環境に応じた機動的な運用を希望する投資経験者向けといえるでしょう。
投資初心者の方は実績のある標準モデルから始めて、慣れてきたらセレクトモデルに切り替えるのも一つの方法です。
以下に、それぞれの特徴をまとめました。
- 標準モデルの特徴
世界中から厳選された約100本のファンドに分散投資
7段階のリスク・リターン特性から選択可能
長期的な実績データが豊富 - セレクトモデルの特徴
投資家自身がファンドを選択できる
3段階 (安定・成長・積極) のリスク設定
市場環境に応じた機動的な運用が可能
どちらのモデルが良いかは、あなたの投資経験や運用スタイルによって変わってきます。
投資初心者の方は実績のある標準モデルから始めて、慣れてきたらセレクトモデルに切り替えるのも一つの方法でしょう。
日興ファンドラップ以外のサービスの評判も気になる方は、ファンドラップ全般の評判をまとめたこちらの記事も参考にしてみてください。
日興ファンドラップの手数料体系と運用実績
日興ファンドラップへの投資を検討する際、手数料と運用実績は最も気になるポイントでしょう。
この章では、具体的なコスト構造と過去の運用パフォーマンスについて詳しく解説していきます。
日興ファンドラップの手数料体系
日興ファンドラップの手数料は3つの要素で構成されています。
運用手数料、運用管理手数料、コンサルティング手数料を合わせると、年間最大1.32% (税込) のコストがかかる仕組みです。
以下の表で、各手数料の内訳を確認してみましょう。
| 項目 | 手数料率 (税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 運用手数料 | 0.33% | 運用モデルの策定 リバランス実施 |
| 運用管理手数料 | 0.44% | 契約管理、財産管理 システム維持 |
| コンサルティング | 0.55% | ポートフォリオ提案 運用報告 |
| 合計 | 最大1.32% | – |
アクティブファンドの標準的な信託報酬が1〜3%程度であることを考えると、日興ファンドラップの手数料は妥当な水準といえます。
ただし、投資信託への投資を通じて運用するため、ファンドラップの手数料に加えて投資信託の信託報酬も発生する点には注意が必要です。
この二重の手数料構造については、金融庁も問題視しており、実質的なコストが高くなりやすい傾向があります。
300万円を投資した場合、年間の手数料は最大で約39,600円 (税込) となる計算です。
このような手数料負担を避けたい方には、運用手数料無料で年利12%を実現するヘッジファンドも検討してみてください。
日興ファンドラップの運用実績と利回りを解説
日興ファンドラップの運用実績を、標準モデルとセレクトモデルに分けて見ていきましょう。
標準モデルはリスクレベルR1からR7まで7段階のポートフォリオから選択でき、2025年8月末時点のデータによると、過去1年間および過去5年間の収益率は以下の通りです。
| モデル | 想定リスク (年率) | 期待リターン (年率) | 過去1年間 の収益率 | 過去5年間 平均収益率 |
|---|---|---|---|---|
| R1 (安定重視) | 8.5% | 5.3% | 5.4% | 5.5% |
| R4 (標準) | 12.3% | 7.2% | 9.6% | 9.0% |
| R7 (積極) | 16.2% | 9.3% | 13.2% | 12.0% |
安定重視のR1でも過去5年平均で5.5%のリターンを実現しており、銀行預金と比べれば十分な運用成果といえるでしょう。
注目すべきは、過去5年間で最大収益率がR1で21.3%(2021年3月)、R7で47.2%(2021年3月)に達した実績がある一方、2022年12月にはマイナスを記録した期間もあり、市場環境による変動幅の大きさが確認できます。
一方、セレクトモデルは2021年10月にサービスが開始されたため、過去5年間の実績データは表示されていません。ただし直近1年間の実績を見ると、以下のようなパフォーマンスを記録しています。
| モデル | 想定リスク (年率) | 期待リターン (年率) | 過去1年間 の収益率 |
|---|---|---|---|
| 安定 | 8.0% | 5.4% | 6.1% |
| 成長 | 12.0% | 7.4% | 10.8% |
| 積極 | 16.0% | 9.5% | 14.0% |
セレクトモデルの積極型では過去1年間で14.0%と、標準モデルのR7(13.2%)を上回るパフォーマンスを記録しました。投資家自身がファンドを選択できる分、市場環境に応じた柔軟な運用が可能になっています。
ただしセレクトモデルの利用には3,000万円以上の資金が必要で、投資経験も求められるため、初心者向けではありません。
日興ファンドラップに関する良い評判・口コミ
日興ファンドラップの実際の利用者からは、どのような評価が寄せられているのでしょうか。
ここでは良い評判を中心に、3つのポイントから詳しく見ていきます。
良い評判①資産運用を完全にお任せできる
日興ファンドラップの最大の魅力は、投資判断から売買まですべてをプロに任せられる点です。
仕事が忙しい方や投資経験の浅い方にとって、日々の市場動向をチェックする必要がなく、運用担当者が市場環境に応じてポートフォリオ管理やリバランスを実施してくれます。
実際の利用者からは「投資の知識がなくても安心して任せられる」「時間を取られずに資産運用ができる」といった声が多く、特に初心者から高い評価を得ています。
担当者との定期的な面談を通じて、運用状況の報告や今後の方針についても相談できる体制が整っています。
良い評判②親切・丁寧な対応が安心感につながる
SMBC日興証券の担当者によるきめ細やかなサポート体制も好評です。
契約前のヒアリングでは、あなたの投資経験や目標、リスク許容度などを丁寧に確認してくれます。
その上で最適な運用プランを提案してもらえるため、納得して投資を始められるでしょう。
運用開始後も定期的な報告や相談の機会が設けられており、疑問点があればすぐに質問できる環境が整っています。
「担当者が親身になって相談に乗ってくれる」「初心者にも分かりやすく説明してくれる」といった口コミが目立ちます。
大手証券会社ならではの安心感と、対面でのサポートを重視する方にとって魅力的なサービスといえます。
良い評判③運用報告書が分かりやすく充実している
定期的に届く運用報告書の内容が充実していて見やすいという評価も多く見られます。
運用成績の推移や資産配分、今後の市場見通しなどが分かりやすくまとめられているため、投資初心者でも状況を把握しやすいでしょう。
報告書には以下のような情報が含まれています。
- 運用資産の時価評価額と損益状況
- 各資産クラスへの配分比率
- 市場環境の分析と今後の見通し
- 実施したリバランスの内容
このような詳細な情報開示により、自分の資産がどのように運用されているか透明性を持って確認できます。
「グラフや図表が豊富で視覚的に分かりやすい」「専門用語も丁寧に解説されている」といった声が寄せられています。
日興ファンドラップに関する悪い評判・口コミ
良い評判がある一方で、日興ファンドラップには気になる口コミも存在します。
契約前に知っておくべきデメリットや注意点を、実際の利用者の声とともに確認していきましょう。
悪い評判①手数料が高くコストパフォーマンスが悪い
日興ファンドラップで最も多く指摘されるのが、手数料の高さとコストパフォーマンスの問題です。
年間最大1.32%の運用管理費用に加えて、投資信託の信託報酬も別途かかる二重構造になっています。
実際の口コミでは「約1%の手数料を払っているのに、2年間で17%のリターンしか得られなかった」という不満の声があり、S&P500やオルカンと比較してパフォーマンスが劣るケースも少なくありません。
金融庁もファンドラップの二重手数料構造を問題視しており、300万円を投資した場合、手数料だけで年間約4万円が差し引かれる計算です。
長期運用を考えると、このコストが運用成績に与える影響は決して小さくありません。
手数料を抑えて高リターンを狙いたい方は、年利12%以上を実現するヘッジファンドという選択肢もあります。
悪い評判②最低投資額300万円のハードルが高い
日興ファンドラップは最低投資額が300万円に設定されているため、投資初心者にとってハードルが高いという声があります。
資産運用を始めたばかりの方や、まとまった資金を持っていない若い世代には手が届きにくい金額でしょう。
NISAやiDeCoなら少額から始められることを考えると、気軽に試せない点はデメリットです。
「いきなり300万円を預けるのは不安」「もっと少額から始めたかった」といった口コミが見られ、投資経験を積んでから判断したい方にとって大きな障壁となっています。
富裕層向けの「プライベート・プレミアム・セレクション」に至っては3,000万円以上が必要となるため、さらに限られた層向けのサービスといえます。
悪い評判③担当者の異動が頻繁で継続性に不安がある
証券会社の担当者は人事異動により定期的に変わることが多く、継続性に不安を感じる利用者もいます。
せっかく信頼関係を築いた担当者が異動してしまうと、また一から関係を作り直す必要があり、「担当者が変わるたびに運用方針の説明をし直すのが面倒」という口コミも見られます。
また、運用内容が一方的に変更されたという不満の声もあります。
投資一任契約である以上、運用会社の判断で資産配分を変更できる仕組みですが、「オルタナティブから債券に勝手に変更されて損失が出た」といった具体的な不満も報告されています。
日興ファンドラップのメリット・デメリットとは?
ここまで日興ファンドラップの評判を見てきましたが、実際に投資するべきか迷っている方も多いでしょう。
この章では、日興ファンドラップのメリットとデメリットを客観的に整理していきます。
日興ファンドラップのメリット|運用の手間が省けて楽になる
日興ファンドラップの最大のメリットは、投資判断から売買タイミングまで全てプロに任せられる点です。
忙しいビジネスパーソンや投資経験の浅い方にとって、日々の市場チェックが不要になり、株価の値動きを気にせず本業や家族との時間に集中できます。
運用担当者が定期的にポートフォリオを見直し、市場環境に応じてリバランスを実施してくれるため、自分で投資信託を選ぶ手間や資産配分を調整する負担から解放されます。
「仕事が忙しくて投資に時間を割けない」「チャートを見るのが苦手」という方には最適なサービスといえるでしょう。
- 投資判断や売買タイミングの見極めが不要
- 市場環境に応じた自動リバランス
- 投資信託選びや資産配分の手間がゼロ
日興ファンドラップのメリット|目的に合わせたポートフォリオを構築してもらえる
あなたの投資目的やリスク許容度に合わせて、最適な運用プランを提案してもらえるのも大きなメリットです。
契約前のヒアリングで年齢や資産状況、運用目標などを丁寧に確認し、7段階のリスク・リターン特性からあなたに合ったポートフォリオを組んでもらえます。
世界中の株式や債券、オルタナティブ資産など約100本のファンドから分散投資でき、個人では手が届きにくい海外資産や特殊な投資対象にもアクセス可能です。
定期的な面談を通じて、ライフステージの変化に応じた運用方針の見直しも相談できる体制が整っています。
日興ファンドラップのデメリット|手数料の二重構造でコストが割高になる
日興ファンドラップの最大のデメリットは、手数料が二重にかかる仕組みになっている点です。
年間最大1.32%の運用管理費用に加えて、投資する投資信託の信託報酬も別途発生し、実質的なコストは年2%以上になるケースも珍しくありません。
300万円を投資した場合、手数料だけで年間6万円以上が差し引かれる計算です。
金融庁もこの二重構造を問題視しており、長期運用を考えると、このコストが最終的なリターンを大きく圧迫する可能性があるでしょう。
| 投資額 | 年間手数料 (目安) | 20年間の 累計コスト |
|---|---|---|
| 300万円 | 約6万円 | 約120万円 |
| 500万円 | 約10万円 | 約200万円 |
| 1,000万円 | 約20万円 | 約400万円 |
20年間で数百万円にも及ぶ手数料負担を避けたい方には、運用手数料無料・二重構造なしで年利12%のヘッジファンドという選択肢もあります。
日興ファンドラップのデメリット|自分で運用スキルが身につかない
すべてをプロに任せられる反面、自分自身の投資スキルが育たないというデメリットもあります。
投資判断を他人に委ねているため、なぜその資産配分になったのか、どういう理由で売買したのかを深く理解できず、将来的に自分で資産運用をしたい方にとって経験を積む機会を失ってしまいます。
また、運用内容が一方的に変更される可能性もあり、自分の意思が反映されにくい面があります。
投資の知識や経験を身につけたい方は、まずNISAやiDeCoで少額から始めて、徐々にステップアップしていく方が良いでしょう。
日興ファンドラップは「時間がない」「投資に興味がない」という方に向いたサービスといえます。
- 将来的に自分で資産運用をしたい
- 投資の知識や経験を積みたい
- 運用内容を自分でコントロールしたい
ご自身で投資スキルを磨きつつ資産形成を進めたい方は、手間をかけずに始められる儲かる投資信託のランキング記事を参考にしてください。
日興ファンドラップと他社ファンドラップの比較一覧表
日興ファンドラップへの投資を検討する際、他社のファンドラップとの違いも気になるところでしょう。
この章では、主要証券会社のファンドラップサービスと日興ファンドラップを比較していきます。
野村證券のファンドラップとの比較
野村證券は「野村ファンドラップ」という名称でサービスを提供しています。
業界最大手の証券会社として、豊富な運用実績と充実したサポート体制が特徴です。
日興ファンドラップとの主な違いを以下の表で確認してみましょう。
| 項目 | 日興ファンドラップ | 野村ファンドラップ |
|---|---|---|
| 運用会社 | SMBC日興証券 | 野村證券 |
| 最低投資金額 | 300万円 | 500万円 |
| 運用管理費用 | 最大1.32% (税込) | 最大1.54% (税込) |
| 基本モデル数 | 標準7種類/セレクト3種類 | 複数コースから選択 |
| 純資産残高 | 約5.03兆円 | 業界最大規模 |
野村ファンドラップは最低投資額が500万円と、日興ファンドラップより200万円高く設定されています。
運用管理費用も若干高めですが、野村證券の豊富な運用ノウハウや情報力を活かした運用が期待できるでしょう。
資金に余裕があり、業界最大手の安心感を重視する方は野村ファンドラップを、コストを抑えたい方は日興ファンドラップが適しています。
野村ファンドラップについてさらに詳しく知りたい場合は、運用実績や手数料を徹底解説したこちらの記事を参考にしてください。
大和証券のファンドラップとの比較
大和証券は「ダイワファンドラップ」として、業界でも早い段階からサービスを展開してきました。
長年の運用実績があり、安定したパフォーマンスに定評があります。
日興ファンドラップとの比較は以下の通りです。
| 項目 | 日興ファンドラップ | ダイワファンドラップ |
|---|---|---|
| 運用会社 | SMBC日興証券 | 大和証券 |
| 最低投資金額 | 300万円 | 300万円 |
| 運用管理費用 | 最大1.32% (税込) | 最大1.54% (税込) |
| サービス開始 | 2006年 | 2007年 |
| 特徴 | 7段階のリスク設定 | きめ細かいコース設定 |
ダイワファンドラップは最低投資額が日興ファンドラップと同じ300万円からスタートできます。
ただし運用管理費用は1.54%と、日興ファンドラップより0.22%高い設定です。
年間で計算すると、300万円の投資で約6,600円のコスト差が出る計算になります。
手数料の安さを重視するなら日興ファンドラップ、大和証券の運用力を信頼するならダイワファンドラップという選択になるでしょう。
ダイワファンドラップについてさらに詳しく知りたい場合は、運用実績や手数料を徹底解説したこちらの記事を参考にしてください。
みずほ証券のファンドラップとの比較
みずほ証券は「みずほファンドラップ」として、みずほフィナンシャルグループの総合力を活かした運用を提供しています。
銀行系証券会社ならではの幅広い顧客基盤を持つのが特徴です。
以下の表で日興ファンドラップとの違いを見てみましょう。
| 項目 | 日興ファンドラップ | みずほファンドラップ |
|---|---|---|
| 運用会社 | SMBC日興証券 | みずほ証券 |
| 最低投資金額 | 300万円 | 300万円 |
| 運用管理費用 | 最大1.32% (税込) | 最大1.485% (税込) |
| コース設定 | 標準7種類/セレクト3種類 | 複数コースから選択 |
| グループ特性 | 三井住友FG系 | みずほFG系 |
みずほファンドラップも最低投資額は300万円からとなっており、参入しやすい水準です。
運用管理費用は1.485%と、日興ファンドラップより0.165%高く設定されています。
みずほ銀行との連携を重視する方や、すでにみずほグループで取引がある方には検討の価値があるでしょう。
総合的に見ると、主要証券会社の中で日興ファンドラップは最も手数料が安いといえます。
なお、運用手数料無料で年利12%のヘッジファンドという選択肢もあります。
日興ファンドラップの運用シミュレーション|投資額別の期待リターン
日興ファンドラップに投資した場合、実際にどれくらいのリターンが期待できるのでしょうか。
この章では、投資額別に具体的なシミュレーションを行い、将来的な資産額を試算していきます。
300万円で運用した場合
最低投資額である300万円で運用を始めた場合、選択するリスクレベルによって将来の資産額は大きく変わってきます。
標準モデルの過去5年平均収益率(コスト控除後)を基に、10年後と20年後の資産額を試算してみましょう。
| モデル | コスト控除後年率 | 10年後 | 20年後 |
|---|---|---|---|
| R1(安定重視) | 3.0% | 約403万円 | 約543万円 |
| R4(標準) | 4.8% | 約479万円 | 約765万円 |
| R7(積極) | 6.9% | 約573万円 | 約1,094万円 |
コスト控除後のリターンで見ると、安定重視のR1でも20年間で約1.8倍に増える計算です。
積極型のR7を選択すれば、20年後には約1,094万円と1,000万円を超える可能性があります。
ただし、手数料が年間約4万円かかるため、実際のリターンは期待リターンより低くなる点に注意しましょう。
より高い利回りを求める方には、手数料を抑えた年利12%以上のヘッジファンドという選択肢もあります。
500万円で運用した場合
500万円の投資額なら、より余裕を持った資産運用が可能になります。同じくコスト控除後の収益率で試算してみましょう。
| モデル | コスト控除後年率 | 10年後 | 20年後 |
|---|---|---|---|
| R1(安定重視) | 3.0% | 約672万円 | 約905万円 |
| R4(標準) | 4.8% | 約798万円 | 約1,276万円 |
| R7(積極) | 6.9% | 約955万円 | 約1,824万円 |
標準型のR4で運用した場合、20年後には約1,276万円となります。
老後資金として2,000万円を目標にしている方は、積極型のR7を選択すれば約1,824万円まで増える試算となり、目標達成に近づけるでしょう。
手数料は年間約6.6万円かかりますが、500万円規模の投資なら許容範囲といえるかもしれません。
500万円の運用先について、ファンドラップ以外の選択肢も含めて比較検討したい方は、こちらの専門記事をご覧ください。
1000万円で運用した場合
1000万円という大きな資金を運用する場合、将来的に数千万円規模の資産形成が現実的になってきます。各モデルでの試算結果を確認してみましょう。
| モデル | コスト控除後年率 | 10年後 | 20年後 |
|---|---|---|---|
| R1(安定重視) | 3.0% | 約1,344万円 | 約1,806万円 |
| R4(標準) | 4.8% | 約1,596万円 | 約2,551万円 |
| R7(積極) | 6.9% | 約1,911万円 | 約3,647万円 |
安定重視のR1でも20年間で約1.8倍に増える計算です。
標準型のR4なら20年後に約2,551万円、積極型のR7では約3,647万円と、老後資金として十分な金額に成長する可能性があります。
ただし1000万円規模の投資では手数料も年間約13.2万円と高額になるため、コストパフォーマンスを慎重に検討する必要があるでしょう。
この規模の資金があるなら、手数料の安い年利12-17%のヘッジファンドへの投資も選択肢に入れて比較検討することをおすすめします。
1000万円という資金で、より高いリターンと効率的な運用を目指す方は、ヘッジファンドに特化した解説記事もチェックしてみてください。
日興ファンドラップより高利回りが期待できるヘッジファンド
日興ファンドラップの手数料の高さが気になる方には、ヘッジファンドへの投資も選択肢の一つです。
ヘッジファンドなら二重の手数料構造がなく、より高い利回りを狙える可能性があります。
ここでは、個人投資家でも投資できるおすすめのヘッジファンドを2つ紹介していきます。
ハイクアインターナショナル
| 運用会社 | 合同会社 ハイクア・インターナショナル |
|---|---|
| 設立 | 2023年 |
| 本社所在地 | 日本(大阪) |
| 主な投資対象 | SAKUKO VIETNAM (ベトナム企業) |
| 主な投資戦略 | 事業融資 |
| 年間期待利回り | 年利12% |
| 最低投資金額 | 500万円 |
| 運用の相談 | 資料請求・面談 |
| 公式サイト | ハイクア・インターナショナル |
ハイクア・インターナショナルは、ベトナムの成長企業「SAKUKO Vietnam」への事業融資により、年利12%の固定リターンを目標とする安定性重視のプライベートデットファンドです。
株式投資と異なり市場変動に左右されにくい収益構造を実現しており、500万円という比較的参入しやすい金額から始められる点も魅力となっています。
年利12%固定の高利回り
ハイクアの最大の特徴は、年利12%という高水準の固定リターンを目指している点です。
投資信託の年利3~5%や定期預金の0.1%と比較すると、圧倒的に高い利回りを実現しています。しかも株式市場の値動きに左右されない安定した収益構造を持つため、長期的な資産形成に適しています。
株式投資と異なり、企業が売上を出せば利息が得られるため、リターンまでの過程がシンプルで直接的です。
市場の値動きに一喜一憂する必要がなく、3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回の分配金が支払われる定期的なキャッシュフローも大きなメリットとなっています。
- 市場変動に左右されない
株価暴落時でも安定した利回りを確保 - 株価変動リスクがない
事業融資型なので株式市場の影響を受けない - 定期的なキャッシュフロー
3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回の分配金 - シンプルな収益構造
企業の売上から直接利息を得る仕組み - 高い透明性と信頼性
投資先の事業内容が明確で追跡可能 - 最低投資額500万円から
ポートフォリオに組み込みやすい金額設定
代表者が情報開示に積極的で、出資前に無料面談が可能、出資後も事業報告会があるなど透明性も高い運営体制となっています。
投資判断に必要な情報がしっかりと提供される環境は、投資家にとって大きな安心材料といえるでしょう。
ベトナム市場の成長性
ハイクアが投資対象とするベトナムは、アジアの中でも特に高い成長率を誇る新興国です。
年間5〜6%の経済成長を継続しており、若い労働力と政治的安定性が経済発展を後押ししています。
投資先の「SAKUKO Vietnam」は、ベトナム国内で確固たる事業基盤を築いており、この成長市場の恩恵を直接受けられる環境にあります。
先進国市場が成熟し、日本経済も低成長が続く中、ベトナムのような成長市場への投資は、ポートフォリオの分散という観点からも有効な戦略です。
- 高い経済成長率
年間5〜6%の安定した成長を継続中 - 若く活力ある労働力
平均年齢約32歳、人口約1億人の内需拡大の潜在力 - 製造業の集積地
「世界の工場」として外資企業の進出が活発化
国内の投資信託や株式だけでなく、成長市場への分散投資を検討している方にとって、ハイクアは魅力的な選択肢となるでしょう。
「日興ファンドラップより高い利回りを求めている」「市場の変動に左右されにくい投資先を探している」と考えているなら、ハイクア・インターナショナルのような個人投資家が参加できる国内ヘッジファンドをポートフォリオの一部に組み込むことを検討してみてはいかがでしょうか。
まずは無料の資料請求で詳細な投資条件をご確認ください。年利12%の安定した固定リターンを実現する投資モデルの仕組みや、ベトナム市場の成長性について詳しく知ることができます。
ハイクアインターナショナルについて、詳しくは下記の記事も参考にしてください。
アクション

| 運用会社 | Action合同会社 |
|---|---|
| 設立 | 2023年 |
| 本社所在地 | 日本(東京) |
| 主な投資対象 | 日本株・事業投資・Web3事業・ファクタリングなど |
| 主な投資戦略 | ・株式の成長投資戦略 ・エンゲージメント、アクティビスト投資戦略 ・ポートフォリオ投資戦略 |
| 利回り | 17.35%(2024年度実績) |
| 最低投資金額 | 500万円 |
| 運用の相談 | 面談 |
| 公式サイト | アクション |
アクション合同会社は、2023年設立の新興ヘッジファンドながら、初年度から年利17.35%という驚異的な実績を達成しました。
日興ファンドラップの手数料に不満を感じる方や、より高度な運用戦略を求める方に、プロフェッショナルな資産運用を個人投資家でもアクセスしやすい形で提供しているファンドです。
2024年度実績は驚異の年利17.35%
アクションの最大の魅力は、その圧倒的な運用実績です。2024年度に年利17.35%という高いリターンを達成し、日本国内のヘッジファンドの中でもトップクラスの成績を残しています。
投資信託の年利3~5%、ロボアドバイザーの年利3~8%と比較すると、アクションの実績は桁違いの高リターンを実現しています。
もちろん、設立間もないファンドのため長期的な実績はこれからですが、この初年度の成果は資産を大きく増やしたい投資家にとって注目に値するものといえるでしょう。
- 2024年度実績17.35%
日本国内ヘッジファンドの中でもトップクラス - 目標年利15%以上
長期的に高い水準のリターンを目指す運用方針 - 金融業界30年以上の経験
実力ある運用チームによる高度な投資判断 - 透明性の高い情報開示
役員陣や実績を公式サイトで公開 - 最低投資額500万円から
比較的参入しやすい金額設定
運用を担うのは、金融業界で30年以上の経験を持つプロフェッショナルチームです。役員陣の経歴や運用実績を公式サイトで公開するなど、透明性の高い運営姿勢も投資家からの信頼を集めています。
多角的な投資でリスク分散
アクションのもう一つの特徴は、マルチストラテジー戦略を採用している点です。
一つの投資手法に依存せず、複数の資産クラスと戦略を組み合わせることで、リスクを分散させながら高いリターンを追求しています。
- バリュー株投資
割安で成長余地のある日本株への投資 - アクティビスト戦略
企業経営に積極的に関与し価値向上を促す - 事業投資
成長性の高い事業への直接投資 - Web3事業
次世代インターネット技術への先行投資 - ファクタリング
債権の買取による安定収益の確保
この多角的なアプローチにより、ある投資が不調でも他の投資でカバーできる体制を構築しています。
投資信託が株式や債券に分散投資するのと同様に、アクションも日本市場を中心としながら多様な投資機会を追求することで、安定性と収益性を両立させているのです。
「日興ファンドラップより高いリターンを目指したい」「日本市場に精通したプロの運用を任せたい」と考えているなら、アクションのような個人投資家が参加できる国内ヘッジファンドは有力な選択肢となるでしょう。
ただし、出資した資金は1年間のロックアップ期間があるため、余剰資金での投資が推奨されます。興味がある場合は、公式サイトから無料面談を申し込むことで詳しい説明を受けてみましょう。
アクション合同会社について詳しくは下記の記事も参考にしてください。
日興ファンドラップの始め方とは?その解約方法も解説
日興ファンドラップへの投資を決めた場合、どのような手順で契約すればよいのでしょうか。契約の流れと解約時の注意点について、実際の手続きに沿って詳しく解説していきます。
日興ファンドラップの始め方
SMBC日興証券の公式サイトから資料請求を行い、担当者との面談を予約します。
面談では投資目的やリスク許容度、運用期間などをヒアリングし、7段階のリスク設定から最適な運用プランを提案してもらえます。
- 基本契約
投資一任契約の基本事項を定める契約書 - 個別契約
個別ポートフォリオの運用に必要な事項を定める契約書
運用開始日は個別契約の締結日から2〜11営業日の範囲で指定できます。
日興ファンドラップの解約方法
解約は担当者に連絡して手続きを進めますが、すでに支払った手数料は返金されない点に注意が必要です。
また、以下の期間中は契約解除できない制限があります。
- 新規契約日または運用開始日が属する評価期間中
- 追加入金・一部解約・モデル変更にかかる取引の約定が完了するまでの期間
運用資産の一部を解約した場合も、日興ファンドラップ手数料および投資一任報酬は返金されません。
契約前にこれらの注意点をしっかり理解した上で、投資判断を行うことが大切です。
よくある質問
日興ファンドラップに関してよく寄せられる質問をまとめました。
契約前の疑問点を解消する参考にしてください。
まとめ
日興ファンドラップは、運用のプロに投資判断を一任できるサービスとして、一定の評価を得ています。
投資の手間を省ける点や定期的なサポートが受けられる点は魅力ですが、手数料の二重構造によるコスト負担の大きさは無視できません。
過去5年の平均収益率は、安定型で4.5%、標準型で7.5%、積極型で10.2%という実績があります。
ただし年間最大1.32%の運用管理費用に加えて投資信託の信託報酬もかかるため、実質的なコストは年2%以上になる可能性があるでしょう。
より高い利回りを目指すなら、ハイクアインターナショナル (年利12%) やアクション (年利17.35%)といったヘッジファンドも検討する価値があります。
これらのヘッジファンドは無料で運用相談ができるため、日興ファンドラップと比較しながら、あなたに最適な投資先を見つけてください。