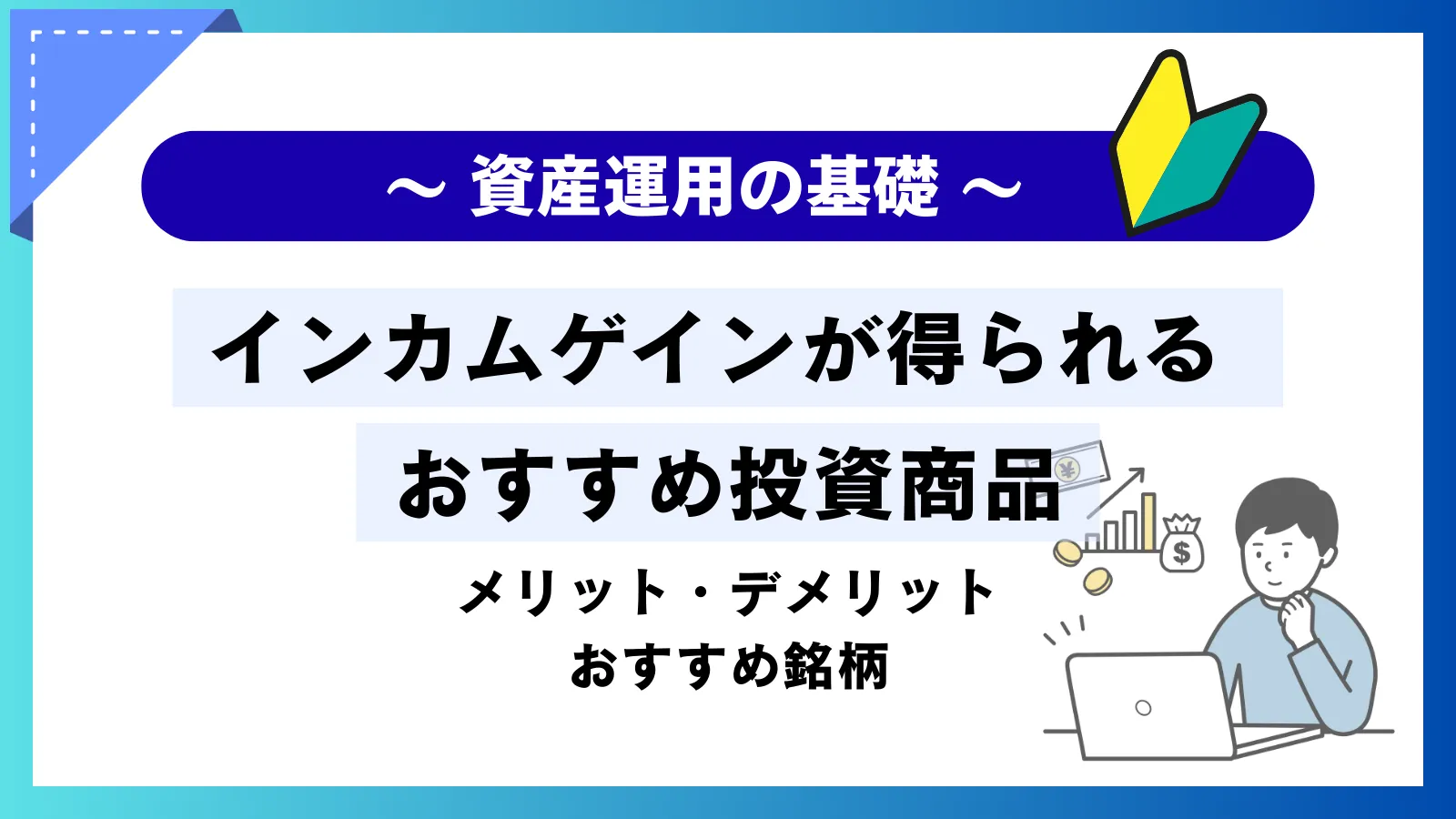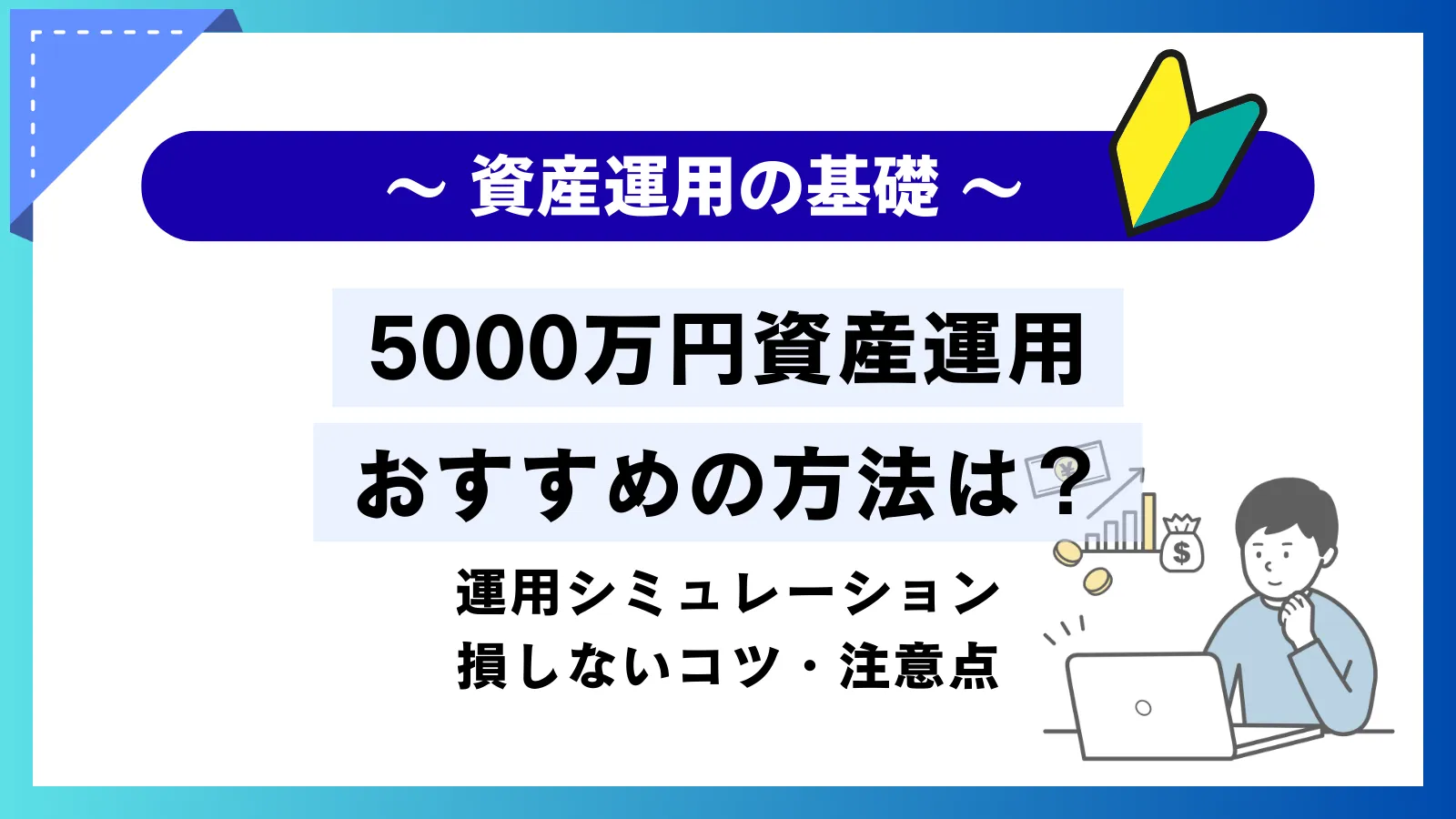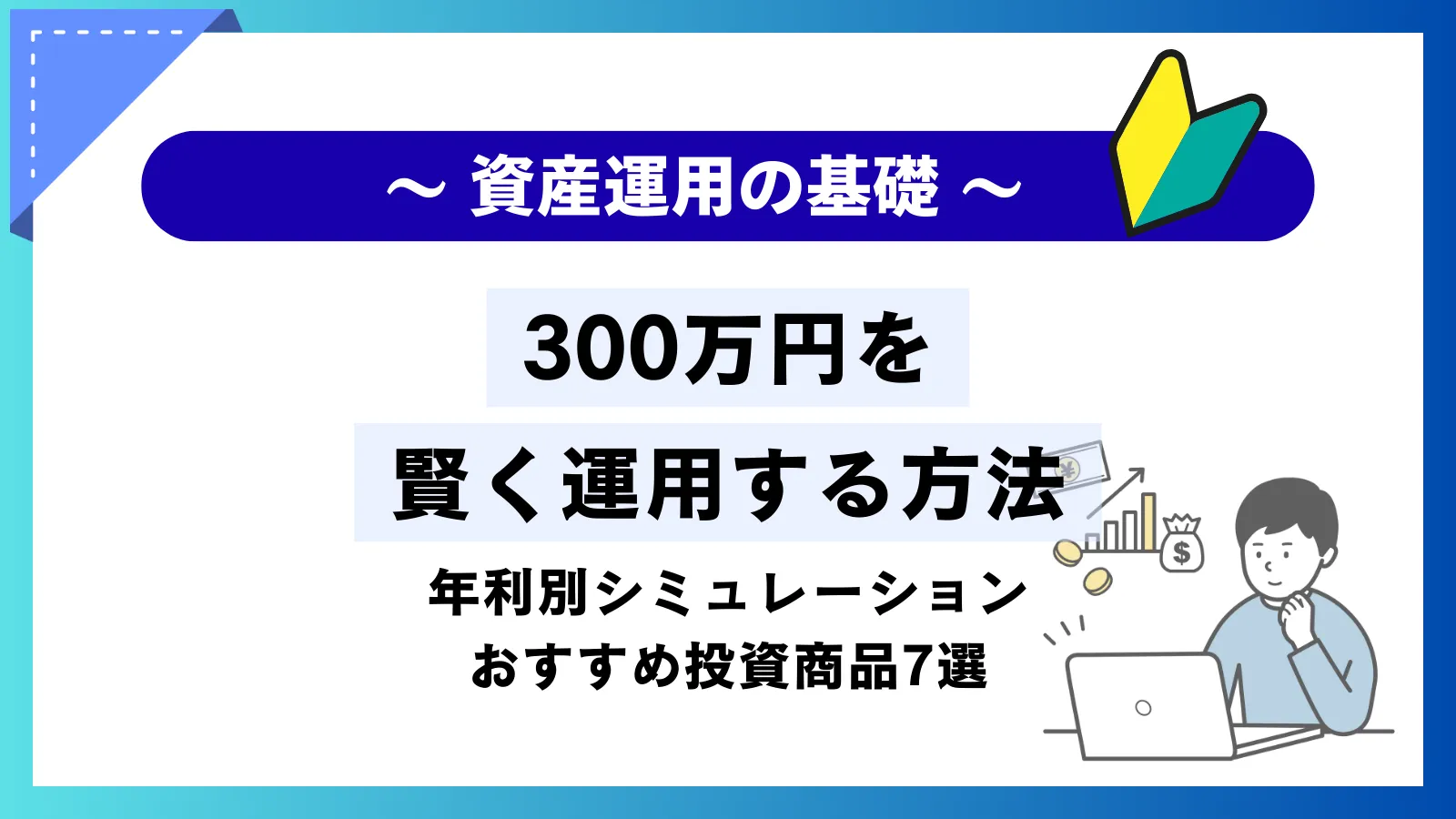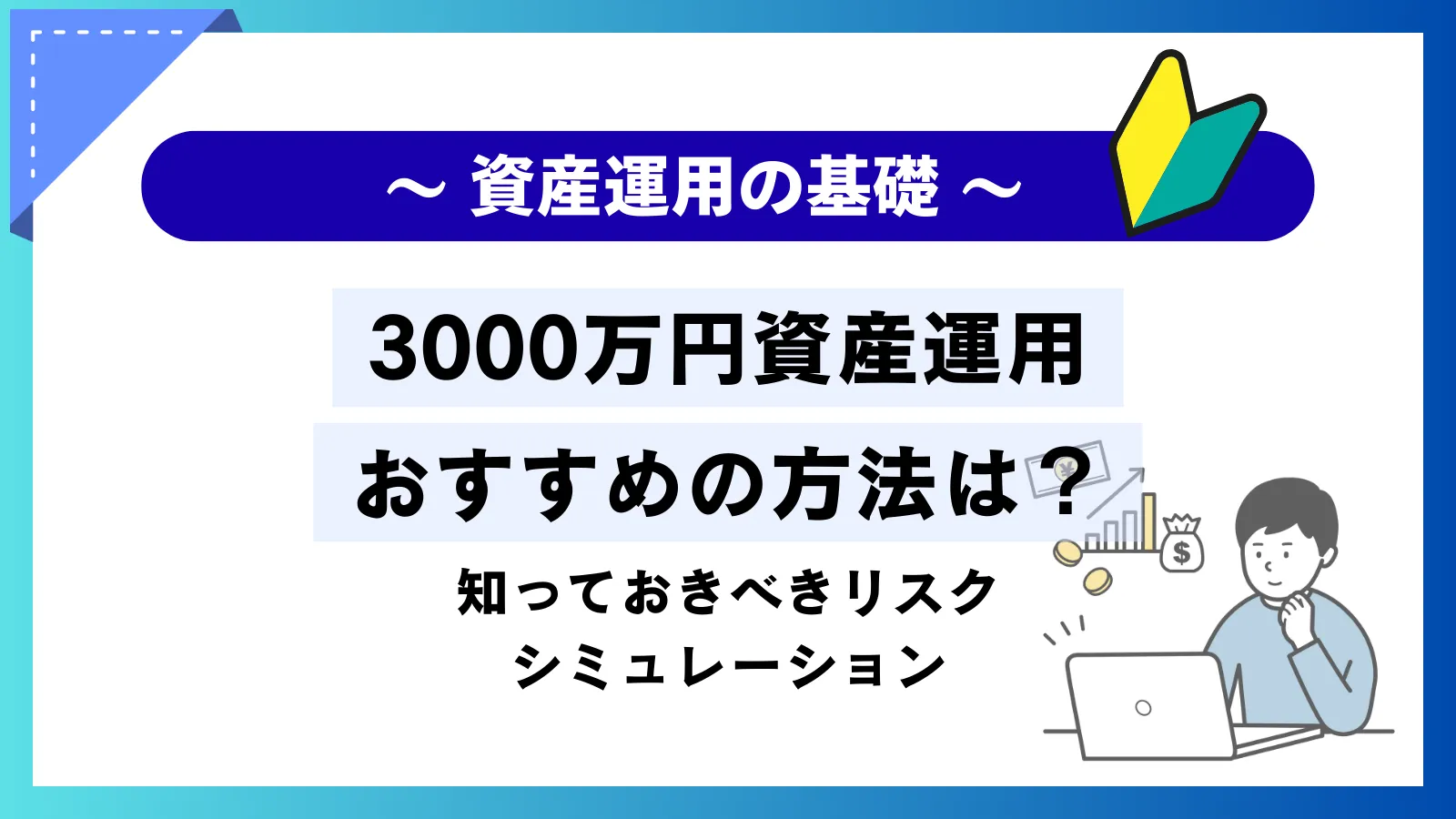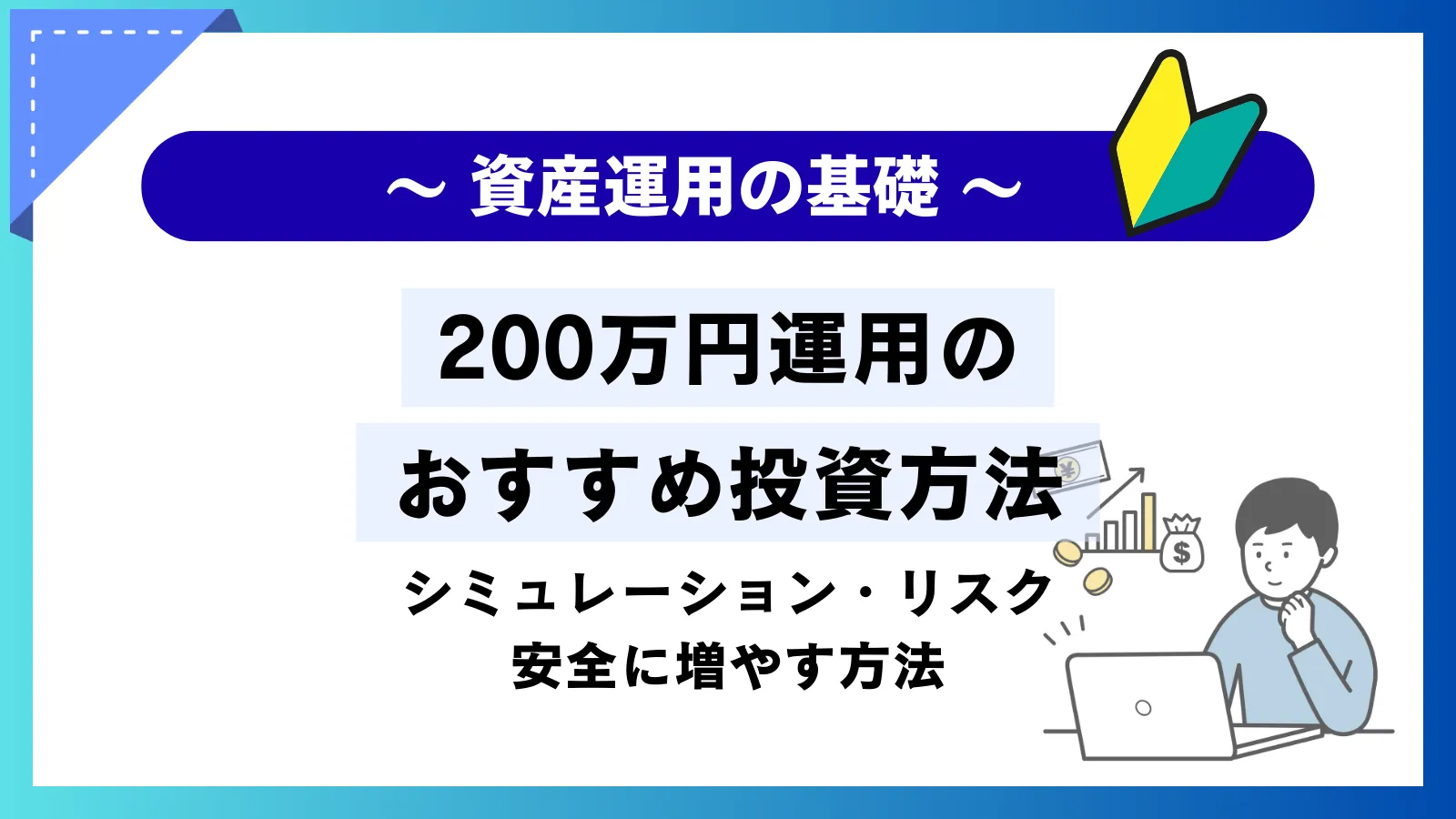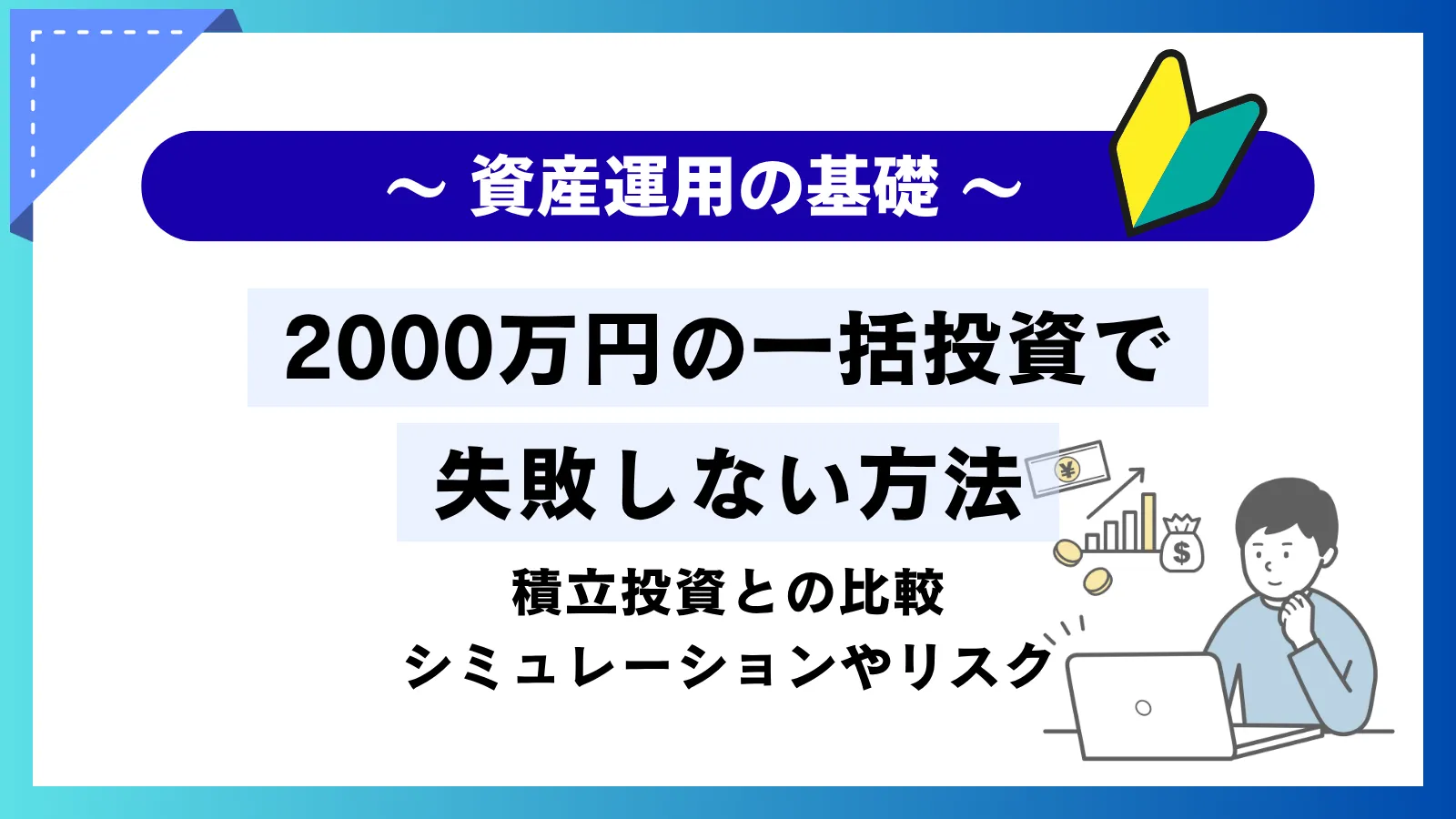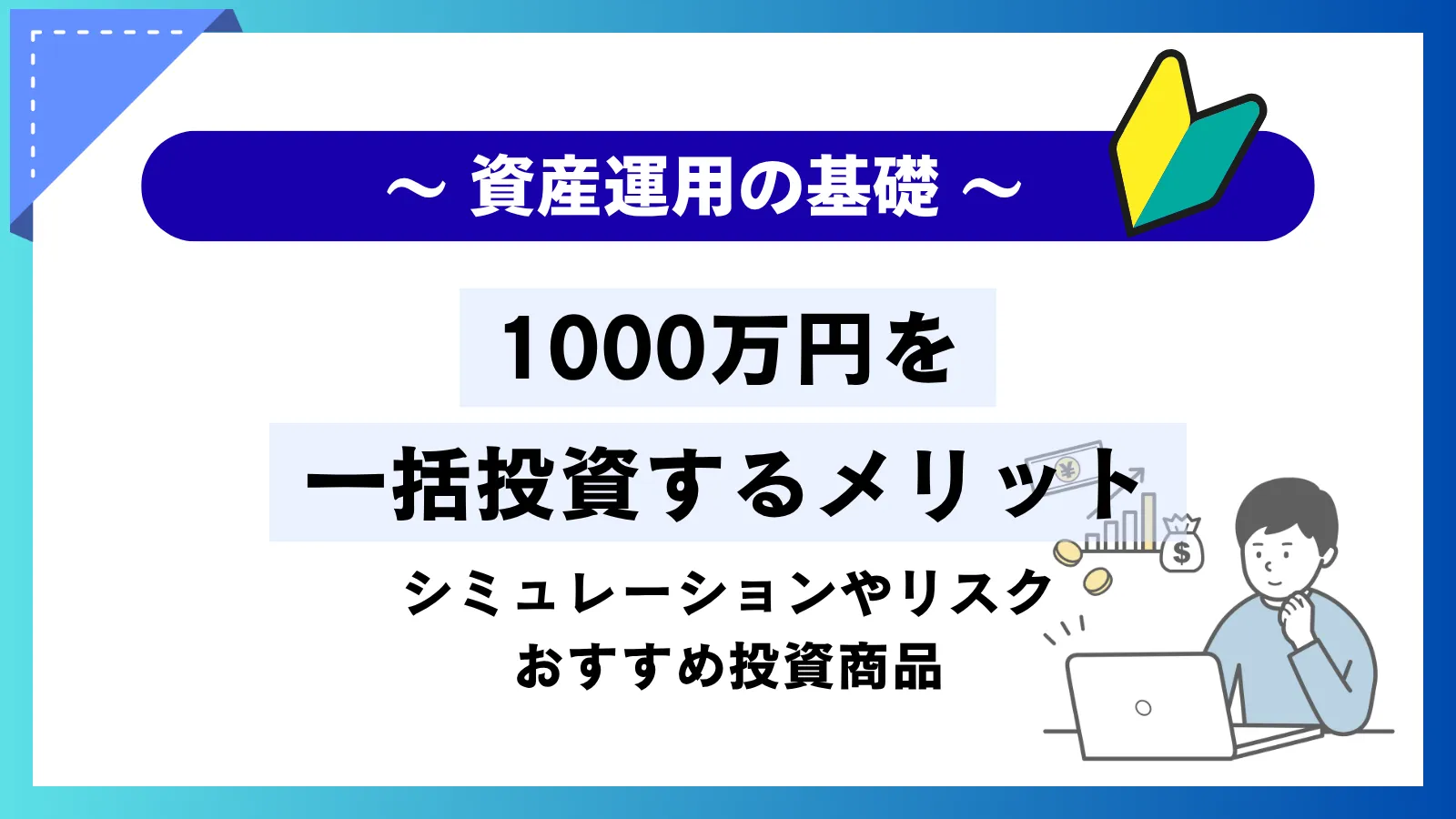「お金を増やす方法ランキングを知りたい」「確実にお金を増やす方法が分からない」
そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
お金を増やす方法には、資産運用や収入アップ、節約など様々な選択肢があります。
しかし、どの方法から始めれば良いか迷ってしまいますよね。
この記事では、2026年最新のお金を増やす方法ランキングを運用編・収入編・支出編に分けて徹底解説します。
初心者でも始めやすい方法から、年利10%以上を狙える本格的な資産運用まで幅広く紹介していきます。
お金を増やす方法ランキング【運用編・2026年最新】
お金を増やす方法として、まず押さえておきたいのが資産運用です。
2026年現在、さまざまな投資商品がありますが、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。
ここでは、期待利回りやリスク、最低投資額などを総合的に評価して、おすすめの運用方法をランキング形式でご紹介します。
1位:ヘッジファンド
お金を増やす方法の中でも、特に注目したいのがヘッジファンドです。
プロの運用者があなたの資産を預かり、高度な投資戦略を駆使して年利10%以上の高いリターンを目指します。
2026年現在、日本のヘッジファンド市場は約12兆円規模まで成長しており、個人投資家の参入も増加傾向にあります。市場が下落している時でも利益を狙える点が、他の投資商品との大きな違いですね。
ヘッジファンドの基本情報を表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期待利回り | 年10~20%程度 |
| 最低投資額 | 500万円~1,000万円 |
| リスク | 中程度 |
| 運用期間の目安 | 3年以上 |
| 主な手数料 | 管理報酬2~5%+成功報酬20~30% (手数料無料のヘッジファンドもあり) |
ヘッジファンドの魅力は、何といっても高い収益性です。
株式や債券、為替など多様な商品を組み合わせることで、リスクを分散しながら安定した利益を追求できます。
ただし、最低投資額が500万円からと高額なため、ある程度まとまった資金が必要になります。
ヘッジファンドのさらなる詳細や、2024年に年利回り17.35%の実績があるおすすめヘッジファンドについては、後述の「高いリターンでお金を増やしたいならヘッジファンド」をご覧ください。
2位:投資信託
少額から始められるお金を増やす方法として人気なのが投資信託です。
100円から投資できる商品もあり、初心者でも気軽にスタートできるのが最大のメリットでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期待利回り | 年3~5%程度 |
| 最低投資額 | 100円~ |
| リスク | 中程度 |
| 運用期間の目安 | 5年以上 |
投資信託は、多くの投資家から集めた資金をプロが運用する仕組みです。
個人では買いにくい海外株式や債券にも分散投資できるため、リスクを抑えながら資産を増やせます。
NISAを活用すれば、運用益が非課税になるメリットもあります。
ただし、運用管理費用として年0.1~2%程度の信託報酬がかかることは覚えておきましょう。
投資信託のメリットを活かすには商品選びが重要です。具体的な人気商品や選び方について知りたい方は、下記の記事で最新のランキングをチェックしてみましょう。
3位:ロボアドバイザー
AIが自動で資産運用してくれるロボアドバイザーは、忙しい方にぴったりのお金を増やす方法です。
投資の知識がなくても、質問に答えるだけで最適なポートフォリオを組んでくれる便利さが魅力ですね。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期待利回り | 年3~8%程度 |
| 最低投資額 | 1万円~ |
| リスク | 中程度 |
| 手数料 | 年0.5~1.1%程度 |
年齢やリスク許容度に応じて、自動的に資産配分を調整してくれるのも大きなメリットです。
ただし、完全に運用をお任せする分、手数料がやや高めになることは理解しておきましょう。
4位:債券
安定した利子収入を得られる債券は、堅実にお金を増やす方法として人気があります。
国や企業にお金を貸すことで、定期的に利息を受け取れる仕組みです。
債券の種類によって期待できる利回りは異なります。
| 債券の種類 | 期待利回り | リスク度 |
|---|---|---|
| 日本国債 | 0.6%程度 | 極めて低い |
| 社債 | 1~3% | 低 |
| 外国債券 | 4~5% | 中 |
株式と比べて値動きが小さいため、安定志向の方におすすめです。
ただし、インフレ時には実質的な価値が目減りするリスクがあることは覚えておきましょう。
債券投資を始めるなら、少額から手軽に分散投資できる「米国債券ETF」が注目されています。そのメリットと具体的な銘柄を下記記事で確認してみましょう。
5位:REIT
不動産投資信託のREITは、少額から不動産投資ができるお金を増やす方法です。
オフィスビルや商業施設などの賃料収入が、年2回の分配金として還元される仕組みになっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期待利回り | 年4~8%程度 |
| 最低投資額 | 10万円程度~ |
| リスク | 中程度 |
実物の不動産と違って、売買が簡単にできるのもメリットです。
ただし、金利上昇時には価格が下がりやすいという特徴があります。
REITは高い分配金が魅力ですが、知っておくべきデメリットやリスクも存在します。REIT投資を始める前に注意点をこちらの記事で必ず確認しておきましょう。
6位:金
世界共通の価値を持つ金への投資は、インフレ対策としても注目されるお金を増やす方法です。
経済が不安定な時期でも、金の価値は比較的安定しているという特徴があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期待利回り | 年3~7%程度 |
| 最低投資額 | 5万円程度~ |
| リスク | 中程度 |
| 投資方法 | 現物・ETF・積立 |
金ETFや純金積立なら、少額から始められるのでおすすめです。
ただし、配当や利息がつかないため、値上がり益だけが収益源になることは理解しておきましょう。
配当がない金投資ですが、少額から手軽に始められる「金ETF」は効率的です。おすすめの銘柄や買い方は、こちらの記事でチェックしておきましょう。
7位:株式投資
企業の成長とともに資産を増やせる株式投資は、お金を増やす方法の王道といえるでしょう。
配当金を重視した投資なら、年2~4%の安定収入が期待できます。
業種別の配当利回りを見てみましょう。
| 業種 | 期待配当利回り | 配当頻度 |
|---|---|---|
| 金融 | 3~5% | 年2回 |
| 通信 | 2~4% | 年2回 |
| 電力・ガス | 3~4% | 年2回 |
個別株への投資は企業分析が必要ですが、その分大きなリターンも狙えます。
初心者の方は、まず身近な企業から始めてみるのがいいでしょう。
8位:定期預金
元本が保証される定期預金は、リスクを取りたくない方向けのお金を増やす方法です。
ただし、現在の金利は年0.1%程度と非常に低いのが現実です。
| 預入期間 | 金利(年利) | リスク度 |
|---|---|---|
| 1年 | 0.1%程度 | 極めて低い |
| 3年 | 0.1%程度 | 極めて低い |
| 5年 | 0.1~0.2%程度 | 極めて低い |
1,000万円まで預金保険制度で保護されるため、安全性は抜群です。
しかし、インフレ率を考えると実質的に資産が目減りする可能性があることは知っておきましょう。
定期預金の安全性を保ちつつ、1,000万円などのまとまった資金を、より効率的に増やすための預け先をこちらの記事で解説しています。
9位:外貨預金
円よりも高い金利が魅力の外貨預金も、お金を増やす方法の一つです。
米ドルなら年4~5%の金利が期待できるケースもあります。
| 通貨 | 期待金利 | 特徴 |
|---|---|---|
| 米ドル | 4~5% | 最も取引が多い |
| 豪ドル | 3~4% | 比較的高金利 |
| ユーロ | 2~3% | 安定性が高い |
ただし、為替変動によって元本割れのリスクがあります。
円高になると損失が出る可能性もあるので、慎重に判断しましょう。
10位:貯蓄型保険
保障と貯蓄を兼ね備えた貯蓄型保険は、将来に備えながらお金を増やす方法です。
終身保険や養老保険なら、保険料の一部が積み立てられていく仕組みになっています。
| 保険の種類 | 期待利回り | 特徴 |
|---|---|---|
| 終身保険 | 1~2% | 一生涯の保障 |
| 養老保険 | 0.5~1.5% | 貯蓄性が高い |
| 個人年金保険 | 0.5~2% | 老後資金向け |
保障もついているため安心感はありますが、途中解約すると元本割れすることが多いです。
長期的な視点で加入を検討することが大切ですね。
お金を増やす3つの基本戦略を徹底解説
お金を増やす方法は、実は大きく分けて3つのアプローチに集約できます。
この3つを組み合わせることで、効果的に資産を築けるんです。
| 戦略 | 効果の速さ | 難易度 | 期待できる成果 |
|---|---|---|---|
| 収入を増やす | 早い | 中~高 | 月3~20万円増 |
| 支出を減らす | すぐ | 低 | 月2~5万円削減 |
| 資産を運用する | 遅い | 中 | 年3~15%の利益 |
- ①収入を増やす方法
今の時代、スキルを活かした副業なら月10万円以上の収入増も現実的になってきました。副業や転職が代表的な手段で、即効性が高いのが特徴です。 - ②支出を減らす方法
一番すぐに効果が出やすい戦略です。固定費の見直しだけで月2~3万円は削減できる場合が多いです。特に通信費や保険料は、プランを変更するだけで大きな節約につながります。 - ③資産を運用する方法
時間をかけて育てていくものです。複利効果を活かせば、10年後には大きな差が生まれます。ただし元本割れのリスクもあるため、しっかりとした知識が必要です。
この3つの戦略は、どれか一つだけでなく組み合わせることが大切です。
例えば、支出を減らして浮いたお金を投資に回す、副業で得た収入を資産運用に充てる、このような相乗効果を狙うことで、より確実にお金を増やせるでしょう。
「元本割れのリスク」が不安なら、市場下落時でも利益を狙うヘッジファンドが選択肢です。プロに任せて着実な運用を目指す方法を検討してみましょう。
収入を増やす方法のおすすめランキングTOP5
お金を増やす方法として、まず取り組みやすいのが収入アップです。
今の給料だけでは物足りない、もっと余裕のある生活がしたいです。
そんな思いを持つ方に向けて、実践的な方法をランキング形式でご紹介します。
1位:副業
本業を続けながら収入を増やせる副業は、リスクが低くて始めやすいお金を増やす方法です。
週末や空いた時間を活用すれば、月3万円から20万円程度の副収入も夢ではありません。
| 副業の種類 | 期待収入 | 必要スキル | 時間の融通 |
|---|---|---|---|
| Webライティング | 月3~10万円 | 文章力 | 高い |
| プログラミング | 月10~30万円 | コーディング | 中程度 |
| 動画編集 | 月5~15万円 | 編集技術 | 中程度 |
| せどり・転売 | 月3~20万円 | リサーチ力 | 高い |
副業選びのポイントは、自分の得意分野を活かすことです。
文章を書くのが好きならライティング、パソコンが得意ならプログラミングというように、スキルに合わせて選べば継続しやすいでしょう。
2位:転職
思い切って転職することで、大幅な年収アップを実現できる可能性があります。
同じ業界でも企業によって給与水準は大きく異なり、転職で年収が30%以上アップするケースも珍しくありません。
転職を成功させるためには、自分の市場価値を正しく把握することが大切です。
スキルや経験を棚卸しして、それが評価される企業を探してみましょう。
転職エージェントを活用すれば、より効率的に活動できます。
3位:昇給
今の職場で昇給を目指すのも、着実にお金を増やす方法の一つです。
転職と違ってリスクが少なく、年収10~20%アップを狙える現実的な選択肢といえるでしょう。
| 昇給のための行動 | 効果 | 難易度 |
|---|---|---|
| 成果を数値化してアピール | 高い | 中程度 |
| 資格取得で専門性を証明 | 中程度 | 高い |
| チームへの貢献度を高める | 中程度 | 低い |
大切なのは、自分の貢献度を目に見える形にすることです。
売上げアップや業務改善など、具体的な成果を上司にアピールしましょう。
評価面談の機会を活用して、積極的に交渉することも必要です。
4位:独立・起業
会社員の枠を超えて大きく収入を増やしたいなら、独立や起業という選択肢があります。
成功すれば収入が2倍、3倍になることも珍しくありません。
ただし、リスクも大きいため十分な準備が必要です。
まずは副業から始めて、ビジネスの感覚をつかむのがおすすめです。
最低でも6か月分の生活費を確保してから独立を考えましょう。
5位:スキルアップ
新しいスキルを身につけることで、より高い報酬の仕事にチャレンジできます。
プログラミングやデザイン、語学など、市場価値の高いスキルを習得すれば収入アップにつながります。
| 習得すべきスキル | 学習期間 | 収入への影響 |
|---|---|---|
| プログラミング | 6か月~1年 | 月5~20万円増 |
| Webデザイン | 3~6か月 | 月3~10万円増 |
| 英語 (TOEIC800点) | 1年程度 | 年収50~100万円増 |
オンライン学習サービスを活用すれば、仕事をしながらでもスキルアップできます。
投資した時間は必ず将来の収入に反映されるはずです。
支出を減らす方法のおすすめランキングTOP5
収入を増やすのと同じくらい大切なのが、支出を減らすことです。
毎月の出費を見直すだけで、意外なほど大きな節約ができるものです。
ここでは効果的な節約方法をランキング形式でお伝えします。
1位:家計の見直し
家計簿をつけて支出を把握することから始めましょう。
意外と知らない無駄遣いが見つかり、月3~5万円の節約も可能です。
| 見直しポイント | 削減可能額 | 難易度 |
|---|---|---|
| 食費 (外食を減らす) | 月1~2万円 | 低い |
| 娯楽費の管理 | 月1~2万円 | 中程度 |
| サブスクの整理 | 月5千~1万円 | 低い |
まずは1か月だけでも、すべての支出を記録してみてください。
スマホアプリを使えば簡単に管理できます。
無意識に使っているお金の多さに驚くはずです。
2位:ポイント活用
日常の買い物でポイントを貯めて活用すれば、実質的な支出を減らせます。
クレジットカードや電子マネーを上手に使い分けることで、年間3~7万円相当の節約につながります。
| ポイントの種類 | 還元率 | 活用のコツ |
|---|---|---|
| クレジットカード | 1~2% | 高還元率カードを選ぶ |
| 電子マネー | 0.5~1% | 少額決済で活用 |
| 共通ポイント | 1~3% | 加盟店を意識して使う |
ポイントはただ貯めるだけでなく、賢く使うことも大切です。
日用品の購入に充てれば、家計の助けになりますね。
3位:税金控除
使える控除をフル活用すれば、手取り収入を増やせます。
医療費控除や住宅ローン控除など、年間数万円から数十万円の節税が可能なケースもあるんです。
| 控除の種類 | 控除額の目安 | 申請方法 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 10万円超の医療費 | 確定申告 |
| 住宅ローン控除 | 年間最大35万円 | 確定申告 |
| 生命保険料控除 | 年間最大12万円 | 年末調整 |
領収書の保管など、日頃からの準備が大切です。
特に医療費は家族分も合算できるので、しっかり記録しておきましょう。
4位:各種手当の活用
会社の福利厚生や公的な手当を見逃していませんか?
住宅手当や家族手当など、申請するだけで月数万円もらえる場合がありますが、実は多くの会社員が、こうした制度の存在を知らないまま損をしているのが現実です。
まずは勤務先の就業規則を確認してみましょう。
通勤手当や資格取得支援金、健康診断の補助など、意外と知らない手当が見つかるかもしれませんし、さらに公的な制度も充実しており、児童手当や高額療養費制度、失業手当など、条件を満たせば活用できるものがたくさんあります。
これらの手当は申請しないともらえない仕組みになっているため、積極的に情報収集することが大切で、手当の存在を知らないまま本来受け取れるはずの支援を逃してしまうのは非常にもったいないことです。
人事部や自治体の窓口に問い合わせるなど、能動的に動くことで受給できる手当が見つかる可能性は高まります。
5位:固定費の削減
毎月必ず出ていく固定費を減らせば、長期的に大きな節約になります。
スマホ代や保険料など、プランを見直すだけで月1~2万円削減できることも珍しくありません。
| 見直し項目 | 削減可能額 | 見直しの頻度 |
|---|---|---|
| 携帯電話料金 | 月3千~1万円 | 年1回 |
| 保険料 | 月5千~2万円 | 2~3年に1回 |
| 電気・ガス代 | 月2千~5千円 | 年1回 |
特に携帯料金は、格安SIMに変更するだけで大幅に削減できます。
保険も必要な補償だけに絞れば、かなりの節約になるでしょう。
面倒でも定期的な見直しが、お金を増やす近道です。
少額から始めるお金を増やす方法!金額別の最適戦略
「投資を始めたいけど、まとまった資金がない。」
そんな悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
実は、少額からでも効果的にお金を増やす方法はたくさんあります。
手持ちの資金に合わせた最適な戦略を見つけていきましょう。
10万円から始めるお金を増やす方法
10万円あれば、十分に投資を始められます。
この金額なら投資信託の積立やポイント投資から始めるのがおすすめです。
| 投資方法 | 期待リターン | おすすめ度 |
|---|---|---|
| つみたてNISA | 年3~5% | ★★★★★ |
| ロボアドバイザー | 年3~8% | ★★★★☆ |
| 少額株式投資 | 年5~10% | ★★★☆☆ |
特につみたてNISAは、運用益が非課税になるため効率的です。
毎月コツコツと積み立てることで、将来の大きな資産につながります。
50万円から始めるお金を増やす方法
50万円あれば、投資の選択肢がぐっと広がります。
分散投資を意識して、複数の商品を組み合わせることが可能になってきます。
投資信託30万円、個別株10万円、債券10万円といった具合に、リスクを分散させながら運用できるでしょう。
この金額なら、REITへの投資も検討できます。
不動産からの安定収入が期待できるため、ポートフォリオの安定性が高まります。
REIT投資について詳しくは、こちらの見出しをご覧ください。
100万円から始めるお金を増やす方法
100万円という資金があれば、本格的な資産運用が始められます。
この段階ではプロに運用を任せる選択肢も視野に入ってきます。
| 運用方法 | 配分比率 | 期待リターン |
|---|---|---|
| 国内株式 | 40% | 年5~8% |
| 外国株式 | 30% | 年6~10% |
| 債券・REIT | 30% | 年3~5% |
100万円を一度に投資するのではなく、時間を分散させることも大切です。
半年から1年かけて段階的に投資することで、購入タイミングのリスクを減らせます。
500万円以上で始めるお金を増やす方法
500万円以上の資金があれば、より高度な投資戦略が可能になります。
この金額ならヘッジファンドへの投資も現実的な選択肢となるでしょう。
年利10%以上を狙える一方で、最低投資額のハードルが高いため、まとまった資金が必要です。
| 投資先 | 最低投資額 | 特徴 |
|---|---|---|
| ヘッジファンド | 500万円~ | プロによる運用 |
| 不動産投資 | 頭金300万円~ | 家賃収入が見込める |
| プライベートバンク | 1,000万円~ | オーダーメイドの運用 |
この規模の投資では、税金対策も重要になってきます。
専門家に相談しながら、効率的な資産形成を目指しましょう。
500万円以上の資産を「プロの運用」に任せるなら、ヘッジファンドが最適です。高いハードルや不安点を解消し、具体的な年利10%を狙う方法をこちらの見出しで解説しています。
税制優遇制度を活用してお金を増やす方法
国が用意している税制優遇制度を使えば、効率的にお金を増やせます。
税金が安くなるだけでなく、運用益が非課税になる制度もあるんです。
賢く活用して、資産形成のスピードを上げていきましょう。
NISAの活用
2024年から始まった新NISAは、お金を増やす方法として最も注目すべき制度です。
年間投資枠が大幅に拡大され、生涯で1,800万円まで非課税で運用できるようになりました。
| NISA枠の種類 | 年間投資枠 | 非課税期間 |
|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 120万円 | 無期限 |
| 成長投資枠 | 240万円 | 無期限 |
| 合計 | 360万円 | 無期限 |
特に若い世代なら、長期間の運用で複利効果を最大限に活かせます。
毎月3万円を30年間積み立てれば、年利5%で約2,500万円になる計算です。
これが全額非課税なのは大きなメリットですね。
特に、退職金などのまとまった資金がある方にとって、新NISAは資産を大きく増やすラストチャンスです。効果的な活用法をこちらの記事で確認しましょう。
iDeCoの活用
個人型確定拠出年金のiDeCoは、老後資金を作りながら節税もできる制度です。
掛金が全額所得控除になるため、年収500万円なら年間約8万円の節税効果が期待できます。
ただし、60歳まで引き出せないという制約があります。
確実に老後資金として残せる反面、急な出費には対応できません。
無理のない金額で始めることが大切です。
iDeCoで効率的に資産を増やすには、手間をかけず着実に増やす「ほったらかし投資」が向いています。具体的な手法をこちらの記事で見てみましょう。
ふるさと納税の活用
ふるさと納税は、実質2,000円の負担で各地の特産品がもらえる制度です。
寄付金額の一部が翌年の税金から控除され、実質的な節税効果が得られます。
| 年収 | 寄付上限目安 | 実質負担額 |
|---|---|---|
| 400万円 | 約4万円 | 2,000円 |
| 600万円 | 約7万円 | 2,000円 |
| 800万円 | 約12万円 | 2,000円 |
返礼品を生活必需品にすれば、実質的に支出を減らすことにつながります。
お米や日用品を選べば、家計の助けになるでしょう。
年代別!お金を増やす方法の最適ポートフォリオ
資産運用を始める際、自分の年代に合った方法を選ぶことが成功への近道となります。
20代と50代では、取れるリスクの大きさや運用できる期間が異なるためです。
年代ごとに最適な投資配分を理解しておくと、効率的に資産を増やせるでしょう。
このセクションでは、各年代に適したポートフォリオの組み方を詳しく解説していきます。
20代向けのお金を増やす方法
20代は人生で最も長い運用期間を確保できる時期といえます。
まだ家族を養う責任も少なく、失敗しても取り返す時間が十分にあることから、積極的にリスクを取った投資配分が可能です。
複利効果を最大限活用できる年代でもあります。
20代におすすめの資産配分を以下の表にまとめました。
| 投資対象 | 配分比率 | 期待利回り | 選定理由 |
|---|---|---|---|
| ヘッジファンド | 30% | 年10%以上 | 高リターンを狙える |
| 投資信託(株式型) | 40% | 年5~8% | 分散しながら 成長を取れる |
| REIT | 20% | 年4~8% | インカムゲインも 得られる |
| 債券・定期預金 | 10% | 年0.5~2% | 緊急資金として確保 |
この配分では、株式関連の資産が全体の70%を占めています。
若いうちは市場の変動に動じず、長期保有を前提とした運用を心がけましょう。
特にヘッジファンドは最低投資額が500万円以上と高めですが、20代のうちから副業などで資金を貯めて投資できれば、30代以降で大きな差がつく可能性があります。
毎月3万円を年利8%で30年間運用すると、約4,000万円を超える資産形成も夢ではありません。
30代向けのお金を増やす方法
30代は結婚や住宅購入、子供の誕生などライフイベントが増える時期です。
収入も20代より増えている一方で、支出も大きくなるため、リスクと安定性のバランスを取った運用が求められます。
ある程度のリスクは取りつつも、急な出費に備えた流動性の確保も意識したいところです。
30代に適した資産配分は以下の通りです。
| 投資対象 | 配分比率 | 期待利回り | 選定理由 |
|---|---|---|---|
| ヘッジファンド | 25% | 年10%以上 | まだ積極運用できる |
| 投資信託 (バランス型) | 35% | 年4~6% | 株式と債券で分散 |
| REIT | 15% | 年4~8% | 安定収益を確保 |
| 債券 | 15% | 年1~3% | 価格変動を抑える |
| 定期預金・現金 | 10% | 年0.1~0.5% | 緊急時の備え |
30代では株式関連の割合を20代より若干下げ、債券の比率を高めています。
住宅ローンの頭金や子供の教育費など、まとまった出費が発生する可能性を考慮した配分といえるでしょう。
投資信託はバランス型を選ぶことで、市場が下落した際の損失を抑えられます。
また、iDeCoやNISAといった税制優遇制度を活用すると、手取りの運用益を増やせるのでおすすめです。
40代向けのお金を増やす方法
40代になると子供の教育費がピークを迎え、支出が最も多くなる時期です。
同時に、老後資金の準備も本格化させる必要があります。
守りながら増やす戦略が基本となり、安全性を重視しつつも一定のリターンを確保する配分を心がけましょう。
40代の資産配分例を見ていきます。
| 投資対象 | 配分比率 | 期待利回り | 選定理由 |
|---|---|---|---|
| ヘッジファンド | 15% | 年10%以上 | 一部で高リターン狙い |
| 投資信託 (バランス型) | 30% | 年4~6% | 安定した成長を期待 |
| 債券 | 30% | 年1~3% | 資産の安定性を確保 |
| REIT | 10% | 年4~8% | 分配金収入を得る |
| 定期預金・現金 | 15% | 年0.1~0.5% | 教育費などに備える |
40代では債券の比率を30%まで引き上げ、安全資産の割合を高めています。
子供の進学や親の介護など、予期せぬ支出が発生しやすい年代だからです。
ヘッジファンドの配分は15%と抑えめですが、完全にゼロにする必要はありません。
資産全体の一部で高いリターンを狙うことで、老後資金の積み増しにつながります。
特に子供が独立した後は、再び積極的な運用に切り替えることも検討できるでしょう。
50代以降向けのお金を増やす方法
50代以降は退職が視野に入り、資産を守ることが最優先となります。
運用期間も限られてくるため、大きな損失を避けながら安定的に資産を維持・増加させる配分が理想的です。
インカムゲインを重視した運用にシフトしていきましょう。
50代以降におすすめの資産配分は以下の通りです。
| 投資対象 | 配分比率 | 期待利回り | 選定理由 |
|---|---|---|---|
| 債券 | 40% | 年1~3% | 元本の安全性を最優先 |
| 投資信託 (債券型) | 25% | 年2~4% | 安定運用を継続 |
| REIT | 15% | 年4~8% | 定期的な分配金 |
| 定期預金・現金 | 15% | 年0.1~0.5% | 生活費の確保 |
| ヘッジファンド | 5% | 年10%以上 | 余裕資金での運用 |
この年代では債券と定期預金で全体の55%を占め、安全性を最重視した配分となっています。
株式関連の投資は最小限に抑え、価格変動リスクを避ける戦略です。
REITは分配金が定期的に得られるため、年金収入を補完する目的で保有するのに適しています。
ヘッジファンドへの投資は5%程度に留め、あくまで余裕資金の範囲内で行うのがよいでしょう。
退職金の運用を考える際も、一度に大きな金額を投じるのではなく、時間をかけて分散投資することをおすすめします。
50代以降のポートフォリオに組み込むヘッジファンドは、市場全体が下がっても利益を狙えるのが強みです。安全志向でも年10%を狙える理由をこちらで確認してみましょう。
初心者でも安心!確実にお金を増やすための重要ポイント5選
投資を始めたばかりの方にとって、どこから手をつければよいか迷うことも多いでしょう。
実は、お金を増やすための基本的なポイントを押さえておくだけで、失敗のリスクを大きく減らせます。
ここでは初心者が実践すべき5つの重要なポイントを紹介していきます。
投資で成功するための情報収集を徹底する
資産運用で成果を出すには、信頼できる情報源から正しい知識を得ることが欠かせません。
間違った情報や偏った意見に惑わされると、大切な資金を失うリスクが高まってしまいます。
どこから情報を集めるべきか、最初にしっかり押さえておきましょう。
初心者におすすめの情報源を以下の表にまとめました。
| 情報源 | 信頼度 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 金融庁・証券会社 の公式サイト | 高 | 正確な情報が得られる | 専門用語が多め |
| 投資関連書籍 | 高 | 体系的に学べる | 情報が古い場合も |
| 投資セミナー | 中 | 実践的な知識を習得 | 営業目的の場合あり |
| 投資系YouTube ・ブログ | 中 | 無料で学べる | 情報の見極めが必要 |
| SNSの投資アカウント | 低 | 最新情報が早い | 誤情報も多い |
まず、金融庁や大手証券会社の公式サイトは信頼性が極めて高く、投資の基礎知識を学ぶのに最適な情報源です。
もし専門用語が多くて難しいと感じるようでしたら、まずは初心者向けの書籍から体系的に学ぶことをおすすめします。
一方、X(旧Twitter)などのSNSは情報更新が早いという利点がある反面、根拠のない噂や誇大広告も多く混在しています。「絶対儲かる」「誰でも簡単に」といった安易な言葉には特に注意が必要です。
複数の信頼できる情報源を常に比較しながら、最終的には自分で判断できる力を養っていきましょう。
副業収入で投資資金を積み上げる
投資を始めるには、まとまった元手が必要になります。本業の収入だけでは投資に回せる余裕がない方も多いでしょう。
そんな時は、副業で得た収入を投資資金として活用するのが効果的です。
在宅でできる副業を中心に、月3万円〜10万円程度の収入を狙えるものをいくつか紹介します。
Webライティングなら1記事1,000円〜5,000円程度の報酬を得られ、実績を積めば高単価案件も受注可能です。データ入力は特別なスキル不要で単価は1件500円程度と低めですが、スキマ時間で作業できる点が魅力です。
フリマアプリは自宅の不用品販売から始められ、仕入れ販売に発展させれば利益率30%〜50%も狙えます。
副業で月3万円を稼げれば年間36万円の投資資金を確保でき、これを年利5%で運用すると、10年後には約450万円の資産を築くことも可能です。
長期投資で資産を増やす複利効果を活用する
短期間で大きく稼ごうとすると、どうしてもハイリスクな投資に手を出してしまいがちです。
確実にお金を増やすなら、時間を味方につけた長期投資がおすすめといえます。
複利の力を活用すれば元本が雪だるま式に増えていくため、その威力を具体例で見てみましょう。
| 運用期間 | 年利5%の場合 | 年利7%の場合 | 年利10%の場合 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 約465万円 | 約518万円 | 約610万円 |
| 20年 | 約1,233万円 | 約1,560万円 | 約2,274万円 |
| 30年 | 約2,497万円 | 約3,679万円 | 約6,783万円 |
10年間では年利5%と10%で約150万円の差ですが、30年後には4,000万円以上の差が生まれます。
運用期間が長いほど、複利効果が大きく働くことがわかるでしょう。
途中で売却したくなる気持ちもあるかもしれませんが、市場の短期的な変動に一喜一憂せず、じっくり保有を続けることが成功への近道です。
毎月コツコツと積み立てる習慣をつけることで、自然と長期投資のスタイルが身につきます。
資産を複数に分けて投資リスクを抑える
一つの投資先に全額を投じてしまうと、その投資先が失敗した時に大きな損失を被りますが、複数の資産に分散して投資することで、リスクを大幅に減らせるのです。
「卵を一つのカゴに盛るな」という投資の格言があるように、分散投資は資産運用の基本といえるでしょう。
初心者向けの分散投資例として、投資資金が100万円ある場合を想定してみます。
- 投資信託(インデックス型):40万円
- 債券:30万円
- REIT:15万円
- 定期預金:15万円
この配分なら、株式市場が下落しても債券や定期預金でカバーできますし、REITは不動産に投資するため株式とは異なる値動きをするのが特徴です。
さらに国内だけでなく海外の資産にも分散すると、為替変動のリスクはあるものの、日本経済だけに依存しない運用が可能になるでしょう。
最初は国内の投資信託で全世界株式型を選ぶと、一つの商品で世界中に分散投資できるのでおすすめです。
投資アプリを使って効率的に資産運用する
スマートフォン一つで投資ができる時代になりました。
投資アプリを活用すれば、いつでもどこでも資産状況の確認や取引が可能で、忙しい方でもスキマ時間を使って効率的に資産運用できるでしょう。
初心者におすすめの投資アプリの種類をまとめました。
| アプリの種類 | 特徴 | 最低投資額 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| ロボアドバイザー | AIが自動運用 | 1万円〜 | 完全お任せしたい人 |
| 投資信託アプリ | 100円から積立可能 | 100円〜 | 少額から始めたい人 |
| 株式投資アプリ | 手数料が安い | 数百円〜 | 個別株に挑戦したい人 |
| 家計簿連携アプリ | 資産を一元管理 | 0円 | 全体を把握したい人 |
ロボアドバイザーは質問に答えるだけで最適なポートフォリオを提案してくれるため投資の知識がなくても始められ、投資信託アプリは100円から積立できるためお試し感覚でスタート可能で、ポイント投資なら現金を使わずに始めることもできます。
家計簿連携アプリを使えば銀行口座や証券口座の残高を一つの画面で確認でき資産全体を俯瞰できるため、バランスの取れた運用がしやすくなるでしょう。
自分のライフスタイルに合ったアプリを選んで、効率的な資産運用を目指してください。
高いリターンでお金を増やしたいならヘッジファンド
お金を増やす方法として本格的な資産運用を検討しているなら、ヘッジファンドは有力な選択肢です。
最低投資額500万円から利用でき、プロの運用により年利10%以上の高いリターンも期待できます。
ここでは、日本の個人投資家に人気の高い2つのヘッジファンドをご紹介します。
| ファンド名 | 年利回り | 最低投資額 | 投資戦略 |
|---|---|---|---|
| ハイクアインターナショナル | 12%(固定) | 500万円 | 新興国企業への融資 |
| アクション | 17.35% (2024年度実績) | 500万円 | バリュー株投資・事業投資 |
ハイクアインターナショナル
| 運用会社 | 合同会社 ハイクア・インターナショナル |
|---|---|
| 設立 | 2023年 |
| 本社所在地 | 日本(大阪) |
| 主な投資対象 | SAKUKO VIETNAM (ベトナム企業) |
| 主な投資戦略 | 事業融資 |
| 年間期待利回り | 年利12% |
| 最低投資金額 | 500万円 |
| 運用の相談 | 資料請求・面談 |
| 公式サイト | ハイクア・インターナショナル |
ハイクア・インターナショナルは、ベトナムの成長企業「SAKUKO Vietnam」への事業融資により、年利12%の固定リターンを目標とする安定性重視のプライベートデットファンドです。
株式投資と異なり市場変動に左右されにくい収益構造を実現しており、500万円という比較的参入しやすい金額から始められる点も魅力となっています。
年利12%固定の高利回り
ハイクアの最大の特徴は、年利12%という高水準の固定リターンを目指している点です。
投資信託の年利3~5%や定期預金の0.1%と比較すると、圧倒的に高い利回りを実現しています。しかも株式市場の値動きに左右されない安定した収益構造を持つため、長期的な資産形成に適しています。
株式投資と異なり、企業が売上を出せば利息が得られるため、リターンまでの過程がシンプルで直接的です。
市場の値動きに一喜一憂する必要がなく、3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回の分配金が支払われる定期的なキャッシュフローも大きなメリットとなっています。
- 市場変動に左右されない
株価暴落時でも安定した利回りを確保 - 株価変動リスクがない
事業融資型なので株式市場の影響を受けない - 定期的なキャッシュフロー
3ヶ月ごとに3%ずつ、年4回の分配金 - シンプルな収益構造
企業の売上から直接利息を得る仕組み - 高い透明性と信頼性
投資先の事業内容が明確で追跡可能 - 最低投資額500万円から
ポートフォリオに組み込みやすい金額設定
代表者が情報開示に積極的で、出資前に無料面談が可能、出資後も事業報告会があるなど透明性も高い運営体制となっています。
投資判断に必要な情報がしっかりと提供される環境は、投資家にとって大きな安心材料といえるでしょう。
ベトナム市場の成長性
ハイクアが投資対象とするベトナムは、アジアの中でも特に高い成長率を誇る新興国です。
年間5〜6%の経済成長を継続しており、若い労働力と政治的安定性が経済発展を後押ししています。
投資先の「SAKUKO Vietnam」は、ベトナム国内で確固たる事業基盤を築いており、この成長市場の恩恵を直接受けられる環境にあります。
先進国市場が成熟し、日本経済も低成長が続く中、ベトナムのような成長市場への投資は、ポートフォリオの分散という観点からも有効な戦略です。
- 高い経済成長率
年間5〜6%の安定した成長を継続中 - 若く活力ある労働力
平均年齢約32歳、人口約1億人の内需拡大の潜在力 - 製造業の集積地
「世界の工場」として外資企業の進出が活発化
国内の投資信託や株式だけでなく、成長市場への分散投資を検討している方にとって、ハイクアは魅力的な選択肢となるでしょう。
「お金を増やす方法として安定した高利回りを求めている」「市場の変動に左右されにくい投資先を探している」と考えているなら、ハイクア・インターナショナルのような個人投資家が参加できる国内ヘッジファンドをポートフォリオの一部に組み込むことを検討してみてはいかがでしょうか。
まずは無料の資料請求で詳細な投資条件をご確認ください。年利12%の安定した固定リターンを実現する投資モデルの仕組みや、ベトナム市場の成長性について詳しく知ることができます。
ハイクアインターナショナルについて、詳しくは下記の記事も参考にしてください。
アクション

| 運用会社 | Action合同会社 |
|---|---|
| 設立 | 2023年 |
| 本社所在地 | 日本(東京) |
| 主な投資対象 | 日本株・事業投資・Web3事業・ファクタリングなど |
| 主な投資戦略 | ・株式の成長投資戦略 ・エンゲージメント、アクティビスト投資戦略 ・ポートフォリオ投資戦略 |
| 利回り | 17.35%(2024年度実績) |
| 最低投資金額 | 500万円 |
| 運用の相談 | 面談 |
| 公式サイト | アクション |
アクション合同会社は、2023年設立の新興ヘッジファンドながら、初年度から年利17.35%という驚異的な実績を達成しました。
お金を増やす方法として高度な運用戦略を求める方に、プロフェッショナルな資産運用を個人投資家でもアクセスしやすい形で提供しているファンドです。
2024年度実績は驚異の年利17.35%
アクションの最大の魅力は、その圧倒的な運用実績です。2024年度に年利17.35%という高いリターンを達成し、日本国内のヘッジファンドの中でもトップクラスの成績を残しています。
投資信託の年利3~5%、ロボアドバイザーの年利3~8%と比較すると、アクションの実績は桁違いの高リターンを実現しています。
もちろん、設立間もないファンドのため長期的な実績はこれからですが、この初年度の成果は資産を大きく増やしたい投資家にとって注目に値するものといえるでしょう。
- 2024年度実績17.35%
日本国内ヘッジファンドの中でもトップクラス - 目標年利15%以上
長期的に高い水準のリターンを目指す運用方針 - 金融業界30年以上の経験
実力ある運用チームによる高度な投資判断 - 透明性の高い情報開示
役員陣や実績を公式サイトで公開 - 最低投資額500万円から
比較的参入しやすい金額設定
運用を担うのは、金融業界で30年以上の経験を持つプロフェッショナルチームです。役員陣の経歴や運用実績を公式サイトで公開するなど、透明性の高い運営姿勢も投資家からの信頼を集めています。
多角的な投資でリスク分散
アクションのもう一つの特徴は、マルチストラテジー戦略を採用している点です。
一つの投資手法に依存せず、複数の資産クラスと戦略を組み合わせることで、リスクを分散させながら高いリターンを追求しています。
- バリュー株投資
割安で成長余地のある日本株への投資 - アクティビスト戦略
企業経営に積極的に関与し価値向上を促す - 事業投資
成長性の高い事業への直接投資 - Web3事業
次世代インターネット技術への先行投資 - ファクタリング
債権の買取による安定収益の確保
この多角的なアプローチにより、ある投資が不調でも他の投資でカバーできる体制を構築しています。
投資信託が株式や債券に分散投資するのと同様に、アクションも日本市場を中心としながら多様な投資機会を追求することで、安定性と収益性を両立させているのです。
「お金を増やす方法として本格的な資産運用に挑戦したい」「日本市場に精通したプロの運用を任せたい」と考えているなら、アクションのような個人投資家が参加できる国内ヘッジファンドは有力な選択肢となるでしょう。
ただし、出資した資金は1年間のロックアップ期間があるため、余剰資金での投資が推奨されます。興味がある場合は、公式サイトから無料面談を申し込むことで詳しい説明を受けてみましょう。
アクション合同会社について詳しくは下記の記事も参考にしてください。
お金を増やす方法を始める前に準備すべきこと
いきなり投資を始めるのは少し危険かもしれません。
お金を増やす方法を実践する前に、まずは土台となる準備を整えておくことが大切です。
準備不足のまま投資を始めてしまうと、想定外の損失に慌てたり、途中で資金が足りなくなったりする可能性があります。
このセクションでは、資産運用をスタートする前に押さえておきたい3つのポイントを解説します。
投資目的と目標金額を明確化する
何のためにお金を増やしたいのか、目的をはっきりさせておきましょう。
老後の生活資金なのか、子どもの教育費なのか、それとも住宅購入の頭金なのか。
目的が違えば、必要な金額も運用期間も変わってくるためです。
たとえば老後資金として2,000万円を貯めたいなら、現在の年齢から逆算して毎月いくら積み立てればいいのか計算できます。
以下の表で、投資目的別の運用期間と適した方法を確認できます。
| 投資目的 | 目標金額の目安 | 運用期間 | 適した運用方法 |
|---|---|---|---|
| 老後資金 | 2,000~3,000万円 | 20年以上 | 投資信託、ヘッジファンド、株式 |
| 教育資金 | 500~1,000万円 | 10~18年 | 投資信託、債券、学資保険 |
| 住宅購入頭金 | 500~800万円 | 5~10年 | 債券、REIT、定期預金 |
| 結婚資金 | 200~400万円 | 3~5年 | 定期預金、債券 |
目的が明確になると、どれくらいのリターンを狙うべきか自然と見えてきます。
運用期間が長ければリスクを取ってリターンを狙える一方、短期間で必要な資金なら安全性を優先すべきでしょう。
目標金額を設定する際は、現実的な数字から始めるのがおすすめです。
いきなり高すぎる目標を立てると、無理な運用で失敗するリスクが高まります。
リスク許容度を確認する
投資では必ずリスクが伴うため、自分のリスク許容度を把握しておくことが欠かせません。
リスク許容度とは、資産が値下がりしたときに心理的・経済的にどこまで我慢できるかを示す指標で、年齢や収入、家族構成によって大きく変わります。
| チェック項目 | リスク許容度が高い | リスク許容度が低い |
|---|---|---|
| 年齢 | 20~30代 | 50代以降 |
| 収入の安定性 | 安定している | 不安定 |
| 扶養家族 | なし・少ない | 多い |
| 投資経験 | ある | ない |
| 運用期間 | 10年以上 | 5年未満 |
| 損失への耐性 | 20%以上OK | 10%未満まで |
リスク許容度が高い人は株式やヘッジファンドなど値動きの大きい商品に投資できますが、低い人は債券や定期預金といった安全性の高い商品を中心に組み立てるのが賢明です。
生活防衛資金を準備する
投資を始める前に、まとまった現金を確保しておくことをおすすめします。
突然の病気や失業など、予期せぬ出費が発生したときに、投資資金を取り崩さずに対応できるようにするためです。
一般的には生活費の3ヶ月分から6ヶ月分を目安に用意しておくとよいでしょう。
以下の表で、家族構成別の生活防衛資金の目安を確認できます。
| 家族構成 | 月の生活費目安 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 |
|---|---|---|---|
| 単身 | 15万円 | 45万円 | 90万円 |
| 夫婦2人 | 25万円 | 75万円 | 150万円 |
| 夫婦+子ども1人 | 30万円 | 90万円 | 180万円 |
| 夫婦+子ども2人 | 35万円 | 105万円 | 210万円 |
生活防衛資金は普通預金や定期預金など、すぐに引き出せる形で保管しておきましょう。
投資に回してしまうと、必要なときに値下がりしていて使えないという事態になりかねません。
自営業の方やフリーランスの方は、収入が不安定なケースが多いため、6ヶ月分以上の確保が望ましいです。
生活防衛資金を確保したうえで、余裕資金を投資に回していく流れが理想的でしょう。
よくある質問
お金を増やす方法について、読者の方からよく寄せられる質問をまとめました。
投資初心者が気になるポイントを中心に、簡潔に回答していきます。
まとめ
お金を増やす方法は、運用・収入・支出の3つの戦略を組み合わせることが重要です。
資産運用では、投資信託やロボアドバイザーなど少額から始められる方法から、ヘッジファンドのような本格的な運用まで、自分の資金とリスク許容度に合わせて選択できます。
収入面では副業や転職、スキルアップで月3万円〜20万円の増加が目指せますし、支出削減では固定費の見直しで月2万円〜5万円の節約が可能です。
特に重要なのは、NISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用することと、年代に応じた最適なポートフォリオを組むことです。
20代なら積極的にリスクを取り、50代以降は安定性を重視するなど、ライフステージに合わせた戦略が成功の鍵となります。まずは生活防衛資金を確保したうえで、長期的な視点で複利効果を活かしながら、着実に資産を増やしていきましょう。
500万円以上の資金がある方は、年利10%以上を目指せるヘッジファンドへの投資も検討してみてはいかがでしょうか。